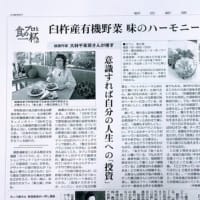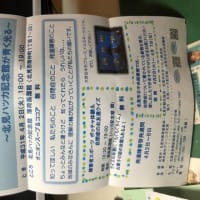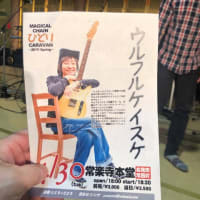北見市議会 9月定例議会で常呂自治区の風力発電計画についての質問内容です。
突然、宗谷から?吹いてきた風力発電計画が、これからの地域づくりに、どのように貢献できるのか?温暖化対策の必要性から、その必要性は理解する中、では、常呂で建設すると、どのようなことになるのか?きっかけは、素朴な好奇心から。
地域の人たちに理解していただくには、どのように伝えたらいいか。と、これからの常呂町の地域づくりの在りについて考える中、風力発電計画を常呂町の住民は本当に素直に求めるだろうかと、自分なりに調べて市長に投げかけてみました。
以下、内容です。
●質問1回目 常呂自治区の地域づくりと風力発電について、お聞きします。
常呂自治区で計画されている風力発電についてお聞きします。▼国は1997年に環境アセスメント法を施行、その法律に基づく手続きとして大規模な開発事業の実施には事前に環境への調査、予測、評価を行った上で、地元住民の理解と同意を求めていますが、2012年10月より風力発電事業においても、その手続きが義務化されました。
北見市は、この国の求める手続きとして、市の環境評価に関する意見書を北海道に提出、北海道も企業が用意した準備書を審査し意見書を6月に国に提出、現在は、国の環境影響評価準備書の審査が行われている段階です。
▼この風力発電計画は、国内では現時点の最大規模であり、一基当たりの能力、大きさは、出力が4.300KW、高さは札幌のテレビ塔の143Mを越える150Mの高さ。常呂町百年記念塔と比較すると、その高さは5倍あります。全体計画では12基の建設を計画していますが、その一期工事では7基の建設を予定しています。そして建設予定地は、常呂町と網走市の境を尾根伝い走る網走市の市道。JAところの育成牧場を横に過ぎて常呂川を見下ろしながら網走市に向かい走る道路沿いに並べて建設するというものです。
▼この計画について、最初の一般対象の企業説明会が本年1月に常呂で開催されましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会活動の自粛要請を受けて、その後の説明会開催は順延となり、6月末に常呂まちづくり協議会での説明、翌月7月に改めての住民説明会が再開されました。▼説明会では市民から風力発電が発生する低周波振動等の人体への影響や国内希少野生動植物種に指定されているオジロワシなど、「主にロシア方面から飛来する多くの野鳥類や常呂川へ回帰する魚など生態系への影響は無いのか?」「なぜ、常呂での計画なのか?」と、様々な角度からの率直な意見等がありました。▼地球温暖化防止のための再生エネルギー開発としてのプラスのイメージを持っていた風力発電ですが、関心を持つ市民自らが風力発電のメリット、デメリットを調査し投げかけられる疑問の声、質問に、その疑念を払しょくするような返答が企業側からは得られず、集まった市民が理解を示し、歩み寄るような空気は感じられませんでした。
▼北海道が国に提出した意見書は、計画予定地周辺に暮らす住民生活への影響や自然環境保全の立場から求められる対応など厳しい内容と理解するところでした。▼7月の説明会後には、所属会派、市民・連合クラブで風力発電に関する情報収集として企業に説明を求め、8月には稚内市の現地視察に出向きました。専門的な見地からとはなりませんが、これまでの情報と常呂自治区と言う地域性の視点から、幾つか質問します。
1)まずは、風力発電、そのものについてお聞きします。
●7月の常呂での市民説明会には市の担当者も傍聴していました。参加者からの建設への理解の声は無かったと思いますが、様々な意見、質問を聴きとり、市としてどのように受けとめているのか?お聞きします。●発生する低周波振動の影響を受ける懸念がある地域に暮らす市民への、企業の対策をどのように認識していますか?▼また道の意見書では、風車のブレードの影による近くに居住する住民への影響を懸念、対策を求めるとしています。説明会においては、その件は大きめのカーテンに付け替える、寝室や居住空間の移動をお願いすると考えを示したそうです。あわせて木陰をつくる植樹も提案するとのことです。これでは、対策と言うより、迷惑をかけますが、辛抱して下さいと言っているように聴こえませんか。風車の位置を変更するとは考えていません。市民に苦痛を強いるような対応であってはいけないと考えますが、見解をお聞かせください。●自然界の生態系への影響、とりわけ野鳥類に対し道意見書は極めて厳しい意見と受けとめています。東京農大准教授・地球環境科学博士であり、道の風力発電影響評価審議委員のメンバーの白木彩子さんに、この計画が、野鳥類の生態にどのような影響があるか?お聞きしました。▼もし常呂・能取風力発電が稼働すると、希少種のオジロワシなどの個体の事故ばかりでなく、その野鳥たちの営巣などの生息できる場所の消失の恐れもある。これまで風力発電の無い紋別市以南、知床半島までのオホーツク圏域においては生息環境の悪化や撹乱によって、つがいが営巣地を放棄し、いなくなることもこれまでの調査や海外での実例から推察され、個体群への影響が大きく懸念されるとのことでした。渡り鳥たちは、この地に開拓に入植した先人たちよりも、もっと遠い過去の時代から、ここを流氷南限の楽園として、幾世代も引き継ぎ、この地を目指して飛来しているのです。▼北海道の意見書を踏まえて、オホーツク海に面した常呂を目指す野鳥類に、どのような影響が有ると認識し、市として企業に対応を求めていく考えか? お聞かせください。
●市は風力発電建設に要する用地の提供を求められています。会派の研修時には、市有地の提供の判断は市民説明会の意見等を判断材料にすると担当部の見解を示していたが、市有地を提供するか否かの判断は、この建設計画への市の認識を示すことになります。何を根拠に、いつの時点で判断するのか?併せて、市有地の提供に関する市民説明を求められたら、どのような対応をとるのか?聞きします。
◆2)●説明会の質問では、地元のメリットとして「災害時の停電対応、電気の供給を地元を優先してできないのか?」と言う質問がありました。あの2年前の胆振東部地震によるブラックアウトを経験した、市民の声としてはうなずけるものですが、企業からの返答は、この風力発電により提供される電力は、すべて北電に供給されるもので、現在の仕組みでは蓄電設備を現地には設置もできず、災害時の対応ができないので、今後の課題として努力するというものでした。▼北見市民にとっては自然災害への対応は、停電だけに限らず誰にとっても関心は高いものです。常呂川に寄り添い暮らす常呂自治区住民には平成28年の常呂川の氾濫による被害はまだ記憶に新しいものです。▼昨年、常呂自治区では住民を対象に命を守るための災害タイムライン試行版ができました。また常呂川の治水対策としての堤防工事、冠水した畑から水をくみ上げる移動式排水機の整備と、今、北見市は災害時への対応に積極的に取り組んでいるところではありますが、私は、これらに合わせて、自然環境の保全、常呂川沿いの豊かな森づくりも保水力を高めるために当然、必要な取り組みと考えます。
●北見市は本年3月に「北見市緑の基本計画」を策定しました。その計画策定に至る背景と目的には、緑、森林の力は大規模災害への対応にも。と書かれています。基本方針のひとつ「緑を保全し次世代に引き継ぐ緑のまちづくり」の具体的な施策として「美しい山並みと、清らかな河川環境の保全とし、既存地形や自然植生の保存、民有林の適切な維持管理、更新に取り組む」。「森林、河川、農地など災害を未然に防ぐ緑の保全に取り組む」とあります。▼この風力発電計画ではJAところと北見市からの用地提供を前提としています。7月の市民説明会で、企業側から初めて風力発電建設に要する樹木伐採面積が示されました。第1期工事の7基分の建設に必要な樹木の伐採面積は8haとしていますが、国に申請している全体計画では12基の予定です。▼あらためて市を通じて全体の樹木伐採面積を確認してもらいましたが、12基建設に必要な樹木伐採面積は約13haのとのことです。市民の目には見えにくい場所に分散していますので、その規模をイメージするのに見えやすいところに移動して想像してみたいと思います。▼例えばとして約13haの樹木伐採の面積を常呂川の流域に沿って(防風林規模の)幅50メートルで置き換えてみると、どの程度か?実に2.6㎞程の延長になります。これが風車に見下ろされる常呂自治区への見返りです。緑の計画との整合性をどう考えるか?お聞かせください。
以上で、一回目の質問を終わります。
●質問2回目
◆再質問・常呂自治区の地域づくりと風力発電について
▼常呂自治区住民は旧常呂町の明治時代から、川の氾濫、洪水を何度も何度も経験しながら常呂川とともに生きてきました。この風力発電の建設を地域づくりの視点で考えるとき、地球温暖化対策という現況から未来を考える横軸的な思考に合わせ、過去を振り返り現在を見つめ直し未来を考える縦軸的な思考も必要だと思っています。▼旧常呂町時代、1990年から10年間発行した「ところ通信」という町制要覧があります。その1999年の最終号の地域づくりの特集は「常呂川」でした。常呂町にとって常呂川は生きる命の源、「森は海の恋人、川は仲人」と謳い、豊かな森づくり運動として取り組んでいる漁業者による植樹活動が紹介され、森づくりをけん引した当時の漁協組合長・小笠原敬さんの功績を記念して、常呂川源流域に植樹し命名された「小笠原の森」のこと。その小笠原組合長によく聞かされた言葉「積小為大」(小さなことを積み重ねて大きなことを為す)を大切にしていきたいとする、当時の漁協青年部長の言葉もありました。▼またカキ養殖の隣人としてご縁が深い宮城県の「牡蠣の森を慕う会」の畠山重篤さんからは、「少しくらい木を植えても、自然は変るものではありません。植樹は単に木を植えて魚が増えるということを大きく通り越して、突き詰めると人間の生き方。私たちの生き方を啓蒙するものです。」と言葉をいただいています。このように町政要覧最終号の特集で、常呂町は地域づくりへの想いを綴って20世紀を閉じました。常呂川沿いの植樹活動は常呂町時代からの継承されている地域づくりの取り組みです。▼常呂漁協は平成4年漁業団体として全国で初の「朝日森林文化賞」を、平成13年には、緑化推進運動の功績が認められ内閣総理大臣賞を受賞。また、常呂漁協婦人部も平成7年に水産庁長官賞を受賞。この常呂の森づくり・植樹活動は、「積小為大」の積み重ねの上に今日があり、風土から学び培ってきた常呂住民の生き方(地域哲学)でもあると言えます。
★これは20世紀を生きた先人たちからの、21世紀の常呂に生きる私たちへの「伝言」だと私は受けとめています。
▼ 現在も「自然を守ろう!森は海の恋人・川は仲人」を合言葉に、これまでの植林面積は345hと常呂漁協のHPに紹介がありました。常呂漁協は、100万本の植樹を目標に、現在も世代を引き継ぎ地域づくりに取り組んでいます。実は、この継続されている常呂自治区の森づくりの取り組みについて、北見市緑の基本計画には紹介されておりません。▼市民協働のまちづくりの北見市です。豊かな森づくりと言う20世紀からの伝言を、しっかり受けついでいる常呂自治区の個性ある地域づくりと理解いただきたいと考えます。▼関連してお聞きします。なぜ取り上げられていなかったのか。また風力発電建設に要する樹木13haの伐採を、常呂自治区の、北見市の地域づくり活動の視点から、どう受けとめられるのか?お聞きします。
▼辻市長は、市長になる前の最後の職は特別職の常呂自治区長でした。その常呂自治区長在任中の平成25年秋に、常呂総合支所の敷地の中に経済と道徳の融和を説いた二宮尊徳像が再建立されています。その像には、「昭和11年に建てられ77年の月日を経て風雪にさらされ老朽化したモノを、当時の意思を引き継ぎ尊徳の教えにある相互扶助をもとに、地域の将来を担う人々への期待と活気にあふれる地域社会を創っていくことを決意し再建したものです。」と記されています。常呂町農協、常呂漁協、北見市商工会常呂支所などが声を掛け合っての再建立したと聞いています。▼常呂の森づくり運動に取り組んだ小笠原敬さんが常々、次世代の人たちに伝えていた言葉「積小為大」は尊徳思想の柱になる言葉です。その実践的な取り組みとして、昭和、平成、令和の時代に引き継がれてきた常呂自治区の森づくり、植樹の地域づくりです。市長も、旧常呂町時代から引き継がれているその想いは十二分に理解していると思います。▼実は私も娘の小学校時代に地元のPTA代表としてオホーツクの森での植樹に参加した経験があります。日頃、浜で働く母さんたちが、「森は海の恋人・川は仲人なのよ」。と、慣れないスコップで穴を掘り、木の苗を植えていました。子どもたちの、子どもたちの、子どもたちのためになると信じて流す汗と笑顔、はっきりと記憶にあります。そういう森づくり運動、常呂川流域の植樹活動なんです。▼風力発電のためにと言われて、常呂のこれまでの地域づくりと相反する大規模な樹木伐採を、地域の住民は安易に容認できるものでしょうか?「風力発電は地球温暖化対策として国が進めているから」という確かに耳触りのいい言葉ですが、市有地の提供を市長は、どうお考えになりますか?▼もちろん、その判断には、幅広く意見を聞いて為されるものと考えます。今、核ごみ問題で注目の寿都町ではありませんが、市民の声をしっかりと聴くことは市民協働のまちづくり、民主的なプロセスとして欠かせません。▼6月末の北見自治区まちづくり協議会では、北見市は「自治区の地域づくりで審議したい事業について、積極的に提案してください」と伝えています。企業説明会では建設に賛成の意見がほとんど無かった風力発電計画です。▼もう特別職の自治区長もいません。市民と行政の相互理解と連携による地域の公共的・公益的課題の解決のためには北見市の自治区制度の要(かなめ)である常呂まちづくり協議会において、話し合いは必要ではないでしょうか。市長の考えをお聞きかせください。
●再々質問)意見・・・常呂自治区の地域づくりと風力発電について
▼まちづくり協議会での話し合いの必要性について、「常呂自治区におきまして、様々な声が寄せられていることから、今後、まちづくり協議会と協議を行ってまいりたいと考えています」という答弁をいただきました。ということは、まちづくり協議会での話し合いの必要性を認識したうえでの言葉と理解します。
▼オホーツクには世界自然遺産の知床半島、網走市にはラムサール条約に登録している水鳥たちの楽園・濤沸湖の他、網走湖、能取湖もあります。もちろん北見市常呂町には常呂川流域の野鳥の営巣地の他に北海道遺産であるワッカ原生花園、サロマ湖もあります。みんな鳥たちの眼からすれば命をつなげる貴重な生息地です。▼風力発電は従来の開発事業と異なり、「鳥類個体群に重大なインパクトをもたらす可能性があり、とりわけ慎重な影響評価が必要である」と、東京農大の白木准教授は研究報告書のまとめの言葉として記載しています。野鳥類の命を未来につなげる生息域が消失することは、常呂だけの影響ではなくオホーツク全域につながっていると想像してください。
▼常呂で行っている植林した樹木のCO2削減量は、風力発電にはとても及ぶものではありませんが、 「常呂町は昭和の時代から、風力発電に先駆けて、コツコツとCO2削減や森の保水力向上に取り組んでいる地域。」と、胸を張って言えます。との自治区住民の声も多くあります。
▼説明会において、企業は「風力発電は適度の風があれば何処でもできるのですが、常呂は道路沿いの建設になり、コストが安く済むからやらせてもらいたい。」と、正直に言っています。
▼市長の政治姿勢の柱は「笑顔ひろがる北見に!」です。誰が笑顔になるのでしょうか?企業は建設コストがかからないから笑顔。いったい何億円費用が浮くんでしょうか?北見市は借地料や固定資産税が入るので笑顔ですか?
▼温暖化対策と耳触りのいい言葉は、直接影響の及ばない人たちには机上の事務処理で済ませられる話かも知れませんが、誰の犠牲のうえに成り立つ話なのか?風車を身近に見上げて暮らす人たちの生活を想像してみてください。ほんとに笑顔になれるでしょうか?市有地を提供するか否かの市長判断は、自治区の市民を代表するまちづくり協議会での話し合いや関係者の声をしっかりと受けとめたうえで行っていただきたいです。
▼最後に紹介させていただきます。
「ピリカおかあさんへの旅」という鮭がふるさとの川へ帰る物語の絵本が2006年に発刊されました。この絵本は、常呂町民とご縁のある絵本作家の越智典子さんと画家の沢田としきさんが常呂の「森は海の恋人、川は仲人」、豊かな森づくり活動や命の連なりの話を聴いて、その精神に共鳴して、いつか常呂川の物語を絵本にしたいな。と、言っていたことを実現してくれたものです。その年の日本絵本賞に輝き、それを記念して、北見市まちづくりパワー支援事業を活用し、北見市4自治区で巡回原画展も行いました。
▼そして、時を過ぎて一昨年の11月、経済の伝書鳩に、「この絵本を幼児たちの愛読書のひとつにしている北見市内のぞみ幼稚園では、園児たちを常呂川支流のルクシニコロ川に連れて行き、絵本で読んだ川を遡上してきたサケと実際に出会う機会をつくった。」との記事が掲載されていました。常呂川と森を大切にする環境教育として、確実に次世代へとつながっています。
▼また、質問で紹介した「ところ通信」について、1999年朝日新聞8/22の全国版のコラム・スクエアに掲載された言葉の一部を紹介します
タイトルは「行政の意思映えるところ通信」。「過去を大切にする行政体の意思表示のように映る。過去を水に流す国は、未来も水に流す。といったイギリスの政治家がいたが、常呂町は水を大切にするために町の過去を捨てない姿勢をカタチにして見せた。99年までの10年間のところ通信の歳月の流れは常呂町の環境問題に対する進取性を伝える。」と、短い言葉ながら、当時の常呂町民へのエールをいただいていました。
もう合併した北見市だからと旧町時代の想いを無視できるものでしょうか。
▼私は、各自治区の個性、多様性を活かす地域づくりを、市民協働の力で理解し合い進める北見市であってほしいと願っています。市長、よろしくお願いします。
以上で、私の質問を終わります。