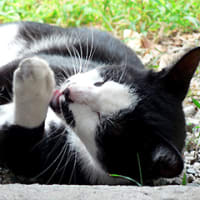今年に入って福島県内主要都市、郡山・福島・いわきの市長選挙で、三人の現職首長が揃って落選したが、昨日も二本松市の現職市長が新人候補に破れた。 敗因はいずれも福島第一原発事故後の除染や、復興の遅れによる住民の不安や不満によるものと、マスコミは伝える。 私は同じ県の住民として、必ずしもそれだけが落選理由とは思ってないが、こうした連鎖は町長選まで広がっており、さらに来年3期目を迎える知事選でも、現職が出馬すれば落選間違いなしとまで言われる。
「除染前2・3マイクロシーベルト/時⇒除染後0・33ミリシーベルト」 こうした掲示板を公共の場で多く目にするが、これまで兆円単位の膨大な費用を注ぎ込みながら、政府が長期の除染目標に掲げる 「1ミリシーベルト以下」を追い求めてきたこの国の財源は、いつまでもつのだろうか・・・。 「どんな微量でも放射線は危険である」 という国際放射線防御委員会(ICRP)の勧告を思い返すと、重篤な潔癖症を患い、狂ったように手を洗うハワード・ヒューズの映画の場面が蘇る。
地球上には自然放射線量の極めて強い地域が存在する。 例えば中国広東省・陽江県の線量は年間6・4ミリシーベルト、ブラジル・ガラバリ海岸では最高6ミリシーベルトに達する。 このうち中国・陽江県における調査では、年間死亡率が全国の10万人当たり6・7人に対し当県は6・1人、がん死亡率では10万人当たり66人に対して58人という平均より低い結果となっている。 こうした事実があってもなお、県民がナーバスに反応するのは、反発を恐れて誰も目標数値の引き上げに対し、正論として踏み込まなかったから。
ところが10月に除染の状況を検証するため来日した国際原子力機関(IAEA)の専門家チームが、政府の掲げる年1ミリシーベルトの除染目標について、「必ずしも達成する必要はない、環境回復に伴う効果対費用のバランスを考慮し、最適化すべき」 と報告書で助言した。 よくぞ言ってくれた!と意を強くした自民党の石破幹事長が、「報告書を分析するとともに、諸外国の基準がどうなっているのか、検討する必要がある」と述べた。 ちなみに世界の一般的基準は、概ね年20ミリシーベルト以下。
『「除染1ミリシーベルト」 の愚』 と題して政府の除染目標に異論を唱える日本人が居る。 福島県三春町に住む寺の住職で、芥川賞受賞作家の玄侑宗久氏である。 詳しくは「wiLL・2013年6月号」を一読願いたいが、面白いデータを紹介している。 年間1.5~3ミリシーベルトの線量域に住む人々が、イタリアでは全人口の71%、ハンガリー・53%、デンマーク・69%、ベルギー・76%、香港では驚くなかれ85パーセントに及ぶ。 日本では52パーセント、そして1・5ミリシーベルト以下の地域に住む日本人は、48パーセント。
「除染前2・3マイクロシーベルト/時⇒除染後0・33ミリシーベルト」 こうした掲示板を公共の場で多く目にするが、これまで兆円単位の膨大な費用を注ぎ込みながら、政府が長期の除染目標に掲げる 「1ミリシーベルト以下」を追い求めてきたこの国の財源は、いつまでもつのだろうか・・・。 「どんな微量でも放射線は危険である」 という国際放射線防御委員会(ICRP)の勧告を思い返すと、重篤な潔癖症を患い、狂ったように手を洗うハワード・ヒューズの映画の場面が蘇る。
地球上には自然放射線量の極めて強い地域が存在する。 例えば中国広東省・陽江県の線量は年間6・4ミリシーベルト、ブラジル・ガラバリ海岸では最高6ミリシーベルトに達する。 このうち中国・陽江県における調査では、年間死亡率が全国の10万人当たり6・7人に対し当県は6・1人、がん死亡率では10万人当たり66人に対して58人という平均より低い結果となっている。 こうした事実があってもなお、県民がナーバスに反応するのは、反発を恐れて誰も目標数値の引き上げに対し、正論として踏み込まなかったから。
ところが10月に除染の状況を検証するため来日した国際原子力機関(IAEA)の専門家チームが、政府の掲げる年1ミリシーベルトの除染目標について、「必ずしも達成する必要はない、環境回復に伴う効果対費用のバランスを考慮し、最適化すべき」 と報告書で助言した。 よくぞ言ってくれた!と意を強くした自民党の石破幹事長が、「報告書を分析するとともに、諸外国の基準がどうなっているのか、検討する必要がある」と述べた。 ちなみに世界の一般的基準は、概ね年20ミリシーベルト以下。
『「除染1ミリシーベルト」 の愚』 と題して政府の除染目標に異論を唱える日本人が居る。 福島県三春町に住む寺の住職で、芥川賞受賞作家の玄侑宗久氏である。 詳しくは「wiLL・2013年6月号」を一読願いたいが、面白いデータを紹介している。 年間1.5~3ミリシーベルトの線量域に住む人々が、イタリアでは全人口の71%、ハンガリー・53%、デンマーク・69%、ベルギー・76%、香港では驚くなかれ85パーセントに及ぶ。 日本では52パーセント、そして1・5ミリシーベルト以下の地域に住む日本人は、48パーセント。