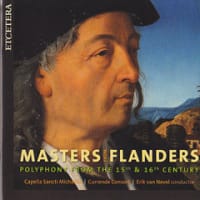ルーミー(1207年~73年)の『語録(その中にはその中にあるところのものがある)』とサーディー(1210年頃~92年頃)の『薔薇園』の読解を中心とした今回の「スーフィズム探求」の記事をいちおうまとめておこう。
☆ ☆ ☆
ルーミーもサーディーもスーフィズム(イスラーム神秘思想)の流れのなかに位置づけられるペルシアの思想家、詩人である。
スーフィズム自体はイスラーム史のなかでアッバース朝の中期におこってきた思想運動であるが、それは、イスラームの根源性を問うという極めてラディカルな側面とイスラームを民衆化していくという平俗な側面の二つの様相をもっていた。同時にスーフィズムは、この二つの側面から、アッバース朝(スンニー派)の体制化した信仰のあり方を問うというもう一つ別の様相をももっていた。
それゆえアッバース朝カリフ政権は、当初スーフィズムに対し高圧的にのぞみ、ハッラージュの処刑などを断行した。しかしそうした高圧的態度とは裏腹に、カリフ体制の弱体化がすすみ、カリフたちは新興軍事的権力にイスラーム社会の支配権をゆだね、みずからは名目的な地位を維持するに甘んじざるをえないという状態が続く。こうしたなかでカリフから支配権をゆだねられた軍事的勢力は次々に交代する。また一方で、地方にはアッバース朝カリフの権威を認めない独自のイスラーム政権が分立していく(その典型がスペインを根拠とし、前政権であるウマイア朝の正統的後継者を自認する後ウマイア朝)。ハッラージュ以降、スーフィズムの内部から優れた思想家が次々と生まれ思想運動が理論的に強化されたという事実を見逃すわけにはいかないが、全体的には、イスラーム社会の動揺、不安定化、分裂が、スーフィズムの運動を加速させたといっていいのではないだろうか。
私はそれは、平安時代から鎌倉時代にかけての日本社会の大動乱期に、法然、親鸞、一遍、栄西、道元、日蓮といった新たなタイプの仏教思想家が次々と登場した状況と非常によく似ているとおもう。そう考えて単純比較を行うと、ルーミーとサーディーは、親鸞(1173年~1262年)、道元(1200年~1253年)、日蓮(1222年~1282年)の同時代人であり、また二人の生きた時代に、日本同様ペルシア社会もモンゴル襲来という事態を迎え、最終的にアッバース朝のカリフが殺害され、異民族・異教徒によって支配されることになる(イル汗国の成立)。
こうなると、世俗的権力はもはやイスラームの宗教問題に対して権威をもって臨むことはできない。
一方、飲酒や同性愛は、イスラームの世界では宗教的=社会的禁忌であるが、アッバース朝の中期からその締め付けも弛んできた。社会全体のなかでそうした弛緩がどの程度進捗したかは不明だが、『薔薇園』を読むと支配階級や社会の上層部では、その禁忌はなかば公然と無視されていたことが窺える。またそれと同時に看過すべきでないのは、アッバース朝期には、たとえばペルシア社会は未だ完全にイスラーム化されておらず(「『中世におけるイスラームへの改宗』を著したリチャード・バレットは、イランの人名辞典に記された有力者の家系をたどり、いつからムスリム名(ムハンマド、ハサン、アリーなど)が登場するかを調べることによって、イスラーム化の進展度を類推しようとした。それによれば、アッバース朝が成立した750年の時点では、イランの全人口にしめるムスリムの割合はわずか8%にすぎなかった。しかし、9世紀はじめになると40%、10世紀には70~80%に達したという」佐藤次高氏『イスラーム世界の興隆』)、そうした非イスラームのペルシア人にとって、酒も同性愛も禁忌ではなかったという点である。そうした複合的社会での酒や同性愛への取締りの有効性にはおのずから限界があろう。
またいつの時代からかは不明であるが、公的には飲酒が禁じられているなかで飲酒が行われたため、非公式の酒場の酌人(サーキー、酒姫とも訳される)は少年が務めることが一般化し、飲酒と同性愛(少年愛)が結びつく要素が、イスラーム裏社会では強かったようだ。
さて、スーフィズムとイスラーム的禁忌の関係の歴史は不明だが、全体として、最後の審判による裁きと救済よりも、現実における神人合一を重視するスーフィズムが、禁忌を軽んじる傾向にあることは否定できないであろう。また、神人合一の恍惚感を「酩酊」と表現するスーフィズムの伝統からいっても、個人としての実行はともかく、飲酒も同性愛も観念的・比喩的表現としては否定されなかった。サーディー『薔薇園』に見られる同性愛の記述、続く世代であるハーフィズの詩に見られる酒の讃歌は、彼らが個人的にどのような行動をしていたかの証言としての前に、そうした観念的・象徴的なものとして受けとめられるべきであろう。
とりあえず同性愛にしぼってスーフィズムがらみのこの時代の様相をまとめると、ちょうど小ブログのNHK大河ドラマ『天地人』の記事(2月14日)に書いたような「信長型」と「謙信型」の2パターンの同性愛に似たものが、当時のイスラーム社会にも認められるのではないだろうか。それはつまり、法や社会的禁忌にわずらわされない権力者を中心とした快楽追求のための同性愛の実行(信長型)と、同性への愛をとおして理念的なものを求め、性欲の充足には必ずしも重点をおかない観念性の強い同性愛(謙信型)の2パターンであり、社会一般の同性愛傾向が「信長型」だとすれば、スーフィズムの文脈なかで言及される同性愛は「謙信型」に近かったようにおもう。実は『薔薇園』は、その二つの型の同性愛の存在をともに紹介している。
もちろん、思想としてのスーフィズムは以上のような同性愛に対する寛容にとどまらないさまざまな面をもち、それらの面もまた興味深い問題を含んでいるのだが、今回はとりあえず、13世紀イスラーム社のなかでスーフィズムと同性愛がどのような関係にあったかの一端を示唆しながら記事をおえたい。
最後に、その後のイスラーム社会の思想運動の展開について、ごく簡単な個人的見とおしを記しておく。
モンゴル侵入後、世俗化する一方のイスラーム社会のなかで、イスラーム法が規定する社会手的禁忌はかなり緩やかなかたちで運用されてきた。これは一つには、イスラーム社会には、キリスト教社会における教会のような組織がなく(ムハンマドはこうした組織をつくることを禁じている)、宗教法上の禁忌に対する違犯を取り締まる組織や権限の所在が不明確であったことが大きく影響しているとおもう。オスマン朝はたしかにアジア、アフリカ、ヨーロッパにまたがる大国家を構築しイスラーム世界の再統一を実現したが(ただしペルシアでは、モンゴル人の支配を脱した後、サファヴィー朝などの王朝が成立し、オスマン朝には従属していない)、スルタンの内政的権限は本質的に治安維持を中心としたものであり、歴代のスルタンはイスラーム法を厳格にまもることに強い関心をいだかなかったのではないだろうか。
近代に入り、ヨーロッパとイスラーム世界の社会格差が逆転するとともに、イスラーム社会のなかからも改革の動きがでてくる。思想的には、一方でイスラーム社会の世俗化・脱宗教化をさらにすすめて社会を近代化しようという動きが権力の側からでてくると同時に、そうした世俗化・脱宗教化への批判や抵抗も生じてくる。具体的には、それはスーフィズムへの批判、スーフィズム以前の状態への回帰と聖典の原典研究というかたちで登場し、しだいに民衆を巻き込んでいく。私はこれは、江戸時代の国学研究、『古事記』や『万葉集』への回帰に似た動きだとおもっている。
そして第二次世界大戦後は、一方で国家としての独立を達成しながら欧米との格差の拡大に悩み、それに石油、パレスチナなどの利権が複雑にからみ混乱を増しているのが現在のイスラーム世界の状況ではないだろうか。
どのようにしたらこの状況を改善できるか、即応的なこたえを出すといったことは私の手には負えないが、少なくともそれは、イスラーム社会のなかに人権思想を普及させるといった理念的提言では解決できないと私は考える。
現在のイスラーム社会がかかえる問題に対し、外部からなにか提言が可能だとすれば、それはまず現在のイスラーム社会が構築されてきたプロセスを詳細にふまえたうえで、イスラーム社会が耳を傾けうるものとしてなされるべきできないだろうか。小ブログのささやかな記事が、そのために少しでも役に立てばいいと、私はおもっている。
☆ ☆ ☆
ルーミーもサーディーもスーフィズム(イスラーム神秘思想)の流れのなかに位置づけられるペルシアの思想家、詩人である。
スーフィズム自体はイスラーム史のなかでアッバース朝の中期におこってきた思想運動であるが、それは、イスラームの根源性を問うという極めてラディカルな側面とイスラームを民衆化していくという平俗な側面の二つの様相をもっていた。同時にスーフィズムは、この二つの側面から、アッバース朝(スンニー派)の体制化した信仰のあり方を問うというもう一つ別の様相をももっていた。
それゆえアッバース朝カリフ政権は、当初スーフィズムに対し高圧的にのぞみ、ハッラージュの処刑などを断行した。しかしそうした高圧的態度とは裏腹に、カリフ体制の弱体化がすすみ、カリフたちは新興軍事的権力にイスラーム社会の支配権をゆだね、みずからは名目的な地位を維持するに甘んじざるをえないという状態が続く。こうしたなかでカリフから支配権をゆだねられた軍事的勢力は次々に交代する。また一方で、地方にはアッバース朝カリフの権威を認めない独自のイスラーム政権が分立していく(その典型がスペインを根拠とし、前政権であるウマイア朝の正統的後継者を自認する後ウマイア朝)。ハッラージュ以降、スーフィズムの内部から優れた思想家が次々と生まれ思想運動が理論的に強化されたという事実を見逃すわけにはいかないが、全体的には、イスラーム社会の動揺、不安定化、分裂が、スーフィズムの運動を加速させたといっていいのではないだろうか。
私はそれは、平安時代から鎌倉時代にかけての日本社会の大動乱期に、法然、親鸞、一遍、栄西、道元、日蓮といった新たなタイプの仏教思想家が次々と登場した状況と非常によく似ているとおもう。そう考えて単純比較を行うと、ルーミーとサーディーは、親鸞(1173年~1262年)、道元(1200年~1253年)、日蓮(1222年~1282年)の同時代人であり、また二人の生きた時代に、日本同様ペルシア社会もモンゴル襲来という事態を迎え、最終的にアッバース朝のカリフが殺害され、異民族・異教徒によって支配されることになる(イル汗国の成立)。
こうなると、世俗的権力はもはやイスラームの宗教問題に対して権威をもって臨むことはできない。
一方、飲酒や同性愛は、イスラームの世界では宗教的=社会的禁忌であるが、アッバース朝の中期からその締め付けも弛んできた。社会全体のなかでそうした弛緩がどの程度進捗したかは不明だが、『薔薇園』を読むと支配階級や社会の上層部では、その禁忌はなかば公然と無視されていたことが窺える。またそれと同時に看過すべきでないのは、アッバース朝期には、たとえばペルシア社会は未だ完全にイスラーム化されておらず(「『中世におけるイスラームへの改宗』を著したリチャード・バレットは、イランの人名辞典に記された有力者の家系をたどり、いつからムスリム名(ムハンマド、ハサン、アリーなど)が登場するかを調べることによって、イスラーム化の進展度を類推しようとした。それによれば、アッバース朝が成立した750年の時点では、イランの全人口にしめるムスリムの割合はわずか8%にすぎなかった。しかし、9世紀はじめになると40%、10世紀には70~80%に達したという」佐藤次高氏『イスラーム世界の興隆』)、そうした非イスラームのペルシア人にとって、酒も同性愛も禁忌ではなかったという点である。そうした複合的社会での酒や同性愛への取締りの有効性にはおのずから限界があろう。
またいつの時代からかは不明であるが、公的には飲酒が禁じられているなかで飲酒が行われたため、非公式の酒場の酌人(サーキー、酒姫とも訳される)は少年が務めることが一般化し、飲酒と同性愛(少年愛)が結びつく要素が、イスラーム裏社会では強かったようだ。
さて、スーフィズムとイスラーム的禁忌の関係の歴史は不明だが、全体として、最後の審判による裁きと救済よりも、現実における神人合一を重視するスーフィズムが、禁忌を軽んじる傾向にあることは否定できないであろう。また、神人合一の恍惚感を「酩酊」と表現するスーフィズムの伝統からいっても、個人としての実行はともかく、飲酒も同性愛も観念的・比喩的表現としては否定されなかった。サーディー『薔薇園』に見られる同性愛の記述、続く世代であるハーフィズの詩に見られる酒の讃歌は、彼らが個人的にどのような行動をしていたかの証言としての前に、そうした観念的・象徴的なものとして受けとめられるべきであろう。
とりあえず同性愛にしぼってスーフィズムがらみのこの時代の様相をまとめると、ちょうど小ブログのNHK大河ドラマ『天地人』の記事(2月14日)に書いたような「信長型」と「謙信型」の2パターンの同性愛に似たものが、当時のイスラーム社会にも認められるのではないだろうか。それはつまり、法や社会的禁忌にわずらわされない権力者を中心とした快楽追求のための同性愛の実行(信長型)と、同性への愛をとおして理念的なものを求め、性欲の充足には必ずしも重点をおかない観念性の強い同性愛(謙信型)の2パターンであり、社会一般の同性愛傾向が「信長型」だとすれば、スーフィズムの文脈なかで言及される同性愛は「謙信型」に近かったようにおもう。実は『薔薇園』は、その二つの型の同性愛の存在をともに紹介している。
もちろん、思想としてのスーフィズムは以上のような同性愛に対する寛容にとどまらないさまざまな面をもち、それらの面もまた興味深い問題を含んでいるのだが、今回はとりあえず、13世紀イスラーム社のなかでスーフィズムと同性愛がどのような関係にあったかの一端を示唆しながら記事をおえたい。
最後に、その後のイスラーム社会の思想運動の展開について、ごく簡単な個人的見とおしを記しておく。
モンゴル侵入後、世俗化する一方のイスラーム社会のなかで、イスラーム法が規定する社会手的禁忌はかなり緩やかなかたちで運用されてきた。これは一つには、イスラーム社会には、キリスト教社会における教会のような組織がなく(ムハンマドはこうした組織をつくることを禁じている)、宗教法上の禁忌に対する違犯を取り締まる組織や権限の所在が不明確であったことが大きく影響しているとおもう。オスマン朝はたしかにアジア、アフリカ、ヨーロッパにまたがる大国家を構築しイスラーム世界の再統一を実現したが(ただしペルシアでは、モンゴル人の支配を脱した後、サファヴィー朝などの王朝が成立し、オスマン朝には従属していない)、スルタンの内政的権限は本質的に治安維持を中心としたものであり、歴代のスルタンはイスラーム法を厳格にまもることに強い関心をいだかなかったのではないだろうか。
近代に入り、ヨーロッパとイスラーム世界の社会格差が逆転するとともに、イスラーム社会のなかからも改革の動きがでてくる。思想的には、一方でイスラーム社会の世俗化・脱宗教化をさらにすすめて社会を近代化しようという動きが権力の側からでてくると同時に、そうした世俗化・脱宗教化への批判や抵抗も生じてくる。具体的には、それはスーフィズムへの批判、スーフィズム以前の状態への回帰と聖典の原典研究というかたちで登場し、しだいに民衆を巻き込んでいく。私はこれは、江戸時代の国学研究、『古事記』や『万葉集』への回帰に似た動きだとおもっている。
そして第二次世界大戦後は、一方で国家としての独立を達成しながら欧米との格差の拡大に悩み、それに石油、パレスチナなどの利権が複雑にからみ混乱を増しているのが現在のイスラーム世界の状況ではないだろうか。
どのようにしたらこの状況を改善できるか、即応的なこたえを出すといったことは私の手には負えないが、少なくともそれは、イスラーム社会のなかに人権思想を普及させるといった理念的提言では解決できないと私は考える。
現在のイスラーム社会がかかえる問題に対し、外部からなにか提言が可能だとすれば、それはまず現在のイスラーム社会が構築されてきたプロセスを詳細にふまえたうえで、イスラーム社会が耳を傾けうるものとしてなされるべきできないだろうか。小ブログのささやかな記事が、そのために少しでも役に立てばいいと、私はおもっている。