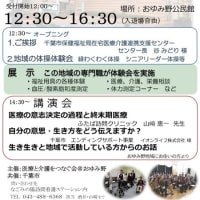新1年生は381人で、全校生徒は1080人を超える規模です。
2週間前までは小学生だった彼らは、体格の差が目立ち、でこぼこした列がなんとも入学式らしく微笑ましい光景です。
さて、呼名に応える一人ひとりを見守りながら、これから3年間、彼らにはどんなドラマが待っているのだろうかと想像し、悲喜こもごものたくさんの体験をしてほしいと思いました。
子育ての経験上、中学時代の3年間は彼らの中に育ってきている正義感を言語化し、彼らなりの人としての理想像を確立していく過程ではないかと感じています。
その過程は混沌としています。
なぜならまず、彼ら自身に、彼らが描く理想を実現する「力」が備わっていないので、常に理想と自分自身とのギャップにイライラするからです。
さらに、彼らが描く正義と現実の社会とのギャップにイラついたり失望を続ける・・・。
このような状況の中で、学校や地域や、あるいは政治に対して批判的な見方が出来るようになり、真っ当な指摘をして大人をドギマギさせるという、力が彼らには着実に育っていきます。
そんな彼らが見ているのは、最も身近な大人たちが、彼ら自身がおかしいと感じることにどう対処するかという大人の作法です。
中学校の入学式でいつも思うのは、この3年間は最も多感で揺れ動く激動の3年間であるということ。
だからこそ、彼らを支える大人がすべきことは、彼らに対して教え諭すのではなく、社会に相対する姿勢、その背を彼らに見せることではないかと思います。
大げさなことに聞こえるかもしれませんが、それは大したことではなく、たとえば親であれば我が子以外にも心を配るような簡単なこと。
教師であれば学校以外の地域に対して関心を持ち、地域資源を積極的に教材に取り入れることで、学校を地域社会とつなげること。それが彼らを守る基盤となります。
保護者会やPTAであれば、子どもたちが育ちやすい社会環境整備のために社会に対して働きかけるなど、内向きではない社会正義を実現する。
当然のことながら、政治に対してもその是非について毅然と意見を言い合い、今何がどう動こうとしているのか、大人の見方を示す。
そして願わくば、大人も間違い失敗するということと共にそれに対処する姿を見せ、正しいことだけが必ずしも良いことではない・・・と気づいてほしいのです。
その具体的な大人たちの動きを見せていくことが、多感な中学生には何よりも必要なのではないか、と感じています。