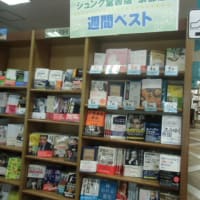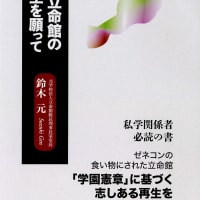N022 常任理事並びに関係各位へ
○疑惑に満ちた茨木土地購入、徹底解明が求められる
○日刊工業新聞インターネット版5月31日付「立命館大学茨木新キャンパス建設/竹中工務店で7月着工」と報道。学内世論と議論経過を無視して、あくまでも専断と独断で茨木建設工事を強行しようとする長田豊臣理事長等。
○常任理事会は急いで工事凍結を決議するとともに、茨木問題について司直の手にゆだねざるを得ないでしょう。
2013年6月5日 元総長理事長室室長 鈴木 元
目次
はじめに
(1) 理事会に売買契約書も提出されなかったサッポロホールディングスとの土地購入
1)立命館、サッポロホールディングス、竹中工務店の三者密約
2)立命館が茨木市分30億円を立て替えし190億円で購入したことによってサッポロは黒字となり外資は売り逃げだすことができた。
3)190億円もの土地購入にあたって理事会に契約書が提出されなかった
4)長田理事長の那須での別荘購入の全貌が明らかにされなくてはならない。
(2) 立命館、都市機構、茨木市の間での摩訶不思議な土地売買と、お金の流れ
1)立命館は茨木市の立て替え払いをする必要は無かった
2)立命館が30億円で購入した土地が都市機構を経由して、茨木市は56億円で購入したと見せかけた。
(3)サッポロとの土地購入契約書を理事会に提出しなかった理由
(3)毎年新たに少なくとも20億円の出費増を伴い、毎年30億円の支出削減を必要とする茨木新キャンパス構想は凍結するしかない。それをしないのは長田理事長、森島専務、川口総長、志方部長がサッポロ、竹中工務店と抜き差しならない約束を行い、何が何でも実行しなれば、竹中工務店から、約束(契約)違反で訴えられることを恐れているからである。これに対抗するためには凍結決議を行うとともに、理事会として長田理事長等を「背任容疑」で告訴するしかないでしょう
はじめに
茨木市の6月議会において、茨木市は都市機構(以下UR)を経由して立命館の社会開放型施設の敷地1.5haを26億7000万円で購入し、立命館に無償貸与するとの議案が出されることになった。社会開放型施設の敷地を茨木市が立命館に無償貸与すると言うのは当初から計画であった。問題はこの土地売買を巡る疑惑に満ちた動きである。新しい理事が多数おられるので改めて経緯を含めて整理し、問題を明確にしておきたい。
立命館は校地となる9haを160億円で購入した。その際、茨木市が建設する防災公園1.5haと立命館の社会開放型施設へ貸与する1.5haの合計3haを立命館が30億円立て替え払いして購入した。つまり12haを190億円で購入した。
その後2011年7月、立命館は、その3haを茨木市ではなくURに約52億円で売却した。URは、それに4億円上積みして56億円で茨木市に売却することにした。
長田理事長、森島常務(当時)が2010年7月の常任理事会に「茨木進出計画」を提案したとき、彼等は「茨木市から音楽ホールの建設など130億円の補助がでます」と説明した。しかし2010年の9月議会において、この真偽を確かめる議員の質問に対して市長は「どこからの情報か分かりませんが、そのような約束はしておりません」と答弁している。また森島常務が「音楽ホールや図書館など社会開放施設も作っていただける」と関係部門の教職員を説得していることについても「土地は市が用意しますが、建物は立命館の責任で建設されます」と回答している。事の初めから作り話による怪しげな話に満ちた提案であった。
その後、2010年11月10日の常任理事会で購入を決定する直前の11月3日の常任理事会において茨木キャンパス建設予算見込みとして400億円(土地代190億円、施設建設210億円)とし、その内茨木市から60億円の補助が出るとの一覧を提出した。それも「根拠にして」茨木キャンパス建設を5学部長の反対を押し切って強引に決定したのである。
ところが今回、森島専務らの報告によると、茨木市からの社会開放型施設建設補助は国費を含めて30億円と説明されている。差額30億円は今後の建設費用に関わる話である。なぜ60億円が30億円となったのか、その差額はどうするのか明確な回答が求められる。
一方、建設とかかわって前回のNO21で指摘したように、この間、森島専務などは「契約は理事長専決事項であり、常任理事会に諮らず直接、理事会に諮る」と言っていたかと思うと、ほとんどの学部長理事はおろか、常務理事の大半も、その詳細はおろか存在さえ知らなかった契約事務取扱規程なるものを根拠に「理事長の責任で契約し、理事会には報告事項とする」と言い出した。6月30日契約、7月1日から工事に入るとの情報が学内に流れた。210億円もの建設契約を常任理事会はおろか理事会にも諮らず、長田理事長の一存で行うことは、理事会(常任理事会)の議決権を否認する行為であり、学校法人の運営としては到底容認されるものではない。
なお川口清史総長は最近、2012年5月30日の常任理事会の議事「大阪茨木新キャンパスの基本設計の到達点と今後の取り組み」の中で、建築確認を合意したかのデマゴギーを振りまいているらしい。その時、常任理事会は総延床面積がこれまでの確認建築面積を超えていることの議論をしたが、基本設計に基づいて建築確認をした事実は無い。もしも川口総長があくまでもそのように確認したと言い張ったとしても、契約書の審議もなしに、それでもって竹中工務店に本年7月に着工すると言う事で確認したとは言えないことは明白である。
常任理事会は直ちに建設契約の凍結決議をあげ、長田理事長、森島専務等の暴走をとめ、既に提起しているように理事会の下に第三者も入った茨木問題調査委員会を設置し徹底調査を行い、調査結果に基づいて法的措置を含め厳格な対応が求められるであろう。
ここまで書いた時、5月31日付、日刊工業新聞のインターネツト版において「立命館大阪茨木新キャンパス建設/竹中工務店で7月着工」とかなり詳しく報道されていることを知った。
5月17付の朝日新聞夕刊は「京都の街 大学戻る」に特集的記事を掲載している。かつて国の政策によって都市部から出て行かざるを得なかった大学が、国の規制が緩和されたのを踏まえ、2018年からの18歳人口減を前に、同志社大学、龍谷大学、学園大学、仏教大学が京都市内にキャバスの充実を図ろうとしていることを報道している。これに対して「総合企画部の今村部長は『大阪府北部は若い人口が多く、兵庫県からも通いやすい。最高の立地』と話す」と報道している。また学内の大半の教職員が知らない間に、6月29日の茨木市での「新キャンパス構想説明会」のチラシ・ポスターが出来上がっていることと合わせると、日刊工業新聞の報道は当局が既成事実化を図るために意図的に流した可能性がある。
したがって「竹中工務店との『建設契約』は既に交わされている」のであろう。この間の一連の学内会議は既に竹中工務店と建設契約が交わされていることをごまかすためのセレモニーに過ぎなかったのであろう。
これら一連の行為は「背任行為である」と言われても何の不思議もない、久岡康成常勤監事を代表とする法人の監査機関が機能しないのであれば司直の手にゆだねる必要に迫られていると言っても過言ではない。
(1)理事会に売買契約書も提出されなかったサッポロホールディングスからの土地購入
1)立命館、サッポロホールディングス、竹中工務店の三者密約
2010年7月、長田理事長、森島常務等は突然「サッポロビール茨木工場跡地を購入し立命館の第三キャンパスを設置する」と提案し、夏休みを挟んだ10月末までに決定するとし、激論が交わされた。
当時、私は「立命館とサッポロホールディングス(サッポロビールの親会社、以下サッポロと記述)と竹中工務店の間に密約がある可能性が高い」「すなわち10月末までにサッポロから敷地を購入し、2015年開設に向けて竹中工務店に建設を発注する」との密約の存在の可能性を指摘した。
私がこの可能性を指摘したのは以下のような情報をつかんでいたからである。
マスコミに「立命館が茨木に進出」が報道された当時、関西の建設業者の間で「立命館の茨木建設は竹中が取ったらしい」との情報が流れた。そこで清水建設を除く大手ゼネコンが竹中工務店にたいして「今時、随意契約はダメだ、公開入札で行くべきだ」と詰め寄った。それに対して竹中工務店から「立命館の長田豊臣理事長のサインと公印が押印された『立命館、竹中工務店、サッポロとの三者の覚書』が示された。内容は上記したようなことであった。各社は『そこまで話が進んでいるなら仕方がない』『下請け、孫請けで仕事をもらおう』との話で分かれた」と言うものであった。
以上の情報から、私は長田理事長等が三者密約を行った可能性があると指摘したのである。ただ私は当時、「契約事務取扱規程」が2010年3月末に策定されていることは知らなかった。長田理事長等は、この規程を使って密約の覚書を作成したのであろう。当時私は、公印使用管理書類を調査する必要があると指摘した。公印は理事長といえども勝手に持ち出して使用することはできない。必ず公印使用管理書類に記載しなければならない。それを見れば長田理事長らが公印を使用したかどうかが明確になるからである。
一方、長田理事長等は私の指摘を無視ししながらも、自ら密約を示唆する言動を行った。
2010年9月25日の部次長会議において森島常務、続いて10月13日の常任理事会において長田理事長から「4月に、長田、森島、志方弘樹(当時・財務部付管財担当部長)の3名がサッポロを訪ね、茨木購入を申し入れたところ、相手側から7月末までに決定してほしい」と言われたが「学内手続きの事もあるので10月末に延期してもらった」と発言している。
その後、学内で意見が分かれ、10月末までに決定できる見通しが立たなくなった。その議論の最中、長田理事長は「決定しなければ、私のクビを差し出す(辞任)ぐらいでは済まない、立命館は大変なことになる」との趣旨の発言を行っている。
そして9月25日の常任理事会において、サッポロにたいして「延期の申し入れを行う」事を決定した。相手側から「役員会に諮らせてもらいます」との回答があつた。つまり10月末を延期すると言うのは役員会に諮らなければならないほどの事であった。その後サッポロから「11月12日までに」とされた。当時、こうした一連の流れに対して、川口総長は10月11日の組合との交渉の場において「商慣行に反することであるが認めてもらった」と答弁している。
そして11月12日の理事会において「茨木市が購入する3ha30億円を立命館が立て替えて購入する」ことを含めて12haを190億円で購入することを強引に決定した。
2)立命館が茨木市分30億円を立て替えし190億円で購入したことによって、サッポロは黒字となり外資は売り逃げすることができた。
当時、私が解明したが、サッポロの最大株主はアメリカのハゲタカファンドであるスティールパートナーズであつた。そしてサッポロの決算時期は3月末ではなく、12月末であった。当時サッポロは業績が落ち業界第六位となっていた。そこで遊休地を売却し連結決算で12月末に向けて決算を確定するために、各社の決算見通しを11月中旬までに確定するように指示していた。
11月12日、立命館は過半数の学生・教職員が在籍している6学部長理事の反対を押し切って立命館の歴史上はじめて多数決で購入を決定した。その会議の決定を待ち受けていたサッポロの役員会は当日、売却を決定した。そしてただちにホームページにおいて166億円の特別譲渡益(帳簿価格23億円、譲渡価格190億円)を得たことを発表した。それは翌13日の朝日新聞の朝刊にも報道されている。11月30日付の株主向け広報によると12月末の決算予測は当初の赤字予測に反して、資産売却によって22億円の黒字となったと報道している。
そして12月10日付の朝日新聞によると株式の調整後終値は、10月29日は317円、11月30日は339円そして12月10日は368円となっている。12月21日付の朝日新聞によるとスティールパートナーズは所有していたサッポロの株すべてを売却して撤収したとしている。
立命館が当初説明通り、校地として9haを160億円で購入しただけであればサッポロの決算は黒字とならなかった。茨木市の分3ha30億円を立て替え払いし12ha190億円で購入したことによってサッポロは黒字決算となったのである。立命館の行動はまさにサッポロ側の利益となったのである。
3)190億円も土地の購入にあたって契約書が提出されなかった
ところでこの190億円に及ぶ土地購入を決定した11月10日の常任理事会ならびに11月12日の理事会において売買契約書が提出されていない。ペーパー1枚に「12haを190億円で購入する」と記載されていただけであったとのことである。機関運営としては異常である。後に提起する疑問の解明を含めて、改めてサッポロと立命館の土地売買契約書を提出させる必要がある。
4)長田理事長の那須での別荘購入の全貌が明らかにされなくてはならない。
この当時「長田理事長が軽井沢で別荘を手に入れた」との情報が学内で流れた。常任理事会において誰も、そのことを発言・質問していないのに長田理事長は突然「自分の金で買ったもので、あれこれ言われる筋合いはない」との趣旨の発言をし、会議参加者を驚かせた。
「李下に冠を正さず」である。このような時に別荘を手に入れれば「そのお金の出所は」と疑問を持たれるのは当然である。彼は総長としての退職金は、家庭の事情で全額使用済みであった。残るお金は川本前理事長と共に常勤役員退任慰労金を倍額にして受け取った4000万円だけであった。その後、別荘の所在地は軽井沢ではなく那須であることが、彼から招待されて訪問した人の口から明らかにされ、本人からも「那須だ」「それほど高いものではない」と語られている。「何故、那須を選ばれたのですか」との質問に対して彼は「再婚した妻の出身地に近いから」と答えている(真偽は分からない)。
いずれにしても長田理事長の那須での別荘確保の全貌について、学園関係者が納得できるように明確にされなくてはならない。
(1) 立命館、都市機構、茨木市の間での不可思議な土地売買と、お金の流れ
1)立命館は茨木市の立て替え払いをする必要は無かった
茨木市がサッポロから土地を購入するのなら直接購入すればよいのである。ところが森島常務は「市の予算を決めるのは3月議会であり、サッポロが求めている10月末には間に合わないので、市から依頼されて立命館が立て替えて購入した」と説明した。「10月末に190億円で購入」した意味については既に述べた。
立て替え払いする根拠については作為的な話である。市のレベルの自治体は、いま直ぐに使用目的が決まっていなくても、適当な土地があった場合に購入できる仕組みとして第三セクターの土地開発公社を持っている。そこが先行取得しておいて、後に自治体おいて使用目的と予算が決まった段階で、自治体が土地開発公社から土地を購入する制度である。茨木市にも土地開発公社がある。したがって茨木市土地開発公社が11月に購入しておいて、後に市が土地開発公社から購入すれば済んだことである。
2)立命館が30億円で購入した土地が都市機構を経由して、茨木市は55億円で購入したと見せかけた。
ところが立命館が購入した3haは茨木市ではなく、都市機構に売却された。それも52億円と言う金額であった。不況下にわずか1年半後に30億円が52億円に化けたのである。その上に都市機構が3億円上積みし茨木市に55億円で売却された。都市機構は粗造成を行ったとしているが、右から左へ名義を移動させただけで3億円を手に入れた。都市機構がそのような「土地ころがし」をすることは許されないだろう。茨木市は「直接購入しておけば30億円で済んだものを55億円で購入した」のである。当時、私は「茨木市は市民に説明する義務があるだろう」と書いた。
市議会において市長は「市が立命館から買い取る値段は、立命館がサッポロから買った値段ではなく、その時の時価である。それが立命館が買った値段より高いか、低いかは分からない」と意味ありげな発言を行っていた。
前記したように、2010年7月、森島常務は「茨木市は立命館に130億円の補助を行っていただくことになっている」と発言している。しかし茨木市は「立命館の茨木進出を歓迎する」とは言っていたが「立命館誘致決議」は行っていない。その状況でしかも財政が厳しい今日、茨木市が立命館に130億円の補助などできない。そこで私は、都市機構をトンネルにして立命館に上積みのお金を渡す仕組みを考えた可能性があると記した。
私はNO21において「立命館は、サッポロから9haを160億円で購入した。茨木市の3haを立命館が30億円で立て替え払いして購入した。立命館が購入したのは1ha当たり17.7億円、茨木市は1ha当たり10億円、なぜそのように高いのか」と提起したが、長田理事長や森島専務は答えられなかった。
3)サッポロとの土地購入の契約書を理事会に提出しなかった理由
(1)において、私は立命館がサッポロから12haを190億円で購入した時、契約書が提出されていないことを問題にした。
契約書は2枚(立命館分9ha160億円と茨木市分3ha30億円)ではなく1枚(12ha190億円)であつたと推察される。それは2010年11月12日の理事会に提出された茨木購入提案において二つの提案ではなく、ただ一行で12ha190億円と一括提案されていることからも間違いではないだろう。
190億円を12haで割ると1ha当たり15.8億円となる。そうすると茨木市の3haは47,4億円となる、それでも55億円は高すぎる。そこで苦肉の策として考えたのが、JR茨木駅から線路に沿った市道の建設にあたってその用地幅10m長さ約400m=4haの土地を茨木市ではなく立命館がJRから購入し(6億円余り)、それを茨木市に無償で貸し付ける。市会で市長は「市がJRから購入する予定であったが、立命館が将来の学部構想のために用地面積を確保する必要があるので、立命館が購入し茨木市に無償で貸していただくことになった。市としては節約となった」と説明している。これで茨木市と立命館はプラス・マイナス・ゼロであり、いずれも得も損もしていないが、茨木市は「立命館から市道の土地を無償貸し付けされた」と言い、立命館は「茨木市から(都市機構を経由して)高い値段で購入してもらった」と言う事にしたのだと推察される。したがつて当初私が予測した「土地購入に関わって茨木市が立命館に差額で便宜を払った」と言う事ではなかったかと推察される。
それよりも問題は「9ha160億円」であろうが「12ha190億円」であろうが、いずれも当時の相場としては高すぎることである。せいぜい9ha90億円、12ha120億円程度であろう。明らかにサッポロの決算を黒字にするために破格に高い値段で購入したのである。
しかしこの子供だましは時間がたつにしたがって矛盾を表面化させることになるだろう。茨木市が幅10m長さ400mにも及ぶ市道を自ら所有しないで市道とすることは認められない。立命館は市に市道として永久的に貸与している土地面積を大学の校地面積として計算して新学部などの設置申請はできない。
なお常任理事会においては教学内容もしたがつて学部名称、学部規模も何も決まっていない心理総合系学部なるものを「2016年に茨木で開設する」と再び多数決で決定した。それを基に竹中工務店に建設発注しようとしている。ところが2013年6月29日に開催を予定されている茨木市における地元説明会への案内文書を見ると「2016年に向けて心理総合系学部の設置を検討しています」と記している。竹中工務店に発注するために学内では強引に「2016年心理総合系学部設置」を決定しておきながら、対外的には「検討中」としているのである。まさになりふり構わず建設だけを進めようとしている。
(2) 毎年新たに少なくとも20億円の出費増を伴い、毎年30億円の支出削減を必
要とする、茨木新キャンパス構想は凍結するしかない。それをしないのは長田理事長、森島専務、川口総長、志方部長がサッポロ、竹中工務店と抜き差しならない約束を行い、何が何でも実行しなれば、竹中工務店から、約束(契約)違反で訴えられることを恐れているからである。これに対抗するためには凍結決議を行うとともに理事会として長田理事長等を「背任容疑」で告訴するしかないでしょう。
この間、茨木新キャンパス構想に対する疑問が噴出する中で、常任理事会から様々な財政試算が提出されてきた。その結論は「新キャンパス開設によって、少なくとも毎年20億円の新たな出費増が必要である」「全学の建物更新と教学改革のためには毎年約30億円の支出削減が必要である」「そのためには奨学金の削減、休学者や中途退学者、留年者数に見合う実員の増加が必要、非常勤教員の削減、事務経費の削減など」が提起された。質の向上が最大の課題となっている今日、30億円の支出削減を捻出のために教学が分からない森島専務、志方財務部長等によって思いつきに提案されたものである。全学からの批判の前に「見上副総長を責任者とした検討委員会を設置し教学的妥当性を吟味して案をまとめる」としている。
しかし、この委員会は、2011年の全学協議会での確認の実践、ならびにR2020の「教育・研究の質の向上を第一とする」ための検討を目的としたものではなく、あくまでも茨木新キャンパス開設による20億円に及ぶ新たな支出増と、30億円の支出削減をどうして捻出するのかが出発になっており、結局のところ削減計画策定だけの作業となり、大学としては本末転倒の作業となるであろう。
以前にも記したが、経営学部に必要な施設はBKCで建設すれば20億円程度、政策科学部の新校舎を衣笠の内外で建設すれば、せいぜい50億円、両方足しても100億円は必要ではない。あらたな支出20億円増も必要でなくなる。その分を教育と研究の質の向上に充てるべきだろう。ここまで事態が明らかになった今、茨木新キャンパスは一旦凍結しかない。
にもかかわらず学内世論と議論経過を無視して、あくまでも茨木の新校舎建設を7月着工で竹中工務店に発注しようとしているのは長田理事長等が竹中工務店と密約を結んでいるからと判断せざるを得ない。
建設業界で三者密約問題が浮上した時、密約文書は竹中工務店の役員室の重要文書保管箱に入れられているとの情報を得ていたので、私は久岡康成常勤監事に対して監事の職務権限で竹中工務店に密約文書の提示を申し入れる必要があると提言した。しかし彼は動かなかった。このことを含めて改めて久岡康成常勤監事の責任は明確にしなければならないだろう。既に売買が終わったサッポロは文書を破棄している可能性がある。
密約文書の存在はサッポロならびに竹中工務店にとっては不利益な事ではないので、その存在が明らかになっても背任には当たらない。しかし長田豊臣理事長が理事会にも諮らず三者密約を結んでいたら、それは背任にあたる。
茨木建設の凍結を議決し、竹中工務店への工事発注が行われない場合、竹中工務店は「密約」を公表し、それを根拠に長田豊臣理事長等を「契約違反」「損害賠償」を求めて告訴する可能性が高い。長田理事長等はそれを恐れて、暴走しようとしている。
常任理事会は茨木建設の凍結決議を行うとともに、立命館の正常な運営のためには長田理事長等を「背任容疑」で告訴し司直の手にゆだねるしかないでしょう。
以上
○疑惑に満ちた茨木土地購入、徹底解明が求められる
○日刊工業新聞インターネット版5月31日付「立命館大学茨木新キャンパス建設/竹中工務店で7月着工」と報道。学内世論と議論経過を無視して、あくまでも専断と独断で茨木建設工事を強行しようとする長田豊臣理事長等。
○常任理事会は急いで工事凍結を決議するとともに、茨木問題について司直の手にゆだねざるを得ないでしょう。
2013年6月5日 元総長理事長室室長 鈴木 元
目次
はじめに
(1) 理事会に売買契約書も提出されなかったサッポロホールディングスとの土地購入
1)立命館、サッポロホールディングス、竹中工務店の三者密約
2)立命館が茨木市分30億円を立て替えし190億円で購入したことによってサッポロは黒字となり外資は売り逃げだすことができた。
3)190億円もの土地購入にあたって理事会に契約書が提出されなかった
4)長田理事長の那須での別荘購入の全貌が明らかにされなくてはならない。
(2) 立命館、都市機構、茨木市の間での摩訶不思議な土地売買と、お金の流れ
1)立命館は茨木市の立て替え払いをする必要は無かった
2)立命館が30億円で購入した土地が都市機構を経由して、茨木市は56億円で購入したと見せかけた。
(3)サッポロとの土地購入契約書を理事会に提出しなかった理由
(3)毎年新たに少なくとも20億円の出費増を伴い、毎年30億円の支出削減を必要とする茨木新キャンパス構想は凍結するしかない。それをしないのは長田理事長、森島専務、川口総長、志方部長がサッポロ、竹中工務店と抜き差しならない約束を行い、何が何でも実行しなれば、竹中工務店から、約束(契約)違反で訴えられることを恐れているからである。これに対抗するためには凍結決議を行うとともに、理事会として長田理事長等を「背任容疑」で告訴するしかないでしょう
はじめに
茨木市の6月議会において、茨木市は都市機構(以下UR)を経由して立命館の社会開放型施設の敷地1.5haを26億7000万円で購入し、立命館に無償貸与するとの議案が出されることになった。社会開放型施設の敷地を茨木市が立命館に無償貸与すると言うのは当初から計画であった。問題はこの土地売買を巡る疑惑に満ちた動きである。新しい理事が多数おられるので改めて経緯を含めて整理し、問題を明確にしておきたい。
立命館は校地となる9haを160億円で購入した。その際、茨木市が建設する防災公園1.5haと立命館の社会開放型施設へ貸与する1.5haの合計3haを立命館が30億円立て替え払いして購入した。つまり12haを190億円で購入した。
その後2011年7月、立命館は、その3haを茨木市ではなくURに約52億円で売却した。URは、それに4億円上積みして56億円で茨木市に売却することにした。
長田理事長、森島常務(当時)が2010年7月の常任理事会に「茨木進出計画」を提案したとき、彼等は「茨木市から音楽ホールの建設など130億円の補助がでます」と説明した。しかし2010年の9月議会において、この真偽を確かめる議員の質問に対して市長は「どこからの情報か分かりませんが、そのような約束はしておりません」と答弁している。また森島常務が「音楽ホールや図書館など社会開放施設も作っていただける」と関係部門の教職員を説得していることについても「土地は市が用意しますが、建物は立命館の責任で建設されます」と回答している。事の初めから作り話による怪しげな話に満ちた提案であった。
その後、2010年11月10日の常任理事会で購入を決定する直前の11月3日の常任理事会において茨木キャンパス建設予算見込みとして400億円(土地代190億円、施設建設210億円)とし、その内茨木市から60億円の補助が出るとの一覧を提出した。それも「根拠にして」茨木キャンパス建設を5学部長の反対を押し切って強引に決定したのである。
ところが今回、森島専務らの報告によると、茨木市からの社会開放型施設建設補助は国費を含めて30億円と説明されている。差額30億円は今後の建設費用に関わる話である。なぜ60億円が30億円となったのか、その差額はどうするのか明確な回答が求められる。
一方、建設とかかわって前回のNO21で指摘したように、この間、森島専務などは「契約は理事長専決事項であり、常任理事会に諮らず直接、理事会に諮る」と言っていたかと思うと、ほとんどの学部長理事はおろか、常務理事の大半も、その詳細はおろか存在さえ知らなかった契約事務取扱規程なるものを根拠に「理事長の責任で契約し、理事会には報告事項とする」と言い出した。6月30日契約、7月1日から工事に入るとの情報が学内に流れた。210億円もの建設契約を常任理事会はおろか理事会にも諮らず、長田理事長の一存で行うことは、理事会(常任理事会)の議決権を否認する行為であり、学校法人の運営としては到底容認されるものではない。
なお川口清史総長は最近、2012年5月30日の常任理事会の議事「大阪茨木新キャンパスの基本設計の到達点と今後の取り組み」の中で、建築確認を合意したかのデマゴギーを振りまいているらしい。その時、常任理事会は総延床面積がこれまでの確認建築面積を超えていることの議論をしたが、基本設計に基づいて建築確認をした事実は無い。もしも川口総長があくまでもそのように確認したと言い張ったとしても、契約書の審議もなしに、それでもって竹中工務店に本年7月に着工すると言う事で確認したとは言えないことは明白である。
常任理事会は直ちに建設契約の凍結決議をあげ、長田理事長、森島専務等の暴走をとめ、既に提起しているように理事会の下に第三者も入った茨木問題調査委員会を設置し徹底調査を行い、調査結果に基づいて法的措置を含め厳格な対応が求められるであろう。
ここまで書いた時、5月31日付、日刊工業新聞のインターネツト版において「立命館大阪茨木新キャンパス建設/竹中工務店で7月着工」とかなり詳しく報道されていることを知った。
5月17付の朝日新聞夕刊は「京都の街 大学戻る」に特集的記事を掲載している。かつて国の政策によって都市部から出て行かざるを得なかった大学が、国の規制が緩和されたのを踏まえ、2018年からの18歳人口減を前に、同志社大学、龍谷大学、学園大学、仏教大学が京都市内にキャバスの充実を図ろうとしていることを報道している。これに対して「総合企画部の今村部長は『大阪府北部は若い人口が多く、兵庫県からも通いやすい。最高の立地』と話す」と報道している。また学内の大半の教職員が知らない間に、6月29日の茨木市での「新キャンパス構想説明会」のチラシ・ポスターが出来上がっていることと合わせると、日刊工業新聞の報道は当局が既成事実化を図るために意図的に流した可能性がある。
したがって「竹中工務店との『建設契約』は既に交わされている」のであろう。この間の一連の学内会議は既に竹中工務店と建設契約が交わされていることをごまかすためのセレモニーに過ぎなかったのであろう。
これら一連の行為は「背任行為である」と言われても何の不思議もない、久岡康成常勤監事を代表とする法人の監査機関が機能しないのであれば司直の手にゆだねる必要に迫られていると言っても過言ではない。
(1)理事会に売買契約書も提出されなかったサッポロホールディングスからの土地購入
1)立命館、サッポロホールディングス、竹中工務店の三者密約
2010年7月、長田理事長、森島常務等は突然「サッポロビール茨木工場跡地を購入し立命館の第三キャンパスを設置する」と提案し、夏休みを挟んだ10月末までに決定するとし、激論が交わされた。
当時、私は「立命館とサッポロホールディングス(サッポロビールの親会社、以下サッポロと記述)と竹中工務店の間に密約がある可能性が高い」「すなわち10月末までにサッポロから敷地を購入し、2015年開設に向けて竹中工務店に建設を発注する」との密約の存在の可能性を指摘した。
私がこの可能性を指摘したのは以下のような情報をつかんでいたからである。
マスコミに「立命館が茨木に進出」が報道された当時、関西の建設業者の間で「立命館の茨木建設は竹中が取ったらしい」との情報が流れた。そこで清水建設を除く大手ゼネコンが竹中工務店にたいして「今時、随意契約はダメだ、公開入札で行くべきだ」と詰め寄った。それに対して竹中工務店から「立命館の長田豊臣理事長のサインと公印が押印された『立命館、竹中工務店、サッポロとの三者の覚書』が示された。内容は上記したようなことであった。各社は『そこまで話が進んでいるなら仕方がない』『下請け、孫請けで仕事をもらおう』との話で分かれた」と言うものであった。
以上の情報から、私は長田理事長等が三者密約を行った可能性があると指摘したのである。ただ私は当時、「契約事務取扱規程」が2010年3月末に策定されていることは知らなかった。長田理事長等は、この規程を使って密約の覚書を作成したのであろう。当時私は、公印使用管理書類を調査する必要があると指摘した。公印は理事長といえども勝手に持ち出して使用することはできない。必ず公印使用管理書類に記載しなければならない。それを見れば長田理事長らが公印を使用したかどうかが明確になるからである。
一方、長田理事長等は私の指摘を無視ししながらも、自ら密約を示唆する言動を行った。
2010年9月25日の部次長会議において森島常務、続いて10月13日の常任理事会において長田理事長から「4月に、長田、森島、志方弘樹(当時・財務部付管財担当部長)の3名がサッポロを訪ね、茨木購入を申し入れたところ、相手側から7月末までに決定してほしい」と言われたが「学内手続きの事もあるので10月末に延期してもらった」と発言している。
その後、学内で意見が分かれ、10月末までに決定できる見通しが立たなくなった。その議論の最中、長田理事長は「決定しなければ、私のクビを差し出す(辞任)ぐらいでは済まない、立命館は大変なことになる」との趣旨の発言を行っている。
そして9月25日の常任理事会において、サッポロにたいして「延期の申し入れを行う」事を決定した。相手側から「役員会に諮らせてもらいます」との回答があつた。つまり10月末を延期すると言うのは役員会に諮らなければならないほどの事であった。その後サッポロから「11月12日までに」とされた。当時、こうした一連の流れに対して、川口総長は10月11日の組合との交渉の場において「商慣行に反することであるが認めてもらった」と答弁している。
そして11月12日の理事会において「茨木市が購入する3ha30億円を立命館が立て替えて購入する」ことを含めて12haを190億円で購入することを強引に決定した。
2)立命館が茨木市分30億円を立て替えし190億円で購入したことによって、サッポロは黒字となり外資は売り逃げすることができた。
当時、私が解明したが、サッポロの最大株主はアメリカのハゲタカファンドであるスティールパートナーズであつた。そしてサッポロの決算時期は3月末ではなく、12月末であった。当時サッポロは業績が落ち業界第六位となっていた。そこで遊休地を売却し連結決算で12月末に向けて決算を確定するために、各社の決算見通しを11月中旬までに確定するように指示していた。
11月12日、立命館は過半数の学生・教職員が在籍している6学部長理事の反対を押し切って立命館の歴史上はじめて多数決で購入を決定した。その会議の決定を待ち受けていたサッポロの役員会は当日、売却を決定した。そしてただちにホームページにおいて166億円の特別譲渡益(帳簿価格23億円、譲渡価格190億円)を得たことを発表した。それは翌13日の朝日新聞の朝刊にも報道されている。11月30日付の株主向け広報によると12月末の決算予測は当初の赤字予測に反して、資産売却によって22億円の黒字となったと報道している。
そして12月10日付の朝日新聞によると株式の調整後終値は、10月29日は317円、11月30日は339円そして12月10日は368円となっている。12月21日付の朝日新聞によるとスティールパートナーズは所有していたサッポロの株すべてを売却して撤収したとしている。
立命館が当初説明通り、校地として9haを160億円で購入しただけであればサッポロの決算は黒字とならなかった。茨木市の分3ha30億円を立て替え払いし12ha190億円で購入したことによってサッポロは黒字決算となったのである。立命館の行動はまさにサッポロ側の利益となったのである。
3)190億円も土地の購入にあたって契約書が提出されなかった
ところでこの190億円に及ぶ土地購入を決定した11月10日の常任理事会ならびに11月12日の理事会において売買契約書が提出されていない。ペーパー1枚に「12haを190億円で購入する」と記載されていただけであったとのことである。機関運営としては異常である。後に提起する疑問の解明を含めて、改めてサッポロと立命館の土地売買契約書を提出させる必要がある。
4)長田理事長の那須での別荘購入の全貌が明らかにされなくてはならない。
この当時「長田理事長が軽井沢で別荘を手に入れた」との情報が学内で流れた。常任理事会において誰も、そのことを発言・質問していないのに長田理事長は突然「自分の金で買ったもので、あれこれ言われる筋合いはない」との趣旨の発言をし、会議参加者を驚かせた。
「李下に冠を正さず」である。このような時に別荘を手に入れれば「そのお金の出所は」と疑問を持たれるのは当然である。彼は総長としての退職金は、家庭の事情で全額使用済みであった。残るお金は川本前理事長と共に常勤役員退任慰労金を倍額にして受け取った4000万円だけであった。その後、別荘の所在地は軽井沢ではなく那須であることが、彼から招待されて訪問した人の口から明らかにされ、本人からも「那須だ」「それほど高いものではない」と語られている。「何故、那須を選ばれたのですか」との質問に対して彼は「再婚した妻の出身地に近いから」と答えている(真偽は分からない)。
いずれにしても長田理事長の那須での別荘確保の全貌について、学園関係者が納得できるように明確にされなくてはならない。
(1) 立命館、都市機構、茨木市の間での不可思議な土地売買と、お金の流れ
1)立命館は茨木市の立て替え払いをする必要は無かった
茨木市がサッポロから土地を購入するのなら直接購入すればよいのである。ところが森島常務は「市の予算を決めるのは3月議会であり、サッポロが求めている10月末には間に合わないので、市から依頼されて立命館が立て替えて購入した」と説明した。「10月末に190億円で購入」した意味については既に述べた。
立て替え払いする根拠については作為的な話である。市のレベルの自治体は、いま直ぐに使用目的が決まっていなくても、適当な土地があった場合に購入できる仕組みとして第三セクターの土地開発公社を持っている。そこが先行取得しておいて、後に自治体おいて使用目的と予算が決まった段階で、自治体が土地開発公社から土地を購入する制度である。茨木市にも土地開発公社がある。したがって茨木市土地開発公社が11月に購入しておいて、後に市が土地開発公社から購入すれば済んだことである。
2)立命館が30億円で購入した土地が都市機構を経由して、茨木市は55億円で購入したと見せかけた。
ところが立命館が購入した3haは茨木市ではなく、都市機構に売却された。それも52億円と言う金額であった。不況下にわずか1年半後に30億円が52億円に化けたのである。その上に都市機構が3億円上積みし茨木市に55億円で売却された。都市機構は粗造成を行ったとしているが、右から左へ名義を移動させただけで3億円を手に入れた。都市機構がそのような「土地ころがし」をすることは許されないだろう。茨木市は「直接購入しておけば30億円で済んだものを55億円で購入した」のである。当時、私は「茨木市は市民に説明する義務があるだろう」と書いた。
市議会において市長は「市が立命館から買い取る値段は、立命館がサッポロから買った値段ではなく、その時の時価である。それが立命館が買った値段より高いか、低いかは分からない」と意味ありげな発言を行っていた。
前記したように、2010年7月、森島常務は「茨木市は立命館に130億円の補助を行っていただくことになっている」と発言している。しかし茨木市は「立命館の茨木進出を歓迎する」とは言っていたが「立命館誘致決議」は行っていない。その状況でしかも財政が厳しい今日、茨木市が立命館に130億円の補助などできない。そこで私は、都市機構をトンネルにして立命館に上積みのお金を渡す仕組みを考えた可能性があると記した。
私はNO21において「立命館は、サッポロから9haを160億円で購入した。茨木市の3haを立命館が30億円で立て替え払いして購入した。立命館が購入したのは1ha当たり17.7億円、茨木市は1ha当たり10億円、なぜそのように高いのか」と提起したが、長田理事長や森島専務は答えられなかった。
3)サッポロとの土地購入の契約書を理事会に提出しなかった理由
(1)において、私は立命館がサッポロから12haを190億円で購入した時、契約書が提出されていないことを問題にした。
契約書は2枚(立命館分9ha160億円と茨木市分3ha30億円)ではなく1枚(12ha190億円)であつたと推察される。それは2010年11月12日の理事会に提出された茨木購入提案において二つの提案ではなく、ただ一行で12ha190億円と一括提案されていることからも間違いではないだろう。
190億円を12haで割ると1ha当たり15.8億円となる。そうすると茨木市の3haは47,4億円となる、それでも55億円は高すぎる。そこで苦肉の策として考えたのが、JR茨木駅から線路に沿った市道の建設にあたってその用地幅10m長さ約400m=4haの土地を茨木市ではなく立命館がJRから購入し(6億円余り)、それを茨木市に無償で貸し付ける。市会で市長は「市がJRから購入する予定であったが、立命館が将来の学部構想のために用地面積を確保する必要があるので、立命館が購入し茨木市に無償で貸していただくことになった。市としては節約となった」と説明している。これで茨木市と立命館はプラス・マイナス・ゼロであり、いずれも得も損もしていないが、茨木市は「立命館から市道の土地を無償貸し付けされた」と言い、立命館は「茨木市から(都市機構を経由して)高い値段で購入してもらった」と言う事にしたのだと推察される。したがつて当初私が予測した「土地購入に関わって茨木市が立命館に差額で便宜を払った」と言う事ではなかったかと推察される。
それよりも問題は「9ha160億円」であろうが「12ha190億円」であろうが、いずれも当時の相場としては高すぎることである。せいぜい9ha90億円、12ha120億円程度であろう。明らかにサッポロの決算を黒字にするために破格に高い値段で購入したのである。
しかしこの子供だましは時間がたつにしたがって矛盾を表面化させることになるだろう。茨木市が幅10m長さ400mにも及ぶ市道を自ら所有しないで市道とすることは認められない。立命館は市に市道として永久的に貸与している土地面積を大学の校地面積として計算して新学部などの設置申請はできない。
なお常任理事会においては教学内容もしたがつて学部名称、学部規模も何も決まっていない心理総合系学部なるものを「2016年に茨木で開設する」と再び多数決で決定した。それを基に竹中工務店に建設発注しようとしている。ところが2013年6月29日に開催を予定されている茨木市における地元説明会への案内文書を見ると「2016年に向けて心理総合系学部の設置を検討しています」と記している。竹中工務店に発注するために学内では強引に「2016年心理総合系学部設置」を決定しておきながら、対外的には「検討中」としているのである。まさになりふり構わず建設だけを進めようとしている。
(2) 毎年新たに少なくとも20億円の出費増を伴い、毎年30億円の支出削減を必
要とする、茨木新キャンパス構想は凍結するしかない。それをしないのは長田理事長、森島専務、川口総長、志方部長がサッポロ、竹中工務店と抜き差しならない約束を行い、何が何でも実行しなれば、竹中工務店から、約束(契約)違反で訴えられることを恐れているからである。これに対抗するためには凍結決議を行うとともに理事会として長田理事長等を「背任容疑」で告訴するしかないでしょう。
この間、茨木新キャンパス構想に対する疑問が噴出する中で、常任理事会から様々な財政試算が提出されてきた。その結論は「新キャンパス開設によって、少なくとも毎年20億円の新たな出費増が必要である」「全学の建物更新と教学改革のためには毎年約30億円の支出削減が必要である」「そのためには奨学金の削減、休学者や中途退学者、留年者数に見合う実員の増加が必要、非常勤教員の削減、事務経費の削減など」が提起された。質の向上が最大の課題となっている今日、30億円の支出削減を捻出のために教学が分からない森島専務、志方財務部長等によって思いつきに提案されたものである。全学からの批判の前に「見上副総長を責任者とした検討委員会を設置し教学的妥当性を吟味して案をまとめる」としている。
しかし、この委員会は、2011年の全学協議会での確認の実践、ならびにR2020の「教育・研究の質の向上を第一とする」ための検討を目的としたものではなく、あくまでも茨木新キャンパス開設による20億円に及ぶ新たな支出増と、30億円の支出削減をどうして捻出するのかが出発になっており、結局のところ削減計画策定だけの作業となり、大学としては本末転倒の作業となるであろう。
以前にも記したが、経営学部に必要な施設はBKCで建設すれば20億円程度、政策科学部の新校舎を衣笠の内外で建設すれば、せいぜい50億円、両方足しても100億円は必要ではない。あらたな支出20億円増も必要でなくなる。その分を教育と研究の質の向上に充てるべきだろう。ここまで事態が明らかになった今、茨木新キャンパスは一旦凍結しかない。
にもかかわらず学内世論と議論経過を無視して、あくまでも茨木の新校舎建設を7月着工で竹中工務店に発注しようとしているのは長田理事長等が竹中工務店と密約を結んでいるからと判断せざるを得ない。
建設業界で三者密約問題が浮上した時、密約文書は竹中工務店の役員室の重要文書保管箱に入れられているとの情報を得ていたので、私は久岡康成常勤監事に対して監事の職務権限で竹中工務店に密約文書の提示を申し入れる必要があると提言した。しかし彼は動かなかった。このことを含めて改めて久岡康成常勤監事の責任は明確にしなければならないだろう。既に売買が終わったサッポロは文書を破棄している可能性がある。
密約文書の存在はサッポロならびに竹中工務店にとっては不利益な事ではないので、その存在が明らかになっても背任には当たらない。しかし長田豊臣理事長が理事会にも諮らず三者密約を結んでいたら、それは背任にあたる。
茨木建設の凍結を議決し、竹中工務店への工事発注が行われない場合、竹中工務店は「密約」を公表し、それを根拠に長田豊臣理事長等を「契約違反」「損害賠償」を求めて告訴する可能性が高い。長田理事長等はそれを恐れて、暴走しようとしている。
常任理事会は茨木建設の凍結決議を行うとともに、立命館の正常な運営のためには長田理事長等を「背任容疑」で告訴し司直の手にゆだねるしかないでしょう。
以上