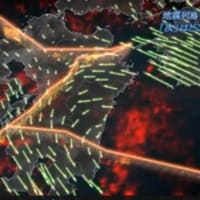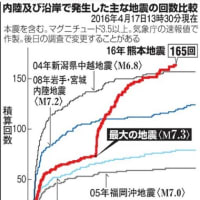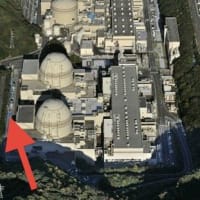「『打てない』から『打てる』という空想への転換」
長島監督の用いたビデオは、今中を打ち込んだ場面だけが編集されていました。
このシーズン、巨人は今中にコテンパンにやられていたのです。そこで、監督は、今中を打ち込んだ場面だけを編集して、選手に見せたのです。その結果、選手たちの空想が、「今中は打てない」から、「今中を打てる」に転換したわけです。
長嶋監督は選手たちの空想を変えようと目論んだのです。それまで巨人軍選手の脳裏に刻みこまれていた今中への苦手意識を、払拭させようとしたのです。
しかし、ここで注目すべきは、このビデオはわずか十三分という短いものだったということです。長いシーズンでたった十三分ですよ。
つまり、今中を打っている場面は、それほど少なかったということです。それなのに、どうして選手たちは「今中を打てる」という気になったのでしょう。これが心の作用の特徴なのです。
心というのは不思議なもので、客観的な事実よりも、インパクトの強さに大きく影響されます。そこで、今中を打った場面ばかり――自分たちにとって都合のよい事実ばかり――を集めたビデを見ると、それが実際には全体の中のごく一部にしかすぎなくても、あたかも全体像であるかのような錯覚が生じるのです。それが長嶋監督の狙いでした。
実は、暗示というのは、多かれ少なかれ、こういう心の性質をうまく用いているわけです。ある事態の断片とか、一部をハイライトすることで、それが全体像であるかのような錯覚を与えるのです。
こういうやり方は、戦争の広報でよく見られます。たとえば、最近では、イラク戦争で、米軍が、自分達のいいところばかりをテレビに映していたようです。
そもそも広報とはそういう面があるのかもしれません。ある特殊な事実でもってイメージを与えようとする。そういう手法には、我々は常に注意しなければなりません。しかし、人間を元気にするために、こういう手法が使えるときもあるのです。暗示を用いようとする人は、志が低くては困ります。
長島監督の用いたビデオは、今中を打ち込んだ場面だけが編集されていました。
このシーズン、巨人は今中にコテンパンにやられていたのです。そこで、監督は、今中を打ち込んだ場面だけを編集して、選手に見せたのです。その結果、選手たちの空想が、「今中は打てない」から、「今中を打てる」に転換したわけです。
長嶋監督は選手たちの空想を変えようと目論んだのです。それまで巨人軍選手の脳裏に刻みこまれていた今中への苦手意識を、払拭させようとしたのです。
しかし、ここで注目すべきは、このビデオはわずか十三分という短いものだったということです。長いシーズンでたった十三分ですよ。
つまり、今中を打っている場面は、それほど少なかったということです。それなのに、どうして選手たちは「今中を打てる」という気になったのでしょう。これが心の作用の特徴なのです。
心というのは不思議なもので、客観的な事実よりも、インパクトの強さに大きく影響されます。そこで、今中を打った場面ばかり――自分たちにとって都合のよい事実ばかり――を集めたビデを見ると、それが実際には全体の中のごく一部にしかすぎなくても、あたかも全体像であるかのような錯覚が生じるのです。それが長嶋監督の狙いでした。
実は、暗示というのは、多かれ少なかれ、こういう心の性質をうまく用いているわけです。ある事態の断片とか、一部をハイライトすることで、それが全体像であるかのような錯覚を与えるのです。
こういうやり方は、戦争の広報でよく見られます。たとえば、最近では、イラク戦争で、米軍が、自分達のいいところばかりをテレビに映していたようです。
そもそも広報とはそういう面があるのかもしれません。ある特殊な事実でもってイメージを与えようとする。そういう手法には、我々は常に注意しなければなりません。しかし、人間を元気にするために、こういう手法が使えるときもあるのです。暗示を用いようとする人は、志が低くては困ります。