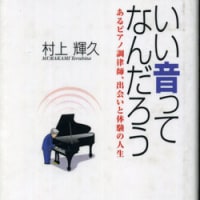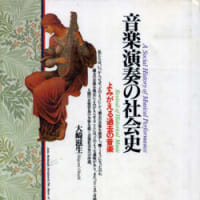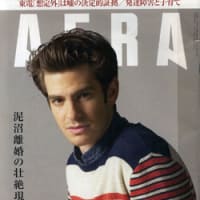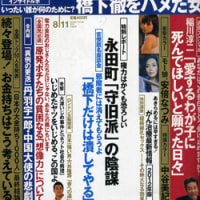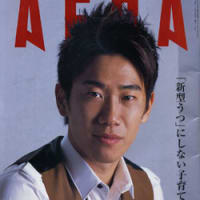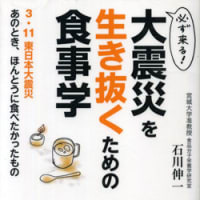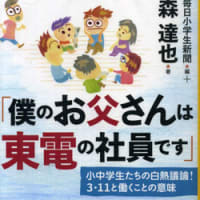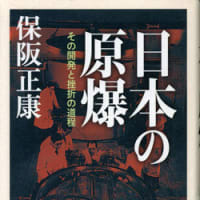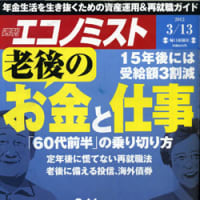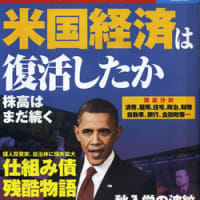『原子力発電をどうするか-日本のエネルギー政策の再生に向けて-』
橘川武郎・著/名古屋大学出版会2011年
帯に書かれてあります。下「」引用。
「現実的なシナリオとは何か
エネルギー産業史研究の第一人者が、もっとも現実的で、かつ総合性に富んだ最適解を示す。歴史的難題をこえて、日本のエネルギー政策に新たな展望をひらくために、いま必要な取り組みを信頼できる叙述で明快に論じた、渾身の提言。」

本書は……。下「」引用。
「本書は、二○一一年三月一一日の東日本大震災にともない発生した東京電力・福島第一原子力発電所事故をふまえて、日本における今後の原子力発電のあり方を論じたものである。執筆時点は、おおむね事故発生から三カ月余りが経過した二○一一年六月中旬から下旬にかけてであり、その後の事態の進展については、本書の記述に反映されていない。」
ビスマルクの名言。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
日本では「歴史は役に立たない」と、カリキュラムから消滅したケースが目立つようになっていたという。
歴史的文脈(コンテクスト)【応用経営史】 下「」引用。
「一般的に言って、特定の産業や企業が直面する深刻な問題を根本的に解決しようとするときには、どんなに「立派な理念」や「正しい理論」掲げても、それを、その産業や企業がおかれた歴史的文脈(コンテクスト)のなかにあてはめて適用しなければ、効果をあげることができない。また、問題解決のためには多大なエネルギーを必要とするが、それが生み出される根拠となるのは、当該産業や当該企業が内包している発展のダイナミズムである。ただし、このダイナミズムは、多くの場合、潜在化しており、それを析出するためには、その産業や企業の長期間にわたる変遷を濃密に観察することから出発しなければならない。観察から出発して発展のダイナミズムを把握することができれば、それに準拠して問題解決に必要なエネルギーを獲得する道筋がみえてくる。そしてさらには、そのエネルギーをコンテクストにあてはめ、適切な理念や理論と結びつけて、問題解決を現実化する道筋も展望しうる、……これが、応用経営史の考え方である。」
本書のねらい。下「」引用。
「本書のねらいは、東京電力・福島第一原子力発電所事故後の日本の原子力発電所のあり方について考察を加えることにある。-略-」
電力自由化は、「九電力体制の突然死」……。下「」引用。
「九電力会社のなかには、原子力発電所事業の分離がアンバンドリングにつながることを懸念する声があるという。しかし、〔中略〕二○○○年の時点で、九電力会社の電源構成に占める原子力の比率は発電設備出力で二一・八%、発電電力量で三八・一%であり、原子力発電事業を分離しても、発送配電一貫の維持に十分に可能である。むしろ、アンバンドリングをもたらしかねないのは、「国策民営」の原子力事業を、九電力会社経営の内部に抱え続けた場合である。原子力事業を内部化しているがゆえに、九電力会社が私企業性を十分に発揮できず、相互間の競争に熱心でないような状況が現出すれば、その状況を打開するため、電力自由化は、「九電力体制の突然死」を意味するアンバンドリングに行き着くかもしれないのである。」
それよりも、住民の死かいな??? 既得権益恐るべし!!!
河野一郎(河野太郎の祖父)vs.正力松太郎。下「」引用。
「原子力発電の受入れ主体をめぐって、政府主導を主張する電源開発(株)と、民間主導を主張する九電力会社との見解が真っ向から対立したことは、そのような軋轢の一例と言える。電源開発(株)と電力会社との見解の対立は政界にも及び、経済企画庁長官河野一郎と原子力委員長正力松太郎との論争を生んだ。この論争で、河野は電源開発(株)寄りの姿勢をとり、正力は九電力会社に近い立場を示した。
結局、この論争は政治的決着をみた。一九五七年八月に行われた河野経済企画庁長官と正力原子力委員長との会談で妥協が成立し、それをふまえて、同年九月の閣議で、「受入れ会社に対する出資比率は、政府関係(電源開発(株))二○%、民間八○%とし、民間の内訳は、おおむね九電力会社四○%、その他一般四○%を目途とする。-略-この閣議了解にもとづいて受入れ会社の設立手続きが進められ、一九五七年一一月に日本原子力発電株式会社が発足した。」
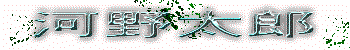 index
index
 index
index
シェールガス。下「」引用。
「残念ながら、わが国ではシェールガスは産出しない。しかし、アメリカでの「シェールガス革命」は、アメリカでのシェールガスの大量生産→アメリカの天然ガス輸入の減少→国際市場での天然ガス需給の緩和、という脈略を通じて、日本の天然ガス調達にも好影響をもたらす。最近では、長いあいだ国際市場で原油価格と連動してきた天然ガス価格が、そのような「油価リンク」から離脱して、相対的に低価格を示す傾向が目立つようになった。」
将来的には【石炭火力】 下「」引用。
「日本の石炭火力技術は、将来的には、IGCC(石炭ガス化複合発電)、IGFC(石炭ガス化燃料電池複合発電)、CCS(二酸化炭素回収貯留)など実現することによって、石炭火力発電自体のゼロ・エミッション電源(二酸化炭素をほとんど排出しない電源)化を実現する可能性がある。-略-」


橘川武郎・著/名古屋大学出版会2011年
帯に書かれてあります。下「」引用。
「現実的なシナリオとは何か
エネルギー産業史研究の第一人者が、もっとも現実的で、かつ総合性に富んだ最適解を示す。歴史的難題をこえて、日本のエネルギー政策に新たな展望をひらくために、いま必要な取り組みを信頼できる叙述で明快に論じた、渾身の提言。」

本書は……。下「」引用。
「本書は、二○一一年三月一一日の東日本大震災にともない発生した東京電力・福島第一原子力発電所事故をふまえて、日本における今後の原子力発電のあり方を論じたものである。執筆時点は、おおむね事故発生から三カ月余りが経過した二○一一年六月中旬から下旬にかけてであり、その後の事態の進展については、本書の記述に反映されていない。」
ビスマルクの名言。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
日本では「歴史は役に立たない」と、カリキュラムから消滅したケースが目立つようになっていたという。
歴史的文脈(コンテクスト)【応用経営史】 下「」引用。
「一般的に言って、特定の産業や企業が直面する深刻な問題を根本的に解決しようとするときには、どんなに「立派な理念」や「正しい理論」掲げても、それを、その産業や企業がおかれた歴史的文脈(コンテクスト)のなかにあてはめて適用しなければ、効果をあげることができない。また、問題解決のためには多大なエネルギーを必要とするが、それが生み出される根拠となるのは、当該産業や当該企業が内包している発展のダイナミズムである。ただし、このダイナミズムは、多くの場合、潜在化しており、それを析出するためには、その産業や企業の長期間にわたる変遷を濃密に観察することから出発しなければならない。観察から出発して発展のダイナミズムを把握することができれば、それに準拠して問題解決に必要なエネルギーを獲得する道筋がみえてくる。そしてさらには、そのエネルギーをコンテクストにあてはめ、適切な理念や理論と結びつけて、問題解決を現実化する道筋も展望しうる、……これが、応用経営史の考え方である。」
本書のねらい。下「」引用。
「本書のねらいは、東京電力・福島第一原子力発電所事故後の日本の原子力発電所のあり方について考察を加えることにある。-略-」
電力自由化は、「九電力体制の突然死」……。下「」引用。
「九電力会社のなかには、原子力発電所事業の分離がアンバンドリングにつながることを懸念する声があるという。しかし、〔中略〕二○○○年の時点で、九電力会社の電源構成に占める原子力の比率は発電設備出力で二一・八%、発電電力量で三八・一%であり、原子力発電事業を分離しても、発送配電一貫の維持に十分に可能である。むしろ、アンバンドリングをもたらしかねないのは、「国策民営」の原子力事業を、九電力会社経営の内部に抱え続けた場合である。原子力事業を内部化しているがゆえに、九電力会社が私企業性を十分に発揮できず、相互間の競争に熱心でないような状況が現出すれば、その状況を打開するため、電力自由化は、「九電力体制の突然死」を意味するアンバンドリングに行き着くかもしれないのである。」
それよりも、住民の死かいな??? 既得権益恐るべし!!!
河野一郎(河野太郎の祖父)vs.正力松太郎。下「」引用。
「原子力発電の受入れ主体をめぐって、政府主導を主張する電源開発(株)と、民間主導を主張する九電力会社との見解が真っ向から対立したことは、そのような軋轢の一例と言える。電源開発(株)と電力会社との見解の対立は政界にも及び、経済企画庁長官河野一郎と原子力委員長正力松太郎との論争を生んだ。この論争で、河野は電源開発(株)寄りの姿勢をとり、正力は九電力会社に近い立場を示した。
結局、この論争は政治的決着をみた。一九五七年八月に行われた河野経済企画庁長官と正力原子力委員長との会談で妥協が成立し、それをふまえて、同年九月の閣議で、「受入れ会社に対する出資比率は、政府関係(電源開発(株))二○%、民間八○%とし、民間の内訳は、おおむね九電力会社四○%、その他一般四○%を目途とする。-略-この閣議了解にもとづいて受入れ会社の設立手続きが進められ、一九五七年一一月に日本原子力発電株式会社が発足した。」
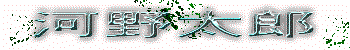 index
index index
indexシェールガス。下「」引用。
「残念ながら、わが国ではシェールガスは産出しない。しかし、アメリカでの「シェールガス革命」は、アメリカでのシェールガスの大量生産→アメリカの天然ガス輸入の減少→国際市場での天然ガス需給の緩和、という脈略を通じて、日本の天然ガス調達にも好影響をもたらす。最近では、長いあいだ国際市場で原油価格と連動してきた天然ガス価格が、そのような「油価リンク」から離脱して、相対的に低価格を示す傾向が目立つようになった。」
将来的には【石炭火力】 下「」引用。
「日本の石炭火力技術は、将来的には、IGCC(石炭ガス化複合発電)、IGFC(石炭ガス化燃料電池複合発電)、CCS(二酸化炭素回収貯留)など実現することによって、石炭火力発電自体のゼロ・エミッション電源(二酸化炭素をほとんど排出しない電源)化を実現する可能性がある。-略-」