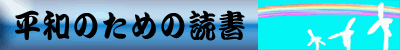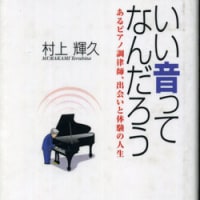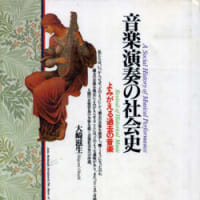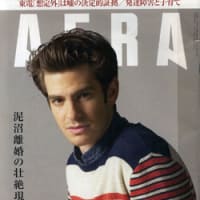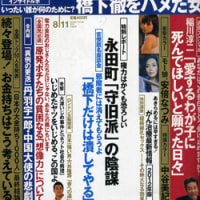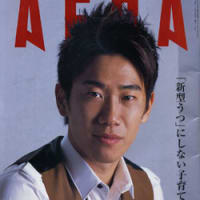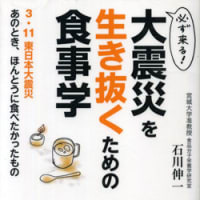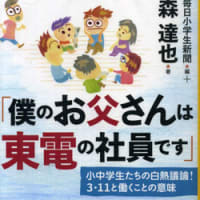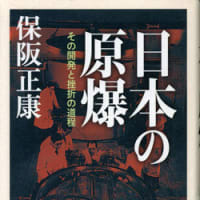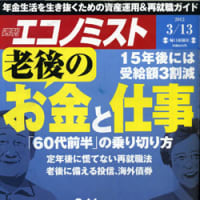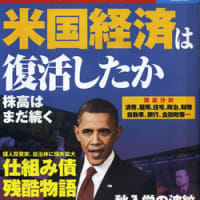『女も戦争を担った』
川名紀美・著/冬樹社1982年
帯に書かれてあります。下「」引用。
「“母たちの永い聖戦”
日中戦争から太平洋戦争へと突入していった“あの暗い時代”に、常に女はみじめな“被害者”とされてきた。果たしてそうだったのだろうか? 朝日新聞第一線女性記者が、母たちの永い“聖戦”の水底を歩く。」

曽野綾子の『ある神話の背景』について、源啓美(ひろみ)。下「」引用。
「読み進めるうちに、啓美さんは登場人物の一人が妙に気にかかり出した。
赤松隊との人たちとの連絡係をつとめていたという島の女子青年団会長。これはどう考えても父の姉、啓美さんから伯母にあたる人にちがいない。
啓美さんもとくにかわいがってもらった、大好きな伯母だ。
島で、古くからたった一軒、旅館を営んできた祖母に、夢中でたずねた。
「おばあちゃん、おばあちゃんはどうしてあのとき、みんなと一緒に死なずにすんだの?」
祖母の顔が、みるみるこわばった。
「いまごろ……なにをいうのさ。もう忘れたよ」
よそよそしくいうと、視線をはずした。
以来、折をみてはこの問題をもち出してみたが、決まって返事は「もう忘れた」であった。
黒いシミのように、抱き続けていた疑惑。それはしだいに大きくふくれあがった。
『あのときも祖母が赤松をかくまったのでは--』
-略-
戦後まもなく、この伯母はまるで逃げるように島を出た。
連絡係なら、赤松隊の内部にもかなり精通していたにちがいない。
もしかすると村人たちに対する集団自決への動きを事前に察知して、自分の家族だけは集合場所へ行かせなかったのではないだろうか。
この話になると口の重い祖母が、たった一度だけこうもらしたことがある。
「あの日、誰かが呼びに来たよ。でも絶対、出ちゃいけないっていわれていたからね」
伯母は戦後しばらく大阪で暮らし、やがて那覇へ戻ってきた。しかし、那覇とは目の鼻の、渡嘉敷島へは決して帰ろうとしない。」
 index
index
三国連太郎は徴兵忌避したという。
感性を麻痺させる……。下「」引用。
「時代が、ぼくのおふくろのような女性の生き方を強いたのです。おふくろだけではなく、日本中の女性が、本来もっているすばらしい感覚をマヒさせられていたのです」
未来の祈りのない日本……。下「」引用。
「日本の家族制度がもっている危険性は、祖先崇拝であっても、現在や未来に対する祈りがまったくないということではないでしょうか」
魂は生き残る--。」
 index
index
汚点(三国連太郎)……。下「」引用。
「私はこれまでの人生にいろんな汚点を残しましたがね、あの戦争に加担したことがいちばん大きな汚点だったというふうに感じているんです」
軍国教師……。下「」引用。
「軍国主義を担った戦時中の教師たち。戦争が激しくなると男性は戦場に狩り出され、教壇は女教師たちが支えた。
あのころ、豆兵士をつくるため腹ペコのこどもたちを追いたてた女教師がいる。
いま、彼女は平和を守るための講座の講師に招かれて、話しながら思わず涙を流す。無論それは、痛恨の涙である。」
原爆で家族を失った……。下「」引用。
「何気なく朝刊の朝日花壇に目を走らせていて、こんな歌を見つけた。
選者の歌人、近藤芳美さんは、広島の原爆で身内を失った。それが原点になって、この歌壇でも戦争への想いを詠んだものをしばしば推薦している。-略-」
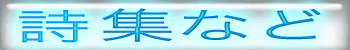 もくじ
もくじ
「教育」が洗脳した……。下「」引用。
「戦前の国語の教科書に「一太郎やあい」という教材があった。
一人息子の出征を見送る老母の健気な“軍国美談”である。
当時こどもたちは教えこまれた。「こんな無学なおばあさんでも、ここまでやれるんだ。ましてお前たちは……」と。
だが、この美談に作為の跡はなかったか。検証をすすめるうちに意外な事実が浮かんできた。
戦意を昴るために、「教育」が果たした役割とは--。」
「目撃者」がいた。下「」引用。
「多度津町に着く-略-郷土史家、米田明三さんに会うことができた。
聞くと教科書に登場する“見送りの場面”に居合わせ、こどもながら一部始終を見ていたという。」
食いちがう……。下「」引用。
「米田さんの話は、私を戸惑わせた。
教科書の中身と、米田さんの証言はずいぶん食いちがっている。
私は念を押した。
「かめさんは“鉄砲あげろ”とはいわなかったのですか?」
米田さんは大きく手を振った。
「そんなん、いわしません」
「じゃ、天子様にご奉公とは何とかは?」
「いや、全然」
米田さんは、前歯のぬけている口を大きくあけて笑った。
「ただ、『かじやん』となんべんも名前を呼んでただけです。名は一太郎じゃなくて、梶太郎。あとでわかったことですがね」-略-」
教授が洗脳をすすめた……。下「」引用。
「東波止に一人息子、梶太郎(当時二十一歳)を見送りに来た岡田かめさん(当時五十二歳)を取り囲んだ数人の紳士は、小野田元熈(もとひろ)香川県知事ら県の幹部たちであった。
二十キロの山道を歩いてきた母の姿に感動した知事が、なぐさめと励ましのことばをかけた。
かめさんは、その紳士が誰なのかも知らず、あわただしく人ごみの中に消えていった。
小野田知事は、部下に命じた。
「名前を確かめなかったのは残念だ。なんとしても、あの母を探し出せ」
自らも講演や会議に行った先々で調査を頼む熱の入れようだった。
この「軍国の母」さがしは、知事が転任してもひきつがれて、続いた。
年号が大正と変わった。一九一九年(大正八年)夏、東京高等師範学校の佐々木吉三郎教授が来県した。
県教育会主催の講習会講師をつとめるためだ。
ここでは軍国の母さがしの話を小耳にはさんだ教授は考えた。
『これは、こどもたちに愛国心を植えつける生きた教材になる』--。」
小野田知事のなまりで、「梶太郎」が「かずたろう」と聞こえ、「一太郎」に……。
母子は「国民的英雄」に……。下「」引用。
「かめさんの待つ家に帰った梶太郎さんは、キヌさんという娘と結婚し、農業にいそしむつつましい生活をおくった。ところが、梶太郎さんは寒い満州でかかった凍傷が悪化していたのだ。
岡田さん一家のみじめな暮しを新聞は報じた。
梶太郎さんは右手の親指を切断し、十三年間病床で苦しんだあげく、両手の全部の指の自由を失っている。豊田村の人たちの好意で義金や食料、衣料品などをもらって、細々と生活をつないでいる。出征美談の主を、こんな状態にしておいていいのか--。
「津波のような」といっていいほどの反響が押し寄せた。
激励の手紙、義援金、慰問品……。
金額は、たちまち五千円を超えた。
地元の豊田村では「岡田母子後援会」がつくられ、会長には小野高介村長が就任した。こうして、母子は“国民的英雄”にまつりあげられていく。-略-」
天皇と拝謁、グッズも……。下「」引用。
「この像が完成した直後、その当時の国民としては最高の栄誉であった天皇陛下との拝謁も許された。
すっかり有名人になったかめさんと梶太郎さんは、戦意昂揚のPRに使われたフシがある。
県内はもとより大阪、京都、名古屋、横浜と招かれ、“講話”をさせられた。「一太郎キャラメル」「一太郎弁当」まで登場し、まさに“一太郎ブーム”だった。-略-」
日蓮宗の信者だった、かめさん。
 もくじ
もくじ
白いエプロンと白いたすき……。下「」引用。
「もし、あなたの家に戦前のアルバムがあったら、一度ひもといてみたい。そこに、白いエプロンと白いたすきの女性の群れが写っている写真をみつけるかもしれないから--。
それが「大日本国防婦人会」。解散時には日本女性の二人に一人が会員だった。
お国のために戦争に行く兵隊さんの役に立ちたい--。
女性たちの素朴な気持ちが軍と結びつくとき、せき止められない大きな流れに変わった。」
「三勇士」の反響は大きかった。
「軍のかいらい」「軍に利用されている」というかげ口があったという……。
聖戦に協力した国防婦人会。
「南京大虐殺」が報道されていたら、日本国民はどう反応しただろう……。マスコミは大切なことを伝えなかった……。今もだが……。
片桐ヨシノ(国防婦人会元幹部)は、戦争未亡人の母子家庭を13世帯(70人)をひきとったという……。
自称“自衛隊おばさん”片桐シヨノ。
差別を見た女学生。下「」引用。
「「男の人に負けずにがんばります。ぜひ軍で働かせて」と志願した沖縄・宮古島の女学生。
意気込んで勤めはじめた軍隊の内部で見たものは陰険な差別だった。
そして“朝鮮ピー”と呼ばれた朝鮮人従軍慰安婦たちの出会いが、あの戦争の真の被害者は誰なのかを教えてくれた。」
 もくじ
もくじ
 もくじ
もくじ
 もくじ
もくじ
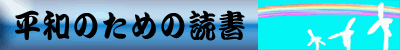


川名紀美・著/冬樹社1982年
帯に書かれてあります。下「」引用。
「“母たちの永い聖戦”
日中戦争から太平洋戦争へと突入していった“あの暗い時代”に、常に女はみじめな“被害者”とされてきた。果たしてそうだったのだろうか? 朝日新聞第一線女性記者が、母たちの永い“聖戦”の水底を歩く。」

曽野綾子の『ある神話の背景』について、源啓美(ひろみ)。下「」引用。
「読み進めるうちに、啓美さんは登場人物の一人が妙に気にかかり出した。
赤松隊との人たちとの連絡係をつとめていたという島の女子青年団会長。これはどう考えても父の姉、啓美さんから伯母にあたる人にちがいない。
啓美さんもとくにかわいがってもらった、大好きな伯母だ。
島で、古くからたった一軒、旅館を営んできた祖母に、夢中でたずねた。
「おばあちゃん、おばあちゃんはどうしてあのとき、みんなと一緒に死なずにすんだの?」
祖母の顔が、みるみるこわばった。
「いまごろ……なにをいうのさ。もう忘れたよ」
よそよそしくいうと、視線をはずした。
以来、折をみてはこの問題をもち出してみたが、決まって返事は「もう忘れた」であった。
黒いシミのように、抱き続けていた疑惑。それはしだいに大きくふくれあがった。
『あのときも祖母が赤松をかくまったのでは--』
-略-
戦後まもなく、この伯母はまるで逃げるように島を出た。
連絡係なら、赤松隊の内部にもかなり精通していたにちがいない。
もしかすると村人たちに対する集団自決への動きを事前に察知して、自分の家族だけは集合場所へ行かせなかったのではないだろうか。
この話になると口の重い祖母が、たった一度だけこうもらしたことがある。
「あの日、誰かが呼びに来たよ。でも絶対、出ちゃいけないっていわれていたからね」
伯母は戦後しばらく大阪で暮らし、やがて那覇へ戻ってきた。しかし、那覇とは目の鼻の、渡嘉敷島へは決して帰ろうとしない。」
 index
index三国連太郎は徴兵忌避したという。
感性を麻痺させる……。下「」引用。
「時代が、ぼくのおふくろのような女性の生き方を強いたのです。おふくろだけではなく、日本中の女性が、本来もっているすばらしい感覚をマヒさせられていたのです」
未来の祈りのない日本……。下「」引用。
「日本の家族制度がもっている危険性は、祖先崇拝であっても、現在や未来に対する祈りがまったくないということではないでしょうか」
魂は生き残る--。」
 index
index汚点(三国連太郎)……。下「」引用。
「私はこれまでの人生にいろんな汚点を残しましたがね、あの戦争に加担したことがいちばん大きな汚点だったというふうに感じているんです」
軍国教師……。下「」引用。
「軍国主義を担った戦時中の教師たち。戦争が激しくなると男性は戦場に狩り出され、教壇は女教師たちが支えた。
あのころ、豆兵士をつくるため腹ペコのこどもたちを追いたてた女教師がいる。
いま、彼女は平和を守るための講座の講師に招かれて、話しながら思わず涙を流す。無論それは、痛恨の涙である。」
原爆で家族を失った……。下「」引用。
「何気なく朝刊の朝日花壇に目を走らせていて、こんな歌を見つけた。
選者の歌人、近藤芳美さんは、広島の原爆で身内を失った。それが原点になって、この歌壇でも戦争への想いを詠んだものをしばしば推薦している。-略-」
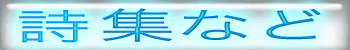 もくじ
もくじ「教育」が洗脳した……。下「」引用。
「戦前の国語の教科書に「一太郎やあい」という教材があった。
一人息子の出征を見送る老母の健気な“軍国美談”である。
当時こどもたちは教えこまれた。「こんな無学なおばあさんでも、ここまでやれるんだ。ましてお前たちは……」と。
だが、この美談に作為の跡はなかったか。検証をすすめるうちに意外な事実が浮かんできた。
戦意を昴るために、「教育」が果たした役割とは--。」
「目撃者」がいた。下「」引用。
「多度津町に着く-略-郷土史家、米田明三さんに会うことができた。
聞くと教科書に登場する“見送りの場面”に居合わせ、こどもながら一部始終を見ていたという。」
食いちがう……。下「」引用。
「米田さんの話は、私を戸惑わせた。
教科書の中身と、米田さんの証言はずいぶん食いちがっている。
私は念を押した。
「かめさんは“鉄砲あげろ”とはいわなかったのですか?」
米田さんは大きく手を振った。
「そんなん、いわしません」
「じゃ、天子様にご奉公とは何とかは?」
「いや、全然」
米田さんは、前歯のぬけている口を大きくあけて笑った。
「ただ、『かじやん』となんべんも名前を呼んでただけです。名は一太郎じゃなくて、梶太郎。あとでわかったことですがね」-略-」
教授が洗脳をすすめた……。下「」引用。
「東波止に一人息子、梶太郎(当時二十一歳)を見送りに来た岡田かめさん(当時五十二歳)を取り囲んだ数人の紳士は、小野田元熈(もとひろ)香川県知事ら県の幹部たちであった。
二十キロの山道を歩いてきた母の姿に感動した知事が、なぐさめと励ましのことばをかけた。
かめさんは、その紳士が誰なのかも知らず、あわただしく人ごみの中に消えていった。
小野田知事は、部下に命じた。
「名前を確かめなかったのは残念だ。なんとしても、あの母を探し出せ」
自らも講演や会議に行った先々で調査を頼む熱の入れようだった。
この「軍国の母」さがしは、知事が転任してもひきつがれて、続いた。
年号が大正と変わった。一九一九年(大正八年)夏、東京高等師範学校の佐々木吉三郎教授が来県した。
県教育会主催の講習会講師をつとめるためだ。
ここでは軍国の母さがしの話を小耳にはさんだ教授は考えた。
『これは、こどもたちに愛国心を植えつける生きた教材になる』--。」
小野田知事のなまりで、「梶太郎」が「かずたろう」と聞こえ、「一太郎」に……。
母子は「国民的英雄」に……。下「」引用。
「かめさんの待つ家に帰った梶太郎さんは、キヌさんという娘と結婚し、農業にいそしむつつましい生活をおくった。ところが、梶太郎さんは寒い満州でかかった凍傷が悪化していたのだ。
岡田さん一家のみじめな暮しを新聞は報じた。
梶太郎さんは右手の親指を切断し、十三年間病床で苦しんだあげく、両手の全部の指の自由を失っている。豊田村の人たちの好意で義金や食料、衣料品などをもらって、細々と生活をつないでいる。出征美談の主を、こんな状態にしておいていいのか--。
「津波のような」といっていいほどの反響が押し寄せた。
激励の手紙、義援金、慰問品……。
金額は、たちまち五千円を超えた。
地元の豊田村では「岡田母子後援会」がつくられ、会長には小野高介村長が就任した。こうして、母子は“国民的英雄”にまつりあげられていく。-略-」
天皇と拝謁、グッズも……。下「」引用。
「この像が完成した直後、その当時の国民としては最高の栄誉であった天皇陛下との拝謁も許された。
すっかり有名人になったかめさんと梶太郎さんは、戦意昂揚のPRに使われたフシがある。
県内はもとより大阪、京都、名古屋、横浜と招かれ、“講話”をさせられた。「一太郎キャラメル」「一太郎弁当」まで登場し、まさに“一太郎ブーム”だった。-略-」
日蓮宗の信者だった、かめさん。
 もくじ
もくじ白いエプロンと白いたすき……。下「」引用。
「もし、あなたの家に戦前のアルバムがあったら、一度ひもといてみたい。そこに、白いエプロンと白いたすきの女性の群れが写っている写真をみつけるかもしれないから--。
それが「大日本国防婦人会」。解散時には日本女性の二人に一人が会員だった。
お国のために戦争に行く兵隊さんの役に立ちたい--。
女性たちの素朴な気持ちが軍と結びつくとき、せき止められない大きな流れに変わった。」
「三勇士」の反響は大きかった。
「軍のかいらい」「軍に利用されている」というかげ口があったという……。
聖戦に協力した国防婦人会。
「南京大虐殺」が報道されていたら、日本国民はどう反応しただろう……。マスコミは大切なことを伝えなかった……。今もだが……。
片桐ヨシノ(国防婦人会元幹部)は、戦争未亡人の母子家庭を13世帯(70人)をひきとったという……。
自称“自衛隊おばさん”片桐シヨノ。
差別を見た女学生。下「」引用。
「「男の人に負けずにがんばります。ぜひ軍で働かせて」と志願した沖縄・宮古島の女学生。
意気込んで勤めはじめた軍隊の内部で見たものは陰険な差別だった。
そして“朝鮮ピー”と呼ばれた朝鮮人従軍慰安婦たちの出会いが、あの戦争の真の被害者は誰なのかを教えてくれた。」
 もくじ
もくじ もくじ
もくじ もくじ
もくじ