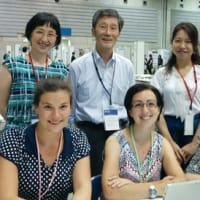以前、なんとはなしにつけていたNHKの番組で
「ぼやき川柳」というののダイジェストをやっていました。
そこで印象に残ったのが
おばちゃんの 話の終わりは 「知らんけど」
・・・あるある
「知らんけどな」「そやな」と言って終えられるおしゃべり、
すぐにイメージできました。
見てきたように、身ぶり手ぶりを交え、表情豊かに伝え
周りもさんざんその話術に引き込まれ、話がある程度の展開を見せると
その一幕の締めを飾るように口から出る一言、
「知らんけど」。
さて、今日は、この「知らんけど」の意味を考えたいと思います。
なぜ、おばちゃんにかぎらず、時に人は、
このように「知らんけど」という言葉を添えるのでしょうか。
1.話に対する責任を放棄するため
2.話の盛り上がりをクールダウンさせるため
3.話に隠された事実を隠すため
この3通りのいずれか、あるいは、いくつかをねらって、
「知らんけど」という言葉は発せられ、そして実際に
私たちのコミュニケーションにおいてその効果を発揮していると思われます。
それぞれ見てみましょう。
* * * * *
1.話に対する責任を放棄するため
これは、「知らない」から「知らない」ということを伝える、
というそのままの素直な自分の気持ちの表現も含まれますが、
ちょっと複雑な意味合いも含んでいます。
ちょっとした出来事があったり、ちょっとした耳にした情報があったりして、
それを人に言いたい
と話し始めたんだけど、そこから対話の中でどんどん妄想が広まって、
出来事の真相やら、情報の尾ひれやらが、さもありなん、というように
付け加わって話がどんどん大きくなっていく。
きっとそうかもしれない・・・と勝手に尾ひれがついてしまい、
もともとの話からは、すっかり様相が変わっているということもあります。
この時、誰かが、そもそも、その話のどこまでが事実であったのか、
そして、話を持ってきた本人は、そもそもどう思っていたのか、
話の途中で何が付け加わり、情報がどう変わり、
話をしたことによって話を持ってきた本人の気持ちがどう変わったか、
などを整理することができれば、もともとどんな話だったか
きっと再度確認する事ができるでしょう。
しかし、かなり自覚的にやらなければ、
自分がもともと思っていた事だったのか、
どこからが対話の中で付け加えられた事だったのか、
分からなくなってしまいます。
この分からなくなった状態、
ふくれあがってしまった話に対して、
もう自分が何を知ってて知らないのか分からなくなってきた~
もともと、そんなに詳しく知ってた訳じゃないし~
と、自分の手に負えなくなったなー、と感じた時、
人は、この話の提供者としての責任を逃れたくなるのではないでしょうか。
そして、この言葉が出るのではないでしょうか。
「知らんけど。」
* * * * *
2.話の盛り上がりをクールダウンさせるため
これは、1.の姉妹版といってもいいかもしれません。
話が盛り上がっていくと、相手の方が、自分以上に興奮したり
真剣になったりしてしまう事があります。
時に、問題を解決しなきゃ 、お祝いをしなきゃ
、お祝いをしなきゃ 、助けてあげなきゃ
、助けてあげなきゃ とか、
とか、
「私たちは何をすべきか 」という方向に
」という方向に
話が流れていく事があります。
しかし、例えば「問題を解決しなきゃ」の場合であっても、
それは、もともとその話題に含まれていたものなのか、
それとも、対話の中で、あるかもしれないと推測されたにすぎないものなのか、
あまり精査されないことがほとんどです。
それが精査されずに、「問題がある」ということを前提として、
その次の段階で盛り上がっているという状態なのです。
何かに向き合おうとする場合、本来はまずはその現状をきちんと知る事が必要ですが
この場合、仮定された状態を確固たる足場としながら、
次の動きを検討してしまっているわけです。
どう動くか、となると、非常に具体的な課題になりますから、
多くの意見が飛び交うでしょう。
その話し合いの中で、仮定された現状は、
さらに細かい部分まで推測されるようになり、
ますます具体的な輪郭をもつようになっていきます。
大抵それは、自分たちがあーだこーだと意見を出し合って
現状がどうであるかを予想しているのに過ぎないのですが、
確認のしようがない場合、その予想は現実だとされていくわけです。
そしてそのまま話が進み、次なる行動へ向けてのスクラムが組まれる・・・
しかし、誰かが「あれ 」と気づく事があります。
」と気づく事があります。
「そもそも、本当にそうなんだっけ」と。
あるいは、そこまで自覚的ではなくても、何か違和感を抱く。
その人はきっと、話の流れを一旦停止させることができるような
なにがしかの意見を述べて、さらにこの言葉を付け加えるのではないでしょうか。
「知らんけど。」
それによって、自分たちが、よく分からない現実を作り上げて
盛り上がってしまっていた事に気付くのではないでしょうか。
つまりは、自分たちも「知らんけど」な状態にあったということに。
* * * * *
3.話に隠された事実を隠すため
これは、「私の友達の話だけどね」などから始まる話に多いと思われます。
誰かに聞いてもらいたい、人の意見を聞きたいような話がある場合、
人は、「自分」のことは「友達の話」、
「自分の友達」のことは「友達の友達の話」として
話をすることがままあるように思います。
なぜそういうことをするかというと、誰の話であるかを
特定されたくない、つまり、そこは隠しておきたいと思うからです。
あるいは、「大した問題じゃないんだけど」とか、
「別にどうでもいんだけど」など前置きしてから、
話を始める事があります。
もちろん、本当にそういう場合(どうでもいい話であることを
断っている場合)もありますが、
その話に対して、めちゃくちゃ関心や興味があるのに、
関心や興味がそこまであるということを悟られないために、
そういう前置きをすることがあります。
いずれにせよ、その話が、自分にとって非常に関わりの深い話であることを
前面に出さないようにするために、
その話題に対して適度な心理的距離をとっている状態にあることを
何気なくアピールしているわけです。
それによって、相手から変な詮索されたりせずにすみますもんね。
しかし、そういう前提で話しているにもかかわらず、
話が進むにつれて、その話に注意が集中してしまうと、
その状態をキープし続ける事が難しくなる事があります。
その結果、やけに真剣な態度をとったり、何でそこまで知ってるの?ということを
ポロリと言ってしまったり、前置きで告げた設定を、自ら破ってしまうという事態に
陥ってしまいます。
その時、
いやいや、これは、あくまで「友達の」あるいは「友達の友達の」話なのよ、
あるいは、
いやいや、本当に別に大した問題じゃないから本当にどうでもいんだけどね、
などという設定を、再度アピールする必要が出てきます。
そこで発せられるのではないでしょうか、
「知らんけど。」
この一言が。
* * * * *
以上、
おばちゃんの話の終わりは「知らんけど」
という川柳からの考察でした。
決しておばちゃんに限らないと思うのですが、いかがでしょうか。
「ぼやき川柳」というののダイジェストをやっていました。
そこで印象に残ったのが
おばちゃんの 話の終わりは 「知らんけど」
・・・あるある

「知らんけどな」「そやな」と言って終えられるおしゃべり、
すぐにイメージできました。
見てきたように、身ぶり手ぶりを交え、表情豊かに伝え
周りもさんざんその話術に引き込まれ、話がある程度の展開を見せると
その一幕の締めを飾るように口から出る一言、
「知らんけど」。
さて、今日は、この「知らんけど」の意味を考えたいと思います。
なぜ、おばちゃんにかぎらず、時に人は、
このように「知らんけど」という言葉を添えるのでしょうか。
1.話に対する責任を放棄するため
2.話の盛り上がりをクールダウンさせるため
3.話に隠された事実を隠すため
この3通りのいずれか、あるいは、いくつかをねらって、
「知らんけど」という言葉は発せられ、そして実際に
私たちのコミュニケーションにおいてその効果を発揮していると思われます。
それぞれ見てみましょう。
* * * * *
1.話に対する責任を放棄するため
これは、「知らない」から「知らない」ということを伝える、
というそのままの素直な自分の気持ちの表現も含まれますが、
ちょっと複雑な意味合いも含んでいます。
ちょっとした出来事があったり、ちょっとした耳にした情報があったりして、
それを人に言いたい

と話し始めたんだけど、そこから対話の中でどんどん妄想が広まって、
出来事の真相やら、情報の尾ひれやらが、さもありなん、というように
付け加わって話がどんどん大きくなっていく。
きっとそうかもしれない・・・と勝手に尾ひれがついてしまい、
もともとの話からは、すっかり様相が変わっているということもあります。
この時、誰かが、そもそも、その話のどこまでが事実であったのか、
そして、話を持ってきた本人は、そもそもどう思っていたのか、
話の途中で何が付け加わり、情報がどう変わり、
話をしたことによって話を持ってきた本人の気持ちがどう変わったか、
などを整理することができれば、もともとどんな話だったか
きっと再度確認する事ができるでしょう。
しかし、かなり自覚的にやらなければ、
自分がもともと思っていた事だったのか、
どこからが対話の中で付け加えられた事だったのか、
分からなくなってしまいます。
この分からなくなった状態、
ふくれあがってしまった話に対して、
もう自分が何を知ってて知らないのか分からなくなってきた~
もともと、そんなに詳しく知ってた訳じゃないし~
と、自分の手に負えなくなったなー、と感じた時、
人は、この話の提供者としての責任を逃れたくなるのではないでしょうか。
そして、この言葉が出るのではないでしょうか。
「知らんけど。」
* * * * *
2.話の盛り上がりをクールダウンさせるため
これは、1.の姉妹版といってもいいかもしれません。
話が盛り上がっていくと、相手の方が、自分以上に興奮したり
真剣になったりしてしまう事があります。
時に、問題を解決しなきゃ
 、お祝いをしなきゃ
、お祝いをしなきゃ 、助けてあげなきゃ
、助けてあげなきゃ とか、
とか、「私たちは何をすべきか
 」という方向に
」という方向に話が流れていく事があります。
しかし、例えば「問題を解決しなきゃ」の場合であっても、
それは、もともとその話題に含まれていたものなのか、
それとも、対話の中で、あるかもしれないと推測されたにすぎないものなのか、
あまり精査されないことがほとんどです。
それが精査されずに、「問題がある」ということを前提として、
その次の段階で盛り上がっているという状態なのです。
何かに向き合おうとする場合、本来はまずはその現状をきちんと知る事が必要ですが
この場合、仮定された状態を確固たる足場としながら、
次の動きを検討してしまっているわけです。
どう動くか、となると、非常に具体的な課題になりますから、
多くの意見が飛び交うでしょう。
その話し合いの中で、仮定された現状は、
さらに細かい部分まで推測されるようになり、
ますます具体的な輪郭をもつようになっていきます。
大抵それは、自分たちがあーだこーだと意見を出し合って
現状がどうであるかを予想しているのに過ぎないのですが、
確認のしようがない場合、その予想は現実だとされていくわけです。
そしてそのまま話が進み、次なる行動へ向けてのスクラムが組まれる・・・
しかし、誰かが「あれ
 」と気づく事があります。
」と気づく事があります。「そもそも、本当にそうなんだっけ」と。
あるいは、そこまで自覚的ではなくても、何か違和感を抱く。
その人はきっと、話の流れを一旦停止させることができるような
なにがしかの意見を述べて、さらにこの言葉を付け加えるのではないでしょうか。
「知らんけど。」
それによって、自分たちが、よく分からない現実を作り上げて
盛り上がってしまっていた事に気付くのではないでしょうか。
つまりは、自分たちも「知らんけど」な状態にあったということに。
* * * * *
3.話に隠された事実を隠すため
これは、「私の友達の話だけどね」などから始まる話に多いと思われます。
誰かに聞いてもらいたい、人の意見を聞きたいような話がある場合、
人は、「自分」のことは「友達の話」、
「自分の友達」のことは「友達の友達の話」として
話をすることがままあるように思います。
なぜそういうことをするかというと、誰の話であるかを
特定されたくない、つまり、そこは隠しておきたいと思うからです。
あるいは、「大した問題じゃないんだけど」とか、
「別にどうでもいんだけど」など前置きしてから、
話を始める事があります。
もちろん、本当にそういう場合(どうでもいい話であることを
断っている場合)もありますが、
その話に対して、めちゃくちゃ関心や興味があるのに、
関心や興味がそこまであるということを悟られないために、
そういう前置きをすることがあります。
いずれにせよ、その話が、自分にとって非常に関わりの深い話であることを
前面に出さないようにするために、
その話題に対して適度な心理的距離をとっている状態にあることを
何気なくアピールしているわけです。
それによって、相手から変な詮索されたりせずにすみますもんね。
しかし、そういう前提で話しているにもかかわらず、
話が進むにつれて、その話に注意が集中してしまうと、
その状態をキープし続ける事が難しくなる事があります。
その結果、やけに真剣な態度をとったり、何でそこまで知ってるの?ということを
ポロリと言ってしまったり、前置きで告げた設定を、自ら破ってしまうという事態に
陥ってしまいます。
その時、
いやいや、これは、あくまで「友達の」あるいは「友達の友達の」話なのよ、
あるいは、
いやいや、本当に別に大した問題じゃないから本当にどうでもいんだけどね、
などという設定を、再度アピールする必要が出てきます。
そこで発せられるのではないでしょうか、
「知らんけど。」
この一言が。
* * * * *
以上、
おばちゃんの話の終わりは「知らんけど」
という川柳からの考察でした。
決しておばちゃんに限らないと思うのですが、いかがでしょうか。