日本人はフランス語を誤解している!・・・と思うけどなあ・・・
フランス語系人のBO-YA-KI
50
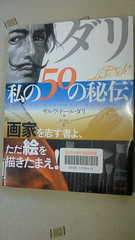
(このエントリーのコメントから続きます)
マルローはちょっと中断で、ダリのお話。
サルバドール・ダリはご存知のとおりシュルレアリスムの画家。スペインはカタルーニャ出身の人ですね。
ずっとずっと以前、テレビで彼のインタビューを見たことがあります。インタビュアーの質問と全然違うことをべらべら喋っていたのが印象的でした。
写真の本、やっと金沢大学に入ったのでこの週末に読んでおりました。midiさんはいい本に目をつけられましたね。

ダリはなかなか有益なことを書いてます。
作品を成功させるためには、とりかかる前に深く眠ることが必要だというのは、あれこれ考えてしまって眠れないというのでは作品にとりかかる機が熟していないということだ、ということのひとつの表現でしょうね。
傑作を作りたいと熱望する優れた画家はすべてダリの妻、ガラと結婚しなければならないというのは、一見超個人的なことに見えるけど、たぶん至言なのです。
他にいろんな、いろんなことが書いてあります。
グレン・グールドの思索を連想させるところもあったんですが、読み返そうと探してみると、はてどこだったか? 例によって最初から最後に向けて線的に読んでいるわけではないので・・・ すでにこの本に「書いてあること」と「触発されたこと」の差が判然としなくなってるかも。
5という数字についての考察もあります。5は有機物の世界を支配する、うんぬん。
こういうのをただの神秘主義として片づけることはしない方がいいと思います。まずはダリの言うことに真摯に耳を傾けましょう。
ところで、スタンダールはよく自分のテクストのなかに「50」という数字を響かせます。50歳というのが彼の時代の感覚だと老境の始まりで楽しい恋愛の生活も終わりという慨嘆と、どんな人物も死後50年たてば社会もその真価で評価するようになるという考えからの考察が大きいと思いますが、他にもときどきこの数字が出てきます。
彼の著『イタリア絵画史』――もし今度日本で「スタンダール著作集」出版が企画されることがあるならわたしは『恋愛論』とこれを担当したいんですけど(『赤と黒』は下川さんにお任せしましょう)――の末尾に「50時間講習」という変なものがついてます。
本当の意味で美術を味わうことができる人になるための提言集、みたいなものですがスタンダールは、これに従えば「ほとんどあなた自身がアーチストになれる(!)」と言ってます。例によって言うことが大胆です。
内容もかなり意表をついていてたとえばスタンダールは、50時間のうちの最初の10時間を「色調colorisの観念を得るために水泳学校に通うこと」で費やせ、と言うんです。印象派みたいなことを言う奴だな(彼の時代には印象派なんてまだなかったのに)。
さてダリの本は『私の「50」の秘伝』ですね。
両者、なんか関係があるような気がしてしまいます。
繰り返しになりますが、こういうのをただの神秘主義だと思ってしまうのはつまらないというか、もったいないことなのです。
ウィトゲンシュタインのような、グロテスクなまでに論理的な思考をする人がときに非常に神秘主義的な印象を与えるのも、理由のないことではないと思ってます。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
| « マルローはど... | おとこ » |





私は仲介者さんから依頼を受けて作業をしただけで、本書を発掘し日本で出すことを決めたのは本書の出版社さんなんです。難解でしんどい仕事でしたが、非常に有意義でした。よくぞこの役が廻ってきたもんだと神にも感謝です(笑)。
スタンダールが「5」ならぬ「50」に言及しているというお話、興味深いです。『恋愛論』は若い頃挫折してしまって最後まで読まなかったからその「講習」は記憶にありません……再読しなくては。それともraidaisukiさまによる新訳を待とうかな~♪
ご紹介いただいた御著書が責任をもってお勧めできる本であったということで、これは大変よろこばしいことです。
わたくしの変な紹介の仕方でこの本の評判が悪くならないことを祈ります。
『恋愛論』はまだしも、『イタリア絵画史』の新訳を出そうなんていう奇特な出版社は、いまどき無いでしょうね・・・ のっとっているのがずいぶん昔の美学だし、スタンダールの著作だといっても盗作部分が多いことで有名ですし。本国フランスでもあまり出版は多くありません。
70年代に人文書院から出された『スタンダール全集』に収録されてますから、いまでも読むことはできます。ただ訳しておられる吉川先生が西洋美術の御専門で、フランス文学は専門外でいらっしゃったこともあって、スタンダールの真意が読み取りやすい形でないのがはがゆいのです・・・
それにしても、ウィトゲンシュタインに関してはまったく何の知識も持ち合わせていませんでした。リンクを張られている5年前のエントリーを拝読し、今むくむくモコモコと興味がふくれあがっております。
講談社『哲学宗教日記』と新書館『色彩について』が気になっております。