日中戦争に始まる15年戦争の経験は、良心的なジャーナリストにも多くの反省をもたらしました。ジャーナリズムこそナショナリズムの陥穽にはまりやすい、という実例を反省したはずなのです。しかし、最近は特に、ナショナリズムに同調するだけでなく、それを煽る報道さえあたりまえにみられるようになりました。中国で反日デモが行われている、中国が宇宙進出に成功した、というニュースが流れると、「中国人は民度が低い」という石原慎太郎東京都知事のコメントを大きく掲載し、ロケットは飛ばせても「中国は経済的にはまだ二流国だ(=日本の優位はまだ脅かされていない、の意)」というような報道が流されます。日本のジャーナリズムは、もう眉に唾をつけてかかったほうがいいような状況になっています。
---------------------------------
日本の戦後ジャーナリズムは、1945年までの国家主義の反省から、むしろナショナリズムを抑制してきた面が強い。しかしそれが経済大国化とともに変化し、ふたたび「普通の覇権大国」への仲間入りがしたいという願望が政・官・財界に生まれ、ジャーナリズムにもそれに同調する動きが強まってきた(これは1997年第一刷発行の本の記述です。今はもっと露骨ですよね)。
日本のエスタブリッシュメント(国家・市民社会のさまざまな次元で、意思決定や政策形成に影響力を及ぼす既成の権力機構、権威的組織、体制、勢力、また既成秩序などをさす:広辞苑第5版より)の中には、…湾岸戦争を機にPKOへの参加とともに、問題の多い国連の実態をそのままにして、安保理常任理事国入りをめざす機運が強まった。メディアの中にも、これを積極的に支持する主張が目立つようになった。折から皇太子の結婚が話題になって、ジャーナリズムによる皇室ブームも起こり、学校教育への「日の丸」「君が代」の強制導入とともにナショナリズム高揚の舞台装置となった。
1992年11月、経団連ホールで開かれた「世界のグランドデザインを考える」シンポジウムで、米UCLA国際センター所長のR・ローズクランスは「日本のナショナリズムとミリタリズムは沸騰しようとしている(慧眼! 10年後の日本を見事に言い当てている)。日本はやがて核武装して世界にその力を認識させるだろう」と基調報告した。これに対し日本側パネラーは「そのような考えも動きもない」と否定していた。報告を聞きながら私自身も、「核武装に反対し戦前型ナショナリズムを抑える日本社会の力は、そんなに弱いものではあるまい」と考えていた。アジアの反発も根強い。そのうえ、米国が日本の核武装に強く反対している情勢を考慮すれば、日本が核クラブの仲間入りできる可能性は当面はないと見るべきだろう。
だが、日本人が気づかない日本ナショナリズムの底流分析を、頭から否定するべきではないと自戒もした。日本人の心情も日本をめぐる国際環境も、ナショナリズムが強まる方向に進んでおり、日本のジャーナリズムも全体として、「国益」や「愛国心」には抵抗力が弱いからである。
(「ジャーナリズムの思想」/ 原寿雄・著)
---------------------------------
この本は1997年に書かれたものですが、著者の指摘は的確ですね。ほんとうに日本のジャーナリズムは「国益」「愛国心」には弱かったことを、わたしたちは今、目の当たりにしています。上掲書はこのように続けて書いています。
---------------------------------
ジャーナリズムの歴史はナショナリズムの歴史である。そのナショナリズムが排外主義に陥りやすいことも、歴史が証明している。何が真の国益かを見分けるのは常に微妙でむずかしく、対外問題の場合、ジャーナリストはほとんどいつも、時の政府の国益論に加担してしまう。特に日本は民主主義の歴史も浅く、市民的、民権的国益観が確立していないため、国家原理にもとづく国権的な国益観が今なお、まかり通りやすい。そしてもちろん、国益と政府益とは峻別されなければならないのに、政府は政権の利益のために「国益」を口実にしたがることが多い。
ジャーナリズムは日常的に、偏狭なナショナリズムを克服して、いつも真の国益とは何かを冷静に追求することが求められる。戦争になってからでは、本当は遅い。時の政府の利益と民衆のための真の国益とを見分ける眼力をどう養うか。それは、いつの時代のジャーナリストにとっても、最大の課題といってよい。とかくごまかされやすい「国益」に代えて、「国民益」という言葉を使うことを考えてみてもよい。「国民の生命、身体、財産の安全」を離れて「国の安全」はない。「国民の利益」を離れて政権の都合による「国益」が独り歩きをするのでは民主主義とはいえない。
---------------------------------
「愛国心」についても同様です。上掲書は次のように述べています。
---------------------------------
明治政府は、日本を近代的な統一民族国家として確立し、そのために天皇制を再編・強化した。そのスローガン「富国強兵」をジャーナリズムは支持した。明治から大正への自由民権、デモクラシー運動も、大勢は国粋主義を超えられなかった。いわゆる「内に自由民権、外に帝国主義」である。自由人福沢諭吉も日清戦争の主戦論者となり、「時事新報(諭吉が創刊した日刊新聞)」で戦費集めのキャンペーンを張った。クリスチャン・ジャーナリスト内村鑑三は日露戦争に反対しながら、旅順港陥落の報を聞いたとき、隣近所に聞こえるような大声で「帝国万歳」を叫んでいた。こういう話を聞くと、ジャーナリストにとって「国籍」の業の深さをあらためて痛感させられる。
朝日新聞も1931年の満州事変を機に、それまですでに軍部の対外膨張路線を支持していた大阪毎日新聞などと足並みをそろえたが、その「転向」の理由は「国益」のためだった。右翼の介入や、軍のボイコット運動を受けた販売(店)側からの圧力もあったが、それはきっかけにすぎない。
やがて日本ジャーナリズムは、軍国主義の支持者から推進者に変貌する。いったん戦争への道を歩み始めれば、新聞も放送も政府以上に愛国者になってしまう。政府が対外政策で世論(情報の一方的提供者のマスコミによって形づくられる)より強硬だったのは近衛内閣の時だけであった、という見方もできるくらいである。…ジャーナリストは普通の愛国者以上に愛国的になりやすい。そういう面があったこと、今もあることを否定できない。
「愛国」は冷静な判断力を失わせる。ジャーナリストは「愛国」の誘惑に負けてはならないのに、「国益」が目を狂わせる。これには、ナショナリズムがメディアにとって商売上の得策になる点も見逃せない。逆に言えば、愛国熱が高まろうとしているときに、それに水をかけるようなメディアは読者・視聴者から嫌われやすい。
戦争とジャーナリズムの歴史を見ると、どこの国でもジャーナリズムが愛国心を煽り、それによって高揚した世論がさらにジャーナリズムを煽りながら、その相乗作用によって新聞は部数を伸ばし、放送は視聴者を増やしてきた。ナショナリズムは、ジャーナリズムというビジネスにとって危険な魔力を持っている。朝日、読売、毎日の各社史とも、戦争によって新聞が発展してきたことをはっきり認めている。
---------------------------------
「愛国」は冷静な判断力を失わせる。たしかにそうです。個人の尊厳の尊重という戦後民主主義の基本的精神が十分に日本に根づかなかったのは、自民党の政策によることとともに、ジャーナリズムが民主主義を消化し切れなかったことに原因があるのではないでしょうか。前回も書きましたが、天皇制というのはそういう民主主義の精神に真っ向から対立する考え方で機能しています。しかもわたしたち国民は、なぜか皇室は別扱いにします。なぜかと問う必要はないでしょう。皇室のこととなると、メディアが別格扱いにするからです。憲法の精神を差し置いて、ただ単に「地位」という価値観で広めてきたからです。
教育基本法の改正についても、歴史的に考察して、また教育行政の批判もなく、ただ子どもたちが荒れている、それは戦後の教育が悪かったからだ=戦後教育のバックである教育基本法に問題があるという、素人くさい短絡的な判断で、改正してあたりまえというような扱いです。日本が世界市場で発展してゆくためには、人間の選別、格差はしかたがない、というそう、「国益」=「企業益」という観点で惑わされているからです。ほんとうに日本のジャーナリズムは、「国益」「愛国心」に弱い。
でもみんながみんなそうであるわけではありません。眼の黒いジャーナリストも少数ながら存在します。民主主義の原理をよく理解する知的で理性的な人の一文をご紹介します。
---------------------------------
私は、秋篠宮夫妻の「第三子」誕生報道に対する自らの立場を社内(共同通信社)で明らかにしておこうと思い、要旨以下のような文章を作って労働組合に投稿した。組合の中でジャーナリズム論を論議する専門部発行の不定期のニュースで発表することを考えたのだ。以前、愛子誕生報道を批判する文章を同じニュースに書いたことがあるが、今回は、予想される大々的な奉祝報道に警告になればと思い、誕生前に投稿した。たまたま、編集責任者の不在で、次善の好評は見送られてしまったが、掲載されることにはなった。投稿の見出しは、「祝意強制する紀子出産奉祝報道をやめよう」。以下、要旨。
紀子の出産は9月初旬を予定していると報道されている。これまでの他のケースと同様、今は表向きは静かだが、その時が来るやとたんに、それこそ馬に喰わせるほどの大量の原稿が、さまざまな出稿各部から吐き出されることになるのだろう。それも、白々しく歯の浮くような賛辞が、仰々しい最大級の敬語を伴って。それを予想しただけで、汚い表現で申し訳ないが、ヘドが出そうになる。気持ち悪い。
今回の子どもの誕生は、じかに「皇室典範改正」論議につながってくる。だが、それなら、その特別な存在を許しているこの社会のおかしさを、問題提起するような報道はできないものだろうか。その子どもが生まれるというだけで、どれほどの貴重な税金が費やされるのか。それは一般の子どもと、どれほどの差があるのか。あるいは、政府や各地の自治体などが、いかにばかげた騒ぎをするのか、それがほんとうに国民、市町村民の税金を使って行政がやるべき仕事なのか、などについて、批判的にチェックするような報道をこそ心がけるべきではないのか。
少なくとも、「おめでたい、おめでたい」と、にやけたしまりのない顔で、おべんちゃらばかりを繰り返す、意味のない駄弁を垂れ流すだけのような原稿だけは願い下げにしてほしい。企業の便乗商法や商店街での祝賀行事だの、ただ社会的な奉祝機運を盛り上げるためだけの記事など、いったいどこに配信する意味があるのだろう。これらを垂れ流すことで、相乗的に、結果的に、読者、視聴者に対し、祝意を強制することにつながることを、私たちは肝に銘じなければならないと思う。
誕生以来、徳仁(なるひと)ら「東宮家」と「秋篠宮家」との間の“待遇”の差を問題にし、いかに「秋篠宮家」が“限られた”費用、体制のなかで、子どもを養育しなければならないかを強調する記事が溢れている「職員数、医療体制…大きな差。皇太子家、秋篠宮家(読売新聞9月7日朝刊)」などと。そして、優先順位の高い“皇位継承者”という、その“地位”に最大の価値を置いて対処することを、当然のこととして政府・宮内庁に要求する。将来、天皇になるのだから、特別の養育態勢を整備すべきだというのだ。「天皇となる可能性のあるお子さまを、皇太子さま以外の宮家でどのように育てていくか。これまでにない知恵や工夫が求められる。宮内庁は職員を増やすなどして養育の態勢を整える必要がある(朝日新聞9月7日社説)」。「皇位継承の可能性が高い男の子だけに、《帝王学》をもにらみつつ、秋篠宮家の処遇を、早急に検討する必要がある(「東京新聞」9月7日社説)」等々。
法的根拠を厳密に問われることなく、その“地位”を最大限の根拠に最大級の待遇が保障される。天皇制とは、本当に無責任制度なのだとあらためて痛感する。それをメディアが率先して支えている。
(「無責任制度を支えるメディア」/ 中島啓明/ 「週間金曜日」9月22日号)
---------------------------------
民主主義がきちんと機能するためには、わたしたちひとりひとりが、冷静に考えなければなりません。そのためにも扇情的な情報を鵜呑みにしていてはならないし、個人と公との間に、きちんと一線を画する知性が求められます。上から期待されている通りにしゃべり、考えていたのでは、結局自分と自分の家族を、一部の権力者の利益のための捨て駒にさせてしまいます(注)。歴史を知り、憲法を理解し、自分の望む生きかた、願望を大切にして生きてゆく。そういう理性を養う必要があるのです。
(注)その究極の姿がエホバの証人です。彼らはエホバの証人の指導部の意志、つまり団体の体制の維持という目的のために、輸血治療を拒否するようにという指示うぃ、唯々諾々と従い続けるのです。それだけでなく、自分の子どもにまでエホバの証人の教理に従うよう半ば強要します。その結果、多くの子どもが死を選ぶことになっているのです。信者は自分で情報を集め、多面的にものごとを比較考量しようとしないから、つまり考え、判断することを、他人まかせにするから、こんな事態が生じているのです。
---------------------------------
英国のBBCはかつて1956年のスエズ戦争に際し、イーデン内閣の介入政策に批判的な立場を貫いた。マンチェスター・ガーディアン紙とともに、マスメディアが自国の戦争に抵抗した数少ない例である。そのBBCが1982年、英国対アルゼンチンのフォークランド戦争では、サッチャー政権から激しい圧力をかけられ、軍事行動に対する疑問や批判を放送することを一切禁じられた。BBCはあらゆる意見を公正に扱う原則で抵抗し、アルゼンチン政府スポークスマンの見解も反英デモも紹介した。
「政府が国益と考えることを伝えるだけが真の国益ではない。ジャーナリズムにとっては真実こそが国益だ」という思想である。厳密に言えばそういう立場を貫こうとして政府との緊張関係を続け、苦心の努力にエネルギーを注いだというのが正確だろう。「事実の報道には主観的判断を加えず、戦争当事者のどちらの味方にもならない」というう客観報道と構成の原則がその武器となった。
(「ジャーナリズムの思想」/ 原寿雄・著)
---------------------------------
日本の戦後ジャーナリズムは、1945年までの国家主義の反省から、むしろナショナリズムを抑制してきた面が強い。しかしそれが経済大国化とともに変化し、ふたたび「普通の覇権大国」への仲間入りがしたいという願望が政・官・財界に生まれ、ジャーナリズムにもそれに同調する動きが強まってきた(これは1997年第一刷発行の本の記述です。今はもっと露骨ですよね)。
日本のエスタブリッシュメント(国家・市民社会のさまざまな次元で、意思決定や政策形成に影響力を及ぼす既成の権力機構、権威的組織、体制、勢力、また既成秩序などをさす:広辞苑第5版より)の中には、…湾岸戦争を機にPKOへの参加とともに、問題の多い国連の実態をそのままにして、安保理常任理事国入りをめざす機運が強まった。メディアの中にも、これを積極的に支持する主張が目立つようになった。折から皇太子の結婚が話題になって、ジャーナリズムによる皇室ブームも起こり、学校教育への「日の丸」「君が代」の強制導入とともにナショナリズム高揚の舞台装置となった。
1992年11月、経団連ホールで開かれた「世界のグランドデザインを考える」シンポジウムで、米UCLA国際センター所長のR・ローズクランスは「日本のナショナリズムとミリタリズムは沸騰しようとしている(慧眼! 10年後の日本を見事に言い当てている)。日本はやがて核武装して世界にその力を認識させるだろう」と基調報告した。これに対し日本側パネラーは「そのような考えも動きもない」と否定していた。報告を聞きながら私自身も、「核武装に反対し戦前型ナショナリズムを抑える日本社会の力は、そんなに弱いものではあるまい」と考えていた。アジアの反発も根強い。そのうえ、米国が日本の核武装に強く反対している情勢を考慮すれば、日本が核クラブの仲間入りできる可能性は当面はないと見るべきだろう。
だが、日本人が気づかない日本ナショナリズムの底流分析を、頭から否定するべきではないと自戒もした。日本人の心情も日本をめぐる国際環境も、ナショナリズムが強まる方向に進んでおり、日本のジャーナリズムも全体として、「国益」や「愛国心」には抵抗力が弱いからである。
(「ジャーナリズムの思想」/ 原寿雄・著)
---------------------------------
この本は1997年に書かれたものですが、著者の指摘は的確ですね。ほんとうに日本のジャーナリズムは「国益」「愛国心」には弱かったことを、わたしたちは今、目の当たりにしています。上掲書はこのように続けて書いています。
---------------------------------
ジャーナリズムの歴史はナショナリズムの歴史である。そのナショナリズムが排外主義に陥りやすいことも、歴史が証明している。何が真の国益かを見分けるのは常に微妙でむずかしく、対外問題の場合、ジャーナリストはほとんどいつも、時の政府の国益論に加担してしまう。特に日本は民主主義の歴史も浅く、市民的、民権的国益観が確立していないため、国家原理にもとづく国権的な国益観が今なお、まかり通りやすい。そしてもちろん、国益と政府益とは峻別されなければならないのに、政府は政権の利益のために「国益」を口実にしたがることが多い。
ジャーナリズムは日常的に、偏狭なナショナリズムを克服して、いつも真の国益とは何かを冷静に追求することが求められる。戦争になってからでは、本当は遅い。時の政府の利益と民衆のための真の国益とを見分ける眼力をどう養うか。それは、いつの時代のジャーナリストにとっても、最大の課題といってよい。とかくごまかされやすい「国益」に代えて、「国民益」という言葉を使うことを考えてみてもよい。「国民の生命、身体、財産の安全」を離れて「国の安全」はない。「国民の利益」を離れて政権の都合による「国益」が独り歩きをするのでは民主主義とはいえない。
---------------------------------
「愛国心」についても同様です。上掲書は次のように述べています。
---------------------------------
明治政府は、日本を近代的な統一民族国家として確立し、そのために天皇制を再編・強化した。そのスローガン「富国強兵」をジャーナリズムは支持した。明治から大正への自由民権、デモクラシー運動も、大勢は国粋主義を超えられなかった。いわゆる「内に自由民権、外に帝国主義」である。自由人福沢諭吉も日清戦争の主戦論者となり、「時事新報(諭吉が創刊した日刊新聞)」で戦費集めのキャンペーンを張った。クリスチャン・ジャーナリスト内村鑑三は日露戦争に反対しながら、旅順港陥落の報を聞いたとき、隣近所に聞こえるような大声で「帝国万歳」を叫んでいた。こういう話を聞くと、ジャーナリストにとって「国籍」の業の深さをあらためて痛感させられる。
朝日新聞も1931年の満州事変を機に、それまですでに軍部の対外膨張路線を支持していた大阪毎日新聞などと足並みをそろえたが、その「転向」の理由は「国益」のためだった。右翼の介入や、軍のボイコット運動を受けた販売(店)側からの圧力もあったが、それはきっかけにすぎない。
やがて日本ジャーナリズムは、軍国主義の支持者から推進者に変貌する。いったん戦争への道を歩み始めれば、新聞も放送も政府以上に愛国者になってしまう。政府が対外政策で世論(情報の一方的提供者のマスコミによって形づくられる)より強硬だったのは近衛内閣の時だけであった、という見方もできるくらいである。…ジャーナリストは普通の愛国者以上に愛国的になりやすい。そういう面があったこと、今もあることを否定できない。
「愛国」は冷静な判断力を失わせる。ジャーナリストは「愛国」の誘惑に負けてはならないのに、「国益」が目を狂わせる。これには、ナショナリズムがメディアにとって商売上の得策になる点も見逃せない。逆に言えば、愛国熱が高まろうとしているときに、それに水をかけるようなメディアは読者・視聴者から嫌われやすい。
戦争とジャーナリズムの歴史を見ると、どこの国でもジャーナリズムが愛国心を煽り、それによって高揚した世論がさらにジャーナリズムを煽りながら、その相乗作用によって新聞は部数を伸ばし、放送は視聴者を増やしてきた。ナショナリズムは、ジャーナリズムというビジネスにとって危険な魔力を持っている。朝日、読売、毎日の各社史とも、戦争によって新聞が発展してきたことをはっきり認めている。
---------------------------------
「愛国」は冷静な判断力を失わせる。たしかにそうです。個人の尊厳の尊重という戦後民主主義の基本的精神が十分に日本に根づかなかったのは、自民党の政策によることとともに、ジャーナリズムが民主主義を消化し切れなかったことに原因があるのではないでしょうか。前回も書きましたが、天皇制というのはそういう民主主義の精神に真っ向から対立する考え方で機能しています。しかもわたしたち国民は、なぜか皇室は別扱いにします。なぜかと問う必要はないでしょう。皇室のこととなると、メディアが別格扱いにするからです。憲法の精神を差し置いて、ただ単に「地位」という価値観で広めてきたからです。
教育基本法の改正についても、歴史的に考察して、また教育行政の批判もなく、ただ子どもたちが荒れている、それは戦後の教育が悪かったからだ=戦後教育のバックである教育基本法に問題があるという、素人くさい短絡的な判断で、改正してあたりまえというような扱いです。日本が世界市場で発展してゆくためには、人間の選別、格差はしかたがない、というそう、「国益」=「企業益」という観点で惑わされているからです。ほんとうに日本のジャーナリズムは、「国益」「愛国心」に弱い。
でもみんながみんなそうであるわけではありません。眼の黒いジャーナリストも少数ながら存在します。民主主義の原理をよく理解する知的で理性的な人の一文をご紹介します。
---------------------------------
私は、秋篠宮夫妻の「第三子」誕生報道に対する自らの立場を社内(共同通信社)で明らかにしておこうと思い、要旨以下のような文章を作って労働組合に投稿した。組合の中でジャーナリズム論を論議する専門部発行の不定期のニュースで発表することを考えたのだ。以前、愛子誕生報道を批判する文章を同じニュースに書いたことがあるが、今回は、予想される大々的な奉祝報道に警告になればと思い、誕生前に投稿した。たまたま、編集責任者の不在で、次善の好評は見送られてしまったが、掲載されることにはなった。投稿の見出しは、「祝意強制する紀子出産奉祝報道をやめよう」。以下、要旨。
紀子の出産は9月初旬を予定していると報道されている。これまでの他のケースと同様、今は表向きは静かだが、その時が来るやとたんに、それこそ馬に喰わせるほどの大量の原稿が、さまざまな出稿各部から吐き出されることになるのだろう。それも、白々しく歯の浮くような賛辞が、仰々しい最大級の敬語を伴って。それを予想しただけで、汚い表現で申し訳ないが、ヘドが出そうになる。気持ち悪い。
今回の子どもの誕生は、じかに「皇室典範改正」論議につながってくる。だが、それなら、その特別な存在を許しているこの社会のおかしさを、問題提起するような報道はできないものだろうか。その子どもが生まれるというだけで、どれほどの貴重な税金が費やされるのか。それは一般の子どもと、どれほどの差があるのか。あるいは、政府や各地の自治体などが、いかにばかげた騒ぎをするのか、それがほんとうに国民、市町村民の税金を使って行政がやるべき仕事なのか、などについて、批判的にチェックするような報道をこそ心がけるべきではないのか。
少なくとも、「おめでたい、おめでたい」と、にやけたしまりのない顔で、おべんちゃらばかりを繰り返す、意味のない駄弁を垂れ流すだけのような原稿だけは願い下げにしてほしい。企業の便乗商法や商店街での祝賀行事だの、ただ社会的な奉祝機運を盛り上げるためだけの記事など、いったいどこに配信する意味があるのだろう。これらを垂れ流すことで、相乗的に、結果的に、読者、視聴者に対し、祝意を強制することにつながることを、私たちは肝に銘じなければならないと思う。
誕生以来、徳仁(なるひと)ら「東宮家」と「秋篠宮家」との間の“待遇”の差を問題にし、いかに「秋篠宮家」が“限られた”費用、体制のなかで、子どもを養育しなければならないかを強調する記事が溢れている「職員数、医療体制…大きな差。皇太子家、秋篠宮家(読売新聞9月7日朝刊)」などと。そして、優先順位の高い“皇位継承者”という、その“地位”に最大の価値を置いて対処することを、当然のこととして政府・宮内庁に要求する。将来、天皇になるのだから、特別の養育態勢を整備すべきだというのだ。「天皇となる可能性のあるお子さまを、皇太子さま以外の宮家でどのように育てていくか。これまでにない知恵や工夫が求められる。宮内庁は職員を増やすなどして養育の態勢を整える必要がある(朝日新聞9月7日社説)」。「皇位継承の可能性が高い男の子だけに、《帝王学》をもにらみつつ、秋篠宮家の処遇を、早急に検討する必要がある(「東京新聞」9月7日社説)」等々。
法的根拠を厳密に問われることなく、その“地位”を最大限の根拠に最大級の待遇が保障される。天皇制とは、本当に無責任制度なのだとあらためて痛感する。それをメディアが率先して支えている。
(「無責任制度を支えるメディア」/ 中島啓明/ 「週間金曜日」9月22日号)
---------------------------------
民主主義がきちんと機能するためには、わたしたちひとりひとりが、冷静に考えなければなりません。そのためにも扇情的な情報を鵜呑みにしていてはならないし、個人と公との間に、きちんと一線を画する知性が求められます。上から期待されている通りにしゃべり、考えていたのでは、結局自分と自分の家族を、一部の権力者の利益のための捨て駒にさせてしまいます(注)。歴史を知り、憲法を理解し、自分の望む生きかた、願望を大切にして生きてゆく。そういう理性を養う必要があるのです。
(注)その究極の姿がエホバの証人です。彼らはエホバの証人の指導部の意志、つまり団体の体制の維持という目的のために、輸血治療を拒否するようにという指示うぃ、唯々諾々と従い続けるのです。それだけでなく、自分の子どもにまでエホバの証人の教理に従うよう半ば強要します。その結果、多くの子どもが死を選ぶことになっているのです。信者は自分で情報を集め、多面的にものごとを比較考量しようとしないから、つまり考え、判断することを、他人まかせにするから、こんな事態が生じているのです。
---------------------------------
英国のBBCはかつて1956年のスエズ戦争に際し、イーデン内閣の介入政策に批判的な立場を貫いた。マンチェスター・ガーディアン紙とともに、マスメディアが自国の戦争に抵抗した数少ない例である。そのBBCが1982年、英国対アルゼンチンのフォークランド戦争では、サッチャー政権から激しい圧力をかけられ、軍事行動に対する疑問や批判を放送することを一切禁じられた。BBCはあらゆる意見を公正に扱う原則で抵抗し、アルゼンチン政府スポークスマンの見解も反英デモも紹介した。
「政府が国益と考えることを伝えるだけが真の国益ではない。ジャーナリズムにとっては真実こそが国益だ」という思想である。厳密に言えばそういう立場を貫こうとして政府との緊張関係を続け、苦心の努力にエネルギーを注いだというのが正確だろう。「事実の報道には主観的判断を加えず、戦争当事者のどちらの味方にもならない」というう客観報道と構成の原則がその武器となった。
(「ジャーナリズムの思想」/ 原寿雄・著)















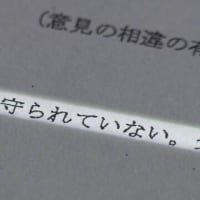
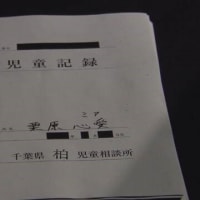






愛国心・・・すなわち、人はいのちそのものより、いのちが所属する場、とりわけ国に執着する・・・ということか・・・
いのちはどこいった???
コメントをどうもありがとうございます。
聖書にある箴言のように整った文章で、わたしの記事を端的にまとめてくださって。
きぼう屋さんのブログ、お風呂入ってから、のぞきに行きますね。
では。