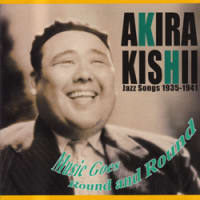去年の10月にバルセロナに滞在していたとき、情報誌「TimeOut Barcelona」の誌上で、同時期に公開されている映画が星5つ満点のうち軒並み3つ星以下という状況下(『インシディアス第2章』『グランドピアノ 狙われた黒鍵』『キャプテン・フィリップス』、そしてミヒャエル・ハネケについてのドキュメンタリー『Michael H.』など)において、唯一5つ星を与えられていたのが『アデル、ブルーは熱い色』だった。
ジュリー・マロの原作漫画『ブルーは熱い色』は未読だが、シナリオはどことなく日本映画ふうである(近年で言えば『NANA』『ハナミズキ』『横道世之介』『舟を編む』といったロングスパンの編年体による青春映画)と同時に、あきらかにオリヴィエ・アサイヤスふう(『8月の終わり、9月の初め』『5月の後』)、またはミア・ハンセン=ラヴふう(『グッバイ・マイ・ファーストラヴ』)でもある。青い髪をしたカリスマ的な男装の令嬢(レア・セドゥ)のありようは、非常に日本的だ。そして、ほぼ全編を手持ちカメラで親密かつ即席的な反美学的画風を強調しているあたりは、90年代以降の「カイエ」派の若手映画作家の系譜に属するだろう。私はこの系譜を勝手に「フィジカル・リアリズム」と名づけているのだが、『アデル、ブルーは熱い色』はそのフィジカル・リアリズムの最新の収穫である。
シックスナインやら松葉崩しやら、微に入り細に入り克明に描かれる百合族(レア・セドゥとアデル・エグザルコプロス)のセックスシーンが長すぎるという指摘があって、私もそれに首肯するのだが、これらのからみはいささかサービスカット的に過ぎはしまいか。本作を話題作にしたいというアブデラティフ・ケシシュ監督のあせりのようなものを感じてしまった。とはいえ、この二人の女の同性愛が決して精神的なきれい事で始まったのではなく、動物的な性的欲望から始まったということを言いたかったことは、じゅうぶんに伝わってくる。
スター街道の途上にあるレア・セドゥのカリスマ性もさることながら、本作の最もすばらしい点は、ヒロインのアデルを演じたギリシャ系フランス人の新人女優アデル・エグザルコプロスが醸す兇暴なまでのプリミティヴさであろう。映画の前半で彼女は、パスタをむさぼり食いつつ校内で喫煙ばかりしている、労働者階級出身のドキュン女子高生として現れて、野生児のような粗暴さがかえって見る者を惹きつける。映画の後半では一転、幼稚園の温かく美しい保母に成長しており、荒々しいヘアスタイルはそのままでも、メランコリックな孤立を際立たせている。このメタモルフォーゼがこの映画の主題だと言っても過言ではない。
ただし、《トマトのパスタ=労働者階級、生牡蠣=インテリ階級》といった描き分けはあまりにも図式的で、この図式性が『最強のふたり』と同レベルなのはいただけない。ヒロインが百合族の仲間入りをしたことが判明すると、高校の仲良しグループが急にヒロインをパージする描写のコンサバさも、どこか『最強のふたり』に似かよっている。
ヒューマントラストシネマ有楽町(東京・有楽町イトシア)ほか全国で順次公開
http://adele-blue.com
ジュリー・マロの原作漫画『ブルーは熱い色』は未読だが、シナリオはどことなく日本映画ふうである(近年で言えば『NANA』『ハナミズキ』『横道世之介』『舟を編む』といったロングスパンの編年体による青春映画)と同時に、あきらかにオリヴィエ・アサイヤスふう(『8月の終わり、9月の初め』『5月の後』)、またはミア・ハンセン=ラヴふう(『グッバイ・マイ・ファーストラヴ』)でもある。青い髪をしたカリスマ的な男装の令嬢(レア・セドゥ)のありようは、非常に日本的だ。そして、ほぼ全編を手持ちカメラで親密かつ即席的な反美学的画風を強調しているあたりは、90年代以降の「カイエ」派の若手映画作家の系譜に属するだろう。私はこの系譜を勝手に「フィジカル・リアリズム」と名づけているのだが、『アデル、ブルーは熱い色』はそのフィジカル・リアリズムの最新の収穫である。
シックスナインやら松葉崩しやら、微に入り細に入り克明に描かれる百合族(レア・セドゥとアデル・エグザルコプロス)のセックスシーンが長すぎるという指摘があって、私もそれに首肯するのだが、これらのからみはいささかサービスカット的に過ぎはしまいか。本作を話題作にしたいというアブデラティフ・ケシシュ監督のあせりのようなものを感じてしまった。とはいえ、この二人の女の同性愛が決して精神的なきれい事で始まったのではなく、動物的な性的欲望から始まったということを言いたかったことは、じゅうぶんに伝わってくる。
スター街道の途上にあるレア・セドゥのカリスマ性もさることながら、本作の最もすばらしい点は、ヒロインのアデルを演じたギリシャ系フランス人の新人女優アデル・エグザルコプロスが醸す兇暴なまでのプリミティヴさであろう。映画の前半で彼女は、パスタをむさぼり食いつつ校内で喫煙ばかりしている、労働者階級出身のドキュン女子高生として現れて、野生児のような粗暴さがかえって見る者を惹きつける。映画の後半では一転、幼稚園の温かく美しい保母に成長しており、荒々しいヘアスタイルはそのままでも、メランコリックな孤立を際立たせている。このメタモルフォーゼがこの映画の主題だと言っても過言ではない。
ただし、《トマトのパスタ=労働者階級、生牡蠣=インテリ階級》といった描き分けはあまりにも図式的で、この図式性が『最強のふたり』と同レベルなのはいただけない。ヒロインが百合族の仲間入りをしたことが判明すると、高校の仲良しグループが急にヒロインをパージする描写のコンサバさも、どこか『最強のふたり』に似かよっている。
ヒューマントラストシネマ有楽町(東京・有楽町イトシア)ほか全国で順次公開
http://adele-blue.com