≪ 日忌み(ヒイミ) ≫
生産に携わらぬ日のことをいい、物忌みを続ける日としている。
☆最も厳重な「日忌み」・・・「6月晦日のナゴシ」
一年の切れ目であるり、
この日を特に「イミ」ともいう。
人々は海水に浸り、またはそれを汲んできて飲み清め身を祓い、
その幸福を牛馬にもわかち与え、後々には司祭者の意味に用い、
忌みが終わった後の職の讃め詞として「オオ」を加えて、
「オオイミ」「オオミ」といい、春日(和珥〈わに〉)の大祝(おおはふり)
の称号ともなった。
「イムコ」・・・大嘗祭に奉仕する斎女
「イムぺ(斎部)」・・・「物イミ・大物イミ」の名を、伊勢神宮その他の
「社人」の意に用い祭祀関係を総称していう。
「清浄=近づけぬ」という思想感がある。
≪夜(ヨ・ヨル・ヨラ)=新たな日≫
「忌みもの」は約して「ヨモノ」といわれる。
「ヨ」は宵の延長、夕方の後で古くは新たな日、
ひいては、新たな年の入り方のこと。
神の憑(ヨ)りてくる時であり、人々が清まわりのために、
忌み籠っているとき、すなわち、ヨ――斎・忌み・夜を中心にして――
夜深く訪れてくるとされる。
神祭りが宵宮(ヨミヤ)から開始される理由でもある。
(前夜祭・斎忌の意・ショウジン入りともいう)
「ヨモノ」を鼠・狐・狸とするのも「夜物」の義ではなく、
形容詞は、「(※2)ユユシ(忌々し)」で、祭礼の夜籠もりを「(※3)ヨミヤ」・
「(※4)ヨド」というのと同じ。これはヤ行の発音とわかる。よって、
「イミ」・「イム」は、計画あって自ら進んで拘束生活に入ることになる。
・鼠の忌詞・・・ヨルノヒト・ヨルドリ・ヨメドノ・ヨモコドノ・
ユルノヒト(ヨルノヒトの訛)など。
・狐の夜詞・・・・・ヨルノワカイシュ
岐阜県――夜分キツネと口に出すと履物など隠されるといわれる。
東京西郊――夜、玄関に履物を揃えるようにといわれる。
・ヨボリ・ヨブリ・・・松明を振って魚を集めとる夜の魚漁りをいう(岡山・東京)
・死者の着物・・・3日目に洗濯し、一週間水をかけては「夜干し」といい
わざわざ北向きに夜干す。 (長崎・東京・四国・他)
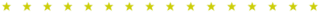
【注釈】
(※1)「斎(ユ)」・・・神秘で霊的な呪力を持っているという信仰上の語で、
これを具有するための準備・動作にも従って用いられる。
清浄を中心にしての戎慎・物忌みの意味。
「イ」と発音、清浄な・斎戎されたなどの意を含有する。
↓
つまり、庶民がたやすく近づくことができないということ。
(※2)「忌々し(ユユシ)」・・・〔形容詞〕:近づきがたい状態を示している
〔命令法〕:「ユメ(慎)」
〔活用語〕:「ユマワリ」
〔修飾語〕:「ユザサ(斎笹)」・「斎庭(ユニワ)」・
「ユツイワムラ(湯津巌群)」
(ユツ=井戸のこと)
(※3)「宵宮(ヨミヤ)」・・・ユウ(夕)・ヨイ(宵)などもユイ(斎日)で
宵宮(ヨミヤ)の行われる時間をさす。
日本の祭りは夕方から始まり翌朝に終わる。
祭礼用語として夕方=昨夜、朝=明朝のこと。
(※4)「ヨド」・・・結人・ユイ人(ユヒと)・交換共同作業仲間のことをいう。
連衆・仲間の意。
正月十五日の晩、田植装束で家々を廻り予祝しえ歩く一団を、
タウエヨド・田植踊などという例もある。
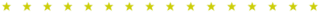
≪ 忌みの「しるし」≫
「オミゴロモ(小忌衣)」・・・その時期につける物
「褌(ちはや)・褶(しびら)の類」・・・大嘗祭に参加する官人の礼服の上につける物
・「ちはや」=たすき。もと、巫女(みこ)の用いたものをいった。
巫女が神事に奉仕するときに着た服。白布で作る。
・「しびら」=衣服の上から裳(も)のように、腰に巻きつけて着るひざ上
までの衣。略儀のもので主に下級の女房の間に用いられた。
その一例で、袖に山藍を用いて、食物の型を摺りだしている、
これが忌みの「しるし」でもあった。
≪ 精進落し ≫
この忌みのまま、すなわち精進のまま人中に出ることはできない。
「精進落し」をしてから人中に出る。
その時、普段着(マナ箸)とは別の精進箸(イモイ箸)で、
海の物(生臭さ物)を食わねば、この忌みは落ちぬと信じている。
喪の明け・盆の時も精進落しをする。盆の時期の漁も、両親を祝福
しにいく生御玉(イキミタマ)の行事も、この忌みの考えに発している。
・「精進」・・・中世の外来語
内容はこのように古く、イモイ・イワイ・イマイと呼ばれ
幸福な結果を予期する禁欲生活であり、もとはイミであった。
・忌みの内容が禁忌に転じたのは、未知の外界に対する一種の
対策後で、忌みがあったため。
・力弱い動物などが常に遁走潜匿に生涯を費やすのに反して、
人々は一定最小限の条件をさえ守っていれば自在に行動しても
いささかも恐れる事なしと確信できた結果のことで、人々の勇気の
根源を養うものとなり、迷信ではない。
≪忌みを気にかけなくなった原因≫
・一般に経験が精確になったこと
・守らなくとも格別の災いは無かった例を知り、それを記憶したため
・異郷人との接触や違った習俗で養われた者が今までの法則をたびたび
破って見せてくれたこと
・忌みの仕事を引き受けてくれる代行者が減ったこと
(異郷人や仲間の中から出た事)
などなど、忌みの不安が人々から無くなっていったからであろう。
≪ 今も残る産の忌み ≫
・産――生誕当座の忌み、ことに産屋の汚れ(赤不浄・白不浄)
を非常に嫌ったが、完全な方法は立たなかった。
・この生誕の忌みは外国にない。
・その忌み明けは、22・23日目のミヤマイリ(ウブヒアケ・ヒアケ)
として行なわれている。
☆しかしながら、忌むべき者の行動もその願いどおりにならぬことに
次第になってきた、一方、儀式や禁忌のやかましい条件が次々と
案出されてなるべく人間の生活に役立ちそうな便宜さを取り入れ、
見慣れない訪問者さえをも最もよい時期に迎えようとした。
(例:クリスマス・バレンタインデーなど)
≪ 豆知識 ≫
この「忌み」の形容詞「イミジ」の訛音
西国地方・・・「イビシイ」
東国地方・・・「イッシイ」
↓
文字に示すと「イシイ」
それが食物に限って、特に敬語をつけた女性用語「オイシイ」となった。
これは、中世以後の上方語「美味」の意で残った。
☆ご参考に!
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪いみ・いむ≫ ☆ 1 」へ
関連obi過去記事はこちら→ 「忌≪ひ≫ ☆ 3」へ
 『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著
『日本民族語大辞典』桜楓社:石上堅著 



























