カネボウの粉飾決算事件に絡んで、中央青山監査法人の公認会計士4人が逮捕されました。粉飾の事実を知っていたどころか、粉飾のご指南までやっていた、という容疑です。
追い討ちをかけるように、足利銀行が旧経営陣による粉飾決算と違法配当の事件に関連して、同じ中央青山に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。
上場企業の会計監査を行い、適正かどうかの判断を下す会計のプロである公認会計士が、その職責を十分に果たしていないということになると、投資家はどうしたらいいんでしょう。
公認会計士一人一人の人間性や、倫理、モラル、正義感などの話も当然出てくるんでしょうけど、そもそも、仕組みや制度として、もっと信頼できる監査をやっていただくためにはどうしたらいいのか、という議論が必要だと思います。
そこで一つ気になるのは「公認会計士のビジネスモデル」です。監査業務に携わる会計士さんたちは、どんな仕事をすれば、お客が喜び、評価が高まり、収入が増えて、出世できるんでしょうか?
がんがん厳しい監査をやって、「うちの先生はいい先生だ」とほめてくれる経営者は少ないことでしょう。顧客企業から、うとまれて、担当を交代させられたり、監査契約自体を打ち切られるような結果を招く会計士は所属監査法人の中でも、きっと高い評価は得にくいことでしょう。
「いい仕事」をすれば「顧客」が満足し、評価が上がって、収入と地位があがる。という単純なビジネスモデルが公認会計士の監査業務にはあてはまらないようであることが問題だと思います。
ここでいう「いい仕事」とは何か?単純に言えば、「顧客が満足する仕事」であるべきです。では、ここにいう「顧客」とは誰か?監査契約を交わし、報酬を支払うのは企業です。しかし、「仕事」の成果物である監査意見つきの財務諸表の消費者は「株主・投資家」をはじめとしたステークホルダーです。
ここにズレが生じる原因があります。契約上の顧客である企業が欲する「いい仕事」と、その株主・投資家が求める「いい仕事」が必ずしも一致しない可能性があるということです。
公認会計士という言葉は英語の Certified Public Accountant (CPA) の訳語だと聞いたことがあります。しかし、意図的にかどうか知りませんが一番大事な言葉が訳されていませんね。それはPublicという言葉です。これはつまり for the public という意味ではないのでしょうか。つまり公認会計士の仕事は顧客企業のために、ではなくて、一般投資家のために行なうべきもの、ということをわざわざ明示しているのではないでしょうか?
監査法人は顧客企業から報酬をもらう訳ですが、そのお金(会社のお金)は本来株主のものです。また、監査法人を選んで雇うのは経営者ですけれど、その経営者を選んで雇っているのは、株主です。
従って、公認会計士たるもの、企業から雇われているのではなく、株主から雇われているのだ。株主のために「いい仕事」をするのだ。との自覚を忘れて欲しくないものです。特に相手が上場企業の場合、株主の顔が見えるわけではありませんので、「一般投資家」つまりパブリックに対して責任を負う仕事をしているのだ、ということを忘れて欲しくないと思います。
上記に沿って、株主および一般投資家のために行なった「いい仕事」が「高い評価」に結びつくという、すっきりしたビジネスモデルを確立し直さないと、会計士さんの憂鬱な日々はまだまだ続きそうです。
追い討ちをかけるように、足利銀行が旧経営陣による粉飾決算と違法配当の事件に関連して、同じ中央青山に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。
上場企業の会計監査を行い、適正かどうかの判断を下す会計のプロである公認会計士が、その職責を十分に果たしていないということになると、投資家はどうしたらいいんでしょう。
公認会計士一人一人の人間性や、倫理、モラル、正義感などの話も当然出てくるんでしょうけど、そもそも、仕組みや制度として、もっと信頼できる監査をやっていただくためにはどうしたらいいのか、という議論が必要だと思います。
そこで一つ気になるのは「公認会計士のビジネスモデル」です。監査業務に携わる会計士さんたちは、どんな仕事をすれば、お客が喜び、評価が高まり、収入が増えて、出世できるんでしょうか?
がんがん厳しい監査をやって、「うちの先生はいい先生だ」とほめてくれる経営者は少ないことでしょう。顧客企業から、うとまれて、担当を交代させられたり、監査契約自体を打ち切られるような結果を招く会計士は所属監査法人の中でも、きっと高い評価は得にくいことでしょう。
「いい仕事」をすれば「顧客」が満足し、評価が上がって、収入と地位があがる。という単純なビジネスモデルが公認会計士の監査業務にはあてはまらないようであることが問題だと思います。
ここでいう「いい仕事」とは何か?単純に言えば、「顧客が満足する仕事」であるべきです。では、ここにいう「顧客」とは誰か?監査契約を交わし、報酬を支払うのは企業です。しかし、「仕事」の成果物である監査意見つきの財務諸表の消費者は「株主・投資家」をはじめとしたステークホルダーです。
ここにズレが生じる原因があります。契約上の顧客である企業が欲する「いい仕事」と、その株主・投資家が求める「いい仕事」が必ずしも一致しない可能性があるということです。
公認会計士という言葉は英語の Certified Public Accountant (CPA) の訳語だと聞いたことがあります。しかし、意図的にかどうか知りませんが一番大事な言葉が訳されていませんね。それはPublicという言葉です。これはつまり for the public という意味ではないのでしょうか。つまり公認会計士の仕事は顧客企業のために、ではなくて、一般投資家のために行なうべきもの、ということをわざわざ明示しているのではないでしょうか?
監査法人は顧客企業から報酬をもらう訳ですが、そのお金(会社のお金)は本来株主のものです。また、監査法人を選んで雇うのは経営者ですけれど、その経営者を選んで雇っているのは、株主です。
従って、公認会計士たるもの、企業から雇われているのではなく、株主から雇われているのだ。株主のために「いい仕事」をするのだ。との自覚を忘れて欲しくないものです。特に相手が上場企業の場合、株主の顔が見えるわけではありませんので、「一般投資家」つまりパブリックに対して責任を負う仕事をしているのだ、ということを忘れて欲しくないと思います。
上記に沿って、株主および一般投資家のために行なった「いい仕事」が「高い評価」に結びつくという、すっきりしたビジネスモデルを確立し直さないと、会計士さんの憂鬱な日々はまだまだ続きそうです。










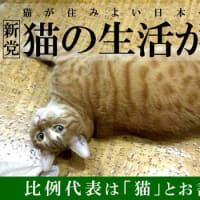

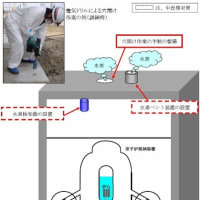


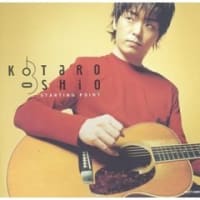

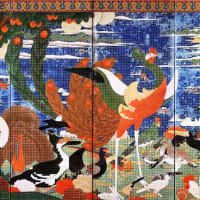


この問題の、何が問題点か、が
よくわかります。
確かに、どんな犯罪も、
犯罪を犯した人間が悪いんでしょうけど、
やぶ猫さんの言う、「単純なビジネスモデル」があてはまらないんじゃ、
仕事をまっとうにしても、割に合わないし、
「やってらんね~よ!」
って気持ちになってしまいますよね。
toshi親分のところでお名前拝見したもので遊びに来させていただきやした。
やぶ猫さんのお立場では、そもそも大手監査法人がコンサル業務を行ってること自体もなんか問題あるってことになるんでしょうかね?
ろじゃあ的にはコンサルやってる企業の監査もそこがやってるってことになると結構問題があるような気がするんすけど、実際にはそういうことは少ないんでしょうか?
またお邪魔させてくださいまし。
>仕事をまっとうにしても、割に合わないし、「やってらんね~よ!」って気持ちになってしまいますよね。
↑こんな気持ちになってる会計士の先生方が多いのではないかと心配です。実際、社会全体から見ればものすごく大事な役割を担っているお仕事であることは間違いないので、彼らが憂鬱にならないでバリバリ仕事に励むことができるような仕組みを用意してあげるべきだと思いますね。
初めまして、コメント有難うございます。
>コンサルやってる企業の監査もそこがやってるってことになると結構問題があるような気がするんすけど
この点はもう結論が出てるんじゃなかったですか?法制度的にどうなっているか知りませんが、少なくともアメリカではこれはもう禁止に等しい状態だと思います。日本でも、少なくとも大手監査法人であれば、同様だと思ってました、(制度的になのか自主的になのかは知りませんけど)。
要するに、監査業務という、アップサイドが無くて、ダウンサイドだけが馬鹿でかいお仕事があまりに憂鬱すぎるので、弁護士やインベストメントバンカーのようなアップサイドがでかくて、リーガルリスクの小さなコンサル、アドバイザリー業務が羨ましくてしょうがなかった、と。
ところが、それを監査担当企業相手にやると、利益相反だと言われて大変お叱りを受けてしまって、ご法度になったという経緯だったんじゃないでしょうか?
今でも平気で監査業務とコンサル業務の両方を同じ顧客企業に提供している監査法人があるとすると、相当問題あると思いますけど。。。
そこで、問題解決の方法ですが、私には3つの方法が考えられると思ってます。その3つにつきましては、また「やぶ猫」さんのエントリーを参考に、ブログに書いてみたいと思います。(思いっきりハズしてしまうかもしれませんが・・)
今後ともよろしくお願いいたします。
ご回等ありがとうございます。
そうかあ・・・そうしたら大手の監査法人とその系列会社って相当の需要減で結構大変ってことなんですね。
それはそれで大変なことですよね。
でもSPC関連の業務とかは誰が担うことになるんでしょうかねえ・・・
単純にSPCから依頼があってSPCの監査を行う・・・以外の業務は会計士の先生がおやりになることはなくなるっとことですかね。そもそもあんまりやってないか(^^;)。
お立ち寄りいただきありがとうございます。問題解決のための三つの方法、楽しみにしております。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
>ろじゃあさんへ、
>そうかあ・・・そうしたら大手の監査法人とその系列会社って相当の需要減で結構大変ってことなんですね。
いや、そういうことではないと思います。利益相反さえなければいいわけで・・・。むしろコンサルのニーズは今後益々多くなると思うし、監査の仕事に比べればはるかにお気楽なので、有能な人材が益々そちらに流れて監査業務の品質が落ちることの心配をした方がいいのではないかと...。
今回の事件では、私もやぶ猫さんと同様の問題意識をもっております。
コンサルの話ですが、おっしゃるように会計会社も今は利害関係のあるところのアドバイザリーにはならないようにしてるようですね。
一人の零細投資家として、この辺の話題にも、たまに触れることがあります。是非、また遊びにいらして下さい。
公認会計士のコンサル業務についてですが、現在は公認会計士法24の2で、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供は法律上禁止されているようです。
ただこの規定も法人によって解釈の仕方に差があるようでして、いわゆるデューデリジェンス業務などは全て問題なしなどとしているところもあるようですね。