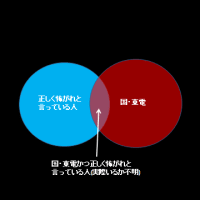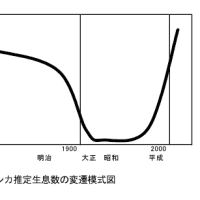WEBRONZA批判その2となります。今回は梨の気持ちをブルーギルとワニガメに代弁してもらいます。長いので、長文が嫌な方は読まなくてもいいと思います。
ブルーギル(以下ギル):お久しぶりです読者のみなさん。
ワニガメ(以下カメ):今回はWEBRONZAには危機感が足りないというのがお題です。
ギル:危機感が足りないと言ってもいくつか複合してるよね。
カメ:と言うと?
ギル:まずはホメオパシー問題に関わってくるものとしての危機感。今さら、ホメオパシーの危険性について知りませんでしたで済むはずも無し。肯定にしろ否定にしろホメオパシーを扱うということのデリケートさに気付いていると思えない。
カメ:それを言っちゃうと、大概のメディアが引っかかりそうな気がしますけどね。朝日のアピタルのおかげでだいぶ知られたと言えど、それ以前ならあの程度どこでもみられたのでは?
ギル:以前ならまだね。ただ、あの記事が出た時点で「代替医療のトリック」という優れた入門書がホメオパシー問題に関わる人間には知られていたわけだから。知らないという言い訳がはたしてどこまで通用するか。さらに、WEBRONZA側の対応が事態をややこしくしてるんだよね。「当方は当然、ホメオパシーには否定的」なんてツイートもあるし(こちら参照)。じゃあ、なんで論文にあたれば分かる間違いを見過ごして載せたのかと。否定にしろ肯定にしろ裏をとらないと足をすくわれる格好の例示になっている。
ギル:次に誤情報を垂れ流したままにしておくことに対しての危機感。間違いがあると分かった後も訂正などなんら公的な対応がない。結果としてこの記事を書いている現在、誤情報が垂れ流し。
カメ:WEBRONZA側としては同じ朝日内部でホメオパシーに詳しい久保田氏の記事が出たからそれでいいだろと思ってる節がありますけどね(注:梨の視点から見たとき)。
ギル:でも肝心の元記事には久保田氏の記事へのリンクすらないからね。検索してきてあれを見た人間が久保田氏の記事まではたして見るか?ということだよな。事前に事情をしってりゃ別だが。
カメ:梨の個人的経験則にすぎませんが、ああいうのを読んで効果があると思っちゃう人が異論、反論があることまで調べることめったにないですからね。熊森批判などをしてきた経験からですが。
ギル:WEBRONZA側が元記事に対して注釈なり追記をつけないと、どうしようもないよな。1人、自力で検証する裏でその何倍もの人が誤情報を鵜呑みにするわけだし。
ギル:次は淘汰されることへの危機感。例えば、梨のような個人ブロガーが誤情報を垂れ流しということがあったら、それは梨という論者にとっての信頼に関わる。最終的に誰からも相手にされなくなる。そういう淘汰されることへの危機感がない。
カメ:ネットじゃ往々にして起こりますからね。誤情報垂れ流し→批判→炎上→記事削除、ブログ閉鎖みたいなコンボ。きちんと訂正などの対応をすれば何とかなることもありますが。
ギル:WEBRONZAの場合、梨の見立てだと批判から炎上に移りかけてるんだよな。すでに梨含め見切りをつけた人が出てきてるし。事態がこれ以上大きくなったらドカッとクレームが来てもおかしくないんじゃね?仮に今回むりやりうやむやにしても禍根を残すし。
カメ:というか、そのうやむやに失敗して今のあり様じゃないですか?なんにせよ読者を甘く見ているなと。
ギル:次、品質管理への危機感。これは淘汰とも被るけど。WEBRONZAって金もらって仕事してるんだよね。それが市井のブロガーに情報精度で圧倒的に負けている。無料と有料、しかも無料のほうが質が高ければ消費者は最終的にどちらになびく?
カメ:そりゃ、無料でしょう。で、最終的には有料は淘汰されると。これが仮に食品メーカーなどだったらどうなるでしょうね?品質管理する気のないメーカーをいつもメディアはどう書きたてるか。
ギル:実際はそんな簡単に淘汰されないと思うけどね。なんだかんだで大企業の一部で安定的なわけだし。でも、安定的であることが逆に淘汰されることへの危機感を薄れさせてるな。多少質の悪いものを提供しても淘汰されないなら、出来うる限り質を下げて売りつけた方が楽だし。向こうとしては上げる理由もないと思ってるんじゃないかな。
カメ:それ、北村氏の受け売りですよね。梨はあの人のブログを面白いと思っていつも読んでますし。
ギル:まとめますと、WEBRONZAに足りない危機感は大きく分けて3つ。問題にかかわること。誤情報の垂れ流し。淘汰されること。
カメ:WEBRONZA問題については以下の記事も読むとよりよいと思います。むしろこんな長い記事を読むより・・・(ry
ホメオパシー記事の訂正を拒む朝日新聞WEBRONZA
この一件に一番深くかかわったMochimasa氏の記事。
Web論座がホメオパシーについて事実誤認の記事を載せっ放しで対応しない件(2011/2/9現在)
非常に分かりやすいまとめとなっています。
ブルーギル(以下ギル):お久しぶりです読者のみなさん。
ワニガメ(以下カメ):今回はWEBRONZAには危機感が足りないというのがお題です。
ギル:危機感が足りないと言ってもいくつか複合してるよね。
カメ:と言うと?
ギル:まずはホメオパシー問題に関わってくるものとしての危機感。今さら、ホメオパシーの危険性について知りませんでしたで済むはずも無し。肯定にしろ否定にしろホメオパシーを扱うということのデリケートさに気付いていると思えない。
カメ:それを言っちゃうと、大概のメディアが引っかかりそうな気がしますけどね。朝日のアピタルのおかげでだいぶ知られたと言えど、それ以前ならあの程度どこでもみられたのでは?
ギル:以前ならまだね。ただ、あの記事が出た時点で「代替医療のトリック」という優れた入門書がホメオパシー問題に関わる人間には知られていたわけだから。知らないという言い訳がはたしてどこまで通用するか。さらに、WEBRONZA側の対応が事態をややこしくしてるんだよね。「当方は当然、ホメオパシーには否定的」なんてツイートもあるし(こちら参照)。じゃあ、なんで論文にあたれば分かる間違いを見過ごして載せたのかと。否定にしろ肯定にしろ裏をとらないと足をすくわれる格好の例示になっている。
ギル:次に誤情報を垂れ流したままにしておくことに対しての危機感。間違いがあると分かった後も訂正などなんら公的な対応がない。結果としてこの記事を書いている現在、誤情報が垂れ流し。
カメ:WEBRONZA側としては同じ朝日内部でホメオパシーに詳しい久保田氏の記事が出たからそれでいいだろと思ってる節がありますけどね(注:梨の視点から見たとき)。
ギル:でも肝心の元記事には久保田氏の記事へのリンクすらないからね。検索してきてあれを見た人間が久保田氏の記事まではたして見るか?ということだよな。事前に事情をしってりゃ別だが。
カメ:梨の個人的経験則にすぎませんが、ああいうのを読んで効果があると思っちゃう人が異論、反論があることまで調べることめったにないですからね。熊森批判などをしてきた経験からですが。
ギル:WEBRONZA側が元記事に対して注釈なり追記をつけないと、どうしようもないよな。1人、自力で検証する裏でその何倍もの人が誤情報を鵜呑みにするわけだし。
ギル:次は淘汰されることへの危機感。例えば、梨のような個人ブロガーが誤情報を垂れ流しということがあったら、それは梨という論者にとっての信頼に関わる。最終的に誰からも相手にされなくなる。そういう淘汰されることへの危機感がない。
カメ:ネットじゃ往々にして起こりますからね。誤情報垂れ流し→批判→炎上→記事削除、ブログ閉鎖みたいなコンボ。きちんと訂正などの対応をすれば何とかなることもありますが。
ギル:WEBRONZAの場合、梨の見立てだと批判から炎上に移りかけてるんだよな。すでに梨含め見切りをつけた人が出てきてるし。事態がこれ以上大きくなったらドカッとクレームが来てもおかしくないんじゃね?仮に今回むりやりうやむやにしても禍根を残すし。
カメ:というか、そのうやむやに失敗して今のあり様じゃないですか?なんにせよ読者を甘く見ているなと。
ギル:次、品質管理への危機感。これは淘汰とも被るけど。WEBRONZAって金もらって仕事してるんだよね。それが市井のブロガーに情報精度で圧倒的に負けている。無料と有料、しかも無料のほうが質が高ければ消費者は最終的にどちらになびく?
カメ:そりゃ、無料でしょう。で、最終的には有料は淘汰されると。これが仮に食品メーカーなどだったらどうなるでしょうね?品質管理する気のないメーカーをいつもメディアはどう書きたてるか。
ギル:実際はそんな簡単に淘汰されないと思うけどね。なんだかんだで大企業の一部で安定的なわけだし。でも、安定的であることが逆に淘汰されることへの危機感を薄れさせてるな。多少質の悪いものを提供しても淘汰されないなら、出来うる限り質を下げて売りつけた方が楽だし。向こうとしては上げる理由もないと思ってるんじゃないかな。
カメ:それ、北村氏の受け売りですよね。梨はあの人のブログを面白いと思っていつも読んでますし。
ギル:まとめますと、WEBRONZAに足りない危機感は大きく分けて3つ。問題にかかわること。誤情報の垂れ流し。淘汰されること。
カメ:WEBRONZA問題については以下の記事も読むとよりよいと思います。むしろこんな長い記事を読むより・・・(ry
ホメオパシー記事の訂正を拒む朝日新聞WEBRONZA
この一件に一番深くかかわったMochimasa氏の記事。
Web論座がホメオパシーについて事実誤認の記事を載せっ放しで対応しない件(2011/2/9現在)
非常に分かりやすいまとめとなっています。