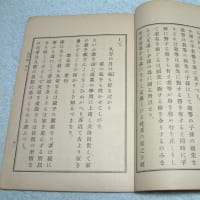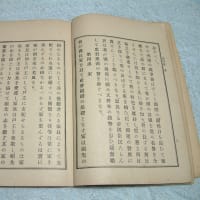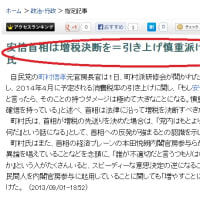http://blog.goo.ne.jp/maniac_club/e/e83deeb1457b963a78ac21626fa1e7b5
続き・・・。ダラダラ書いてます。
製造する製品は原価計算をし、仕入れる商品には適切な販売価格を設定していれば、”利益”は生じる。これには”目標とする売上”を超えるという前提があるのだが、目標とする売上高を確保していても利益が出ないのは二つのケースが考えられる。
一つは、原価設定の甘さ、そして、もう一つは営業関連経費が過大になっている。の二点である。
製造業と小売業では、その原価構造というのは異なるのだが、販売価格(納入価格)の設定の構造は似通っている。小売業が消費者のニーズによって価格が決定されるのに対して、製造業は納入先のニーズによって価格は決定される。つまり、相手先があってこその売上・・・どのような業種・業態であってもいえることである。
では、原価とは何か・・・。基本的には、製品に対する調達や製造のコストということになるのだが、これに営業に必要な費用・・・人件費などを含めたものを指す。
原価設定の構造としては二つの手法がある。一つは積み上げ式、そして、もう一つは予測される売上高からの分解である。これらは業種や業態によって異なる。
建設業や製造業などで事前に価格が決まっているものはその価格から各コストを割り振る分解方式が多様される。サービス業のように個々に提供するものが床なる場合には積み上げ式となることが多い。しかし、建設業でも、リフォームのように個々に提供する内容が異なれば積み上げ式になることもある。
市場というのは不思議なもので、独創的な製品やサービスにおいて独自の市場開拓を行っても、その市場の規模が拡大することによって、市場においての”値ごろ感”というものが発生してくる。市場の成立期は高額な製品やサービスも市場の拡大に伴い参入する他の企業の製品などによって、市場の中に企業間や企業と成否者の間に不思議なコンセンサスが生まれ、価格がある一定の枠内に収まってしまう。これが値ごろ感といわれるものである。
積み上げ式においてもこの値ごろ感というものを無視することはできず、当初は積み上げ式で算出していても、競合他社の価格と比較しながら価格の落ち着き先を模索することになる。
市場を独占する技術なり、アイディアや製品がない限りは、この値ごろ感というものの存在は無視できない。
マイクロソフト社が急速な成長と売上規模の拡大を計ることができたのに対して、ハードを供給する企業の売上や利益が比例しなかったことは、これらの説明を裏付けるものであるといえる。
つまり、特殊な環境下にあるもの以外は原価というものは常に変動するものであり、その多くの場合、売上高の低下と共に変動せねばならないという事情を抱えるものであるといえる。
そして、もう一つ。生産や販売というピラミッドの中で、ピラミッドの下部に位置する企業ほど単価は安くなるということである。つまるところ、利益幅もうすくなるということである。
しかしながら、誤解されることのないように願いたいが、大企業が儲けを多く得るためにその下部にいる企業に負担を求めていると単純に考えていただきたくはない。様々な説明を省略するが、売上高対総利益率で売上高に対しての利益率から見れば、大企業は売上高そのものの規模の大きい分だけ利益額も大きいが、売上高に占める利益の割合がずば抜けて多いわけではない。
さて、寄り道をしながら原価について書いたわけだが、この原価と原価計算の本来の意味を今後のエントリーで書いてみたいと思う。