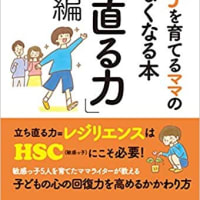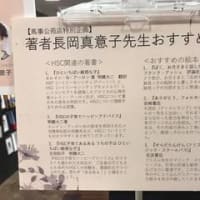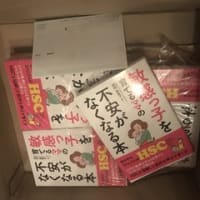この夏、
いくつか米国東海岸近辺の大学を訪ねる機会があったのですが、
とにかく気づいたのは、「多様な学生」を集めようとしている、
ということ。
それは、文化的背景であったり、人種であったり、生育環境の経済的背景であったり、
成績やテストスコアとはまた別の能力、
例えば、リーダーシップや創造性であったり。
(経済的には、親の年収が約1500万円以下なら、
学費免除&生活費支給を施すとしている大学も多かったです)
こうした「多様性を包み込む姿勢」は、
米国の建国理念にも基づいているわけですが、
同時に、「理念」だけではなく、
実はとても「プラグマティック(実利的)な方法」であるという
大学側の共通の認識があるように感じています。
つまり、大学側も、
「多様性」が「創造性や革新」を生み出す要、
そして「創造性や革新」こそが、
これからの世界をリードするための鍵となると分かっているんです。
同じような意見や見方をする集団よりも、
様々異なる視点、アイデア、発想が寄り集まった方が、
それは「創造や革新」につながりますよね。
そうした「エートス(場の心的倫理的雰囲気)」のなかで切磋琢磨し、
「創造や革新」的な成果をあげる人材を輩出することで、
大学側も名をあげ、これからの世界を生き残っていけるというわけです。
また、
アメリカという国自体の創造性や革新といった強みも、
この「多様性」が源になっているんですよね。
今回の大統領選結果というのは、
理念的にもプラグマティックな理由からも、
主要大学はじめ、急成長する企業や国が促進する、
「多様性」の流れに、
まさしく逆行しているかのようです。
トランプ氏は今のところ(当選後のオバマ大統領との話し合いをみても)、
キャンペーン中の過激な発言は、
キャンペーンを戦うための演技&交渉を始めるための手段であり、
実際はより多様な人々を包み込んだ「現実路線」を歩むとしているようですから、
どう動いていくのかみていきたいですが。
状況を見守りつつ、
日々の生活で私達ひとりひとりにできることのひとつは、
自身と向き合うこと、だと思っています。
異なる意見にカチンとくる、
異質さに不快な気持ちを持つ、
これらは、
人類が長い歴史の中で自らを守るために培ってきた自然な感情ですが、
それらの感情を、どう行動へと表していくかは「選択」できるわけです。
自らの感情の隆起に、
なぜ自分はこう感じるんだろう?
相手は何を言わんとしてるんだろう?
ここで大切なこととは何なんだろう?
どうしたら互いのよい部分が生かされるだろう?
などなど、問うてみる、考えてみる。
こうした姿勢を磨いていくことが、
異なる者同士が共に生きることのできる場を生み出すためのひとつの方法ですね。
こう書きながら、
ああ、夫婦関係もまさになあ、と思いつつ ← 昨日夫婦喧嘩したばかり
「夫婦関係」というのも、異なる者同士が力を合わせ創造するための
最たるトレーニング場かもしれないですね。
今できることを、こつこつとしていきたいですね!
みなさん、今日もよい日を!