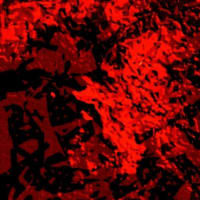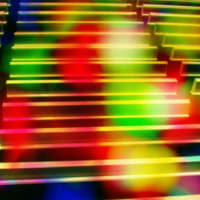少し前のこと、近くの運動公園辺りまで夜のウオーキングをしていた時に、何故か分からないけれども浮かんできたある言葉があった。「gentile」。意味の分かるような言葉でもない。ジェンタイル。どこかで触れたような気もするけれども、でもその何処かの見当は全くつかないし、記憶と全く結びつかない言葉がふいと浮かんできたというような感覚。その言葉を忘れないようにして、帰ったら意味も見てみなければと考えた。その通りに戻ってからすぐに手帳にメモをしたものの、そのままにしてしまって意味を確かめたのは2日位後。全く記憶にない意味だった。そこで知ったような意味がその言葉にあるというのも、結びつかないような印象。知らない言葉の、知らない由来。何にしてもその言葉に意味を結びつけ、必要であれば記憶をする、そういうことでしかないと思われたが、兎も角何処で出会った言葉なのか、全く記憶からは消えていて、辿りようもない。
また何日かが過ぎるうち、なにかそうした宗教の絡むようなビデオを、YouTubeで見たことからなのではないかと思うようになった。英米のビデオには当然ながら殆どサブタイトルのようなものはないから、英語そのまま。よって見ていて分からない言葉が出てくるとビデオを一端止めたりなどして、電子辞書で確かめることになる。多分、gentileという言葉も、そんなふうにして電子辞書で見たものなのだろう。だが記憶にとどめる必要のあるような言葉ではなし、その場で解ればすぐに忘れて構わない言葉。実際、すぐに意味を知ってビデオに戻ってじきに、もう忘れてしまっていたようなもの。それが意味を忘れられたまま、言葉がどれだけの期間を置いた後にか、謎の筋道を辿って記憶の何処かから甦ってきた。そんなところであるらしいもの、と。
* * *
自分の人生の中でも珍しい、特異ということになるような体験の一つ。そういうのを、何年か前の夏に経験した。当人の感覚としては、やはりそうした言い方をするしかないようなものだったと思う。全く記憶のない時間の中の出来事を、自身がその時間の中で手にしていたカメラが明らかにしてくれる、というような状況の生まれた体験。夏に故郷にお墓参りに行った時のこと。早朝此方を出て新幹線を使い、昼近くに故郷の親戚宅に着いて、それからご馳走になり、普段は全く飲まないアルコールを、例年のようにその日だけは飲むことにしたのである。2時間程してみんなでゆっくり歩いて15分ほどの墓地に出掛けたのだけれども、その出掛ける前の、何処辺りからなのか、記憶が全く無くなってしまった。よってどのような自分がそこにいたのか、分からない。見当もつかない。酔っていたとすれば、まともに行動できていたのか。他の者たちは私をどのように見ていたのか。無事にお墓参りができていたのか。記憶にないほどに酔いが回っていたのだとすれば、恥ずかしくなるようなことをしていたのではないだろうか? 非常に気になった。気になったのは、帰って眠った後の、通常の意識に戻った翌日になってからである。
覚えているのは、帰りの新幹線の中辺りからのことであるから、それ以前のこと。夕方になって出発し、新幹線に乗るJR駅まで1時間もかかるバスに乗ってやってきたわけだけれども、どのような自分がそこにいたのか、全く分からない。知ることもこわい、というのが普通状態に戻った翌日の感覚。一緒にお墓参りに行ったのは、東京から車で行った姉、甥夫婦とその双子の赤ちゃんや5歳の長男、故郷の従姉などなのだけれども、さてさて、恥ずかしい酔態を見せなかったものか。例えばのこと、お墓参りというのに酔いによろけてしまうようなことでもそう。それにしても、何故にそのような酔いになったのか? 普段はアルコールを飲まないという人間が、ビールで始め、消防署に勤める従姉の息子などと次には焼酎を割って何杯か、ということになって、大丈夫と思っている間に回ってしまったものらしいのだが、飲むのは毎年のことだしペースも同じようなものだったのにということ。実際にはまさかという展開になって、その記憶にない時間の中のなにかをカメラの画像が見せてくれる、それに頼るしかないということになったという次第。
なにが見えてくるか。真っ暗闇状態の記憶部分。そこに浮き出るはずのカメラの画像。PC上で、見る。未体験。ということでは、面白い経験ができたもの、という結果ともなることだったが、アルコール絡み。人には知られたくないような体験。画像を見る勇気のようなものがでてきたのは、その日も遅くになってからと記憶する。恐る恐るという感覚。写っていたのは毎年の、見慣れた彼らのそこでの様子。ということでは、私もまた変わらぬ、ごく常識的な振る舞いに終始していたもの? 印象としては、そのように伝わってきた。だがともかくその後、彼らにその日のことをきいたわけでもない。夕刻に近くなって彼らと別れるまで自身がどのようであったかは、暗闇の中のまま。