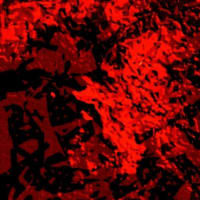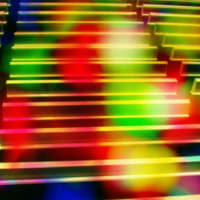私というのは何だろう、それは人生の中でさまざまな時に思うことなんだろうけれども、ある時の自身のこと。ずうっと向こうの駅に向かって、途中に消防署、その隣に中学校の校門に向かう路のある坂道を歩きながら、全体を構成する細胞の集まりから成るものにすぎない、というようなイメージに達したことも。そういう、心云々とは無縁の処にある形のものが、人間の私なるもの、というイメージ。私とは、細胞の集合に過ぎない、それが実際の姿、というような妄想。
あるいはまた、だれしもそういう経験はするものだろうけれども、鏡の中の自身に、不思議な思いを抱かされる瞬間の訪れ、などというもの。何を感ずることもなく当たり前に鏡の中の自身を見ていることが普通の日常の中、ふいと鏡を境にした自身と映る姿の距離の間で、向こう側の自身のものである顔が、不可解な入りえない別の側にいる何者かの相を帯びて感じられる。そうしたある意味、詩的、幻視的、とも思えるような経験など。
1970年結成のイギリスのバンド、Supertramp。その1979年リリースのアルバムにBreakfast in Americaがあるのだけれども、それに収められた曲の中に、結成メンバーの一人Roger Hodgson作の"Logical song"がある。When I was young it seemed that life was so wonderful の言葉で始まり、そして現実の世界を知り生きる中のこと、それにつづいて、夜、世界が眠りにつく頃、さまざまな疑問が頭の中をかけめぐる、、、、、、と歌われる。
その終わりに、please tell me who I am/Who I am,who I am,Who I am と繰り返されるのだけれども、歌うRogerの声はwho I amの繰り返されるごとに音階が上がり、最後はよくぞそこまで声が出るもの、と思えるような音に行く。切実な思いの、声をもっての表現。そのwho I am というのが、そう以前の事ではない自身の夜などに、やってくることがあった。その言葉通りに、分からなくなる自分がいたということ。自身が希薄になる、そういう状況。
自身がそうしたところまで行くとは、思ってはいなかったというようなこれまでだったと思うけれども、年齢的なものもあってのものかとも思う。おそらくは自身が確かにあることを感じるためには、当たって確認できるような対象が、必要ということなんでしょう。そこのところが抜けているうちには、やはり夜のような時間、自身が何者なのかが分からないような、希薄さに嵌まり込んでいくようなことに。それはある一夜の、その時だけに濃く来るものであるかもしれない。その余波が何日もつづくことも、思われる。
R.Hodgsonの歌うWho I amの言葉が甦ったと言っても、その曲の中のWho I amと私の場合のWho I amは、内景が異なるわけで、"私は誰なのか?" という問いかけは同じでも、ひとそれぞれにその状況も感覚も異なるはずのもの。最初に書いた、ある時に自身が振り落されるように至ってしまった自身とは細胞の集成によるものでしかない、というようなある意味無残でしかないような心的状況からのものも、Who I am に突きつけられたあるイメージ。
あまり本は読まなくなっているのだけれども、今少し読んでいるのが坂口安吾(1906-1955)。同じ新潟の出身ということからの関心などもあって、昔から書かれたものとのつきあいある作家で、読んでいるのは自伝的な作品ばかりが収められた一冊。自身を巡ることについて、赤裸々に書いてくれている、興味深い内容。そこに「私は誰?」という一篇がある。彼という人を思えば、そのタイトルから推して、その先が朧に見えそうな、そしてまたそれを知りたい思いにさせる、書かれての真実に触れる部分。
その最後の処で、彼はこのように書いている。「(略)別に、年齢が四十をすぎたというようなことも、まるで感じていない。私の魂は一向に深くもならず、高くもならず、生長したり、変化している何物も感じていないのだ。/私はたゞ、うろついているだけだ。そしてうろつきつゝ、死ぬのだ。すると私は終る。私の書いた小説が、それから、どうなろうと、私にとって、私の終りは私の死だ。私は遺書などは残さぬ。生きているほかには何もない。/私は誰。私は愚か者。私は私を知らない。それが、すべて。」
「私は私を知らない」、それを、言われてしまう。普通には、人は何らかの形で自身を飾りたがるものだけれども、裸の精神をそのままに見せてくれる人。やはり、そういう人を見たい。そういう人の言葉が、心に響く。残る。ということを思う。そうして彼もまた答からは見放されていたような、「私は誰?」。 その問いを究極向けるとなると、知ることのできない宇宙の果てのような、底の知れない深淵と向き合わざるを得ない処に、やはり行くしかないことになるように思える。