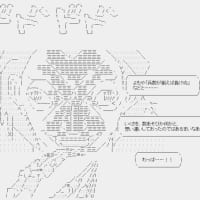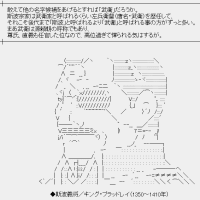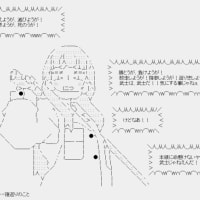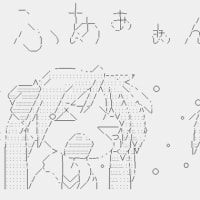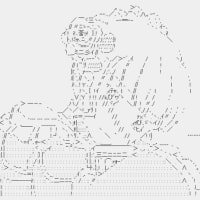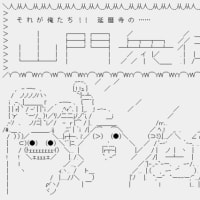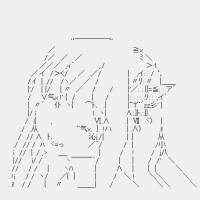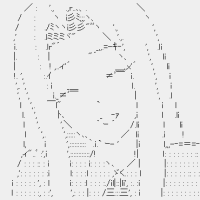【怪獣とは何か?】
ここしばらく、このブログでは『怪獣』の話を、ぼちぼち、したり、しなかったり、しているかと思いますが、まず、ここらで僕の中の『怪獣』に対する定義付けの話をしておこうと思います。
とは言ってもパブリックな怪獣の定義というわけではないので、気をつけて欲しいのですが(汗)………まず、僕が“怪獣好きな人”という前提があって…日本の怪獣映画と、洋画のモンスター(型)映画を観ていると「何かが違う?味わいのようなものが違う」と思うわけです。それで怪獣映画とモンスター映画を見比べていて「あ、これは怪獣映画っぽいかも?」「…これは怪獣じゃないな?」とか…怪獣好きですからね。そうやって選別して行く中で、まあ、大体こういう感じだと怪獣映画と言えるかな?という線引きのようなものが視えて来たわけです。
そこを詰めた話はまた別にして行きたいのですが、ここでは、分かりやすく大雑把に僕が何に怪獣を感じるか?を述べます。①近代兵器(またはそれに準じるもの)が通じない超存在~畏怖される存在~である事②基本的に人類と相入れぬ物(多くは敵)として描かれ、人型を為していない異形の対象であるにも関わらず感情移入~あるいは託願~の対象として扱われている事。
これを畏怖と託願とまとめますが、特に託願(感情移入)が重要ですね。そして、それは「受け手の、心象によって変化するもの」であると言えます。つまり、僕が感情移入できず「怪獣映画じゃない」と思っても、他の人には怪獣映画(的な受け止め方)になり得ると言う事です。
たとえば、以前に取り上げた『ボアvsパイソン』(2004年公開)ですが…
▼『ボアVSパイソン』~洋画の“怪物対決もの”はどんな感じか?
…僕はこの映画は人間の描きに重点が置かれた「怪獣映画ではないもの」という判定をしていますが、この判定は非常に微妙でして、一応、人間側の味方っぽい位置についたボアの方には、ある程度の“感情移入”を見て取れるのですよね。二大怪物の激突をウリにしている事からも、怪獣映画と捉える事も充分に可能な映画と言えます。~ただ『ボアvsパイソン』は、ちょっと変わった映画と言ってもいいとは思っていて……大元の『アナコンダ』なんかは単体の怪物パニック映画であるが故にタイトルに出ている主役怪物にも関わらず、およそ感情移入の対象とされず、ただ“恐ろしい物”として描かれていたと言えます。

洋画の、大体においてハリウッドの、海を渡ってくるものは、大抵、あくまで人間主体の、この視点が揺らがないものが多いです。(というより、例外といえるものは、ぼちぼち取り上げて行きたいと考えています)
たとえば『ジョーズ』シリーズ(1975年~1980年代?)とかどうでしょう。スピルバーグ監督の出世作の一つであり、一世を風靡したモンスター・パニック映画ですが、ジョーズは凡そ怪獣とは言えない。何故か?ジョーズを感情移入の対象として扱っていないから…と言えます。『ジョーズ2』では、子の鮫を殺された母鮫の復讐という、解釈が用意されているのだけどジョーズが人間を襲う事の説明付のレベルにとどまっている。(※ジョーズに憐憫を感じるようには描かれていないと思うが、それでも2のジョーズに憐憫を感じる人がいれば、それはその人にとって怪獣を感じる入り口足りえるとは言えます)また、ジョーズシリーズのプロットは概ね同じものであり、プロットに大きな変更が見られない事にも、“非怪獣性”を見て取る事ができます。当時の作り手にとってジョーズとはパニックのシチュエーションに至るプロットこそが本体/主格であり、ジョーズというモンスターは本体/主格として見られていなかった…と解する事ができます。
これが日本の怪獣映画なら『ジョーズ対メカジョーズ 決戦バミューダ海!!』…というタイトルになるかどうかは分かりませんが(汗)ジョーズという“怪獣”のポテンシャルを極限まで生かしたプロットで「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」という映像で僕らをワクワクさせてくれたと思うんですよ!(`・ω・´)少なくとも東宝が怪獣映画を量産していたあの時代ならw
逆に言うとアメリカでは「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」というプロットに大きな価値は認められなかったという事です。…ここらへんの話の感覚から「あ、確かに、何かちょっと違うね」と思ってくれたら、僕がなんで怪獣とモンスターをわざわざ分けて語ろうとしているのか分かってもらえるのじゃないかと思います。(※ハリウッドも『アバター』とか、感情移入対象を拡散する流れはあるのですけどね…それはまた別の機会に)


じゃあ、アメリカには“怪獣的”なるもの見られないかと言うと…そんな事もないと言うか『キングコング』(1933年公開)が、かなり“怪獣”…と言えそうです。いや、そもそも日本の怪獣映画の真祖とさえ言える存在なのですけどね。しかし、彼は怪獣としては弱く、近代兵器の前に敗れ去ります。……そこが重要で、僕はそこに、アメリカひいては西洋における“怪獣の末路”を見て取れると思うんです。
…と、その前にもう一つ、西洋において“怪獣的”に見て取れる映画として『白鯨』(1956年公開)を上げておきたいです。近代兵器ではありませんが、当時、大洋を荒らしまわっていた西洋の捕鯨船団に怯れられた畏怖性。そしてエイハブ船長に執拗な追跡を受ける宿敵としての存在から見えるキャラクター性、託願性は、充分に『怪獣』と言える存在だと思います。
原作は1851年の刊行で様々な解釈がされているようですが、グレグリー・ペック主演のこの映画は原作にかなり忠実に作られている模様。…とそこで、1928年に作られた『白鯨』について引用してみます。(↓)
1928年の『白鯨』はエイハブ船長が白鯨を倒してしまうんですねえwこれを知った時は軽く驚きました。(同時に、さもありなんとも思いましたが)別にエイハブ船長が白鯨を倒せたら怪獣映画ではないと言うつもりもないのですが、先ほど言った「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」というプロットをよしとせぬアメリカを見て取れるかと思います。
逆に原作通りに白鯨と死闘の果てにエイハブは海の藻屑となる1956年版の『白鯨』は興行的に大失敗しました。主演のグレゴリー・ペックも『白鯨』の出来を嫌っていた……という情報まであります。面白いんですけどねえ……。その活躍シーンがほとんど無い事から映画『白鯨』を怪獣映画とは言いづらいのですが、白鯨という存在はかなり怪獣にあたると思います。
しかし、この存在を継ぐものは、少なくとも顕著に見て取れるものは現れなかった。いや、実は『ジョーズ』は白鯨のインスパイアの面がある見たいなのですが、しかし、ジョーズからはその畏怖も託願も、消失としたと言っていい程、減退しています。
『キングコング』に戻ります。何で洋画のモンスター映画に『怪獣』はいないのか?という事で追っていたのですが、その答えはモンスター映画としても怪獣映画としても原点にあたる『キングコング』の中にあったんですよね。
プロットそのものにその答えがある。『キングコング』とは登場した時点で、西洋にとっての怪獣の末路を描いてしまった映画だった…と言えるんです。
キングコングは明らかに“感情移入”の対象として描かれている。観客が“彼”を哀れに思うように描いている。そして、彼は最強無比にして“畏怖”の存在だった。彼の棲む秘境においてはです。それが“西洋”に連れて来られる事によって、怪獣であった、彼の存在は、巨大なゴリラとして暴かれ、見世物にされ、恐竜を倒す程の無双の強さを誇りながら、機関銃の餌食となって滅びさってしまう。
その『物語』には真の意味での怪獣の最期があります。『怪獣とは何か?』、なぜ、アメリカの映画に怪獣を観る事が困難なのか?その全てが『キングコング』にはある。怪獣は暴かれる事で、その力を失う。そして西洋は暴く事によって世界に席巻する力を得た。彼らは「畏れる事を止め、全てを暴こう」という意志で、ここまでやってきた。(話が無駄に大きくなっているな?)その彼らの捨てた、止めた、何かの残滓が『キングコング』という映画を作らせ、そしてその時点で、怪獣映画が生まれる道を閉じてしまったのかもしれません。
海を渡りキングコングのスピリッツを受け継いだ『ゴジラ』(1954年公開)は「あれが最後の一匹だとは思えない。水爆実験が続く限り、いつか……」と、その復活を示唆して物語を終える。
しかし、(怪獣としての)キングコングは二度と現れない。それは彼が機関銃で倒せると暴かれてしまった怪獣だからだ。そしてそれは、エメリッヒの『GODZILLA』(1998年公開)が、戦闘機のミサイルによって滅ぼされるシーンに至るまで連綿と継承されて来た怪獣の墓標だったのかもしれません。
ここしばらく、このブログでは『怪獣』の話を、ぼちぼち、したり、しなかったり、しているかと思いますが、まず、ここらで僕の中の『怪獣』に対する定義付けの話をしておこうと思います。
とは言ってもパブリックな怪獣の定義というわけではないので、気をつけて欲しいのですが(汗)………まず、僕が“怪獣好きな人”という前提があって…日本の怪獣映画と、洋画のモンスター(型)映画を観ていると「何かが違う?味わいのようなものが違う」と思うわけです。それで怪獣映画とモンスター映画を見比べていて「あ、これは怪獣映画っぽいかも?」「…これは怪獣じゃないな?」とか…怪獣好きですからね。そうやって選別して行く中で、まあ、大体こういう感じだと怪獣映画と言えるかな?という線引きのようなものが視えて来たわけです。
そこを詰めた話はまた別にして行きたいのですが、ここでは、分かりやすく大雑把に僕が何に怪獣を感じるか?を述べます。①近代兵器(またはそれに準じるもの)が通じない超存在~畏怖される存在~である事②基本的に人類と相入れぬ物(多くは敵)として描かれ、人型を為していない異形の対象であるにも関わらず感情移入~あるいは託願~の対象として扱われている事。
これを畏怖と託願とまとめますが、特に託願(感情移入)が重要ですね。そして、それは「受け手の、心象によって変化するもの」であると言えます。つまり、僕が感情移入できず「怪獣映画じゃない」と思っても、他の人には怪獣映画(的な受け止め方)になり得ると言う事です。
たとえば、以前に取り上げた『ボアvsパイソン』(2004年公開)ですが…
▼『ボアVSパイソン』~洋画の“怪物対決もの”はどんな感じか?
…僕はこの映画は人間の描きに重点が置かれた「怪獣映画ではないもの」という判定をしていますが、この判定は非常に微妙でして、一応、人間側の味方っぽい位置についたボアの方には、ある程度の“感情移入”を見て取れるのですよね。二大怪物の激突をウリにしている事からも、怪獣映画と捉える事も充分に可能な映画と言えます。~ただ『ボアvsパイソン』は、ちょっと変わった映画と言ってもいいとは思っていて……大元の『アナコンダ』なんかは単体の怪物パニック映画であるが故にタイトルに出ている主役怪物にも関わらず、およそ感情移入の対象とされず、ただ“恐ろしい物”として描かれていたと言えます。

洋画の、大体においてハリウッドの、海を渡ってくるものは、大抵、あくまで人間主体の、この視点が揺らがないものが多いです。(というより、例外といえるものは、ぼちぼち取り上げて行きたいと考えています)
たとえば『ジョーズ』シリーズ(1975年~1980年代?)とかどうでしょう。スピルバーグ監督の出世作の一つであり、一世を風靡したモンスター・パニック映画ですが、ジョーズは凡そ怪獣とは言えない。何故か?ジョーズを感情移入の対象として扱っていないから…と言えます。『ジョーズ2』では、子の鮫を殺された母鮫の復讐という、解釈が用意されているのだけどジョーズが人間を襲う事の説明付のレベルにとどまっている。(※ジョーズに憐憫を感じるようには描かれていないと思うが、それでも2のジョーズに憐憫を感じる人がいれば、それはその人にとって怪獣を感じる入り口足りえるとは言えます)また、ジョーズシリーズのプロットは概ね同じものであり、プロットに大きな変更が見られない事にも、“非怪獣性”を見て取る事ができます。当時の作り手にとってジョーズとはパニックのシチュエーションに至るプロットこそが本体/主格であり、ジョーズというモンスターは本体/主格として見られていなかった…と解する事ができます。
これが日本の怪獣映画なら『ジョーズ対メカジョーズ 決戦バミューダ海!!』…というタイトルになるかどうかは分かりませんが(汗)ジョーズという“怪獣”のポテンシャルを極限まで生かしたプロットで「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」という映像で僕らをワクワクさせてくれたと思うんですよ!(`・ω・´)少なくとも東宝が怪獣映画を量産していたあの時代ならw
逆に言うとアメリカでは「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」というプロットに大きな価値は認められなかったという事です。…ここらへんの話の感覚から「あ、確かに、何かちょっと違うね」と思ってくれたら、僕がなんで怪獣とモンスターをわざわざ分けて語ろうとしているのか分かってもらえるのじゃないかと思います。(※ハリウッドも『アバター』とか、感情移入対象を拡散する流れはあるのですけどね…それはまた別の機会に)


じゃあ、アメリカには“怪獣的”なるもの見られないかと言うと…そんな事もないと言うか『キングコング』(1933年公開)が、かなり“怪獣”…と言えそうです。いや、そもそも日本の怪獣映画の真祖とさえ言える存在なのですけどね。しかし、彼は怪獣としては弱く、近代兵器の前に敗れ去ります。……そこが重要で、僕はそこに、アメリカひいては西洋における“怪獣の末路”を見て取れると思うんです。
…と、その前にもう一つ、西洋において“怪獣的”に見て取れる映画として『白鯨』(1956年公開)を上げておきたいです。近代兵器ではありませんが、当時、大洋を荒らしまわっていた西洋の捕鯨船団に怯れられた畏怖性。そしてエイハブ船長に執拗な追跡を受ける宿敵としての存在から見えるキャラクター性、託願性は、充分に『怪獣』と言える存在だと思います。
原作は1851年の刊行で様々な解釈がされているようですが、グレグリー・ペック主演のこの映画は原作にかなり忠実に作られている模様。…とそこで、1928年に作られた『白鯨』について引用してみます。(↓)
The Sea Beast(1928年)
ミラード・ウエッブ(Millard Webb)監督、ジョン・バリモア主演。邦題は『海の野獣』。サイレント映画。ただし、原作が余りに暗く難解なため、大幅にアレンジされた。足を失う前のエイハブの姿が描かれ、エイハブが愛するエスターという美女や彼の舎弟デレックなど原作に存在しない人物が登場する。更にラストはエイハブが白鯨を倒し、エスターと結ばれるハッピーエンドとなっている。
(Wikipedia『白鯨』より)
1928年の『白鯨』はエイハブ船長が白鯨を倒してしまうんですねえwこれを知った時は軽く驚きました。(同時に、さもありなんとも思いましたが)別にエイハブ船長が白鯨を倒せたら怪獣映画ではないと言うつもりもないのですが、先ほど言った「ジョーズ、つぇぇぇええええ!!」というプロットをよしとせぬアメリカを見て取れるかと思います。
逆に原作通りに白鯨と死闘の果てにエイハブは海の藻屑となる1956年版の『白鯨』は興行的に大失敗しました。主演のグレゴリー・ペックも『白鯨』の出来を嫌っていた……という情報まであります。面白いんですけどねえ……。その活躍シーンがほとんど無い事から映画『白鯨』を怪獣映画とは言いづらいのですが、白鯨という存在はかなり怪獣にあたると思います。
しかし、この存在を継ぐものは、少なくとも顕著に見て取れるものは現れなかった。いや、実は『ジョーズ』は白鯨のインスパイアの面がある見たいなのですが、しかし、ジョーズからはその畏怖も託願も、消失としたと言っていい程、減退しています。
『キングコング』に戻ります。何で洋画のモンスター映画に『怪獣』はいないのか?という事で追っていたのですが、その答えはモンスター映画としても怪獣映画としても原点にあたる『キングコング』の中にあったんですよね。
プロットそのものにその答えがある。『キングコング』とは登場した時点で、西洋にとっての怪獣の末路を描いてしまった映画だった…と言えるんです。
キングコングは明らかに“感情移入”の対象として描かれている。観客が“彼”を哀れに思うように描いている。そして、彼は最強無比にして“畏怖”の存在だった。彼の棲む秘境においてはです。それが“西洋”に連れて来られる事によって、怪獣であった、彼の存在は、巨大なゴリラとして暴かれ、見世物にされ、恐竜を倒す程の無双の強さを誇りながら、機関銃の餌食となって滅びさってしまう。
その『物語』には真の意味での怪獣の最期があります。『怪獣とは何か?』、なぜ、アメリカの映画に怪獣を観る事が困難なのか?その全てが『キングコング』にはある。怪獣は暴かれる事で、その力を失う。そして西洋は暴く事によって世界に席巻する力を得た。彼らは「畏れる事を止め、全てを暴こう」という意志で、ここまでやってきた。(話が無駄に大きくなっているな?)その彼らの捨てた、止めた、何かの残滓が『キングコング』という映画を作らせ、そしてその時点で、怪獣映画が生まれる道を閉じてしまったのかもしれません。
海を渡りキングコングのスピリッツを受け継いだ『ゴジラ』(1954年公開)は「あれが最後の一匹だとは思えない。水爆実験が続く限り、いつか……」と、その復活を示唆して物語を終える。
しかし、(怪獣としての)キングコングは二度と現れない。それは彼が機関銃で倒せると暴かれてしまった怪獣だからだ。そしてそれは、エメリッヒの『GODZILLA』(1998年公開)が、戦闘機のミサイルによって滅ぼされるシーンに至るまで連綿と継承されて来た怪獣の墓標だったのかもしれません。
 | キングコング [DVD] FRT-032 |
| ノーブル・ジョンソン/サム・ハーディ/フランク・ライヘル/フェイ・レイ/ブルース・キャボット/ロバート・アームストロング | |
| ファーストトレーディング |