【怪獣とは何か?】

▼前回の記事:『キングコング』~怪獣物語の終焉
しばらく、このブログでは『怪獣』の話を、ぼちぼち、したり、しなかったり、していて、その流れで『キングコング』の話題に及んでいるわけですが、ちょっと最近、製作されたリメイクの『キングコング』(2005年公開、監督・ピーター・ジャクソン)の話からはじめてみたいと思います。いや、実は2作目のリメイクに当たるジョン・ギラーミン版の『キングコング』(1976年公開)が、けっこう評判良くないんですよね(汗)主に、特撮面とかの評価だと思うのですが……まあ、そこらへんの話は次回に譲るとして。
このピーター・ジャクソン版の『キングコング』、僕の感覚の中の『怪獣映画(…の真祖のリメイク)』としてかなり良い出来だと思うんです。主役のキングコングの実在感は相当細かい所まで気をつかっていますし、シナリオが『怪獣映画』として外れている所もない。前回の記事で取り上げた、畏怖と託願が充分に感じられる作りです。クラッシックな1933年版よりも、ある意味、とっつきが良く、オススメと言えるかもしれません。この一連の記事の空気(怪獣おたくの?)が掴めない人は一度観てもらうといいかも?
しかし、それは大元となる『キングコング』のプロットに、ほとんど手を加えていないから……という事でもあるんですよね。1976年版も、2005年版も、最初のキングコングと違うもの、新解釈と呼べるものにはほとんど手を付けてない。翻案と呼べる域には達していない~そのつもりもないでしょうけど~。あくまで真性のリメイクと言う事です。
この“プロットの檻”から出られないと、キングコングは真の意味で怪獣(=スター)と呼べる存在には至っていない……とも言えます。僕がキングコングが怪獣として甦らないと言った意図はそこにあります。(※『コングの復讐』、『キングコング2』等はまた次の記事に譲ります)
それくらい『キングコング』のプロットは、削る所も加える所もない程に完璧と言う事です。
それ故、キングコングはそのプロットの檻から逃れて怪獣で居続けるのは困難になってしまったし、ハリウッドのモンスター映画自体の数は多いけれども“彼ら”にキングコングの遺伝子は継承されなかった。(または非常に希薄になってしまった)
…こうやって書くと「この人は、何をそんなに持ち上げているのだろう?」と思う人もいるかもしれません。「巨大な野生のゴリラが、無理やり文明都市に見世物として連れてこられて、案の定暴れ出して、人間の勝手な都合で殺されてしまった。…そういう可哀想なゴリラの物語って、そんな大したストーリーなのかなあ?」…て思った人、いません?w
キングコングが単なる動物に見える人、単なるゴリラに見える人にとっては、そうかもしれません。キングコングが単なる猛獣に過ぎないなら、この『物語』のテーマは、動物愛護を訴えるお涙頂戴の悲劇でしかないのでしょう。
しかし、“彼”を『怪獣』として見た場合どうか?ちょっと、言葉を変えます。畏怖と託願の話です。“彼”は怪生物が棲まう未開の島において、恐竜たちの上に君臨し、島民たちが生贄を捧げて崇める、絶対の王者だった。その事に神霊(かみ)を見い出せないか?『怪獣』には、神霊(かみ)を感じないか?そう捉えた時、この物語はどういう観え方になるか?
その意味において2005年版のヒロインがコングを観て「美しい…」とつぶやく事にはすごい意味があります。あの一点は2005年版の価値だと思えます。怪獣好きの人には、こんなくどくど説明しなくても分かる話かと思います。逆に怪獣とか興味ない人には、どこまで行っても何の事か分からないかもしれませんが、多少でも分かって欲しくて、雰囲気を掴んで欲しくて、こういう長々とした文章書いています。
キングコングを神霊とした時、この物語はどういう観え方になるか?それは「神霊はただの獣に過ぎない」と、「獣を神霊と崇めるのは迷信である」と、神霊を暴き立て、そして殺す物語となる。暴き立てられた獣は、もはやただの獣で、獣を無理やり見世物に引っ張り出して、そして殺す物語へと変じてしまう。その意味で、動物愛護を訴える悲劇を観ていても、何らおかしな話ではない。
しかし、それ以前は、“彼”は白人未踏の地において君臨した神霊だった事を僕は強調したいです。そこからの凋落こそがキングコングの物語だと思うからです。
そして、日本のある有名なアニメ映画が、これに非常に近い観点を持って描かれている事がわかるので、ちょっと紹介しておきますが…。


『もののけ姫』(1997年公開)の事ですね。『もののけ姫』が、怪獣映画かどうか?の議論はおいておくとして、これに登場するシシ神様は、かなり僕が言う怪獣の要件を満たしていて、キングコングに近い者である事は確かです。まあ、神ですしねw そして、シシ神様が殺される事の“意味”もキングコングに近い…と思う。キングコングは複葉の戦闘機、シシ神はエボシの石火矢、いずれも当時の“最新の兵器”によって葬られている事の意味も大きい。
ただ『もののけ姫』に関しては、蟲に神性を見出すような、生物への畏怖と託願を決して失わない人が監督なのでwシシ神や、他の“もののけ”たちに関しても畏怖と託願が失われる事はなかったですね。要するに、神は殺されるが、暴かれはせず、神の威厳は保たれる。神殺しの業に対し、人々はみずからの行為に恐怖するという構成になっていて、ここは大きく違います。
しかし、本当に「神を殺す」なら、徹底的に暴く事なんですよね。キングコングは強烈な暴きにさらされる。本当の意味での“神殺し”に遭う。彼を見た白人たちは、一目で巨大なゴリラである事を看破し、何とか捕まえて見世物にしようと画策する。……もう、この時点でキングコングの“暴き”は、はじまっているし、この時点でキングコングは『怪獣』ではなくなっているとも言えます。
一方、シシ神は“神霊”としての対面が守られ、暴かれないからこそ、死した後も、その畏怖と受けて呪いが降り注ぎ君臨を続ける。ゴジラや、ガメラなどの、異形の怪獣たちが、怪獣として君臨し続けるのは、キングコングやシシ神様を屠ったその兵器が通用せず、決して暴かれない設定だからなんですね。そんな所で、まだしばらく『怪獣』の話は続けたいです。

▼前回の記事:『キングコング』~怪獣物語の終焉
しばらく、このブログでは『怪獣』の話を、ぼちぼち、したり、しなかったり、していて、その流れで『キングコング』の話題に及んでいるわけですが、ちょっと最近、製作されたリメイクの『キングコング』(2005年公開、監督・ピーター・ジャクソン)の話からはじめてみたいと思います。いや、実は2作目のリメイクに当たるジョン・ギラーミン版の『キングコング』(1976年公開)が、けっこう評判良くないんですよね(汗)主に、特撮面とかの評価だと思うのですが……まあ、そこらへんの話は次回に譲るとして。
このピーター・ジャクソン版の『キングコング』、僕の感覚の中の『怪獣映画(…の真祖のリメイク)』としてかなり良い出来だと思うんです。主役のキングコングの実在感は相当細かい所まで気をつかっていますし、シナリオが『怪獣映画』として外れている所もない。前回の記事で取り上げた、畏怖と託願が充分に感じられる作りです。クラッシックな1933年版よりも、ある意味、とっつきが良く、オススメと言えるかもしれません。この一連の記事の空気(怪獣おたくの?)が掴めない人は一度観てもらうといいかも?
しかし、それは大元となる『キングコング』のプロットに、ほとんど手を加えていないから……という事でもあるんですよね。1976年版も、2005年版も、最初のキングコングと違うもの、新解釈と呼べるものにはほとんど手を付けてない。翻案と呼べる域には達していない~そのつもりもないでしょうけど~。あくまで真性のリメイクと言う事です。
この“プロットの檻”から出られないと、キングコングは真の意味で怪獣(=スター)と呼べる存在には至っていない……とも言えます。僕がキングコングが怪獣として甦らないと言った意図はそこにあります。(※『コングの復讐』、『キングコング2』等はまた次の記事に譲ります)
それくらい『キングコング』のプロットは、削る所も加える所もない程に完璧と言う事です。
それ故、キングコングはそのプロットの檻から逃れて怪獣で居続けるのは困難になってしまったし、ハリウッドのモンスター映画自体の数は多いけれども“彼ら”にキングコングの遺伝子は継承されなかった。(または非常に希薄になってしまった)
…こうやって書くと「この人は、何をそんなに持ち上げているのだろう?」と思う人もいるかもしれません。「巨大な野生のゴリラが、無理やり文明都市に見世物として連れてこられて、案の定暴れ出して、人間の勝手な都合で殺されてしまった。…そういう可哀想なゴリラの物語って、そんな大したストーリーなのかなあ?」…て思った人、いません?w
キングコングが単なる動物に見える人、単なるゴリラに見える人にとっては、そうかもしれません。キングコングが単なる猛獣に過ぎないなら、この『物語』のテーマは、動物愛護を訴えるお涙頂戴の悲劇でしかないのでしょう。
しかし、“彼”を『怪獣』として見た場合どうか?ちょっと、言葉を変えます。畏怖と託願の話です。“彼”は怪生物が棲まう未開の島において、恐竜たちの上に君臨し、島民たちが生贄を捧げて崇める、絶対の王者だった。その事に神霊(かみ)を見い出せないか?『怪獣』には、神霊(かみ)を感じないか?そう捉えた時、この物語はどういう観え方になるか?
その意味において2005年版のヒロインがコングを観て「美しい…」とつぶやく事にはすごい意味があります。あの一点は2005年版の価値だと思えます。怪獣好きの人には、こんなくどくど説明しなくても分かる話かと思います。逆に怪獣とか興味ない人には、どこまで行っても何の事か分からないかもしれませんが、多少でも分かって欲しくて、雰囲気を掴んで欲しくて、こういう長々とした文章書いています。
キングコングを神霊とした時、この物語はどういう観え方になるか?それは「神霊はただの獣に過ぎない」と、「獣を神霊と崇めるのは迷信である」と、神霊を暴き立て、そして殺す物語となる。暴き立てられた獣は、もはやただの獣で、獣を無理やり見世物に引っ張り出して、そして殺す物語へと変じてしまう。その意味で、動物愛護を訴える悲劇を観ていても、何らおかしな話ではない。
しかし、それ以前は、“彼”は白人未踏の地において君臨した神霊だった事を僕は強調したいです。そこからの凋落こそがキングコングの物語だと思うからです。
そして、日本のある有名なアニメ映画が、これに非常に近い観点を持って描かれている事がわかるので、ちょっと紹介しておきますが…。


『もののけ姫』(1997年公開)の事ですね。『もののけ姫』が、怪獣映画かどうか?の議論はおいておくとして、これに登場するシシ神様は、かなり僕が言う怪獣の要件を満たしていて、キングコングに近い者である事は確かです。まあ、神ですしねw そして、シシ神様が殺される事の“意味”もキングコングに近い…と思う。キングコングは複葉の戦闘機、シシ神はエボシの石火矢、いずれも当時の“最新の兵器”によって葬られている事の意味も大きい。
ただ『もののけ姫』に関しては、蟲に神性を見出すような、生物への畏怖と託願を決して失わない人が監督なのでwシシ神や、他の“もののけ”たちに関しても畏怖と託願が失われる事はなかったですね。要するに、神は殺されるが、暴かれはせず、神の威厳は保たれる。神殺しの業に対し、人々はみずからの行為に恐怖するという構成になっていて、ここは大きく違います。
しかし、本当に「神を殺す」なら、徹底的に暴く事なんですよね。キングコングは強烈な暴きにさらされる。本当の意味での“神殺し”に遭う。彼を見た白人たちは、一目で巨大なゴリラである事を看破し、何とか捕まえて見世物にしようと画策する。……もう、この時点でキングコングの“暴き”は、はじまっているし、この時点でキングコングは『怪獣』ではなくなっているとも言えます。
一方、シシ神は“神霊”としての対面が守られ、暴かれないからこそ、死した後も、その畏怖と受けて呪いが降り注ぎ君臨を続ける。ゴジラや、ガメラなどの、異形の怪獣たちが、怪獣として君臨し続けるのは、キングコングやシシ神様を屠ったその兵器が通用せず、決して暴かれない設定だからなんですね。そんな所で、まだしばらく『怪獣』の話は続けたいです。
 | キング・コング 【Blu-ray ベスト・ライブラリー100】 |
| ナオミ・ワッツ,エイドリアン・ブロディー,ジャック・ブラック,トーマス・クレッチマン,コリン・ハンクス | |
| ジェネオン・ユニバーサル |










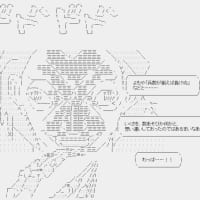
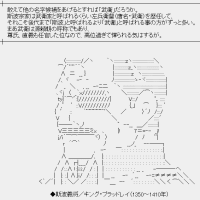
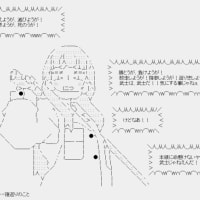
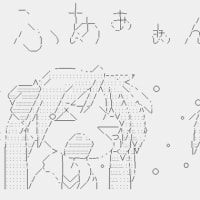

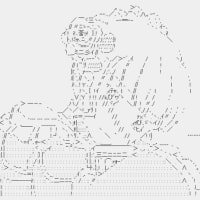

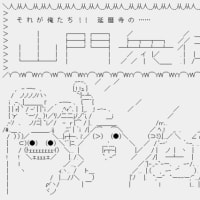
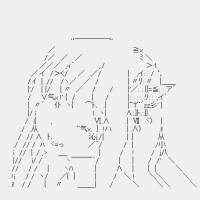
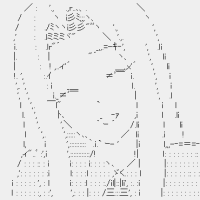
最近、文庫にまとまった京極夏彦氏の『妖怪の理 妖怪の檻』には、前近代の剥奪としてキングコングとゴジラが挙げられ、近代的存在を得る事で「怪獣」として認知されるという検証が成されていました。
また怪獣は“種”でなく“個”として認知されているとか、“妖怪”と“怪獣”は神道と仏教の関係に似ているとか、第一次怪獣ブーム→妖怪ブームは、怪獣・妖怪・海外モンスターが混沌となっていたのをより分ける作業であり、送り手が意図的に行っていた側面があるという記述もあり、中々興味深いです。
読むのはシンドイですが一読をお勧めします。
『妖怪の理 妖怪の檻』興味深いですね。読んでみます。
神霊/神威/神力が映画フレームに収まる事で、怪獣に変じるという考え方を元に語っているのですが、この映画が曲者というか、科学文明の肯定によって怪獣映画が作られるのですから……何て言えばいいのかな?完全なオカルトとして描かれてはいない事は怪獣の特徴なのかもしれませんね。
「近代的存在を得る事で「怪獣」として認知される」とはそういう話ですかね。
逆に完全なオカルトとして、完全な科学への離反として、妖怪ブームが興っているという事は考えられそうです。TV特撮『悪魔くん』あたりが分岐っぽい?そこらへんも、詰めて行く必要はありそうです。