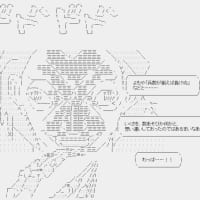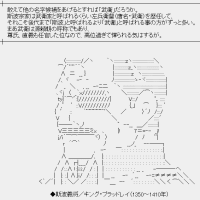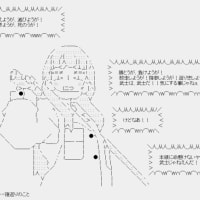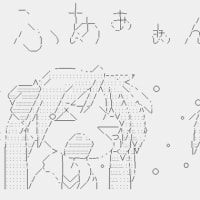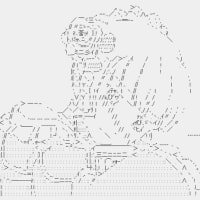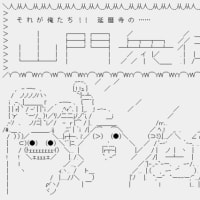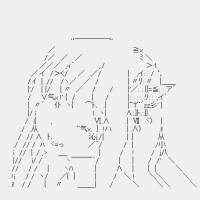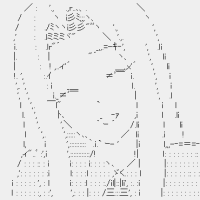【怪獣とは何か?】


テレビ東京の午後のロードショーで“巨大生物の逆襲”シリーズみたいな週間プログラムを組んでいたので観てみました。『ボアVSパイソン』(2004年公開)は、とある若手の大富豪が、仲間内でエキサイティングな狩りをエンジョイするために、遺伝子操作でばかでかくなった巨大なパイソンを空輸するのですが、その輸送機が事故にあって浄水場に潜伏して人々を襲う。FBIはパイソンに対抗(?)するため動物をコントロールする技術を使って巨大なボアを操り、追跡を始めるという『物語』。
大富豪のハンター仲間はハンティングを中止するかとおもいきや「ますます楽しくなってきたぜ!ヒャッハァァアア!?」という感じでパイソンの追跡を始めます。…このハンター・チームの登場が、ちょっとしたワイルド7の登場というか、全員一曲も二曲もありそうな連中で、横一列に並んで妙にカッコ良くって、ちょっと笑ってしまった。
…結局、この人達全滅するんですけどね。なんとな~く、山田風太郎先生の忍法帳ものの“やられ忍者軍団”を彷彿とさせるものがあります。まあ、この人達、人が死んでいる状況もゲームのシチュエーション程度にしか思っていない人たちで、金にあかした違法行為も相当やっているようなので…パイソンにどんどん喰われて行っても、自業自得というか、あんまり心が傷まないというか、けっこう純粋に「パイソンすげえ~!!」みたいな見方ができる所が上手いですね。
このハンター・チームの追跡に勝利してゆくパイソンに対して、遅れがらも軍とコントロールされた巨大ボアの追跡が迫る、ハンター・チームはものともせずに屠り続けた(強さが証明されている)パイソンだが、果たしてボアには勝てるのか?という構成の盛上げ方も良くって、B級ながらも非常に楽しめる映画になっていました。
それを、“怪獣対決もの”として観るとどうか?今回、僕は『ボアVSパイソン』というタイトルから、怪獣同士の対決は洋画でどんな感じに処理されているかを主体に眺めた所があります。個々で言う“怪獣”とは、僕が感じている、日本独特の巨大獣に関する畏怖を含めた感情の対象物としての“怪獣”という意味になりますが…。
その角度で話をすると、やはり“怪物対人間”が主体の話になっているなあ…という感じでしょうか。最後のシーンで、ボアとパイソンは対決に至るのですが、やはりそれは何というか…おまけとまでは言わないんですけど、クライマックスのワン・ギミックくらいの感じになっています。実際に、ボアとパイソンだけでは決着がつかず、人間の手によって二匹とも葬られていますしね。結局、先ほど述べたハンター・チームとパイソンの対決がやはり楽しかったんです。
これは別の見え方としては「いや、あくまで人間対パイソンを描いて行って、最後のボアとの決戦をトーナメント的に盛り上げたんだよ」というものもあるとは思うんですけどね。ボアの活躍というか暴れもありましたしね。いや、B級モンスター・ムービーとしては充分な『面白さ』だったんですよ?(汗)

しかし、『ボアVSパイソン』とまで、銘打たれているのに、実際に映画ができあがって見ると“彼ら”に主眼が置かれていないような……そういう不思議な感覚があります。
まあ、不思議とか言っていますが、至って普通の作劇でもあるんですよね。「そもそもボアとかパイソンに感情移入できる観客なんて、極少数でしょう?なら、その対決に関わる人々の“主体的行動”(傍観的行動ではない)を描いて、そっちに感情移入させないと」という、そういう話なんだと思います。
しかし、それはモンスターものを描く時の考え方で“怪獣”は違うと、僕は思っている。たとえばゴジラや、ガメラ、あるいはこれは議論があるかもしれませんが大魔神~僕は(その意思疎通の難しさから)大魔神も怪獣にカテゴライズしたいと思っています~など、その他諸々の日本産の怪獣たちは、観客~主に怪獣ブームを牽引した子供たちによって~感情移入の対象として扱われていて、概ねにおいて、その旨に沿った作劇がされていたと僕は思っています。
そこが今回の『ボアvsパイソン』という“怪物対決もの”と、ゴジラやガメラに代表される日本産の“怪獣対決もの”の違いだと思う。……ボアやパイソンに全く感情移入できないってワケではないですけどね。逆に、積極的にボアやパイソンに感情移入してしまえが、この映画は怪獣映画として楽しめてしまう……と、そういう受け手の景観の話でもあります。
とは言え、今、邦画の中にゴジラシリーズや、ガメラシリーズが消滅して行ったのは、こういう怪獣に対する感情移入が、日本人の中から無くなって行った、薄れていったからかな~?などと考えたりしているんですよね。もう、今、怪獣を観ても、受け手は『ボアvsパイソン』を観るのと同じ感覚になっているのかも…というか。
『怪獣とは何か?』という語りは、もしかしたら無くなって行くかもしれない心象に対する証言の意識はあります。ちょっと自分なりに語っておきたいと。
この怪獣感覚……僕は、日本人独特という語り口で語っているのですが(あるいはアジア圏全域を対象にしてもいいのかもしれないのですが、現状、僕のカバー範囲を超えてしまってますね)、じゃあ、それは欧米の洋画には見られないのか?というと、一概にそうとも言えないですね。
…しかし、今、一口に言うなら「西洋人は“怪獣”を恐れるのを止めようと決意する事によって、今の西洋人になった」面があると思っていて、それは残滓のような形で映画には出る事になる…と僕は観ている。ここまで語った上で「『キングコング』(1933年公開)が当にそれです」というと、ピンと来る人は分かってもらえるかと思いますがw
キングコングは原初的な怪獣にして、日本の特撮上の怪獣の始祖でもあると思います。あと『白鯨』(1851年発表)なんかも西洋にとっての“怪獣”に当たるかなと観ています。しかし………まあ、『キングコング』については、また日を改めて、記事に書きたいと思います。
※僕は、感情移入できる対象として、ある種のヒーローとしての“怪獣”という位置づけで語っていますが、特撮おたくの中の“怪獣好き”は、完全な線引きは無理ではありますが、別のタイプもいます。“ミリタリー型”、“科学型”というか、あくまで怪獣を人間側から見た災害と位置づけて理詰めで対処して行く様を描くのを好むタイプとでも言えばいいのか。……これは、ぶっちゃけアニミズムで怪獣を語る僕とは対の位置から怪獣を語る事になります。無論、僕も『サンダ対ガイラ』のような怪獣対自衛隊の「人間かっこええ!!」って描きも好きなんですが、自分が怪獣について語れというと“こっち”側になってしまうという事ですね。ただ、一応、違う方向の語りもあるよという事をここで書き留めておきます。


テレビ東京の午後のロードショーで“巨大生物の逆襲”シリーズみたいな週間プログラムを組んでいたので観てみました。『ボアVSパイソン』(2004年公開)は、とある若手の大富豪が、仲間内でエキサイティングな狩りをエンジョイするために、遺伝子操作でばかでかくなった巨大なパイソンを空輸するのですが、その輸送機が事故にあって浄水場に潜伏して人々を襲う。FBIはパイソンに対抗(?)するため動物をコントロールする技術を使って巨大なボアを操り、追跡を始めるという『物語』。
大富豪のハンター仲間はハンティングを中止するかとおもいきや「ますます楽しくなってきたぜ!ヒャッハァァアア!?」という感じでパイソンの追跡を始めます。…このハンター・チームの登場が、ちょっとしたワイルド7の登場というか、全員一曲も二曲もありそうな連中で、横一列に並んで妙にカッコ良くって、ちょっと笑ってしまった。
…結局、この人達全滅するんですけどね。なんとな~く、山田風太郎先生の忍法帳ものの“やられ忍者軍団”を彷彿とさせるものがあります。まあ、この人達、人が死んでいる状況もゲームのシチュエーション程度にしか思っていない人たちで、金にあかした違法行為も相当やっているようなので…パイソンにどんどん喰われて行っても、自業自得というか、あんまり心が傷まないというか、けっこう純粋に「パイソンすげえ~!!」みたいな見方ができる所が上手いですね。
このハンター・チームの追跡に勝利してゆくパイソンに対して、遅れがらも軍とコントロールされた巨大ボアの追跡が迫る、ハンター・チームはものともせずに屠り続けた(強さが証明されている)パイソンだが、果たしてボアには勝てるのか?という構成の盛上げ方も良くって、B級ながらも非常に楽しめる映画になっていました。
それを、“怪獣対決もの”として観るとどうか?今回、僕は『ボアVSパイソン』というタイトルから、怪獣同士の対決は洋画でどんな感じに処理されているかを主体に眺めた所があります。個々で言う“怪獣”とは、僕が感じている、日本独特の巨大獣に関する畏怖を含めた感情の対象物としての“怪獣”という意味になりますが…。
その角度で話をすると、やはり“怪物対人間”が主体の話になっているなあ…という感じでしょうか。最後のシーンで、ボアとパイソンは対決に至るのですが、やはりそれは何というか…おまけとまでは言わないんですけど、クライマックスのワン・ギミックくらいの感じになっています。実際に、ボアとパイソンだけでは決着がつかず、人間の手によって二匹とも葬られていますしね。結局、先ほど述べたハンター・チームとパイソンの対決がやはり楽しかったんです。
これは別の見え方としては「いや、あくまで人間対パイソンを描いて行って、最後のボアとの決戦をトーナメント的に盛り上げたんだよ」というものもあるとは思うんですけどね。ボアの活躍というか暴れもありましたしね。いや、B級モンスター・ムービーとしては充分な『面白さ』だったんですよ?(汗)

しかし、『ボアVSパイソン』とまで、銘打たれているのに、実際に映画ができあがって見ると“彼ら”に主眼が置かれていないような……そういう不思議な感覚があります。
まあ、不思議とか言っていますが、至って普通の作劇でもあるんですよね。「そもそもボアとかパイソンに感情移入できる観客なんて、極少数でしょう?なら、その対決に関わる人々の“主体的行動”(傍観的行動ではない)を描いて、そっちに感情移入させないと」という、そういう話なんだと思います。
しかし、それはモンスターものを描く時の考え方で“怪獣”は違うと、僕は思っている。たとえばゴジラや、ガメラ、あるいはこれは議論があるかもしれませんが大魔神~僕は(その意思疎通の難しさから)大魔神も怪獣にカテゴライズしたいと思っています~など、その他諸々の日本産の怪獣たちは、観客~主に怪獣ブームを牽引した子供たちによって~感情移入の対象として扱われていて、概ねにおいて、その旨に沿った作劇がされていたと僕は思っています。
そこが今回の『ボアvsパイソン』という“怪物対決もの”と、ゴジラやガメラに代表される日本産の“怪獣対決もの”の違いだと思う。……ボアやパイソンに全く感情移入できないってワケではないですけどね。逆に、積極的にボアやパイソンに感情移入してしまえが、この映画は怪獣映画として楽しめてしまう……と、そういう受け手の景観の話でもあります。
とは言え、今、邦画の中にゴジラシリーズや、ガメラシリーズが消滅して行ったのは、こういう怪獣に対する感情移入が、日本人の中から無くなって行った、薄れていったからかな~?などと考えたりしているんですよね。もう、今、怪獣を観ても、受け手は『ボアvsパイソン』を観るのと同じ感覚になっているのかも…というか。
『怪獣とは何か?』という語りは、もしかしたら無くなって行くかもしれない心象に対する証言の意識はあります。ちょっと自分なりに語っておきたいと。
この怪獣感覚……僕は、日本人独特という語り口で語っているのですが(あるいはアジア圏全域を対象にしてもいいのかもしれないのですが、現状、僕のカバー範囲を超えてしまってますね)、じゃあ、それは欧米の洋画には見られないのか?というと、一概にそうとも言えないですね。
…しかし、今、一口に言うなら「西洋人は“怪獣”を恐れるのを止めようと決意する事によって、今の西洋人になった」面があると思っていて、それは残滓のような形で映画には出る事になる…と僕は観ている。ここまで語った上で「『キングコング』(1933年公開)が当にそれです」というと、ピンと来る人は分かってもらえるかと思いますがw
キングコングは原初的な怪獣にして、日本の特撮上の怪獣の始祖でもあると思います。あと『白鯨』(1851年発表)なんかも西洋にとっての“怪獣”に当たるかなと観ています。しかし………まあ、『キングコング』については、また日を改めて、記事に書きたいと思います。
※僕は、感情移入できる対象として、ある種のヒーローとしての“怪獣”という位置づけで語っていますが、特撮おたくの中の“怪獣好き”は、完全な線引きは無理ではありますが、別のタイプもいます。“ミリタリー型”、“科学型”というか、あくまで怪獣を人間側から見た災害と位置づけて理詰めで対処して行く様を描くのを好むタイプとでも言えばいいのか。……これは、ぶっちゃけアニミズムで怪獣を語る僕とは対の位置から怪獣を語る事になります。無論、僕も『サンダ対ガイラ』のような怪獣対自衛隊の「人間かっこええ!!」って描きも好きなんですが、自分が怪獣について語れというと“こっち”側になってしまうという事ですね。ただ、一応、違う方向の語りもあるよという事をここで書き留めておきます。
 | ボアvs.パイソン [DVD] |
| デヴィッド・ヒューレット,ジェイミー・バーグマン,エンジェル・ボリス | |
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント |