あなたは「地球上に住むどんな人にも適用でき、だれもが納得する、そしてこの世界をシンプルに説明することができる、たった一つの答え」に興味がありますか?
最近「水からの伝言」という本が評判になっているという。
同じ著者の同シリーズ本「水は答えを知っている―その結晶にこめられたメッセージ」から一部を引用する。
わはははははははははは。
思わず大笑いしてしまった。「その一言で世界が救われるような、シンプルで決定的な答え」が「人間の体は平均すると七〇%が水である」なのかよっ!
こりゃ「生命、宇宙、そして万物についての究極の答=42」に匹敵する素晴らしいナンセンスだ。
…とネタ的に大いに感心したが、なんとこのトンデモを教育現場で情操教育の教材として利用する教師がいるという。
なんてこった。
*上記の引用はHal Tasaki’s -<log p>:水は答えを知っているから転載させていただいた。
プロの理論物理学者が書いた「水からの伝言」批判である。長文だがとても読みやすい文章である。ぜひリンク先をお読みください。
実際に小学校の朝礼で使われた一例を挙げる。
~水からの伝言~(水が伝えるもの)より引用(読みやすくなるよう改行を変えた)。
読んでいるうちに脱力し、「信じられない」という思いがだんだん怒りに変わっていく。
怪しげな実験で作られた水の結晶を例にして「善意を投げかければ必ずよい結果が返ってくる」という信仰を広めようとする人たち、そして簡単にそれを信じてしまう人たち(教師たち)とはいったい何なのだろう。
実に安直であり、自分の頭で考えることを放棄しているとしか思えない。
人間とは「Aを与えれば必ずA´という結果が返ってくる」ような単純な存在ではない。
Aに対してBやC、ときにはΣや罩(←読めない)といった意外な答えが返ってくるのが人間の不思議さであり、素晴らしくかつ難儀なところである。
我々の生きている世界は美しくも複雑で時には残酷である。「美しい言葉・良き意思が必ずよい結果を生む」ほど単純ではないのだ。それくらいのことは20歳、いや12歳以上であればほとんどの人間は身に沁みて思い知らされるものだと思っていたが、そうではない人が多くいることに驚く。
人間性の複雑さを否定し、単純な型に嵌めこもうとするのはそれこそ「非人間的」である。
その発想法は(100%の善意に基づいているとしても)ファシストや共産主義者と変わるところがない。
現実の複雑さを否認して単純で美しい夢想を称揚するのは教育ではない。
そのような「教育の名のもとに行われる愚かさの押し付け」は愚育と呼ぶべきだろう。
参考リンク
ニセ科学入門
kikulog:水伝:mixiに書いたこと
7635log | 江本勝「水は答えを知っている」(サンマーク出版)レビュー
あなたは「水」に答えを求めますか
どらろぐ・「水」別館
「水からの伝言」を教育現場に持ち込んではならないと考えるわけ
「水からの伝言」関連リンク集-選定版
水商売ウォッチング
「TOSSランド」(教育技術法則化運動)へのコメント
「水からの伝言」江本氏の主張
最近「水からの伝言」という本が評判になっているという。
同じ著者の同シリーズ本「水は答えを知っている―その結晶にこめられたメッセージ」から一部を引用する。
だれもが、このアリ地獄のような世界の中で、救いを求めています。だれもが答えを求めているのです。その一言で世界が救われるような、シンプルで決定的な答えを、さがしつづけているのです。(p.11)
私は、ここで、それを提示したいと思っています。それは、人間の体は平均すると七〇%が水である、ということです。(p.12)
わはははははははははは。
思わず大笑いしてしまった。「その一言で世界が救われるような、シンプルで決定的な答え」が「人間の体は平均すると七〇%が水である」なのかよっ!
こりゃ「生命、宇宙、そして万物についての究極の答=42」に匹敵する素晴らしいナンセンスだ。
…とネタ的に大いに感心したが、なんとこのトンデモを教育現場で情操教育の教材として利用する教師がいるという。
なんてこった。
*上記の引用はHal Tasaki’s -<log p>:水は答えを知っているから転載させていただいた。
プロの理論物理学者が書いた「水からの伝言」批判である。長文だがとても読みやすい文章である。ぜひリンク先をお読みください。
実際に小学校の朝礼で使われた一例を挙げる。
「水からの伝言」(出版 波動教育所)の写真を使った,全校朝会での話(10分間)である。
(略)
説明2 どちらも同じ水道からとった水です。同じ冷蔵庫で凍らせました。
発問3 でも,形が全然違いますね。なぜでしょう。
これだけでは少し難しいようだったのでヒントを与えた。
説明3 ヒントを言います。じつはひとつだけ違うことをしました。水に何かをしました。何をしたのでしょう。
・「Bに塩をかけた。」
説明4 答えは言葉かけをしました。二つの水を入れたコップにある言葉を書いたシールをはって一晩おきました。
一晩経つと,同じ水から作ったのに違う結晶になりました。
発問4 どんな言葉を書いたのでしょう。その二つの言葉は、みんなもよく使ったり聞いたりする言葉です。
・「え?」 ・「ありがとうかな?」 ・指名して聞いていった。
説明5 そうです。答えは「ありがとう」と「バカやろう」です。
(略)
発問6 さて,私たち人間の体には,どのくらい水が入っているでしょう。
・「三分の一」 ・「半分です」 ・「三分の二です」 (黒板に人型を書き意見を色チョークで塗って記入していく)
説明8 じつは私たちの体は70%以上が水でできています。受精卵では95%,お母さんのお腹の中では90%,
生まれたときに80%,生きている今は70%,死ぬときに50%になると言われています。だから,自分で
わかっていなくても言葉によって,体の水分はそれなりの反応をしていることになりますね。
発問7 最後にこれ(E)とこれ(F)にかけた言葉を当てて下さい。
説明9 Eは「むかつく,殺す」という言葉をかけられた水の結晶です。すごい形ですね。
Fは「愛・感謝」という言葉です。さらにきめ細かい美しい結晶となってますね。
説明10 こちら,プラスの言葉と言います。こちらは,マイナスの言葉と言います。水にかけた言葉で,形が
こんなに変わるのですから,水で出来ている私たち人間にも,どちらがいいか,わかりますね。言葉
というもの,文字というものの人体への影響は,すごいものといえるでしょう。「ありがとう」の言葉,
優しい言葉,相手をはげます言葉,そういう言葉だけが私の口から出ますように。
そして,すべての人の体の中の水がいつもきれいな結晶を作っていられますように。
お互いが相手のダイヤモンドの輝きをいつも見ることのできますように。。。終わります。
※45分間の授業として行う場合は,発問の後に,発表でなく,書かせたり,討論させたりすると良いだろう。
~水からの伝言~(水が伝えるもの)より引用(読みやすくなるよう改行を変えた)。
読んでいるうちに脱力し、「信じられない」という思いがだんだん怒りに変わっていく。
怪しげな実験で作られた水の結晶を例にして「善意を投げかければ必ずよい結果が返ってくる」という信仰を広めようとする人たち、そして簡単にそれを信じてしまう人たち(教師たち)とはいったい何なのだろう。
実に安直であり、自分の頭で考えることを放棄しているとしか思えない。
人間とは「Aを与えれば必ずA´という結果が返ってくる」ような単純な存在ではない。
Aに対してBやC、ときにはΣや罩(←読めない)といった意外な答えが返ってくるのが人間の不思議さであり、素晴らしくかつ難儀なところである。
我々の生きている世界は美しくも複雑で時には残酷である。「美しい言葉・良き意思が必ずよい結果を生む」ほど単純ではないのだ。それくらいのことは20歳、いや12歳以上であればほとんどの人間は身に沁みて思い知らされるものだと思っていたが、そうではない人が多くいることに驚く。
人間性の複雑さを否定し、単純な型に嵌めこもうとするのはそれこそ「非人間的」である。
その発想法は(100%の善意に基づいているとしても)ファシストや共産主義者と変わるところがない。
現実の複雑さを否認して単純で美しい夢想を称揚するのは教育ではない。
そのような「教育の名のもとに行われる愚かさの押し付け」は愚育と呼ぶべきだろう。
参考リンク
ニセ科学入門
kikulog:水伝:mixiに書いたこと
7635log | 江本勝「水は答えを知っている」(サンマーク出版)レビュー
あなたは「水」に答えを求めますか
どらろぐ・「水」別館
「水からの伝言」を教育現場に持ち込んではならないと考えるわけ
「水からの伝言」関連リンク集-選定版
水商売ウォッチング
「TOSSランド」(教育技術法則化運動)へのコメント
「水からの伝言」江本氏の主張











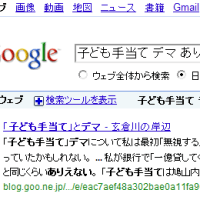

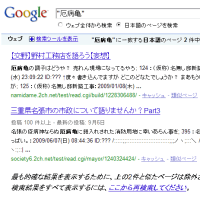
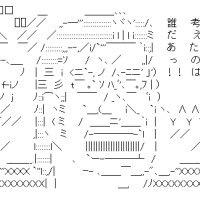



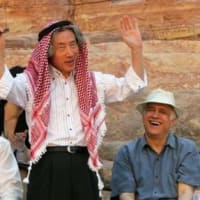

このあたりは、教育において、宗教的素養や信仰心をどのように、どこまで教えるべきかという話かと。
まあ水云々は宗教としても程度の低いものかもしれませんが、高度に体系化され人格の向上に資する宗教であっても、入門はきれいごとからでしょうからね。
信仰の世界と現実の世界を区別して教えさえすれば、私的にはアリかな。水は笑うけど。
・・・という先生がいたら、大いに勉強にもなるでしょうね。実験装置の扱いからリテラシーから、大人のズルさまで(w
ひょっとしたら、これが似非科学であることを教師たちは知っているにもかかわらず、他に適切な教材を求めもせず「理科じゃないし、道徳だからまあいいか」程度の安易な考えで利用しているのかしら?
だとしたら道徳教育の問題は色々な次元で深刻だと思います。
「参考リンク」は本当に参考になりました。ご紹介を感謝します。
>01-21 22:51:02のUnknownさん
私も宗教教育を否定するものではありませんが、「エセ科学」を道徳の教材に使うのは許せません。
無生物を擬人化するのなら「かさじぞう」のお話でも使えばいいのです。おとぎ話なら「科学的な事実」と勘違いされることもないでしょう。
この話を教える年齢にもよりますが、たいていの子供は「無いだろ」って科学的に思うはずです。
もし小学校の授業で理科を習う前に使われたとしても、成長するにつれてわかるはずです。
それに道徳の内容なんてこの「水からの伝言」と似たり寄ったりな内容じゃないですか。悪いことはしないでいいことをしなさい。っていう。それが悪いとは言わないけど。
なんで、推測に過ぎませんが特に問題は無いかと思うんですが。子供だってそんなに何でも信じませんよ。
ちなみに私が記憶にある道徳の授業は王貞治には選挙権がない、かつ日本人ではない、です。
コメントありがとうございます。ですが水無瀬さんのご意見にはまったく同意できません。
> たいていの子供は「無いだろ」って科学的に思うはずです。
「どらろぐ・「水」別館」→ http://doralin.blog17.fc2.com/
をお読みください。
子供どころか大人までが「水伝」をそのまま受け入れてしまってます。
> もし小学校の授業で理科を習う前に使われたとしても、成長するにつれてわかるはずです。
科学的な装いをこらしたデタラメを教える必要はありません。有害無益です。