
西アフリカの小さな村で、割礼を嫌がった4人の少女たちがコレのもとへ逃げ込んで来る。第一、第三ママや子どもたちと暮らすコレは、自分が割礼で苦労し、二人の子どもを死産した経験から、娘には割礼をさせていなかった。少女たちはそ... 続き
小さな村の局所の出来事に、アフリカ的現在の縮図が描かれている。
吉本隆明の「アフリカ的時間」をめぐる一連の考察を、すっかりわかった気で読んでいながら、この作品を見て、「俺はなんにもわかっちゃいないよな」と、思うことしきりであった。
「ホテル・ルワンダ」「ナイロビの蜂」「ラスト・キング・オブ・スコットランド」「名もなきアフリカの地で」「ダーウィンの悪夢」・・・頭の中でこの間観たアフリカの映像がぐるぐる巡る。アフリカを舞台にした一連の作品は、これからも次々と上映が予定されている。
それにしても。
「アフリカ映画の父」とされる80数歳にもなろうとするウスマン・センベーヌ監督の作品を、僕は、恥ずかしながら、今回が初見である。これまでに、5つの小説、5つの短編小説、4つの短編映画、9つの長編映画、4つのドキュメンタリーを発表しているらしい。
まるで、知らない。
レンガ職人であったセンベーヌ監督は、運命に導かれるように国際的な革命闘士となり、とくに仏領アフリカの解放戦線に飛び込んだ。出身のセネガルを超えて、識字率のきわめて低いアフリカの民衆のために、映画というプロパガンダ手法を求め、モスクワで映像制作を学んだ。40歳もすでに超えていた。1962年に帰国し、翌年にはすでに映像作品を発表している。

2004年、カンヌ映画祭「ある視点部門」でグランプリを授賞したこの作品に、僕は正直なところぶったまげてしまった。
ヒューマニズム映画であり、西アフリカを中心に現在も続いている女性の「割礼」(宗教的側面の強調を避けるためFGM(女性器切除)と呼ばれている)に対する告発をテーマにしている作品であるが、左翼教条主義的でも欧米的視点からの懺悔ないし啓蒙的な角度でもない。
西アフリカの普通の小さな村。描かれているのは、どこをとっても「大状況」ではない。きわめて「局所的」な関係世界の中で成立している日常のなかの、「ある事件」に焦点をあてている。
ある日、割礼を強制された少女たちが、コレ(ファトゥマタ・クリバリ)のところに逃げ込んでくる。かつて、割礼の後遺症でふたりの子供を流産し、3人目の娘アムサトゥは帝王切開でようやく出産したコレ。そのことがあって、娘アムサトゥには割礼を受けさせず、「ピラコロ」(割礼を受けていない娘のことで、結婚できないとされる)と呼ばれても耐えていることを、逃げ込んだ少女たちは知っていたのだ。
娘の助言もあり、コレは少女たちをかくまう決意をする。地域の風習である「モーラーデ」(保護を求める人々に対して一定の期間、全力で守ること。この宣言をした者には、対抗者も迂闊に踏み込めない)を利用し、少女たちを渡さないと宣告をする。
当然、「ピラコロ」になることで村八分になることを怖れる少女たちの母親や、女性が割礼をすることは当たり前だと考える男たち、そして割礼師と呼ばれる伝統的助産婦たちは、コレから少女たちを取り戻そうとするが、モーラーデが結界のような役割を果たし、踏み込むことが出来ない。
男たちは「モーラーデ」をコレに解除させるため、コレの亭主を情けないと責め立て、鞭を渡して大衆の面前で亭主により鞭打たせる。
コレはひたすら耐える。
少女のひとりが攫われ割礼されることで命を落とす。女たちはついに怒りを爆発させ、集団として男たちや割礼師たちと対決をする。「私たちの子供には、もう割礼をさせない」と。

大きな革命劇や政治劇ではない。
もともと、宗教的な根拠も無いのに、何千年かの土着的な未開の慣習が、男尊女卑的土壌と重なって、女たちに根拠無き強制(割礼)をしてきた。
ラジオなどを通じて、外の世界を知るにいたった女たちは、小さな村の直接民主制を装った長老支配の慣習に、反旗を翻した。それだけのことである。
きわめて局所的な事件であるが、それが逆に「アフリカという現在」の見事な縮図になっている。
孤立するコレをまっさきにピラコロである娘が勇気づける。そして、第一ママと第三ママ(一夫多妻である)も、ほどなくしてコレの味方になる。次いで、女たちの集会場とも言える水汲み場で、一人ひとりが、発言するようになる。最後は、コレに反対していて娘を割礼で死なせてしまった女が、哀しみで慟哭し、赤ちゃんを高く掲げて、男たちに「もう割礼はさせない」と宣言する。
一方で男たちも一枚岩ではありえない。「傭兵」と呼ばれる雑貨商。外の世界を知っており、コレへの鞭打ちを止めさせようとする。この男は、国連軍に参加していたが、上司の腐敗を告発し、恨みを買って、投獄されていた経験を持つ。男は、村を追われるどころか、殺戮されることになる。
フランスから帰ってきた村長の息子。アムサトゥと婚約していたが、ピラコロであることから当然のように親たちの猛反対を受け、11歳の親戚の娘をあてがわれようとされる。この息子は近代主義の洗礼を受けたように描かれているが、結局、村長である父に押さえつけられていた。ついにコレたち女たちの反乱で、目覚めることになる。
コレに泣きながらも鞭打ちをしたことを後悔していた亭主もまた、屹然と男たちの集会を離れ、コレのもとに行く。
僕たちはこの小さな村の日常の描写に淡々と醸し出されるだけなのだが、やはりアフリカ的エネルギーの豊穣さに驚かされる。
曲線の塔のような施設は、ある意味で、ハリーポッターに出てくるような魔法的な可愛らしさだ。
女たちの原色を巧みに着こなすファッションセンスには脱帽だ。
「モーラーデ」のために門口に渡される結界の「紐」でさえも、とてもおしゃれに見えてくる。安っぽいバケツも、使い古された家財道具も、ちょっとした女たちの装飾品も、とても個性に満ちている。
いったい文化とはなんだろう。たしかに、アフリカ的世界は、必ず、西欧的世界を文明史的には、遅れて経験するのだろう。けれど、文化の世界は、多義的であり、十分アフリカ的世界の文化は豊穣で、逆に僕たち先進国の住人の中にもあるアフリカ的な感性、霊性の記憶のようなものを、たしかに、つき動かされるのである。

「モーラーデ」という風習は、期限を除けば、日本の駆け込み寺のような存在であり、きわめてアジールな空間である。
そこでは、地上の法律や慣習や身分や罪業や、そういうものが突然無化される。治外法権であり、徳政令や恩赦布令がもたらすリセット感覚に似ている。
最後の逃げ場所といってもいい。
息苦しく窮屈な、近代法治国家や表層的な道徳観念に縛られている市民主義的常識に、もっとも欠けている概念である。
「モーラーデ」という空間をうまく駆使できれば、うんざりするほどの自殺者の群れは、激減するに決まっている。
マリ、ギニア、エジプト、スーダン、エチオピアでは、80%以上の女性が現在でも割礼を強いられている。アフリカでは30カ国以上、1億3000万人の女性が割礼に苦しみ、毎日8000人以上の少女たちが、強制的に割礼されている。
FGMの80%はクリトリスと小陰唇の一部または全部の切除でクリトリデクトミーと呼ばれる。さらに悲惨なのは、15%ほどといわれるが、大陰唇を縫い合わる膣口縫合である。
FGMとは、性器切除時の一過性の痛みではなく、排泄、生理、性交に関しての苦痛は、一生ついてまわることになる。不衛生でもあり、麻酔なしの処置であるFGMが元で、死にいたることも少なくない。
そうした現実に対し「割礼」とはよくユダヤ教でいわれるほとんどは男児に対してのものであり、包茎手術のようなものである、といったとんでもない無知を曝け出していた自分が、本当に恥ずかしい。
今からでもたぶん遅くない。
僕は、センベーヌの仕事を、まともに追ってみようと思う。











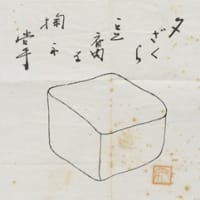


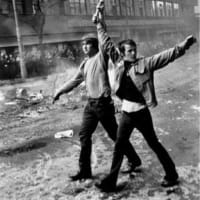



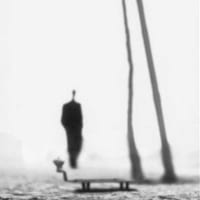

実は文中の言葉がgooブログの規制に引っかかるようで、TBできないみたいですので、コメントにてお邪魔いたします^^
センベーヌ監督は、他国からの介入で自国の悪しき風習をなくすのではなく、あくまでも自分たちの問題として捉え自分たちで行動を起こすべきと考えているようで、感銘を受けました。私もセンベーヌ監督の他の作品、見てみたいです。
はは、そうですね。僕も、引っかかるかなと思いつつ表現しました。画像検索などの場合は、解除できるんですけどね。blogのTBの場合は、解除できないのかな。
監督は絵本作家の経歴もあるんだそうですよ。
たかが映画を人より多く観てるぐらいで、
世界のことなど何ひとつわかってはいないんですが、
ホントに自分はのん気に生きてんだなぁと痛感しました。
襟を正して観なきゃイカン映画ですよね。
まあ、あんまり社会派、人権派をきどるのは、イヤなんですけどね(笑)
「善への道は墓場に通ず」という言葉がありますが、僕は無私な無類のおろかな善を愛するものですが、市民社会主義的な良識善というのは、馬鹿にしています(笑)
モーラーデの風習、確かに中世日本の駆け込み寺や縁切り寺を思わせますね。
それを「前近代的なもの」と切り捨てるのではなく、「私たちの社会に欠けているもの」として感じておられるkimion20002000さんの視点に、ハッとさせられました。
この映画、もし欧米の人間が制作していたなら、何となく啓蒙主義的な匂いを感じて胡散臭く思えたかも知れません。センベーヌ氏はあくまで「自分たちの問題」としてとらえていたのだろうと思いました。
映画に出てくる村人と自分の間には、かなりの隔たりを感じましたが、見て良かったと思える作品でした。
考えたら身の毛もよだつ恐怖を感じましたが、映画的には
淡々と力強く、そして明るく描いてあったので、余計に心に染み渡りました。
なんでもかんでも世界統一になるのには反対ですが、
やはりこういう風習は無くなって欲しいと思いました。
それにしても綺麗な村でしたよね~。
きちんと掃除してるんだろうなと思われる道や庭や家。
それに綺麗な色彩の服。 その他の部分にもエネルギーに
満ち溢れてましたよね♪
TBさせていただきましたm(_ _)m
最初、モーラーデの意味が一瞬わからなかったんですよ。
宗教的な特別の日の一種かなと。でも、それが、保護を求めるという行為に対しての宣言で成立する、というのがわかり、なんか、単純に感動しちゃったところがあります。
水汲みとか重労働なんだけど、頭の上に樽とか載せて運ぶ姿が、優雅ですね。プラスチック製品を持っても、なんか、コーディネイトしてしまう。不思議ですね。
それにしても、男たちは、昼間からごろごろ何をやって生計をたてているんだ?(笑)
映画を観る前にセンベーヌ監督のプロフィールを読み、それだけでえらく感動しました。
すばらしいですよね。
TBは「性器」が引っかかるようです。
そこを一時的に変更したら送れました。
まさに、アフリカの現代史とともに、生きてきた人ですね。
また、作品が、軽やかです。本当に、感心しました。