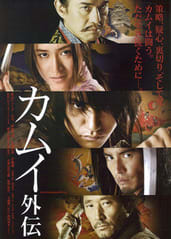
白土三平原作の傑作コミックを『血と骨』の崔洋一が実写化したアクション娯楽大作。忍びのおきてに背き、たった一人で追っ手から身をかわす不屈の主人公の苦悩と孤独を浮きぼりにする。孤高のヒーローをその抜群のセンスで演じるのは、『L change the WorLd』の松山ケンイチ。ヒロインを『ラスト・ブラッド』の小雪が演じている。人気脚本家、宮藤官九郎と監督が共同で手掛けた脚本からあふれ出す人間味に満ちた物語に圧倒される。[もっと詳しく]
白土三平はもう一度、カムイ伝を本格的に描くことが出来るのだろうか。
白土三平の膨大な劇画群に関しては、初期の貸本屋時代の作品で見落としがあるかもしれないが、復刻されたものも含めて、すべてに目を通してきた。
「カムイ伝」に関しては、1964年から1971年まで『ガロ』で発表され、10年近くの間を置いて、88年から2年間『ビッグ・コミック』誌上で第二部が発表された。途中中断しているが、本来は三部構成であり、第三部が描かれるかどうかはわからない。
カムイとは「狼」の別称。江戸初頭、身分制度厳しき日置藩を舞台にし、の子であるカムイ、農民の子である正助、武士の子である竜之介の成長を描く長編劇画であるが、数百人の登場人物が複雑に絡み合い、そこに歴史史観が入り、階級闘争が組み込まれ、文化人類学的な描写がありということで、とてつもないスケールの物語の骨格を持っている。
「カムイ外伝」は、この長編劇画から、カムイのある時期のエピソードだけを取り出したものだが、時代設定的には「カムイ伝」の一部と二部の間とされている。
「カムイ伝」連載中に、『少年サンデー』で不定期連載され、その後82年から87年に『ビッグコミック』誌上で「カムイ外伝第二部」として連載され、最近「カムイ外伝第三部」を期待させるような執筆があった。
これらの作品の一部は、劇場版アニメになったりテレビ版アニメとして放映されたりもした。
崔洋一監督の実写版『カムイ外伝』は、外伝第二部の「スガルの島」をベースとして、宮藤官九郎と崔監督との共同脚本となっている。
「抜け忍」であるスガル(小雪)は、瀬戸内の奇ヶ島に流れ着き、お鹿と名前を変えて3人の子どもをもうけ、半兵衛(小林薫)と平穏な暮らしをしている。
半兵衛は疑似餌に加工するために、備中松山藩の領主水谷軍兵衛(佐藤浩市)の愛馬「一白」の足を切り取り、追われるはめになるが、同じく「抜け忍」として追われていたカムイ(松山ケンイチ)と連れ立って、島に逃げ帰ることになる。
くの一で抜け忍であるスガルはカムイが「追忍」ではないかと警戒するが、娘のサヤカ(大後寿々花)がカヌイに思慕し「月日貝」を送るような関係になり、島での生活にカムイも馴染んでいく。
密告で捕まった半兵衛を、危機一髪救い出すカムイとスガルだが、抜け忍の集団であるらしい大きな千石船を操る「渡り衆」に助けられたりもする。
その頭目は不動(伊藤英明)であり、カムイを仲間に誘ったりするのだが・・・。
この映画をめぐり、朝日新聞の映画評論家の秋山登が「仕立てが大味」などとケチをつけたため、崔監督は朝日新聞のライバル紙である中日新聞紙上で「ちゃんと観ろ!」と反論するという場外乱闘に発展した。
秋山登という御仁は、個人的には僕は好きではなく、韓国映画の『グエムルー漢江の怪物ー』の紹介記事に対してチャチャをいれたことがある(笑)。
製作過程のエピソードなどを読む限りでは、崔監督は相当な苦労をして、この作品を仕上げたらしく、秋山登に対して相当腹が立ったのだろう。
「差別」に対する問題意識に対して、良識を自負する朝日新聞と、出自から来るこだわりを持つ崔監督との、無意識の本家争いみたいなところもあるのではないか、というのは僕の邪推であるが。
「カムイ伝」の単行本出版部数はのべ1000万部を超えており、「カムイ外伝」だけで300万部を超えている。
とくに中高年にとってみれば、白土三平はある意味でカリスマのような存在である。
長らく千葉県の海沿いに居住しながら、現在では狩猟や自然生態観察の第一人者のようにもなっている白土三平が、リップサービスかどうか、「生身のカムイがはじめて映像化された」といった賛辞を贈ったなどとの話もある。
しかしどのように作品に仕上げてもかならず不満の声はあがることになる。
それが超有名な原作を映像化するということの宿命みたいなものだ。
崔監督も力が入ったのだろう。
白土三平の劇画を引用しながら、政治の季節に『忍者武芸帖』を映像化した大島渚よりも、もしかしたらプレッシャーは大きかったかもしれない。
崔洋一監督の『カムイ外伝』で実写映像化にあたって、かなり意識しただろうなと思わせられたことが三つほどある。
ひとつは、忍びの目まぐるしい超人的な動きの中に、「はっははっは」という呼吸音を明瞭に響かせたことである。
劇画でも文字としては表されるかもしれないが、やはり生身の役者が演じるリアリティをこの呼吸音に現わしたかったのかもしれない。
ふたつめは、動物の特殊効果によるリアリティ造形である。
最初に山道で鹿のようなものが登場するときから、その奇妙に生々しい動きからそれが感じられる。
大空を舞う鳥もそうだが、半兵衛に足を切られ川でもがく馬もそうだし、圧巻は渡り衆が対峙する巨大な海の鯱であろう。
もうひとつは、海の描写である。
この映画はある意味で「海洋アドヴェンチャー」的な側面も持っているが、通常忍者ものであると、山間の人知れぬ争闘が主軸になると思われるが、原作の「スガルの島」ということに拠ってはいるのだが、海の描写を工夫しているところは、白土三平へのリスペクトがあるのかな、と思わされる。
「カムイ伝」をはじめとする白土三平の作品の研究としては、四方田犬彦が第一人者である。
白土三平が、壮大なる社会思想実験のようにこの作品世界に傾注してきた姿を、四方田はよく解読している。
白土三平の父はプロレタリア作家であり、妹は絵本作家として知られている。
一時期、信州は真田村に疎開していたことがあり、そこから忍者、差別、村落コンミューンといった世界に接近していったようだ。
日置藩、花巻村、夙谷といった「カムイ伝」を構成する地勢とその下部構造のかかわりに、僕たちは見たこともない歴史教科書をひもとくような興奮をもって、作品を待ちわびたものだった。
最近話題になっている書籍では、江戸文化研究で注目され、僕たちには歴史学のマドンナと称されている田中優子が、法政大学であろうか、学生たちへの授業としてセットした『カムイ伝講義』がある。
彼女は、この時代の「カムイ伝」を構成する民衆を「技能集団」として捉えなおしている。
農民もマタギもサンカも海の民もそうなのだが、職業的・身分的な命名だけではなく、豊穣な技能を持った自立した集団が構成する社会の可能性を見て取っている。
学生の授業に、例えばマタギの後継者の智慧を学ぶフィールドワークを課していたりもする。
とても面白い試みだ。
『カムイ外伝』という映画作品をその水準としてみれば、過去の忍者劇の幼稚さは脱却しているものの、特殊撮影やCG技術の適用に関しては、スタッフの苦労はいろいろあるだろうが、別に驚かさせられる映像表現はなにもない。
「変移抜刀霞斬り」や「飯綱落とし」といったカムイの代名詞のような技などは懐かしく観ることが出来るが、役者たちの動きに関しては、なんだか鈍重に思えた。
キャストの訓練の成果を問うているのではない。
ここではあくまでも特殊撮影やVFXの水準が、中途半端に終わっているということが問題なのだ。
思想的バックボーンの解釈はともあれとして、僕には崔洋一監督が、動きの早いアクション演出に優れているとはとうてい思えない。
どういうわけかせっかく山崎努を起用したナレーションも、なんだか間が抜けたものであった。
松山ケンイチは体当たりの演技をしているが、カムイが持つ「孤高」というものを匂わさせられたかどうかといえば、とても微妙である。
時代劇に重用される小春の演技はワンパターンでいただけないし、藩主をはじめ松山藩の連中ときたら、とてもじゃないが、リアリティがない。
結局のところ、白土三平はカムイを本格的に復活させることが出来るのかどうか、ということに僕たちの関心は向かざるを得ない。
世界はこの数十年でますます複雑化しており、カムイの背景にある世界観もどうやって現代に通じる暗喩にしていくかということで言えば、とても困難を極めていることは確かだ。
kimion20002000の関連レヴュー
『グエムルー漢江の怪物ー』











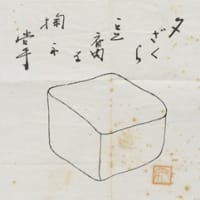


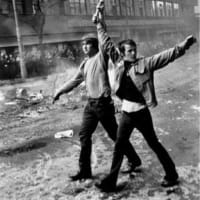



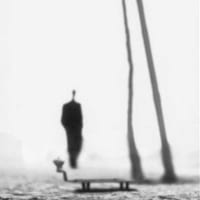

>特殊撮影やVFXの水準が、中途半端
>ナレーションも、なんだか間が抜けたもの
>「孤高」というものを匂わさせられたかどうかといえば、とても微妙
等々、同感です。
原作との違いをうんぬんするつもりはありませんが、
はっきり言って、カムイ外伝ってこんなだっけかな?
てな感じでした。
これ、アクション監督とVFX監督に、香港の連中を使ったほうがよかったかもしれません。
あと、クドカンの脚本も、なんだかなあ。
この映画の価値は、中高年のカリスマを、若い人に知らせたことだったかな・・と。
ただし、その真髄が伝わったかは、ちょっときつかったですね。
あたしも、秋山某氏の評は、いつも頭をかしげます。
誰がやっても難しいかもしれませんね。
まあでも、若い世代がこれでカムイ伝や白土三平に興味を持って、読むようになったら、この映画も意味を持つようになるでしょう。
僕も本作の問題はそれに尽きると思います。
“中途半端”まで行っていないような気さえしました(笑)。
大体ワイヤーとスローが嫌い(多くは才能のない連中の誤魔化し)なので、余計がっかりしましたねえ。
僕が小学生の時に観たTVアニメシリーズは大好きでした。
我が家は貧乏だったということもあり、親に負担をかける漫画本は読まなかったですね。
いずれにしても、松山ケンイチ君にカムイのイメージがなく、観る前も観た後もNGです(笑)。
最後に秋山登なる批評家のレベルは存じ上げませんが、映画批評家は批評をするのが仕事ですから、作者は過剰な反応は控えた方が良いと思います。
他人の喧嘩は観ていて楽しいですが(笑)。
そうね、他人の喧嘩以外の何者でもないですけどね(笑)。