
なめきった大人たちが、青春物語を「通俗」に導く。
僕たちは思春期の頃、やはりどこかでアメリカに憧れていたところがある。
「アメリカン・グラフィティ」のように、御馬鹿で少しキュートな青春物語。
どの街にも、少し年上に、オートバイ野郎とか、アメ車の信奉者とか、ロックンローラーやサーファーがいた。
クスリをやっているグループもいたし、自慢のナイフを持ち歩いている兄貴もいた。真夜中にグラサンをしてみたり、うまくもないのに、マールボロを吸ってみたりもした。
皮ジャンにリーゼントスタイルの友人と、Junの細身の花柄シャツに肩まで長髪の少年(僕のことだ)が、一緒に歩いているという滑稽も気にならなかった。

しかも田舎の町である。
高校も中退し、ガソリンスタンドで働きながら、たまに、農作業を終わって繰り出した兄ちゃんたちと、酒場でいざこざを起す。
たった1件しかない、ビリヤードホールで、女の子をはべらかしたりする。
もちろん、黒人がいるわけでもないし、牧師以外には白人などいない。ジャズもブルースも有線でかかっているような街だ。
福生や横須賀や佐世保に憧れたりした。六本木なんて、想像のしようもないし、湘南の海は、どこからどこまでがそうなのか、てんでわからない。
だから、もっぱら、片岡義男の小説である。
そのなかのアメリカが、自分たちにとってのアメリカだ。
もう少し、時代があとになれば、村上龍だ。「限りなく透明に近いブルー」は福生の青春物語。
雑誌「POPAYE」の創刊は1976年。おしゃれなアメリカがそこにはあった。

山田詠美の短編を下に、この映画は製作された。
製作/亀山千広、企画・プロデュース/大多亮、監督/中江功、脚本/水橋文美江。
いわずもがな、吐き気の出るような駄作「冷静と情熱の間」のフジテレビ系のスタッフである。
出演は主人公志郎に柳楽優弥、初恋の相手乃里子に沢尻エリカ。アメリカ狂いのお婆ちゃん(グランマ)に夏木マリとその若い恋人役マイクにチェン・ボーリン。優弥の恋敵矢野に高岡蒼甫。
福生の街を舞台に、乃里子への初恋とそして失恋を通しての志郎の成長物語。そこに、人生の達人であるかのようにグランマが助言をする。
たとえば「女の子は甘くて優しいだけじゃ駄目なのよ。強引に引っ張ってくれることも願っているの」まあ、そういったことがタイトルの「シュガー&スパイス」である。

カンヌで主演男優賞を14歳でとった柳楽優弥は、前作「星になった少年」もそうだが、フジテレビの子飼いになったのか。なんなんだ?いまや、絶好調の沢尻エリカと組み合わされて、アイドルロマンがしたいのか?
夏木マリのあのもったいぶった演技はなんなんだ?「チョイ悪姐御」の路線で評判がでつつあったのに、これはコメディのつもりで参加したのか?
チェン・ポーリンは、なんでこんなところに意味もなくでしゃばっているんだ?日本の観客をなめているのか?なにがよくて、グランマのお守りをしているんだ?
19歳になったら・・・志郎と乃里子のおままごとが続く。
思春期のドキドキは誰にもあるし、乃里子はちょっぴり大人で、結果として矢野に二股かける小ざかしい娘になっている。まあ、男と女は微妙だ。くっついたり離れたりまたくっついたりは、はいて捨てるほどある。
友人たち(マッキー、ヨウコ、尚樹)も、性をめぐるドタバタで青春している。
正直といえば正直な、オツムが良さそうにない、青春群像であり、等身大といえば等身大の、青春説話である。

こういう作品を、わざわざ、スタッフを動員しての映画にする魂胆がよくわからない。
テレビであればわからなくもないが、それでも1クールもつようなお話でもない。もちろん、谷崎潤一郎賞を受けたこの小品を、けなしているわけではない。
山田詠美は、当代きっての物語メーカーだ。いつも、その斬新な言葉に、はっとさせられる。頭で、捻くった、言葉ではない。
思春期を思い出す。
ある意味で、女の子のことしか、頭になかったかもしれない。
何時間も、何時間も、公園のベンチにたたずんで、なにを話すともなく、ただ一緒にいるのが幸せだった。
無知な頭の中で、欲望だけが膨らんでいく。自分が汚いもののように思えてくる。眠れない夜に、感情を持て余して、犬のように遠吠えをする。
世間知も何もない。自己嫌悪と自己憐憫と・・・。
この時期にしかない、宝物のような時間であり、そのほとんどは後悔と化していく。

それでも、と僕は思う。
たしかに、「シュガー&スパイス」だ。
だけど、この映画のように、なめきった大人たちによって、「通俗」にまみれさせてほしくはないのだ、と。











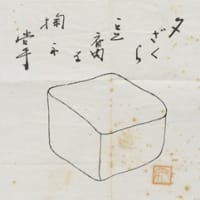


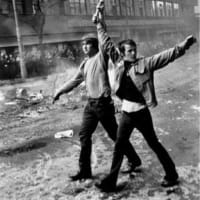



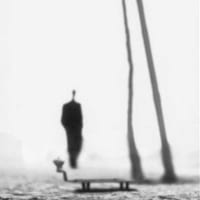

試写会で見たので、あんまり酷評もできず。
(一応、試写には宣伝してねの意味があったので)
しょうもない映画見てると、いろいろな無駄が出てきた、エコに反するなあ、などとも思った覚えがありますです。
基本はこれからご覧になる方もおられますから、あんまり酷評はしないんですけどね。
ときどき、僕の「地雷」というのがあります<笑)
じゃあ、blogはパスすればいいじゃないの、という反論がきそうですが、悪口は悪口で、また楽しいんですね、はは。