
5度芥川賞候補に挙がりながら、41歳で自殺した作家・佐藤泰志の遺作を映画化したオムニバス・ストーリー。北海道・函館をモデルにした架空の地方都市を舞台に、さまざまな事情を抱えた人々が必死に生きる姿を描く。監督は『ノン子36歳(家事手伝い)』の熊切和嘉。『アウトレイジ』の加瀬亮、『おにいちゃんのハナビ』の谷村美月、『春との旅』の小林薫らが出演する。リアルな人間ドラマとオール函館ロケによる映像に注目だ。[もっと詳しく]
街全体がオープンセットのような函館を舞台にして、あえて逆を行った誠実さ。
エンドロールに延々と、ほとんどが函館にゆかりがあるらしき人たちの名前が連ねられている。
『海炭市叙景』製作委員会に、地元のシネマ経営者や原作の佐藤泰志の高校時代の同期生たち製作委員会の二十数名を始めとして、インディペンダントなこの映画の製作費用を賄うために、さまざまな催しを通じて1000万円以上の費用を集めた人たちの名前も多く連ねられている。
函館フィルムコミッションの呼びかけに応じたのであろう500人を超えるエキストラの名前も、たぶんそのなかにあるのだろう。
撮影場所になった商店や公共施設や民間企業も、協力先としてずらっと並べられている。
僕も何度か行ったことがあるが、函館はとても「絵になる街」だ。
街全体がオープンセットのようだといわれることもある。
函館をロケ地とした映画は、すでに70本にものぼっているそうだ。
函館を舞台にした映画は、すぐにいくつかを思い出すことが出来る。
古くは日活アクションの『ギターを持った渡り鳥』や『夕陽の丘』。少しバタ臭い埠頭のイメージで選ばれたのかもしれない。
先日お亡くなりになった森田芳光監督は、『キッチン』『キリコの風景』『海猫』『わたし出すわ』と相次いで函館を舞台に選んだ。
宮崎あおいが16歳で出演し、尻尾が生えた女の子が『パコダテ人』として人気者になるという可愛い映画もあったし、人気子役時代の神木君が『小さな恋の物語』で少年DJに扮したり、田中麗奈が『犬と私の十の約束』でお涙頂戴をしたり、常盤貴子が『引き出しの中のラブレター』で函館山から街を一望できるスタジオのDJ役で感涙の手紙を読み上げたり、『ACACIA』ではアントニオ猪木が寂れた老人団地のようなところで哀愁を振りまいてもいた。
なかでももっとも函館の情感を映像化していたのは、香港映画のパクリかもしれないが、竹内結子主演の『星に願いを』であるかもしれない。
お話自体は、時空を超えた恋愛悲劇でなんということもないのだが、今でもそのシーンのいくつかを、函館特有のスポットと重ね合わせて、思い出すことが出来るし、胸がざわめいたりもする。
空港が出来てすっかり寂れてしまったが、青函連絡船は情緒があったし、函館市内の路面電車や車庫は絵にもなる。
ハリスト正教会や元町教会や旧ロシア領事館や50年以上も前のレトロ倉庫群は異国情緒を漂わせるし、ロープーウェイで昇っていく函館山からのライトアップされた街並みは美しい。
少し市街を離れれば、カモメが飛び交う侘しくもなる漁港のたたずまいだ。

けれども、『海炭市叙景』は明らかに函館市を舞台としているにもかかわらず、そして多くの函館の関係者がたぶん協力を惜しまなかった地元映画であるにかかわらず、それまでの函館を舞台にした映画とは明らかに空気が異なっている。
もちろん、原作の佐藤泰志は、注意深くその都市の名前を「海炭市」に変えて、函館にはないボタ山や炭住やの北海道特有の炭鉱町の歴史的イメージも重層している。
それは、『海炭市叙景』という短編群で、東京のことを首都と呼んでいるように、またその短編集に多くの海炭市およびその周辺の町名などが出てくるが、たぶんその名前も創作であるように、本当は函館でなくても、あるバブル期末期の地方都市とそこに生きる普通の人たちを、典型したかったのではないかと思わせられるところもある。

人口は30万人で北海道の南に位置する砂嘴で構成されたこの特異な地域に、年間300万人の観光客が訪れる。
そして、これまでの函館を理想のオープンセットとした数々の映画は、そのことを十分に意識して制作されているはずだ。
しかし『海炭市叙景』はまるで異なっている。
一部、函館山から見下ろす夜の街の光のシーンはあるが、それは元旦の朝の日の出を見る地元の人たちのシーンだ。
観光客が、この美しい夜景を見に来るのは、ほとんどが夏場である。
それ以外は、ひたすら「理想のロケ地」を裏切るような場所ばかりを、北海道帯広出身の熊切和嘉監督たちスタッフは注意深く選んでいる。
そのことは、この作品を遺作として41歳で自死を遂げた佐藤泰志への、誠実なリスペクトであるかのように思えて仕方がない。
原作は18組の登場人物たちが微妙に連関しているオムニバス連作だ。
ただ僕たちが手にすることが出来るのは、全体の折り返し地点である1章と2章であり、季節としては冬と春だ。
構想では夏と秋の物語群が予定されていたが、残念ながらそれは書かれることがなかった。
映画は、残された18の物語のうちから、5本が抽出されて質の高いオムニバス映画となっている。
その5本にしても、原作短編と映画とでは、微妙にシナリオを変えてあったりする。
原作を読んだ人ならたぶん感知する事が出来るだろうが、この5本の物語は18本の掌編の中でも、とくに暗く重苦しいトーンの作品が選ばれている。
映画的時間の制約からか、構成上の問題からかは、よくわからない。
けれど、『海炭市叙景』という遺作の、描きたかった世界は、十分にこの映画からも伝わってくる。

町の雇用吸収のひとつであった造船ドッグの縮小からお決まりの人員削減が象徴的にこの街に吹き荒れるところが小説でも導入部となっている。
失業した若い兄妹が、わずかな所持金をかき集めて、年越し蕎麦を小さなアパートで食べた後、思い立ったように函館山に初日の出を見に行く最初の物語のトーンが、その後の展開のかすかな基調音となっている。
物語の構成がたとえ10本になっても15本になっても、その基調音はあまり変わらないように思える。
帰りのロープーウェィの切符代が足りず、兄は「歩いて山を降りるから」と妹と別れ、妹は麓の待合室で6時間あまりも暗い予感に怯えつつ、ひとりで木の椅子に座って兄を待ち続け、結局兄が崖から転落したことを知ることになる。
こんな描写がある。

夏の観光シーズンには、他の土地からたくさんの人たちが夜景を見る目的であわただしくやって来る。人口三十五万人のこの街に住んでいる人々は、その夜景の無数の光のひとつでしかない。光がひとつ消えることや、ひとつ増えることは、ここを訪れる人にとって、どうでもいいことに違いない。それを咎めることは誰にもできない。
(第一章 物語のはじまった崖 1 まだ若い廃墟より引用)
無数の光に、それぞれの物語がいとおしくも哀しく奏でられていくということが、この作品の基調音となっている。
ジム・オリークの音楽が、そこにスコアを情感深くつけている。
1980年代末期、都市の一極集中と産業の空洞化と金融資本のバブル政策の中で、どこの地方都市でも農地は争って売られ、産業道路が造られ、結局ほとんど見果てぬ夢に終わった産業団地が造成され、中央からは大規模ショッピングセンターが進出して古くからの商店は潰れ、貧富の差が増大し、家族そのものが浮遊しながら彷徨うことになった。
欲望は果てしなく、自分が自分であることを見失い、羨望や嫉妬の感情が不必要に渦巻いた。
つつましやかな価値観は、もう過去からの抑圧以上のものとは感じられなくなってきた。
暴力や諍いは、剥き出しになったり、内向したりした。
そんな時代に、たぶんどこの地方都市でもおこったであろう、普遍的な普通の人々のリアルな物語を、佐藤泰志はあるがままのように描きたかった。
村上春樹や中上健次らとデヴューを競いあい、五度も芥川賞候補になり、三島由紀夫賞候補にもなりながら結局受賞を逃し、理由はともあれ、佐藤泰志は41歳で自死した。
それから20年ほどの歳月がたち、その頃からの数少ないが熱心な読者と、地元函館の有志たちによって、佐藤泰志は甦ったのだ。
同人誌に書き始めていたような小さな物語群が、今では文庫で洩れなく読むことが出来る。
そして僕たちは、書かれなかった『海炭市叙景』の第三章と第四章をあれこれ想像したりしてみる。
『海炭市叙景』には、明るく小奇麗で異国風な観光スポットはほとんど映されていない。
むしろ、何の変哲もない戸建住宅や、トラックが粉塵をたてて走り去るような産業道路や、場末の欲望が剥き出しのスナックや、ほとんど観客もいないようなプラネタリウム館や、家庭の崩壊の中でギスギスしているプロパンガス商店や、立ち退きを拒否したまま残ってしまったバラックの建物や・・・そういう風景の中で、家族でも分かち合えない孤独感と寂量とした地元特有の人間関係が、どの物語も等質にオムニバスされている。
普通であれば、ご当地映画の特権として、華やかな祭りの部分がクライマックスと重なったり、名勝、旧跡が舞台で絵葉書のように使われたり、地元の善意の人情がエキストラの表情とともに醸し出されたり、するはずである。
そして撮影終了後の打ち上げでは、キャスト・スタッフ、地元民たちが和気藹々と撮影のエピソードを披露しあったり、隠された「街自慢」で笑顔が絶えないはずだ。
けれども、この『海炭市叙景』では、たぶんずっと静かに、協力をした人々の心の中に、佐藤泰志が凝視したものが、おりのように沈殿していったように僕には思えてしかたがない。
そのことがフィルムロケ誘致として、「街の活性化」に役立ったかどうかということは別として、ひとりの佐藤泰志のファンとして、あるいは『ノン子36歳(家事手伝い)』で埼玉の寄居であったか変哲もない商店街とその周辺に奇妙な愛着を感じさせた熊切監督と大学時代からのスタッフたちを評価するものとして、この映画の完成を僕も静かに祝福したいと思う。
kimion20002000の関連レヴュー
『引き出しの中のラブレター』
『ノン子36歳(家事手伝い)』
『星に願いを』
『海猫』











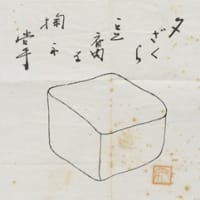


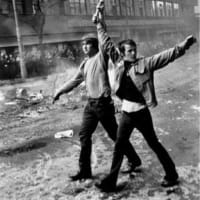



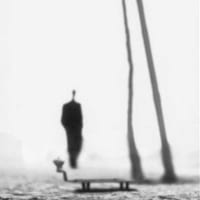

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます