
昨日研究仲間で読書会をやった。その後に別のメンバーも加わってスカイプで議論をした。内容は全体的には覚えているが、細かい点は記憶が蘇ってこない。なぜか。12時間近くにわたって食を忘れて没頭したせいではあるまいか。長い間やりすぎて効率が、著しく低下したにちがいない。パネルの前にすでに議論でヘトヘトに疲れてしまっているような感がある。いったい何を得たのだろうか。その点を整理しておかなくては、今後は、なおさらのこと思い出せないのかもしれない。Viveiros de Castro のCosmological Deixis という論文を、ほんとうに理解しているのかというのが出発点であった。再読であるが、以前本当に理解していたのかどうかきわめて怪しい。それだけ含蓄の深い論文である。途中までしか読み進むことができなかったが、大きくまとめるならば、相対主義とか普遍主義というような文化をめぐる議論は、西洋のある見方を踏まえて行われているというようなことが述べられている。それは、一つの自然があり、多くの文化があるという「多文化主義」の考え方である。アメリカ先住民は、これとはまったく逆に、文化は普遍的なものであり、自然が多様なかたちで現われるという(「多自然主義」)。西洋思考では、文化を一つ一つ区切って、その間の交渉が行われるというような事態が起きる。その上に、相対主義とか普遍主義というような議論がなされている。しかし、アメリカ先住民の世界では、そういったことはありえない。多自然主義者たちは、多様なかたちで存在する精霊や動物と交渉する。いわゆるコスミック・ポリティクスが行われるという。また、この論文を読んで、ヴィヴェイロス・デ・カストロが、それ以前に出たデスコーラの論文の「自然を対象化する三つの様式」を批判し、それに応じて、デスコーラが修正を加えて、「同定化の四つの様式」を提起したのではないかということも分かった。「存在論」に関してもわれわれは議論をした。それは、基本的に、実践を伴う。さらに、そのタームの使用には、より強烈なクリティシズムの匂いが嗅ぎ取れる。社会や社会的なるものが、西洋においてつくりだされた概念であり、わたしたちは、それを疑ってみることはないが、デスコーラの存在論の「同定化の四つの様式」は、社会という大きなくくりにおいては作動しない。その可変的なモデルは、コレクティブというより小さな集合において考えることができる。そういった意味で、存在論というタームは、既存の概念やそれを生み出した西洋思考に対する何らかの挑戦であるのかもしれない。荒っぽいが、備忘のために。










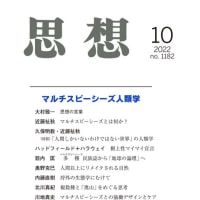

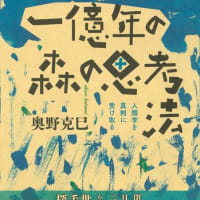
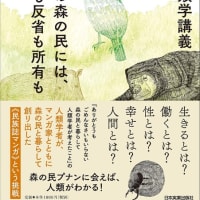



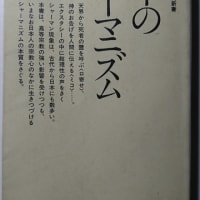


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます