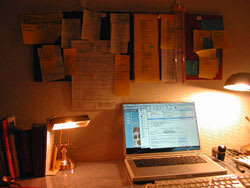
自分の過去記事を読んで一人悦に入る、というのはややナルっぽいと言えるかもしれない。しかしブログが日記あるいは思考の整理のための雑記、と割り切ると、過去記事を読み返してみるのは有意義で楽しいことだ。
「何だ、こんなこと考えてたのか」「この頃は文体違うな」なんてちょっとした発見もあり、みんなが書いてくれたコメントにはもっと面白い再発見があるに違いない。「あ~、こんな初期からやりとりしてたんだ。昔からの仲間だなあ」なんて。たとえ数ヶ月でも感慨深いものがあるのだ。
そこからその人のブログに飛んでいって、今度はそこのバックナンバーを読んでみる。一番最初の記事なんかガチガチだったりして面白い。初めてトラックバックのピンを打ったとき。初めてトラックバックをもらったとき。その感動の様子を書き表した記事を読んで、うんうんと頷かずにはおれないのだ。何と言っても自分だってそうだったのだから。
ブログって何だろうなあ~と思う。僕は文作の練習にいいやと思って始めたのだが、コメントでのやりとりが楽しくなってくると、人とのふれあいを求めて毎日記事を書くようになった。第1回『これからのブログ人へ』にも書いた通り、みんなの書く記事には興味をそそられるものが多く、すぐに影響を受けてトラックバック記事を書きたくなるのだ。それが“占い”のようなブームになることもある。
時にはコメントで言葉が足りずに相手に誤解を与えてしまうこともあった。しかしその後のやりとりでお互いがだんだん分かってくると、誤解を恐れず思い切ったツッコミをしたり、あえて説明を省いて単語だけ残したり。それで通じると(通じるのだ!)、また嬉しくなる。何よりも大切な“信頼関係”が出来た証だ。そんな居心地のいい場所に、思い切って自分を表現する。本音を書かないと続かないものだし、読んでいて心にストレートに伝わってくるのはたとえ反対意見であっても本音が書かれたものだ。
バックナンバーを読んでいくと、そんな“歴史”がみえる。次第に信頼関係を築いていく様子が分かる。ネット上の世界もやはりリアルな世界に違いない。
やっぱりブログはコミュニケーションツールなのだ。こんな道具、今までなかったなあ。
コメント編2へ
番外編へもどる
サイト内検索へもどる
コメント編へもどる
初回へもどる










