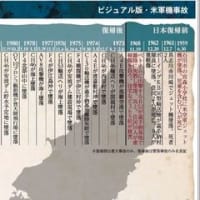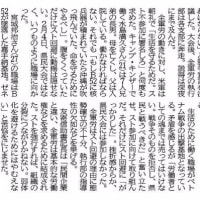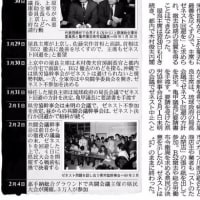日本型ネオリベラリズムを乗り越える戦略的議論!/昨今の景気回復にもかかわらず、「失われた10年」と呼ばれた1990年代以来の日本の喪失感はむしろ強まっている。年金や雇用をめぐる不安、戦後かつてない所得格差の広がり、持続する金融・財政危機のほか、日本経済を底支えしてきた地域社会が極度に疲弊し、崩壊の淵にある。本シリーズの編者の1人で経済評論家の内橋克人が早くから警鐘を鳴らしてきた通り、その背後にあるのは、市場原理を偏重した「構造改革」にほかならない。
ラテン・アメリカ諸国では、同じく「失われた10年」と呼ばれた社会経済現象が一足早く1980年代にみられた。南米アルゼンチンの場合は90年代にも「もうひとつの失われた10年」を経験した。前後一連の社会経済病理も含めて、これらもまた日本と同様、市場原理偏重の「構造改革」によってもたらされた。これは批判的なラテン・アメリカ地域研究者の常識である。とすれば、日本はラテン・アメリカの先行経験から反面教師的な教訓を得られるのではないか。またラテン・アメリカの政府、企業、市民社会が「失われた10年」の罠から逃れようと編み出してきた知恵からも、積極的な示唆を読み取れるに違いない。このような直感の下、内橋克人とわれわれラテン・アメリカ地域研究者が共同研究を重ねて編んだのが本シリーズ〈「失われた10年」を超えて――ラテン・アメリカの教訓〉全3巻である。
第1巻『ラテン・アメリカは警告する――「構造改革」日本の未来』は、シリーズ全体の総論となる。そこでの主な論点は、日本の「アルゼンチン化」の危険性、日本とラテン・アメリカにおける財政危機・金融危機・積立年金問題・雇用柔軟化の類似性、それにポスト「構造改革」政策(チリ、ブラジル)や「共生セクター」(中小企業の産業集積、メキシコの先住民協同組合、アルゼンチンやエクアドルの地域通貨など)の成果と限界、さらにはそれらが日本に与える示唆である。
なお、続刊の第2巻と第3巻では、地域社会の再生に果たすべき中小企業と市民社会の役割を考える。
-------------------------------------
シリーズタイトル シリーズ〈「失われた10年」を超えて―ラテン・アメリカの教訓〉第1巻
書籍タイトル ラテン・アメリカは警告する
サブタイトル 「構造改革」日本の未来
著者・編者・訳者 内橋克人・佐野誠編
第1巻執筆者
内橋克人、佐野誠、山崎圭一、宇佐見耕一、安原毅、小倉英敬、吾郷健二、岡本哲史、子安昭子、篠田武司、小池洋一、山本純一、新木秀和
出版社 新評論
発行年月日 2005年4月22日
価格 2730円
ISBNコード ISBN4-7948-0643-4
版型 四六判上製
頁数 355ページ -
-----------------------------------------------------
シリーズ続刊案内
第2巻 田中祐二・小池洋一 編
地域経済はよみがえる
ラテン・アメリカの産業集積にどう学ぶか 来春刊
第3巻 篠田武司・宇佐見耕一 編
不安社会を突破する
ラテン・アメリカにおける地域再生と市民社会 来春刊
*各280頁/予価2625円
----------------------------------------
インターネット新聞JANJANの書評
本書は、シリーズ「失われた10年」を超えて-ラテン・アメリカの教訓」の第1巻です。
1990年代の日本は「失われた10年」といわれる社会経済的困難に直面し、今もそれが続いている感があります。
この「失われた10年」、先輩格がいます。それが、本書で取り上げるラテン・アメリカで、1980年代に「失われた10年」に陥り、またアルゼンチンなどは1990年代にもまた「失われた10年」に陥りました。
日本とラテン・アメリカの「症状」は、必ずしも同一の現象というわけではありません。しかし、一定の共通した側面があります。新自由主義、市場原理を過信した自由化・規制緩和政策であり、それがもたらした一連の負の累積効果です。
日本はラテン・アメリカから、どのような反面教師的な教訓を得ることできるのか?同時にラテン・アメリカの政府、企業、市民社会が「失われた10年」から脱するために編み出してきた政策や戦略とその成果や限界から何を日本がすべきかを読み取る。
そうした問題意識の元、内橋克人さんとラテン・アメリカの専門家が合作で本書を発刊しました。財政危機、社会保障、金融、労働などあらゆる分野でラテン・アメリカのことが、ときに日本のことに言及しつつ分析されています。
新自由主義の仕組み
新自由主義者の唱導者たちは、常にその時代の最強の秩序形成者(権力者)に寄り添い、言動をともにすることによってのみ存在を誇示し、大衆を説得します。権力を攻撃するように見えるときでも、実際は、秩序意向に取り残された脱落者か「おろかな」抵抗者へのものに限られる(自民党「抵抗勢力」が良い例)。真の攻撃目標は、秩序形成者がやむなく与えた妥協の産物にあるというわけです。「妥協の産物」とは、いわゆる福祉国家のことと言って差し支えないでしょう。
共産主義国があった時代、共産化を防ぐためにも、秩序形成者(日本の場合自民党政府)は妥協して、労働に関する権利や社会保障、社会的規制などを与えざるを得なかった。また、大恐慌の教訓から、ビルト・イン・スタビライザー(経済自動安定化)の機能を財政にもたせることにした。最低生活保障制度などです。
これらを、新自由主義者は投げ捨てろというわけです。むろん、投げ捨てた結果は、健全な市場経済の足元を掘り崩すことになります。
ともかく、こうした新自由主義の仕組みを見破るポリシー・インテレクチュアル(政治知性)が求められると、内橋さんは言います。
新自由主義と経済危機
ラテン・アメリカの一部の国では、1970年代に新自由主義改革を行いました。特にアルゼンチンは1990年代にも同じ事を繰り返しました。そして、投機的ブーム、通貨危機、金融危機、対外債務危機、雇用と社会保障の脆弱化を招きました。
アルゼンチンでは、1976年から新自由主義的改革が行われました。1980年から82年にかけ、通貨危機・金融危機に見まわれました。
そして、歴史は繰り返し、1989年から金融と資本の自由化、貿易の自由化が断行され民営化も行われました。そして、事実上のドル本位制が導入され、金融政策も裁量がなくなりました。この改革も2001年、通貨危機が起きて崩壊したのです。
本来あるべき改革が……
一方で、ラテン・アメリカが抱えている本来の構造問題には手はつけられなかった。大土地所有制、不公平税制をはじめ、数々の不平等が挙げられるでしょう。不平等の問題は、むしろ新自由主義で悪化しました。
日本でも、土地無策、含み益経営、不公平税制、ゆるい労働規制、低福祉、大企業と中小企業の二重構造、政官財癒着などの構造問題こそ、手をつけられるべきだった。
ところが、両者ともに、規制緩和など新自由主義的改革こそが改革だという風に「誤認」されていった。そして、ポピュリズム改革(ラテン・アメリカ)や戦後改革(日本)の成果さえ掘り崩していったというわけです。
日本への教訓
今、小泉政府が行っている構造改革は、まさにラテン・アメリカが行った新自由主義改革と、ほぼ同じです。それは、アメリカを頂点としたグローバリゼーションを無条件に受け入れるということです。資本の自由を極大に認める一方で、市民の自由は削り取られるという按配です。
1998年頃に一騒動あったMAI(多国間投資協定)は、まさにそうでしたが、MAI自体はつぶれたが、日本の小泉政府はそれを国内でしていると「総論」の中で内橋さんは言います。
日本でも、「構造改革」がさらに構造問題を生んでいます。例えば、日本では景気回復といわれているが、実際には、家計には及んでいない。規制緩和で賃下げが進んでいることもあります。家計分野から企業への「所得移転」の構造は、改革どころか深刻化しています。
日本の場合、経済全体の貯蓄が大きいために対外債務危機にはなりませんが、その代わり、デフレ不況が深刻化しています。また、不良債権処理を進めたからといって、銀行の貸出しは増えるどころか減り、国債の購入が増えているというのは、日本とラテン・アメリカ共通であることを確認し興味深く思いました。
各章で力の入った分析
各章で各専門家の力の入った分析が見られました。
財政問題については、第1部第1章で山崎圭一さんからの日本・ラテンアメリカ双方への提言が目を引きます。新自由主義が進めてきたのは「小さな政府」(法人税減税)+政府支出カット)です。供給側を刺激するために、法人税を減税するというのが基本的な考え方です。
そうではなく、グローバル化時代に対応した大きな政府、「良い政府」が必要であり、法人への累進課税による増税をという提言も興味深くみました。
緊縮財政(政府支出抑制)路線をとりつつ、庶民増税(法人税減税はそのままに放置)で家計を圧迫し不況を続けているのが今の小泉政府ですから、その正反対の政策を取れば良い、というわけです。
現在、家計は苦しく、大手企業の多くが最高益という時でもあり、なるほど、と思いました。記者も、1990年代末以降の誤りの一つは、政府支出増加よりも(法人税)減税のほうが効果的という議論だと思っています。
現状より政府支出を増やしつつ法人税を増税するというのは、所得を増やすという意味でも財政という点でも、良いと思います。(政府支出の中身を環境・福祉重視にすることは必要でしょうが)。山崎さんによれば、例えば、レーガン減税も結局は成功とは言えなかったそうです。
アジアのラテン・アメリカ化という問題も第5章で取り上げています。アジア通貨危機後、アジアでも、それまでに比較的自立的で経済的平等を進める発展モデルから、アングロサクソン型システムへ、すなわち、外資の支配が強いラテン・アメリカ型に変わってきている。
もちろん日本にも、そういう傾向が及んでいることを示しています。アジアにおいても多国籍企業を先頭にした「新自由主義複合体」が覇権を確立しつつあるということです。そして、社会的不平等が拡大するなどしているというわけです。
大企業の利潤を中心に据えたアングロサクソン・システムではなく、働く人を基盤とした、新しい、自らのシステムを日本は作り出さなければならない、と、この章担当の吾郷健二さんは言います。
一方で、ラテン・アメリカでは新自由主義の弊害を補正したり、これに対抗する動きも出ています。第7章で紹介されたブラジルでの社会自由主義国家の試み。不充分に終わった部分もあるが、教育や保健などの社会指標は改善されました。
チリでも、軍政期の新自由主義的政策を改め、社会支出を増やし、公正と成長を両立させる路線に転換しているそうです。(チリの軍政期の高成長を新自由主義の成果として賞賛する向きもあるが、実際には、貧困層の大幅な拡大など犠牲も大きかったそうです)
また、ラテン・アメリカでは、人間中心主義の経済・社会の建設を求める議論が起きているそうです。メキシコ・チアパス州では連帯経済への模索が起きています。今まで日本ではあまり報じられてこなかった情報だけに貴重です。
こうしたところは日本も教訓とすべきと思います。
同じ轍を踏むのは避けたい
日本の現在の閉塞状況がなぜ起きているか、また、このまま進めばどうなるかということが、ラテンアメリカの例も通じて、本書でよくわかりました。
それにしても、新自由主義改革で失敗した先例がありながら、同じ失敗を繰り返し続けることは愚かです。日本の「アルゼンチン化」は避けねばなりませんが、従来の政策路線を踏襲すれば、より「アルゼンチン化」は進むでしょう。アルゼンチンは通貨危機、日本はデフレ不況の継続と、危機の内容は違うにせよです。
新自由主義を脱し、人間中心の経済政策に転換していくこと。そのためにも対米輸出に依存する構造の転換を進めること(対米輸出に依存する限り、新自由主義的な構造改革競争を強いられることになります)。このことが今、日本にとって、本当に必要だと思います。
(さとうしゅういち)
ラテン・アメリカ諸国では、同じく「失われた10年」と呼ばれた社会経済現象が一足早く1980年代にみられた。南米アルゼンチンの場合は90年代にも「もうひとつの失われた10年」を経験した。前後一連の社会経済病理も含めて、これらもまた日本と同様、市場原理偏重の「構造改革」によってもたらされた。これは批判的なラテン・アメリカ地域研究者の常識である。とすれば、日本はラテン・アメリカの先行経験から反面教師的な教訓を得られるのではないか。またラテン・アメリカの政府、企業、市民社会が「失われた10年」の罠から逃れようと編み出してきた知恵からも、積極的な示唆を読み取れるに違いない。このような直感の下、内橋克人とわれわれラテン・アメリカ地域研究者が共同研究を重ねて編んだのが本シリーズ〈「失われた10年」を超えて――ラテン・アメリカの教訓〉全3巻である。
第1巻『ラテン・アメリカは警告する――「構造改革」日本の未来』は、シリーズ全体の総論となる。そこでの主な論点は、日本の「アルゼンチン化」の危険性、日本とラテン・アメリカにおける財政危機・金融危機・積立年金問題・雇用柔軟化の類似性、それにポスト「構造改革」政策(チリ、ブラジル)や「共生セクター」(中小企業の産業集積、メキシコの先住民協同組合、アルゼンチンやエクアドルの地域通貨など)の成果と限界、さらにはそれらが日本に与える示唆である。
なお、続刊の第2巻と第3巻では、地域社会の再生に果たすべき中小企業と市民社会の役割を考える。
-------------------------------------
シリーズタイトル シリーズ〈「失われた10年」を超えて―ラテン・アメリカの教訓〉第1巻
書籍タイトル ラテン・アメリカは警告する
サブタイトル 「構造改革」日本の未来
著者・編者・訳者 内橋克人・佐野誠編
第1巻執筆者
内橋克人、佐野誠、山崎圭一、宇佐見耕一、安原毅、小倉英敬、吾郷健二、岡本哲史、子安昭子、篠田武司、小池洋一、山本純一、新木秀和
出版社 新評論
発行年月日 2005年4月22日
価格 2730円
ISBNコード ISBN4-7948-0643-4
版型 四六判上製
頁数 355ページ -
-----------------------------------------------------
シリーズ続刊案内
第2巻 田中祐二・小池洋一 編
地域経済はよみがえる
ラテン・アメリカの産業集積にどう学ぶか 来春刊
第3巻 篠田武司・宇佐見耕一 編
不安社会を突破する
ラテン・アメリカにおける地域再生と市民社会 来春刊
*各280頁/予価2625円
----------------------------------------
インターネット新聞JANJANの書評
本書は、シリーズ「失われた10年」を超えて-ラテン・アメリカの教訓」の第1巻です。
1990年代の日本は「失われた10年」といわれる社会経済的困難に直面し、今もそれが続いている感があります。
この「失われた10年」、先輩格がいます。それが、本書で取り上げるラテン・アメリカで、1980年代に「失われた10年」に陥り、またアルゼンチンなどは1990年代にもまた「失われた10年」に陥りました。
日本とラテン・アメリカの「症状」は、必ずしも同一の現象というわけではありません。しかし、一定の共通した側面があります。新自由主義、市場原理を過信した自由化・規制緩和政策であり、それがもたらした一連の負の累積効果です。
日本はラテン・アメリカから、どのような反面教師的な教訓を得ることできるのか?同時にラテン・アメリカの政府、企業、市民社会が「失われた10年」から脱するために編み出してきた政策や戦略とその成果や限界から何を日本がすべきかを読み取る。
そうした問題意識の元、内橋克人さんとラテン・アメリカの専門家が合作で本書を発刊しました。財政危機、社会保障、金融、労働などあらゆる分野でラテン・アメリカのことが、ときに日本のことに言及しつつ分析されています。
新自由主義の仕組み
新自由主義者の唱導者たちは、常にその時代の最強の秩序形成者(権力者)に寄り添い、言動をともにすることによってのみ存在を誇示し、大衆を説得します。権力を攻撃するように見えるときでも、実際は、秩序意向に取り残された脱落者か「おろかな」抵抗者へのものに限られる(自民党「抵抗勢力」が良い例)。真の攻撃目標は、秩序形成者がやむなく与えた妥協の産物にあるというわけです。「妥協の産物」とは、いわゆる福祉国家のことと言って差し支えないでしょう。
共産主義国があった時代、共産化を防ぐためにも、秩序形成者(日本の場合自民党政府)は妥協して、労働に関する権利や社会保障、社会的規制などを与えざるを得なかった。また、大恐慌の教訓から、ビルト・イン・スタビライザー(経済自動安定化)の機能を財政にもたせることにした。最低生活保障制度などです。
これらを、新自由主義者は投げ捨てろというわけです。むろん、投げ捨てた結果は、健全な市場経済の足元を掘り崩すことになります。
ともかく、こうした新自由主義の仕組みを見破るポリシー・インテレクチュアル(政治知性)が求められると、内橋さんは言います。
新自由主義と経済危機
ラテン・アメリカの一部の国では、1970年代に新自由主義改革を行いました。特にアルゼンチンは1990年代にも同じ事を繰り返しました。そして、投機的ブーム、通貨危機、金融危機、対外債務危機、雇用と社会保障の脆弱化を招きました。
アルゼンチンでは、1976年から新自由主義的改革が行われました。1980年から82年にかけ、通貨危機・金融危機に見まわれました。
そして、歴史は繰り返し、1989年から金融と資本の自由化、貿易の自由化が断行され民営化も行われました。そして、事実上のドル本位制が導入され、金融政策も裁量がなくなりました。この改革も2001年、通貨危機が起きて崩壊したのです。
本来あるべき改革が……
一方で、ラテン・アメリカが抱えている本来の構造問題には手はつけられなかった。大土地所有制、不公平税制をはじめ、数々の不平等が挙げられるでしょう。不平等の問題は、むしろ新自由主義で悪化しました。
日本でも、土地無策、含み益経営、不公平税制、ゆるい労働規制、低福祉、大企業と中小企業の二重構造、政官財癒着などの構造問題こそ、手をつけられるべきだった。
ところが、両者ともに、規制緩和など新自由主義的改革こそが改革だという風に「誤認」されていった。そして、ポピュリズム改革(ラテン・アメリカ)や戦後改革(日本)の成果さえ掘り崩していったというわけです。
日本への教訓
今、小泉政府が行っている構造改革は、まさにラテン・アメリカが行った新自由主義改革と、ほぼ同じです。それは、アメリカを頂点としたグローバリゼーションを無条件に受け入れるということです。資本の自由を極大に認める一方で、市民の自由は削り取られるという按配です。
1998年頃に一騒動あったMAI(多国間投資協定)は、まさにそうでしたが、MAI自体はつぶれたが、日本の小泉政府はそれを国内でしていると「総論」の中で内橋さんは言います。
日本でも、「構造改革」がさらに構造問題を生んでいます。例えば、日本では景気回復といわれているが、実際には、家計には及んでいない。規制緩和で賃下げが進んでいることもあります。家計分野から企業への「所得移転」の構造は、改革どころか深刻化しています。
日本の場合、経済全体の貯蓄が大きいために対外債務危機にはなりませんが、その代わり、デフレ不況が深刻化しています。また、不良債権処理を進めたからといって、銀行の貸出しは増えるどころか減り、国債の購入が増えているというのは、日本とラテン・アメリカ共通であることを確認し興味深く思いました。
各章で力の入った分析
各章で各専門家の力の入った分析が見られました。
財政問題については、第1部第1章で山崎圭一さんからの日本・ラテンアメリカ双方への提言が目を引きます。新自由主義が進めてきたのは「小さな政府」(法人税減税)+政府支出カット)です。供給側を刺激するために、法人税を減税するというのが基本的な考え方です。
そうではなく、グローバル化時代に対応した大きな政府、「良い政府」が必要であり、法人への累進課税による増税をという提言も興味深くみました。
緊縮財政(政府支出抑制)路線をとりつつ、庶民増税(法人税減税はそのままに放置)で家計を圧迫し不況を続けているのが今の小泉政府ですから、その正反対の政策を取れば良い、というわけです。
現在、家計は苦しく、大手企業の多くが最高益という時でもあり、なるほど、と思いました。記者も、1990年代末以降の誤りの一つは、政府支出増加よりも(法人税)減税のほうが効果的という議論だと思っています。
現状より政府支出を増やしつつ法人税を増税するというのは、所得を増やすという意味でも財政という点でも、良いと思います。(政府支出の中身を環境・福祉重視にすることは必要でしょうが)。山崎さんによれば、例えば、レーガン減税も結局は成功とは言えなかったそうです。
アジアのラテン・アメリカ化という問題も第5章で取り上げています。アジア通貨危機後、アジアでも、それまでに比較的自立的で経済的平等を進める発展モデルから、アングロサクソン型システムへ、すなわち、外資の支配が強いラテン・アメリカ型に変わってきている。
もちろん日本にも、そういう傾向が及んでいることを示しています。アジアにおいても多国籍企業を先頭にした「新自由主義複合体」が覇権を確立しつつあるということです。そして、社会的不平等が拡大するなどしているというわけです。
大企業の利潤を中心に据えたアングロサクソン・システムではなく、働く人を基盤とした、新しい、自らのシステムを日本は作り出さなければならない、と、この章担当の吾郷健二さんは言います。
一方で、ラテン・アメリカでは新自由主義の弊害を補正したり、これに対抗する動きも出ています。第7章で紹介されたブラジルでの社会自由主義国家の試み。不充分に終わった部分もあるが、教育や保健などの社会指標は改善されました。
チリでも、軍政期の新自由主義的政策を改め、社会支出を増やし、公正と成長を両立させる路線に転換しているそうです。(チリの軍政期の高成長を新自由主義の成果として賞賛する向きもあるが、実際には、貧困層の大幅な拡大など犠牲も大きかったそうです)
また、ラテン・アメリカでは、人間中心主義の経済・社会の建設を求める議論が起きているそうです。メキシコ・チアパス州では連帯経済への模索が起きています。今まで日本ではあまり報じられてこなかった情報だけに貴重です。
こうしたところは日本も教訓とすべきと思います。
同じ轍を踏むのは避けたい
日本の現在の閉塞状況がなぜ起きているか、また、このまま進めばどうなるかということが、ラテンアメリカの例も通じて、本書でよくわかりました。
それにしても、新自由主義改革で失敗した先例がありながら、同じ失敗を繰り返し続けることは愚かです。日本の「アルゼンチン化」は避けねばなりませんが、従来の政策路線を踏襲すれば、より「アルゼンチン化」は進むでしょう。アルゼンチンは通貨危機、日本はデフレ不況の継続と、危機の内容は違うにせよです。
新自由主義を脱し、人間中心の経済政策に転換していくこと。そのためにも対米輸出に依存する構造の転換を進めること(対米輸出に依存する限り、新自由主義的な構造改革競争を強いられることになります)。このことが今、日本にとって、本当に必要だと思います。
(さとうしゅういち)