朝日新聞ブログ「ベルばらkidsぷらざ」で連載中の「世界史レッスン<映画篇>」8回目の今日は、「男を破滅させる運命の女」(⇒ http://bbkids.cocolog-nifty.com/bbkids/2009/01/post-9bc9.html#more スペイン映画『carmenカルメン』について書きました。
個人的にはカルロス・サウラ監督の『ガデスのカルメン』が一番好きかな。『カルメン』をダンス化してゆく過程で、夢と現の境が次第に曖昧になってゆくという作り方がすごくうまかった。煙草工場のダンスシーンの迫力にも圧倒されたし。
オペラでは、これはもう若き日のバルツァ=カルメンと、カレーラス=ホセで決まり! メゾと思えないほど高音の伸びのいいバルツァと、スペイン的暗い情熱のカレーラスは最強コンビと思います。
黒人だけのミュージカル『カルメン・ジョーンズ』も見たけれど、あまりいただけなかった。ビゼーの音楽のいいとこどりというか、何もかも中途半端。。。
むしろ男性版カルメン『カーマン』の方が良かったかな。『カルメン』と『郵便配達は二度ベルを鳴らす』をミックスしたモダン・バレエ?だったけれど、奇妙な面白さがあった。
それにしても、日本が「フジヤマ、ゲイシャ、サムライ」の国と言われれば複雑なのと同じで、スペインも「闘牛、フラメンコ、カルメン」と言われて憮然とするみたい。「カルメンと呼ばないで」というポップスがヒットしたこともある由。
『オペラギャラリー』でも書いたが、『カルメン』の成り立ちはちょっと面白い。原作者はスペイン人ではなくフランス人、カルメンはスペイン人ではなくロマ、ホセはスペイン人ではなくバスク人。
バスクは今もって独立運動で流血の戦いをしているし、ホセの台詞には「スペインが我が国の悪口を言ったら許さない」なんていうのまである。
我々は『カルメン』を「いかにもスペイン的」と思いがちだが、どうもちょっと違うようである。
☆来月刊行予定の『歴史が語る 恋の嵐』(角川文庫)の紹介はこちら⇒ http://www.kadokawa.co.jp/bunko/bk_detail.php?pcd=200809000383
☆☆集英社ブログ<レンザブロー>で連載中の「王妃たちの光と闇」第3回がアップされました⇒ http://renzaburo.jp/
☆最新刊「名画で読み解く ハプスブルク家12の物語」(光文社新書)、5刷中。
2月の神戸での講演会情報です⇒ http://www.kobunsha.com/news/index.html#a000093

☆最新刊「危険な世界史」(角川書店)
毎日新聞での紹介⇒ http://mainichi.jp/enta/book/shinkan/news/20080903ddm015070149000c.html

☆「怖い絵2」、5刷中。
月刊誌『一枚の絵』1月号で、紹介と本のプレゼントを行なっています。ごらんください。

☆『怖い絵』、10刷になりました。ありがとうございます♪ 「ほぼ日」での紹介。再録⇒ http://www.1101.com/editor/2007-11-13.html
個人的にはカルロス・サウラ監督の『ガデスのカルメン』が一番好きかな。『カルメン』をダンス化してゆく過程で、夢と現の境が次第に曖昧になってゆくという作り方がすごくうまかった。煙草工場のダンスシーンの迫力にも圧倒されたし。
オペラでは、これはもう若き日のバルツァ=カルメンと、カレーラス=ホセで決まり! メゾと思えないほど高音の伸びのいいバルツァと、スペイン的暗い情熱のカレーラスは最強コンビと思います。
黒人だけのミュージカル『カルメン・ジョーンズ』も見たけれど、あまりいただけなかった。ビゼーの音楽のいいとこどりというか、何もかも中途半端。。。
むしろ男性版カルメン『カーマン』の方が良かったかな。『カルメン』と『郵便配達は二度ベルを鳴らす』をミックスしたモダン・バレエ?だったけれど、奇妙な面白さがあった。
それにしても、日本が「フジヤマ、ゲイシャ、サムライ」の国と言われれば複雑なのと同じで、スペインも「闘牛、フラメンコ、カルメン」と言われて憮然とするみたい。「カルメンと呼ばないで」というポップスがヒットしたこともある由。
『オペラギャラリー』でも書いたが、『カルメン』の成り立ちはちょっと面白い。原作者はスペイン人ではなくフランス人、カルメンはスペイン人ではなくロマ、ホセはスペイン人ではなくバスク人。
バスクは今もって独立運動で流血の戦いをしているし、ホセの台詞には「スペインが我が国の悪口を言ったら許さない」なんていうのまである。
我々は『カルメン』を「いかにもスペイン的」と思いがちだが、どうもちょっと違うようである。
☆来月刊行予定の『歴史が語る 恋の嵐』(角川文庫)の紹介はこちら⇒ http://www.kadokawa.co.jp/bunko/bk_detail.php?pcd=200809000383
☆☆集英社ブログ<レンザブロー>で連載中の「王妃たちの光と闇」第3回がアップされました⇒ http://renzaburo.jp/
☆最新刊「名画で読み解く ハプスブルク家12の物語」(光文社新書)、5刷中。
2月の神戸での講演会情報です⇒ http://www.kobunsha.com/news/index.html#a000093

☆最新刊「危険な世界史」(角川書店)
毎日新聞での紹介⇒ http://mainichi.jp/enta/book/shinkan/news/20080903ddm015070149000c.html

☆「怖い絵2」、5刷中。
月刊誌『一枚の絵』1月号で、紹介と本のプレゼントを行なっています。ごらんください。

☆『怖い絵』、10刷になりました。ありがとうございます♪ 「ほぼ日」での紹介。再録⇒ http://www.1101.com/editor/2007-11-13.html











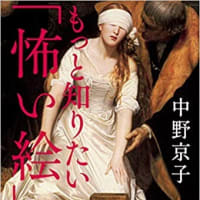






『誰がために鐘は鳴る』の紹介で、ヒロインのマリアを「黒髪に小麦色の肌の情熱的なスペイン娘」と表現していたので、なんとまあヌケヌケとステレオタイプな、と笑えたくらいです(それなのになんでバーグマンが指名されたんだ?見たことないですが)。現代フランス作家による歴史小説『アンジェリク』にも、たいへん強烈なスペイン美女が登場しています。スペインに対するイメージってどこから作られたのでしょうね。少なくともフランス擬古典主義の演劇では、名誉にやたらとこだわる、という描き方が出ていたような気がします。
そうなんですね、知らなかった。スペインは行ったこともないのですが。
先日ペドロ・アルモドバル監督の「トーク・トゥー・ハー」をTVでやっていて見たのですが、この監督やペネロペ・クルスなどは、世界でのそう言うスペインのイメージをうまく使ってる、って言う事でしょうか?
しかし、今は変わって来ているけど、海外でのご年配の方達や、田舎での日本人に対するイメージには本当困ります。
確かにバーグマンはないですよね。
2,3年前見た「サロメ」(オペラじゃなくてダンス映画)では、ヨカナーンが黒人でした。なのに台詞は、「ヨカナーン、おまえの肌はなんて白いの」!
あんまりではないでしょうか。。。
ベベさん
日本女性は(というかアジア女性は)ひたすら男性に尽くす蝶々夫人タイプと思われて人気がある、というのを読んだことがあります。やれやれですね!
もうすぐ里帰りしますので「怖い絵」も購入に走ります~。楽しみです。外国にいると日本語活字にとてつもなく餓えるのです。こうしてブログをお書きになってることも、とっても嬉しくて楽しみが増えました。
リンクを貼らせていただいても構いませんか?
これからのご活躍も期待しております。
拙著の感想もありがとうございました。リンク、お貼りください。わたしも訪問させてくださいね!
帰国後、早速苦手なハプスブルク家まつわるあたりの世界史の勉強に、と「ハプスブルク家 12の物語」も読ませて頂き、わたしのブログに紹介させて頂きました。
スペインでビゼーのカルメンをホテルの部屋でちらっと弾いてみましたが、あれはやはりフランスものですね、はっきりそう感じました。
わたしはシチェドリンのアレンジしたバレエ用の打楽器と弦楽器バージョンのカルメンが、ドラマティックで好きです。
カルメンジョーンズは、確かにわたし的にもダメ(笑)どうして原作じゃいけないのか、意味がわかっていないからかもしれませんが…。
カルメンという名前は、日本の花子さんみたいなもので、スペインではとても沢山ある代表的な名前なのだとか。
今は家父長制時代から変化しつつ、女の子は結婚したがらず、子供も平均1.1人とか…。どこかの国の現状に都市部の悩みはよく似ていますよね。もっとも、バスク問題やカタルーニャの言語問題ほどではありませんが、北から南まで距離のある国は、民族の問題も抱えてしまいますね、宗教的にも長い歴史が複雑な国ですし…日本人のようなキャラでないと、沖縄やアイヌの問題も太平洋戦争後、ああなっていたかもしれないですね。
スペインは色々な意味で面白い国です。
ダンス映画なら、カルロス・サウラのカルメンも見てみたいな、と思っています。イベリアが凄いというので先日買ったばかりですが。。。(笑)
長々と失礼致しました。これからも楽しみにしています。
わたしもリンクを晴らせて頂いて宜しいでしょうか?
ちょうどスペイン旅行前だったのですね。お役に立って嬉しいです。現地ではきっとハプスブルクの残光をそこここに感じてこられたことでしょう。それにしても出産率がいつの間にかそんなに下がっていたとは知らず、びっくりです。