
「統合化された知的資産マネジメント」の訳者はしがきに、こういうくだりがあります。
「知的財産部門が、調達、製造、流通、販売、マーケッティングなどの部門が構成するビジネスラインに関与しづらいことである。顧客からの要求が知的財産部門に及ばないがゆえに、他部門との連携に切迫感がもてないことも連携の阻害要因となっている。」
知的財産に関するマネジメントがうまく機能しにくい理由の1つとして挙げられていることですが、これは全くそのとおりだと思います。評論家であれば分析して嘆いていればよいかもしれませんが、実務家、プロフェッショナルとしては、やはりこの部分の解決策を考え、行動していかなければならない。上記の文章の中に、そのためのヒントが何となく隠されているような気がしてきました。
顧客からの要求を含めた外的な要求から生じる業務というものは、企業の中でも優先度が高くなるのが通常です。品質向上、コストダウンといった顧客からの要求はもとより、近年の企業経営における切迫したテーマを考えても、内部統制強化のような法的な規制への対応、買収防衛策のような市場でのプレッシャーに対する対応など、優先度の高いテーマの殆どは外的な要求から生じています。これに対して知財業務は侵害訴訟に直面したような場合を除き、基本的には企業の内的な要求によって行われるものです。個人レベルで考えてみても、自分の行動のほとんどは外的な要求によって規定されていて、内的な要求から何かを継続するということは容易ではありません。内的な要請によって自己を変化させるためには、そこには意志の力、その意志を支える哲学が必要です。企業レベルでも同じで、真に意味のある知財業務を根付かせるために最も必要なものは、知識や情報ではなく、おそらく「知財のポリシー」「知財の哲学」みたいなものなのだろうと思います。
昨今の「知財人材」に関する議論の中ではあまり語られていないことだと思いますが、哲学を考え、語る力みたいなものが、実はとても重要になってくるのではないでしょうか。「知的財産とは何なのか?」、「知財業務は本当に必要なのか?」、「必要であるすればそれは何故か?」、「それをどのように表現したら伝えられるのか?」、こうしたテーマから今年も考えていきたいと思います。
「知的財産部門が、調達、製造、流通、販売、マーケッティングなどの部門が構成するビジネスラインに関与しづらいことである。顧客からの要求が知的財産部門に及ばないがゆえに、他部門との連携に切迫感がもてないことも連携の阻害要因となっている。」
知的財産に関するマネジメントがうまく機能しにくい理由の1つとして挙げられていることですが、これは全くそのとおりだと思います。評論家であれば分析して嘆いていればよいかもしれませんが、実務家、プロフェッショナルとしては、やはりこの部分の解決策を考え、行動していかなければならない。上記の文章の中に、そのためのヒントが何となく隠されているような気がしてきました。
顧客からの要求を含めた外的な要求から生じる業務というものは、企業の中でも優先度が高くなるのが通常です。品質向上、コストダウンといった顧客からの要求はもとより、近年の企業経営における切迫したテーマを考えても、内部統制強化のような法的な規制への対応、買収防衛策のような市場でのプレッシャーに対する対応など、優先度の高いテーマの殆どは外的な要求から生じています。これに対して知財業務は侵害訴訟に直面したような場合を除き、基本的には企業の内的な要求によって行われるものです。個人レベルで考えてみても、自分の行動のほとんどは外的な要求によって規定されていて、内的な要求から何かを継続するということは容易ではありません。内的な要請によって自己を変化させるためには、そこには意志の力、その意志を支える哲学が必要です。企業レベルでも同じで、真に意味のある知財業務を根付かせるために最も必要なものは、知識や情報ではなく、おそらく「知財のポリシー」「知財の哲学」みたいなものなのだろうと思います。
昨今の「知財人材」に関する議論の中ではあまり語られていないことだと思いますが、哲学を考え、語る力みたいなものが、実はとても重要になってくるのではないでしょうか。「知的財産とは何なのか?」、「知財業務は本当に必要なのか?」、「必要であるすればそれは何故か?」、「それをどのように表現したら伝えられるのか?」、こうしたテーマから今年も考えていきたいと思います。










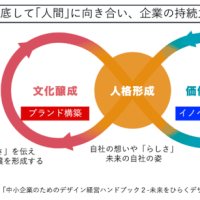
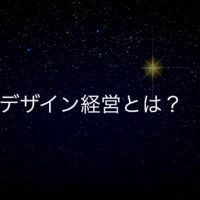



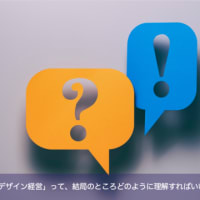
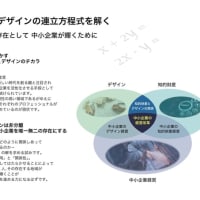


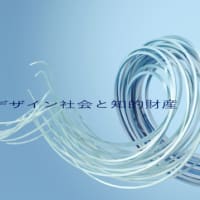
上の訳者はしがきの「顧客からの要求が知的財産部門に及ばないがゆえに」のところは、まさにその通りであり、私が知財部を経験した後に営業に出たときに気付いた点でした。
知財部や特許事務所にいると、技術ニーズや商品ニーズは、開発者等から知るだけで、顧客の「生」の要求を知ることはできません。
このため、開発者が「技術的に進歩性が高い」と言うものが、企業にとっても重要なものであり、こうしたものを中心に出願すれば良いという、誤解を招くことになってしまいます。
知財担当者としては、常に、「この技術が自社製品の商品力を上げるのに有効であるか否か」を「客観的」に検討して、権利化の判断をすべきだと思います。
新年最初のコメント、ありがとうございます。
「顧客の視点を反映する」という点はまさにそのとおりで、私もこれまで考えてきたところなのですが、結局のところ難しいのはそれをどうやって実践するかです。次の段階で考えなければならないのは、「そういう方向性で考えられるように変革していくためにはどうすればよいのか」という問題で、そのためには理屈や知識だけではなかなか難しいものがあり、人や組織がそういう方向に動くような内的な力を生む哲学みたいなものが必要なのではないか、とこのくだりから感じました。