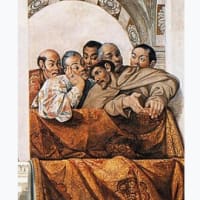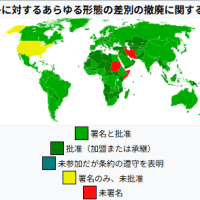2010年7月20日(火) スカイツリー君は何処から見える?
先日、7月14日(水)の読売新聞夕刊に、建設中のスカイツリーが、着工から2年を迎えたのを機に、現在、どの範囲から見えるか、の記事が掲載された。この時点の高さは、398mである。
記事の中で、「東京スカイツリーここから見えるよMAP」が紹介されており、早速、覗いてみた。自分の町や、登った山から見えた、と言う記事が、写真つきで載っている。現在は、700枚を越える写真が、投稿されているようだ。
「どの範囲から見えるか、記録を募集したら面白いだろうなー」、などと思っていただけに、ぴったりの企画である。
首都圏からは、良く見え、足立区内の我が家からも、直線距離にして、9km程度の距離にあり、毎日、成長振りを楽しんでいるところである。
スカイツリーに関しては、愛着を込めて、これまで、以下のように、当ブログで取り上げてきている。
2010/4/02 スカイツリー君の成長
2010/4/14 スカイツリー君の横顔
2010/5/14 スカイツリー君を見上げる
新聞記事に触発されて、理論的には、どのくらいの範囲から見えるのかな? という、数学的な興味が湧いてきた。ネットで得られる情報などを、色々参考にしながら、今回、検討してみることとした。
距離計算のモデルを考える時、地球が丸い(球体と仮定)ことを考慮しなければならない。海などに行くと、水平線(地平線)の彼方から、船の帆柱が、少しづつ現れてくる光景をよく見るが、これは、地球が丸いことが実感できる体験である。
半径Rの地球上で、H1の高さの視点P1から、高さH2の目標物P2を遠望する場合の距離限界は、地平線を超えて見通せる限界点から、求めることができる。視点P1と目標物P2を結んだ直線(地平線)が地表にGで接する状態が、距離限界になる。この時、視点P1と接点Gと地球の中心Oとは、直角三角形を構成すると考えられる。同様に、接点Gと、目標物P2と地球の中心Oも、直角三角形を構成すると考えられる。

先ず、H1の高さの視点から、地平線の接点Gまでの距離X1は、地球の半径をRとすると、ピタゴラスの定理から
X1=√((H1+R)**2-R**2) (**2は、2乗の表記)
=√(H1**2+2H1R)
ここで、H1=0.0017km(身長の高さ)、R=6370kmとすると
X1=√(0.00000289+21.66)≒√21.66=4.65km
となる。
これから、海などで、海岸から眺める地平線の距離は、意外に近いことが分かる。
次に、地平線の接点G(視点の高さは0)から、H2の高さの建造物を、見た時の距離を計算する(これは、H2の高さの視点から、反対方向に、地平線の接点Gまでの、距離を求めるのと同じである)。 接点Gから目標物までの距離X2は、同じように、ピタゴラスの定理から、
X2=√((H2+R)**2-R**2)
=√(H2**2+2H2R)
ここで、H2=0.398km、R=6370kmとすると
X2=√(0.158404+5070.52)=√5070.68
=71.2km
となる。
ここで、H2=0.634km(スカイツリーの完成時の高さ)としてみると
X2=√(0.402+8077.16)=√8077.56
=89.88km
となり、見える範囲が、現在よりも、かなり広がることが分かる。
従って、現在のスカイツリーを、身長の高さの視点から、地平線を通して遠望できる限界直線距離Xは、以下のようになる。
X=X1+X2=4.65+71.2=75.85km
これは、北は、栃木県南部、西は、神奈川県西部くらいになろうか。 完成時は、これより、更に、20km近く広がることになる。
視点1が、身長の高さでなく、仮に、1000m近い山頂とすると、H1=1.0kmを代入すれば
X1=√(1+12740)=112.88kmになり
全体のXは
X=X1+X2=112.4+71.2=183.6km
と、かなり広がることが分かる。北は、福島県南部辺りの1000m級の山頂から、西は、南アルプス辺りの1000m級の山頂から、現在でも、見える計算になる。
ただし、これらの計算は、途中に山岳や建物や、雲等の障害物が、一切無い場合の計算である。
このモデルで、H2=0の時が、高さH1の視点から見渡せる地平線までの距離X1になる。スカイツリーで言えば、スカイツリーの展望台に登ってH1の視点から見渡せる地平線までの距離範囲となるので、展望台の高さを、0.450km(第二展望台)とすると
X1=√(0.2025+5733)=√5733.2=75.72km
となり、首都圏中心部が展望できるが、群馬や栃木は、入らないかも知れない。
ここまでのモデルでは、視点P1と目標物P2間の直線距離を求めたが、地表面での距離を求めるには、地球円周の弧の長さを求める、逆三角関数の計算が必要で、今回は省略する。
今回の話題に関連して思い浮かぶのは、日本一の名山、富士山である。 富士山といえば、誰しも一生に一度は、登ってみたい山で、360度のパノラマが楽しめる、天然の展望台だ。幸い、自分は以前、家人と、登ったことがある。
この名峰富士が、どこから見えるか、と言うことで調べたら、膨大な情報があるようだ。
距離的には見える範囲なのだが、途中の山でマスクされて、見えないところも多いようだ。パソコン用の3D立体地図ソフト、カシミールなどで、障害物の有無を検証したデータもあるようだ。富士山の写真撮影に成功した、最も遠い地点は、和歌山県那智勝浦町の妙法山(距離 322km)で、次の地点は、福島県二本松市の日山(距離 299km)という。
先のモデルで、視点P1を1000m級の山頂(H1=1.0km)とし、遠望する目標P2を富士山(H2=3.776km)とすると、
X1=√(1+12740)=√12741=112.88km
X2=√(14.26+48106.24)=√48120.5
=219.36km
直線距離X=X1+X2=332.24km
となる。 この距離は、日本地図で言えば、北は宮城県北部、西は、志摩半島あたりになろうか。
日本には、特に、関東を中心に、富士見○○といった地名が、あちこちにある。以前、尾瀬に行った時に、沼田から入って富士見峠を上った記憶があるが、あそこからも、勿論、富士山は見えたのであろう。
現在、国内で、富士山が見える最遠の地となっているのは、上述の妙法山のようで、客観的に記録されたのが、1997年と言うから、意外に最近なのである。
古来から、那智勝浦の熊野大社への熊野詣の際に、熊野古道から富士山が見えた、という言い伝えがあったと言う。
先日、7月14日(水)の読売新聞夕刊に、建設中のスカイツリーが、着工から2年を迎えたのを機に、現在、どの範囲から見えるか、の記事が掲載された。この時点の高さは、398mである。
記事の中で、「東京スカイツリーここから見えるよMAP」が紹介されており、早速、覗いてみた。自分の町や、登った山から見えた、と言う記事が、写真つきで載っている。現在は、700枚を越える写真が、投稿されているようだ。
「どの範囲から見えるか、記録を募集したら面白いだろうなー」、などと思っていただけに、ぴったりの企画である。
首都圏からは、良く見え、足立区内の我が家からも、直線距離にして、9km程度の距離にあり、毎日、成長振りを楽しんでいるところである。
スカイツリーに関しては、愛着を込めて、これまで、以下のように、当ブログで取り上げてきている。
2010/4/02 スカイツリー君の成長
2010/4/14 スカイツリー君の横顔
2010/5/14 スカイツリー君を見上げる
新聞記事に触発されて、理論的には、どのくらいの範囲から見えるのかな? という、数学的な興味が湧いてきた。ネットで得られる情報などを、色々参考にしながら、今回、検討してみることとした。
距離計算のモデルを考える時、地球が丸い(球体と仮定)ことを考慮しなければならない。海などに行くと、水平線(地平線)の彼方から、船の帆柱が、少しづつ現れてくる光景をよく見るが、これは、地球が丸いことが実感できる体験である。
半径Rの地球上で、H1の高さの視点P1から、高さH2の目標物P2を遠望する場合の距離限界は、地平線を超えて見通せる限界点から、求めることができる。視点P1と目標物P2を結んだ直線(地平線)が地表にGで接する状態が、距離限界になる。この時、視点P1と接点Gと地球の中心Oとは、直角三角形を構成すると考えられる。同様に、接点Gと、目標物P2と地球の中心Oも、直角三角形を構成すると考えられる。

先ず、H1の高さの視点から、地平線の接点Gまでの距離X1は、地球の半径をRとすると、ピタゴラスの定理から
X1=√((H1+R)**2-R**2) (**2は、2乗の表記)
=√(H1**2+2H1R)
ここで、H1=0.0017km(身長の高さ)、R=6370kmとすると
X1=√(0.00000289+21.66)≒√21.66=4.65km
となる。
これから、海などで、海岸から眺める地平線の距離は、意外に近いことが分かる。
次に、地平線の接点G(視点の高さは0)から、H2の高さの建造物を、見た時の距離を計算する(これは、H2の高さの視点から、反対方向に、地平線の接点Gまでの、距離を求めるのと同じである)。 接点Gから目標物までの距離X2は、同じように、ピタゴラスの定理から、
X2=√((H2+R)**2-R**2)
=√(H2**2+2H2R)
ここで、H2=0.398km、R=6370kmとすると
X2=√(0.158404+5070.52)=√5070.68
=71.2km
となる。
ここで、H2=0.634km(スカイツリーの完成時の高さ)としてみると
X2=√(0.402+8077.16)=√8077.56
=89.88km
となり、見える範囲が、現在よりも、かなり広がることが分かる。
従って、現在のスカイツリーを、身長の高さの視点から、地平線を通して遠望できる限界直線距離Xは、以下のようになる。
X=X1+X2=4.65+71.2=75.85km
これは、北は、栃木県南部、西は、神奈川県西部くらいになろうか。 完成時は、これより、更に、20km近く広がることになる。
視点1が、身長の高さでなく、仮に、1000m近い山頂とすると、H1=1.0kmを代入すれば
X1=√(1+12740)=112.88kmになり
全体のXは
X=X1+X2=112.4+71.2=183.6km
と、かなり広がることが分かる。北は、福島県南部辺りの1000m級の山頂から、西は、南アルプス辺りの1000m級の山頂から、現在でも、見える計算になる。
ただし、これらの計算は、途中に山岳や建物や、雲等の障害物が、一切無い場合の計算である。
このモデルで、H2=0の時が、高さH1の視点から見渡せる地平線までの距離X1になる。スカイツリーで言えば、スカイツリーの展望台に登ってH1の視点から見渡せる地平線までの距離範囲となるので、展望台の高さを、0.450km(第二展望台)とすると
X1=√(0.2025+5733)=√5733.2=75.72km
となり、首都圏中心部が展望できるが、群馬や栃木は、入らないかも知れない。
ここまでのモデルでは、視点P1と目標物P2間の直線距離を求めたが、地表面での距離を求めるには、地球円周の弧の長さを求める、逆三角関数の計算が必要で、今回は省略する。
今回の話題に関連して思い浮かぶのは、日本一の名山、富士山である。 富士山といえば、誰しも一生に一度は、登ってみたい山で、360度のパノラマが楽しめる、天然の展望台だ。幸い、自分は以前、家人と、登ったことがある。
この名峰富士が、どこから見えるか、と言うことで調べたら、膨大な情報があるようだ。
距離的には見える範囲なのだが、途中の山でマスクされて、見えないところも多いようだ。パソコン用の3D立体地図ソフト、カシミールなどで、障害物の有無を検証したデータもあるようだ。富士山の写真撮影に成功した、最も遠い地点は、和歌山県那智勝浦町の妙法山(距離 322km)で、次の地点は、福島県二本松市の日山(距離 299km)という。
先のモデルで、視点P1を1000m級の山頂(H1=1.0km)とし、遠望する目標P2を富士山(H2=3.776km)とすると、
X1=√(1+12740)=√12741=112.88km
X2=√(14.26+48106.24)=√48120.5
=219.36km
直線距離X=X1+X2=332.24km
となる。 この距離は、日本地図で言えば、北は宮城県北部、西は、志摩半島あたりになろうか。
日本には、特に、関東を中心に、富士見○○といった地名が、あちこちにある。以前、尾瀬に行った時に、沼田から入って富士見峠を上った記憶があるが、あそこからも、勿論、富士山は見えたのであろう。
現在、国内で、富士山が見える最遠の地となっているのは、上述の妙法山のようで、客観的に記録されたのが、1997年と言うから、意外に最近なのである。
古来から、那智勝浦の熊野大社への熊野詣の際に、熊野古道から富士山が見えた、という言い伝えがあったと言う。