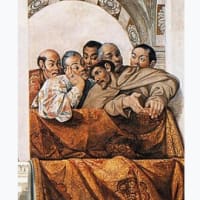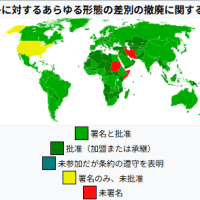2011年2月11日(金) 豆まき
立春も過ぎて、いよいよ春である。 今朝は、久々の雨模様で、だんだん、雪混じりになって来た。この冬は、異常乾燥が長く続いただけに、ありがたい雨である。受験生の事もあるが、どうせなら、一面の銀世界を、期待したいところであるがーー。
今年は、先週の3日が節分で、節分と言えば、豆まきが、恒例の年中行事である。 我が家では、夜は、出かける都合があったので、珍しく、日中に、福は内、とやった。 今回は、趣向を変え、通常の、炒り豆に加えて、初めて、柊の小枝と、目刺しも、近くのスーパーで調達した。
 目刺し 炒り豆 柊の小枝
目刺し 炒り豆 柊の小枝
柊は出入口に下げたが、柊の葉には、堅い刺があり、触れるとチクチク痛いので、鬼サンが近寄らないという。 暮れに、知人から、花の咲いた柊の枝を頂いたりしたので、親しみを込めて飾った。
イワシの頭の代わりに手に入れた目刺しを、レンジで焼いて、家の中に煙を立てたので、鬼達は、臭くって逃げ出して行ったようである。
昨年の豆まきの時は、鬼の事などについて、当ブログの、以下の記事で触れている。
節分の豆まき (2010/2/4)
先週、立春の4日から5日にかけて、知人達と千葉県の南房総に旅行した。4日に、昼食に立ち寄った、鰻屋の入り口の両脇には、前夜の節分の名残で、柊の枝に、イワシの頭を刺したものが飾ってある。 中に入ると、大きな一升枡に入った、炒り豆をご馳走になった。
同行した仲間の話によると、関西では、節分には、恵方巻(えほうまき)という、太巻きを食べる習慣も、あるようだ。 食べる時の作法があり、今年は、南南東の方向を向いて、心に願い事を唱えながら、黙って頬張るのだそうである。 最近では、関東でも、時期になると、少しでも売上増にしようとの営業努力か、恵方巻が、目に付くようになっている。
現在は、豆まきは、立春の前日の、節分に行うのだが、以前の旧暦(太陰太陽暦)では、追儺の行事として、大晦日に行ったようである。 改めて、高島暦を見ると、今年は、節分の日が、旧暦の元旦になっていて、これだと、豆まきの日が、一日ずれることとなる。
24節気の中で、節分は、四季の終わりごとに、本来、年4回あるのだが、農作業等で最も大事な立春の、前日だけが、節分として残っている。言うまでも無く、此方の暦は、太陽の運行に基づいた暦で、季節とも一致しており、年による変動は殆どない。
一方、旧暦は、月の運行を基準にしたものなので、年によって、暦と季節との、ずれが大きく、それを調整するため、閏月を入れる、などが行われている。
24節気と旧暦は、本来、別物なのである。
自分が幼かった終戦前の田舎には、かなり、旧暦の習慣が残っていた。 でも、豆まきは何時やったのか、大晦日と節分とは、どんな関係にあったのか、等、 余り詮索するのは控えよう。 自然と人事との狭間で、色んな暦を編み出して来た、先人達のご労苦に、思いを馳せたいものである。
立春も過ぎて、いよいよ春である。 今朝は、久々の雨模様で、だんだん、雪混じりになって来た。この冬は、異常乾燥が長く続いただけに、ありがたい雨である。受験生の事もあるが、どうせなら、一面の銀世界を、期待したいところであるがーー。
今年は、先週の3日が節分で、節分と言えば、豆まきが、恒例の年中行事である。 我が家では、夜は、出かける都合があったので、珍しく、日中に、福は内、とやった。 今回は、趣向を変え、通常の、炒り豆に加えて、初めて、柊の小枝と、目刺しも、近くのスーパーで調達した。
 目刺し 炒り豆 柊の小枝
目刺し 炒り豆 柊の小枝柊は出入口に下げたが、柊の葉には、堅い刺があり、触れるとチクチク痛いので、鬼サンが近寄らないという。 暮れに、知人から、花の咲いた柊の枝を頂いたりしたので、親しみを込めて飾った。
イワシの頭の代わりに手に入れた目刺しを、レンジで焼いて、家の中に煙を立てたので、鬼達は、臭くって逃げ出して行ったようである。
昨年の豆まきの時は、鬼の事などについて、当ブログの、以下の記事で触れている。
節分の豆まき (2010/2/4)
先週、立春の4日から5日にかけて、知人達と千葉県の南房総に旅行した。4日に、昼食に立ち寄った、鰻屋の入り口の両脇には、前夜の節分の名残で、柊の枝に、イワシの頭を刺したものが飾ってある。 中に入ると、大きな一升枡に入った、炒り豆をご馳走になった。
同行した仲間の話によると、関西では、節分には、恵方巻(えほうまき)という、太巻きを食べる習慣も、あるようだ。 食べる時の作法があり、今年は、南南東の方向を向いて、心に願い事を唱えながら、黙って頬張るのだそうである。 最近では、関東でも、時期になると、少しでも売上増にしようとの営業努力か、恵方巻が、目に付くようになっている。
現在は、豆まきは、立春の前日の、節分に行うのだが、以前の旧暦(太陰太陽暦)では、追儺の行事として、大晦日に行ったようである。 改めて、高島暦を見ると、今年は、節分の日が、旧暦の元旦になっていて、これだと、豆まきの日が、一日ずれることとなる。
24節気の中で、節分は、四季の終わりごとに、本来、年4回あるのだが、農作業等で最も大事な立春の、前日だけが、節分として残っている。言うまでも無く、此方の暦は、太陽の運行に基づいた暦で、季節とも一致しており、年による変動は殆どない。
一方、旧暦は、月の運行を基準にしたものなので、年によって、暦と季節との、ずれが大きく、それを調整するため、閏月を入れる、などが行われている。
24節気と旧暦は、本来、別物なのである。
自分が幼かった終戦前の田舎には、かなり、旧暦の習慣が残っていた。 でも、豆まきは何時やったのか、大晦日と節分とは、どんな関係にあったのか、等、 余り詮索するのは控えよう。 自然と人事との狭間で、色んな暦を編み出して来た、先人達のご労苦に、思いを馳せたいものである。