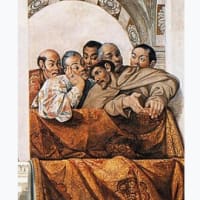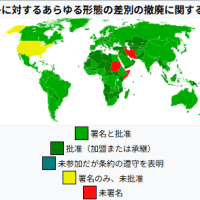2011年1月15日(土) 新年の歌
正月も、早いもので半月になる。 この正月も、色んな年賀状を頂いたが、其の中に、自作の短歌を認められたものがある。 家人の知人が詠んだ、以下の歌である。
万葉の 花の咲けりと 訪めゆけば
武蔵の国の 寺庭に咲く
万葉集の歌に詠まれている草花には、萩や梅など、150種以上もある、といわれるが、これらを楽しめる、万葉植物園は、全国各地にある。 この歌も、作者が、武蔵野のとある寺の、境内にある植物園を、訪れた時につくられたもののようで、草花を訪ね求める、素直ないい歌である。
この歌を見た時、 訪めゆけば という表現が、少し、気になった。 とめゆけば と読んで、訪ねていく、訪問する、という意味なのは、大方、推測できるのだが、言葉としては、どうなのだろうか。
国語辞典、漢和辞典の他に、大分昔に、使ったことのある、古語辞典も引っ張り出して、あれこれ、調べてみた。歌の中の動詞の形としては、訪めゆく だが、このような言葉は、口語にも、古語にも見当たらなかった。
一方、古語辞典によれば、漢字は異なる、尋(と)めゆく という言葉があるようだ。 たずねていく と言う、類似の意味だが、この言葉を使うなら、尋めゆけば となろうか。
訪う という言葉を使って、訪いゆけば とすれば、より、自然な言葉になるのだが、咲けり という語感と合わず、インパクトが少なくなってしまう。
折角の歌に、注文を付ける積りは、さらさらないのだが、歌の世界では、尋も、訪も、余り区別せずに、使われるのかもしれない。
昨日、1月14日は、皇居 松の間で、歌会始が開催され、たまたま、TVの中継を見させて貰った。今年のお題は「葉」で、一般応募から選ばれた歌や、召人の歌などが、披露された後、皇族の歌が、朗々と披露された。 皇后につづいて、天皇の歌が、最後に披露されたが、お二方の歌で、改めて知らされたことがある。
皇后の歌
おほかたの 枯葉は枝に のこりつつ
今日まんさくの 花一つ咲く
まんさくは、早春に、葉に先だって、赤黄色の糸状の花を、賑やかに付けるもので、好きな花木の一つである。 昨年の枯葉が、まだ、多く残っているなかで、たった一輪、咲き初めた、という、皇后の、嬉しい感慨を歌われたもので、場景の描写と、観察の鋭さが、素晴らしい。
自分が改めて気付いたのは、まんさくに、葉がある、ということだ。 まんさくの、花は、これまで、梅園等で、何度も見たことがあるのだが、花の後に、葉が出て茂り、実も付けるというのは、残念ながら、実感として無かったのである。樹木図鑑を見てみると、当然の事だが、花だけでなく、葉も(名前にも、マルバマンサクなどと、葉の形を言っているものもある!)、実も、載っている。
天皇の歌
五十年(いそとせ)の 祝いの年に 共に蒔きし
白樺の葉に 暑き日の射す
成婚50年の記念の年に、皇居内の白樺の木に実った種を採り、皇后と共に蒔かれた。その種から育った若木が、夏の暑い日差しを浴びながら、元気に育っている、という場景を、喜ばれた歌であろう。 白樺は、美智子皇后の、お印になっているようだ。
ここで、自分が改めて知ったのは、山では良く見かける白樺に、実が付く、ということである。樹木図鑑によれば、房状の長い花が咲き、小さな実が付くようだ。その様子を良く観察され、実を収穫され、蒔いて実生からの成長を楽しまれているという、天皇の観察力に、敬服した次第である。
草花は、どうしても、花の咲く時や、美しい実のなる時など、メインの時期に注目が集まるものだが、四季を通じた、目立たない佇まいにも、注目していきたいものである。
正月も、早いもので半月になる。 この正月も、色んな年賀状を頂いたが、其の中に、自作の短歌を認められたものがある。 家人の知人が詠んだ、以下の歌である。
万葉の 花の咲けりと 訪めゆけば
武蔵の国の 寺庭に咲く
万葉集の歌に詠まれている草花には、萩や梅など、150種以上もある、といわれるが、これらを楽しめる、万葉植物園は、全国各地にある。 この歌も、作者が、武蔵野のとある寺の、境内にある植物園を、訪れた時につくられたもののようで、草花を訪ね求める、素直ないい歌である。
この歌を見た時、 訪めゆけば という表現が、少し、気になった。 とめゆけば と読んで、訪ねていく、訪問する、という意味なのは、大方、推測できるのだが、言葉としては、どうなのだろうか。
国語辞典、漢和辞典の他に、大分昔に、使ったことのある、古語辞典も引っ張り出して、あれこれ、調べてみた。歌の中の動詞の形としては、訪めゆく だが、このような言葉は、口語にも、古語にも見当たらなかった。
一方、古語辞典によれば、漢字は異なる、尋(と)めゆく という言葉があるようだ。 たずねていく と言う、類似の意味だが、この言葉を使うなら、尋めゆけば となろうか。
訪う という言葉を使って、訪いゆけば とすれば、より、自然な言葉になるのだが、咲けり という語感と合わず、インパクトが少なくなってしまう。
折角の歌に、注文を付ける積りは、さらさらないのだが、歌の世界では、尋も、訪も、余り区別せずに、使われるのかもしれない。
昨日、1月14日は、皇居 松の間で、歌会始が開催され、たまたま、TVの中継を見させて貰った。今年のお題は「葉」で、一般応募から選ばれた歌や、召人の歌などが、披露された後、皇族の歌が、朗々と披露された。 皇后につづいて、天皇の歌が、最後に披露されたが、お二方の歌で、改めて知らされたことがある。
皇后の歌
おほかたの 枯葉は枝に のこりつつ
今日まんさくの 花一つ咲く
まんさくは、早春に、葉に先だって、赤黄色の糸状の花を、賑やかに付けるもので、好きな花木の一つである。 昨年の枯葉が、まだ、多く残っているなかで、たった一輪、咲き初めた、という、皇后の、嬉しい感慨を歌われたもので、場景の描写と、観察の鋭さが、素晴らしい。
自分が改めて気付いたのは、まんさくに、葉がある、ということだ。 まんさくの、花は、これまで、梅園等で、何度も見たことがあるのだが、花の後に、葉が出て茂り、実も付けるというのは、残念ながら、実感として無かったのである。樹木図鑑を見てみると、当然の事だが、花だけでなく、葉も(名前にも、マルバマンサクなどと、葉の形を言っているものもある!)、実も、載っている。
天皇の歌
五十年(いそとせ)の 祝いの年に 共に蒔きし
白樺の葉に 暑き日の射す
成婚50年の記念の年に、皇居内の白樺の木に実った種を採り、皇后と共に蒔かれた。その種から育った若木が、夏の暑い日差しを浴びながら、元気に育っている、という場景を、喜ばれた歌であろう。 白樺は、美智子皇后の、お印になっているようだ。
ここで、自分が改めて知ったのは、山では良く見かける白樺に、実が付く、ということである。樹木図鑑によれば、房状の長い花が咲き、小さな実が付くようだ。その様子を良く観察され、実を収穫され、蒔いて実生からの成長を楽しまれているという、天皇の観察力に、敬服した次第である。
草花は、どうしても、花の咲く時や、美しい実のなる時など、メインの時期に注目が集まるものだが、四季を通じた、目立たない佇まいにも、注目していきたいものである。