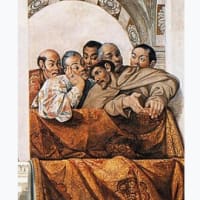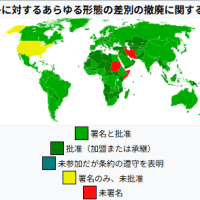2012年4月11日(水) 原発再稼働の技術的知見
原発再稼働の判断基準を纏めるように、との総理の指示が出たら、2~3日で、如何にも、泥縄式に、あっという間に、判断基準が纏まったように見えた。今頃になって何をしているのか! どうしてもう少し前から準備しなかったのか、と言うのが率直な感想だったが、少し調べて見ると、可なりの蓄積があったようだ。
この3月に、安全保安院から出された、下記の資料で、今後の規制に反映すべきと考えられる事項として、30項目に上る、原発の安全対策が整理されている。
「東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」
平成24年3月 原子力安全・保安院
保安院が示していたこの安全対策は、本来は、今後の原発に関するもので、必ずしも、停止中の原発の再稼働のためのものではないのだが、今回は、それを準用した、と言う事ができよう。
当初の報道では、30項目の安全対策の中から、第一段階として、13項目(後に16項目)を当面の緊急安全対策とした、とあったが、色々探したが、残念ながら、大元の情報が手に入らなかったのだ。が、TVの画面で、たまたま見た、“技術的知見”を含む資料名から検索したら、保安院のサイトで、やっと、上記の報告書を見付けることができた、ということだ。
この報告書は、この2月に案が出て、意見聴取を行った上で、3月に出来上がったようで、今回の原発事故に対する、現時点での技術的知見を纏めた、大変な労作である。
決して泥縄ではない、しっかりした情報なのだが、国民への周知等で、工夫が足りなかったために、社会に無用の不安を与えてしまい、大変、損をしている、と言える。
上記の報告にある、安全対策30項目を、2段階に分け、緊急性の高い16項目を、当面の第一段階で確認することとしたようだ。 これら、16項目については、先の当ブログ記事
原発再稼働の判断基準 (2012/4/09)
で、具体的に触れている。
残る項目は、第二段階として、中長期的な課題、と言うことであろう。
報告書にある、30項目は、少し長くなるが、以下である。
[外部電源対策]
1 外部電源系統の信頼性の向上
2 変電所設備の耐震性向上
3 開閉所設備の耐震性向上
4 外部電源設備の迅速な復旧
[所内電気設備対策]
5 所内電気設備の位置的な分散
6 浸水対策の強化 ○
7 非常用交流電源の多重性と多様性の強化 ○
8 非常用直流電源の強化
9 個別線用電源の設置
10外部からの給電の容易化
11電気設備関係予備品の備蓄
[冷却・注水設備対策]
12事故時の判断能力の向上 ○
13冷却設備の耐浸水性確保・位置的分散 ○
14事故後の最終ヒートシンクの強化
15隔離弁・SRVの動作確実性の向上
16代替注水機能の強化 ○
17使用済燃料プールの冷却・給水機能の信頼性向上○
[格納容器破損・水素爆発対策]
18格納容器の除熱機能の多様化
19格納容器トップヘッドフランジの過温破損防止対策*
20低圧代替注水への確実な移行* ○
21ベントの確実性・操作性の向上 ○
22ベントによる外部環境への影響の低減
23ベント配管の独立性確保
24水素爆発の防止(濃度管理及び適切な放出)*
[管理・計装設備対策]
25事故時の指揮所の確保・整備
26事故時の通信機能確保 ○
27事故時における計装設備の信頼性確保 ○
28プラント状態の監視機能の強化 ○
29事故時モニタリング機能の強化
30非常事態への対応体制の構築・訓練の実施 ○
*主にBWRのみ
これらの中から、緊急度が高い安全対策として、前述の、16項目が抽出されたものであろう。(自分の推定で○印)
今回示された判断基準1の中での、緊急安全対策16項目を見て見ると、あまり、金と時間をかけない対策と言える。固定的な設備は殆ど変えずに、可搬形の機材・機器の配備や、非常用設備への習熟、照明の確保策、浸水対策の強化、などが主だ。
そして、全交流電源喪失{当初から組み込まれている電源機能や機器(多ルート化した商用電源、予備電源等)が駄目になった状態}という、最悪の状況になっても、電源車や、消防車等によって冷却機能は確保し、照明等も確保しながら、緊急に設備を管理して、炉心溶融や、水素爆発には至らない様にする、という、ギリギリのレベルを確保する、という意図が感じられる。
自然の脅威に対して、設備が壊れない様に徹底的に防護する、という発想ではなく、仮に壊れても、重大事態には至らない様にし、時間を稼ぐ、と言う方向への転換であるという点では、防災から、減災への、発想の転換、と言え、自分の意見とも合致するもので、この点も評価できる。
これまでよく言われて来た、“原発事故は、決して起こらない”、といった、いわゆる、「安全神話」を捨てているのだ。 設計上で、ある程度の強度や防護策は確保するものの、自然の脅威への対応には、当然、限界があるため、事故は起こっても、最悪の事態には至らない様にしておく、ということだ。
上記の30項目の中で、今後に廻すものは、必要性は高いのだが、時間と金を掛けた、防災にも配慮した対策として、実施すると言うことになろう。
大飯原発でも、免震事務等の建設や、フィルターつきベント設備の整備等々、今後の工程で対応する事項が、まだ、多く残っている。
国内の原発は、今後、福島第一原発と同程度の地震と津波がある場合でも、 今回の緊急安全対策によって、重大事態には至らない、と言うのだが、福島第一、大飯原発での、実際を見て見よう。
設備機器類の設計値と、福島第一での、実際の来襲時の値は以下である。
地震(最大加速度) 津波高
設計 来襲 設計 来襲
福島第一#3 449ガル 507ガル 3.1/5.7m 14~15.5m
大飯#4 700ガル 2.85m
(以前は1.86m)
これから分るように、福島第一では、設計値と比較して、来襲した地震による揺れの規模は、あまり超えていないのだが、津波の高さの規模は、圧倒的に設計値を越えて居たことだ。
これと同程度の地震や津波が来襲した場合は、大飯原発ではどうなるだろうか。大飯原発の場合、ストレステストの結果では、1260ガル以上の振動で、冷却機能が失われ、津波の高さが、11.4mを超えると、交流電源全てを喪失するという。
即ち、特に津波に関して、現在の設備状況では、設備・機材に、可なりの被害が出ることが想定される。
仮に、電源は確保できても、配管等がかなり損傷するため、組み込まれている通常の冷却系は機能できなくなるのではないか。
又、たとえ、メルトダウンや、水素爆発は起こらないとしても、機材や配管の損傷で、建屋内に高濃度の汚染水が漏れ出す事態は考えられるし、サイト内が高線量になることも、あるのではないか。
今回の緊急安全対策で、たとえ設備が損傷しても、敷地内は兎も角、敷地から外の環境には、放射性物質が出て行かないようにすることが、ミニマムの条件だろうが、果たして上手くいくだろうか、という、一抹の不安はあるのだがーーー。
今回の、福島第一に関する技術的知見では、地震由来の損害は、あまり見られない、と言うことだが、事故の詳細な原因調査が完了しなければ、はっきりとは言えないことだ。
今回の事故についての、事故調査・検証委員会(畑村委員会)は、この夏を目途に最終報告をまとめる、としているが、現状では、原子炉内の状況が分らないのは勿論、地下には、高濃度汚染水が大量にあって十分な調査ができず、変則的な循環冷却システムで凌いでいる状況で、これが大きく変わらない限り、今回の結論と、あまり変わらないだろう。本当の原因が分るには、年オーダーが必要だろうか。
自然の脅威に対して、出来るだけ強くして、耐えられるようにしておく事がのぞましいのは当然だが、金も時間もかかる。○○年に一度、と言った確率的なリスクに、どこまで備えるかは、難しい判断となる。
各原発の立地条件について、過去の歴史も含めて、もう一度精査し、自然の脅威の大きさを想定する必要がある。
今回、東北地方太平洋沖で巨大地震が起きることは、どう想定されていただろうか。地盤の構造からして、十分に予想していたのだが、マグニチュードの大きさが、これまでは、もっと小さかったのだが、今回、M9.0になった、というのだろうか。
津波の想定でも、あの場所であのような規模の地震が起これば、今回の様な津波が、各地に来襲すると、予想できるようなシステムが、どう整備されていただろうか。
これまでの、地震の予測や津波の予測に不備があったのであれば、今回の経験を踏まえて改めればいいことだ。
そして、福島第一原発に来襲したと同程度の自然の脅威が、当該地の原発を襲った場合、想定される脅威が大きな地域では、防災的な対策と減災的な対策を組み合わせて対処し、それ程大きくないと想定される地域では、防災的な対策を主に、対処することとなろう。
自分の結論は、この夏に向けて、多くの地域で、需給がひっ迫すると見込まれる状況から、あれこれ、小田原評定をしている時間的余裕は、もはや無く、今回の判断基準によって、速やかに、各原発の再稼働に踏み切るべき、と考える。
そして、時限を切って、例えば2~5年後に、事故原因や、地震や津波に関する解明や研究が進展する事に照らして、安全対策や稼働自体を、見直す事とするのがいい、ように思う。
原発の再稼働に当たって、先だってのブログ記事
原発の再稼働 その2 (2012/2/12)
で述べた、上記結論の方向は、より、状況が分ってきた今も、変わっていない。