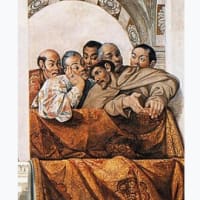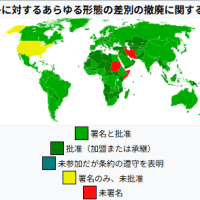4月3日(土) 火災に対する住まいの安全は?
東京都では、この4月1日から、全ての住宅で、火災警報器の設置が、義務化された。これまでは、平成16年10月から、新築・改築住宅が義務づけられており、既存住宅については、今回から対象となったものである。現在住んでいるマンションは、義務化以前に建築されたものだが、火災警報器類は既に各部屋に設置されていて、これまでも、何回か、業者による警報器の定期点検が行われており、特に問題はないようだ。
この機会にと、改めて、自宅内の火災警報器類の設置状況を調べた。台所、リビング、和室、洋室、納戸、など、全ての部屋の天井に設置されている。さらに、各部屋の押入れ・物入れの天井、さらに、洗濯機置き場やトイレや洗面所の天井にもついている。警報器の種類としては、最も危険な台所は、ガス漏れ警報器と熱式警報器の2個、そのほかは、熱式警報器、煙式警報器のどちらかが1個ついていて、電源は、全て配線式になっている。高価なガス漏れ警報器だけは、5年間の有効期限があることを、再確認した。
実際に火災が起こった時に、警報器がどのように火災を知らせてくれるのか、マンションの管理センターに問い合わせてみた。それによると、異常を検出すると、その自宅内だけ、ランプが付き、音が出るようだ。マンション内全体には知らされない、という。専門部署と連携できる、管理センターと警備会社に、電気信号が伝送される。業者による定期点検時は、棒の先に皿が付いたような道具で、皿の内部でテスト用の熱を発生させて、ランプの点灯を確認しているようだ。定期点検の時も、管理センターには、警報信号は行くが、予め定期点検の日時は連絡しているという。点検時に音を聞いたことはないが、インターホンのレベルとも関係しているので、業者に確かめて欲しい、と言われた。
電源が、配線式だと、火災で断線する恐れもある。又、管理センターと警備会社に、電気信号が伝送されるのは、有線式と思われるが、こちらも、火災時は、断線の危険性もある。
ネットによれば、火災警報知器には、電池寿命が10年で、配線工事が不要で自分で取り付けられ、70dbの警報音で知らせてくれるという、簡便な警報器もある(4280円)。
今更ながらの問だが、住宅用の火災警報器は、何のためにつけるのか、というのは重要である。留守中に自宅が火事になった時は、留守宅内で警報が鳴っても、外には聞こえず、役に立たないかもしれない。
家族が在宅中に火事になった時は、日中なら、警報器が、警報音や光で知らせてくれるので、対応しやすい。最も怖いのは、夜間の就寝中である。たとえば、2階で就寝中に、1階の台所で出火し、警報が出たり、寝ている時に、隣部屋の警報器が作動する場合などで、いち早く、避難や消火を行う必要があるが、間に合わないかもしれない。老人や子供が同居している場合は、特に、初期の避難救出が重要になるのだがーー。
消火器については、先だってのブログ(10/3/14 やはり最も怖いのはーー地震)で触れたが、昨年秋で期限切れになっていた、家庭用ABC消火器を、先日更新し、設置場所や操作法を、改めて確認したところである。
火事の、いち早い検出と消火も大事だが、火事を出さない、火事にならない配慮も、それに勝るとも劣らず大切だ。最近は、ガスに比べて、極めて安全性の高い電気を、調理等に使う傾向があり、そのようなマンションは、子供や高齢者のいる世帯に人気があるようだ。
我が家の、台所のガスレンジは、以前のものは、点けっ放しにすると、何時までも火が点いているものだった。ガスを点けっ放しにして、危うく火事になる寸前だった苦い経験がある。
数年前に、ガスレンジの寿命がきたので、新しいものに更改した際、この経験を踏まえ、点火時間が1時間以上になると、自動的に火が止まる仕様のものにした。長時間かけてじっくり煮る場合などでは、火が消えてしまうので、多少面倒な点もあるが、何はともあれ、安心である。
それでも、時々、煮物の鍋を焦してしまうのだからーー。余談だが、この焦げつきを、無理に削ったりするのは禁物! 焦げ付いた鍋を、ベランダなどに出して、暫く放って置くと、綺麗に取れるのは不思議だが、家人から教わった、立派なノウハウである。
一方、夜の楽しみの風呂も、一つ間違えば、怖い火元にもなりうるものだ。自宅のこれまでの風呂では、自分で水を入れて、いい所で給水を止め、その後点火するものだった。水を止め忘れて、水が湯舟(バスタブ)から溢れ出たことは何度もある。が、これは、水道代がもったいない位なもので、大したことではない。
風呂で最も怖いのは、空焚き、である。うっかりして、湯舟に水が無い状態で、点火してしまった事がある。その時は、点火直後に、念のためにと湯舟のカバーを開けて気がつき、すぐ止めたので、給湯器も損傷せず、大事に至らずに助かった。が、それでも、わざわざ業者に来てもらい、湯水が循環するようにして貰う迄、暫く風呂が使えなかったのである。
昔の戸建住宅用の風呂では、空焚きにして、恐ろしい火事になった話は、よく耳にした。身近な親戚の家でも、空焚きで、風呂場周辺でボヤを出したことがあるのだ。
長年使ってきた給湯器の寿命が来たので、数年前、取り替えた時に、全自動式にした。湯舟の排水口の栓を締めて、後は、「自動」のボタンを押すだけである。給水から、ボイラー焚きまで、全てお任せ。爽やかな女性の声で、“お湯が沸きました!”との知らせがあるのを、待つだけなのである。給水で水が湯舟から溢れ出す心配や、空焚きの心配から、すっかり開放された。
将来、この全自動機能がおかしくなった時、安全性はどう確保されるのか、などと気にするのは、杞憂というべきで、考えないことにしている。
以前お世話になった、ガスストーブや、石油ストーブなどの暖房器具についても、火気の取り扱いや、地震の時などに備えての安全性には、結構、神経を使ったものだ。現在は、エアコンだけなので、電気代は嵩むものの、火事の心配は殆ど無い。
又、ここ10数年は、来客時以外は、家の中にはタバコの火が無いので、この点でも、火気の不安は大幅に減っている。
人間の不注意は、無くなることは無いのだが、文明の利器を具現化した、各種システムや機器のお蔭で、一頃に比べ、格段に、安全で安心な生活が送れるようになってきている、といえよう。
東京都では、この4月1日から、全ての住宅で、火災警報器の設置が、義務化された。これまでは、平成16年10月から、新築・改築住宅が義務づけられており、既存住宅については、今回から対象となったものである。現在住んでいるマンションは、義務化以前に建築されたものだが、火災警報器類は既に各部屋に設置されていて、これまでも、何回か、業者による警報器の定期点検が行われており、特に問題はないようだ。
この機会にと、改めて、自宅内の火災警報器類の設置状況を調べた。台所、リビング、和室、洋室、納戸、など、全ての部屋の天井に設置されている。さらに、各部屋の押入れ・物入れの天井、さらに、洗濯機置き場やトイレや洗面所の天井にもついている。警報器の種類としては、最も危険な台所は、ガス漏れ警報器と熱式警報器の2個、そのほかは、熱式警報器、煙式警報器のどちらかが1個ついていて、電源は、全て配線式になっている。高価なガス漏れ警報器だけは、5年間の有効期限があることを、再確認した。
実際に火災が起こった時に、警報器がどのように火災を知らせてくれるのか、マンションの管理センターに問い合わせてみた。それによると、異常を検出すると、その自宅内だけ、ランプが付き、音が出るようだ。マンション内全体には知らされない、という。専門部署と連携できる、管理センターと警備会社に、電気信号が伝送される。業者による定期点検時は、棒の先に皿が付いたような道具で、皿の内部でテスト用の熱を発生させて、ランプの点灯を確認しているようだ。定期点検の時も、管理センターには、警報信号は行くが、予め定期点検の日時は連絡しているという。点検時に音を聞いたことはないが、インターホンのレベルとも関係しているので、業者に確かめて欲しい、と言われた。
電源が、配線式だと、火災で断線する恐れもある。又、管理センターと警備会社に、電気信号が伝送されるのは、有線式と思われるが、こちらも、火災時は、断線の危険性もある。
ネットによれば、火災警報知器には、電池寿命が10年で、配線工事が不要で自分で取り付けられ、70dbの警報音で知らせてくれるという、簡便な警報器もある(4280円)。
今更ながらの問だが、住宅用の火災警報器は、何のためにつけるのか、というのは重要である。留守中に自宅が火事になった時は、留守宅内で警報が鳴っても、外には聞こえず、役に立たないかもしれない。
家族が在宅中に火事になった時は、日中なら、警報器が、警報音や光で知らせてくれるので、対応しやすい。最も怖いのは、夜間の就寝中である。たとえば、2階で就寝中に、1階の台所で出火し、警報が出たり、寝ている時に、隣部屋の警報器が作動する場合などで、いち早く、避難や消火を行う必要があるが、間に合わないかもしれない。老人や子供が同居している場合は、特に、初期の避難救出が重要になるのだがーー。
消火器については、先だってのブログ(10/3/14 やはり最も怖いのはーー地震)で触れたが、昨年秋で期限切れになっていた、家庭用ABC消火器を、先日更新し、設置場所や操作法を、改めて確認したところである。
火事の、いち早い検出と消火も大事だが、火事を出さない、火事にならない配慮も、それに勝るとも劣らず大切だ。最近は、ガスに比べて、極めて安全性の高い電気を、調理等に使う傾向があり、そのようなマンションは、子供や高齢者のいる世帯に人気があるようだ。
我が家の、台所のガスレンジは、以前のものは、点けっ放しにすると、何時までも火が点いているものだった。ガスを点けっ放しにして、危うく火事になる寸前だった苦い経験がある。
数年前に、ガスレンジの寿命がきたので、新しいものに更改した際、この経験を踏まえ、点火時間が1時間以上になると、自動的に火が止まる仕様のものにした。長時間かけてじっくり煮る場合などでは、火が消えてしまうので、多少面倒な点もあるが、何はともあれ、安心である。
それでも、時々、煮物の鍋を焦してしまうのだからーー。余談だが、この焦げつきを、無理に削ったりするのは禁物! 焦げ付いた鍋を、ベランダなどに出して、暫く放って置くと、綺麗に取れるのは不思議だが、家人から教わった、立派なノウハウである。
一方、夜の楽しみの風呂も、一つ間違えば、怖い火元にもなりうるものだ。自宅のこれまでの風呂では、自分で水を入れて、いい所で給水を止め、その後点火するものだった。水を止め忘れて、水が湯舟(バスタブ)から溢れ出たことは何度もある。が、これは、水道代がもったいない位なもので、大したことではない。
風呂で最も怖いのは、空焚き、である。うっかりして、湯舟に水が無い状態で、点火してしまった事がある。その時は、点火直後に、念のためにと湯舟のカバーを開けて気がつき、すぐ止めたので、給湯器も損傷せず、大事に至らずに助かった。が、それでも、わざわざ業者に来てもらい、湯水が循環するようにして貰う迄、暫く風呂が使えなかったのである。
昔の戸建住宅用の風呂では、空焚きにして、恐ろしい火事になった話は、よく耳にした。身近な親戚の家でも、空焚きで、風呂場周辺でボヤを出したことがあるのだ。
長年使ってきた給湯器の寿命が来たので、数年前、取り替えた時に、全自動式にした。湯舟の排水口の栓を締めて、後は、「自動」のボタンを押すだけである。給水から、ボイラー焚きまで、全てお任せ。爽やかな女性の声で、“お湯が沸きました!”との知らせがあるのを、待つだけなのである。給水で水が湯舟から溢れ出す心配や、空焚きの心配から、すっかり開放された。
将来、この全自動機能がおかしくなった時、安全性はどう確保されるのか、などと気にするのは、杞憂というべきで、考えないことにしている。
以前お世話になった、ガスストーブや、石油ストーブなどの暖房器具についても、火気の取り扱いや、地震の時などに備えての安全性には、結構、神経を使ったものだ。現在は、エアコンだけなので、電気代は嵩むものの、火事の心配は殆ど無い。
又、ここ10数年は、来客時以外は、家の中にはタバコの火が無いので、この点でも、火気の不安は大幅に減っている。
人間の不注意は、無くなることは無いのだが、文明の利器を具現化した、各種システムや機器のお蔭で、一頃に比べ、格段に、安全で安心な生活が送れるようになってきている、といえよう。