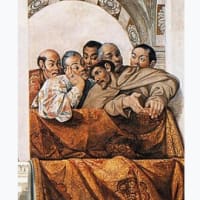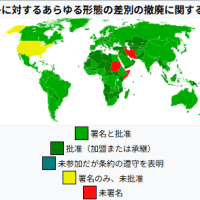6月17日(木) 消費者金融 その2
当ブログで、先日(10/6/3)
消費者金融 その1
として、改正貸金業法などについて触れた。明日6月18日から、本改正法が本施行となるのを前に、今回は、その2として、関連の話題について述べてみたい。
前回取り上げた、某都銀のカードローンだが、その後、当該銀行の窓口に出向いて確かめたところ、長年仕舞い込んでいた、手持ちの磁気カードでも、問題なく使えることを確認できた。
ATMにそのカードを挿入し、何とか覚えていたパスワードを入力すると、恰も、数十万円の残高の預金があるように表示され、必要な資金を自由に引き出せるのである。これで、急な資金需要があっても、カバーできることが分かり、一安心である。勿論、立派な借り入れだから、返済しなければならないのは当然のことだ。
こつこつ金を貯めて、貯まったところで使う、というのが、ある意味で、理想的なのだが、なかなか貯まらず、どんどん時間ばかりが経過して、経済の規模も小さなものとなる。このため、時間の先ヅモとして、金融機関が預金で集めた資金等を基に、事業への融資や住宅ローンの貸付を行うことで、経済の規模も大きくなることから、世の中、信用をベースにした取引が、盛んに行われている訳である。
この文脈で、注意すべきは、国が国債を発行して資金を調達する方法だ。これは、国自体が、時間を先取りして、将来の世代に借金するという、最も安易で最も危険な方法なのである。日本の場合、国民一人当たりの国債残高が、700万円以上とも言われており、積年の政治の付けが廻って来ているのである。この件は、別の機会に触れることがあろうと思う。
通常の売買の商取引では、売る側は、物やサービスを提供し、買う側は、その対価として金を支払うということで、バランスしたやり取りとなり、分かりやすい。一方、資金の貸し借りは、取引とは言うものの、物やサービスの売買の時とは異なり、貸し手側の金融機関としては、借り手側の将来を信用する、のが基本となる。通常の取引と異なり、バランスしない、アンバランスな取引といえるだろう。それだけに、慎重な審査が行われることとなる。
貸し手側から見て、借り手側が返せなくなるリスクは常にあり、そのリスクを極力減らすために、担保を取ることも多い。これは、貸し借りの取引を、出来るだけ、バランス型に近づける工夫と言えよう。土地や建物等の不動産などが、担保物件となる場合が多い。
個人のレベルでは、銀行の住宅ローンなどの場合、物件自身が担保になっている。ローンが払えなくなると、担保物件の住宅を取り上げられてしまう。この様な担保物件がある場合でも、貸す側のリスクを極力少なくするため、借り手の就業状況や今後の収入の見通しなどについても、結構、厳しく審査が行われるのが普通である。自動車ローンの場合なども、同様であろう。以前は、七つ屋、16銀行などとも呼ばれて親しまれた質屋は、サラ金業者に押され気味だが、質草という担保を取って貸し付けているわけだ。返せなくなると、質草は戻らず、質流れ品として処分される。
余談だが、金融機関で住宅ローンを組む場合、銀行が、手続きも、懇切丁寧にやってくれる。が、何年か後、住宅ローンを完済すると、その住宅に設定されていた抵当権はなくなるのだが、この時は、銀行は何故か不親切である。結局、自分で不動産登記所に出向き、手続きを行って、住宅の登記簿から抵当権を消去してもらった、ことが思い出される。
今回の貸金業法の改正のポイントは、総量規制の導入と、上限金利の引き下げであろう。
前者については、前回触れたので、今回は、後者について述べたみたい。
此処で言う、貸金とは、いわゆる、個人向けの無担保貸付で、審査はあるものの、不動産物件等の担保を伴わない、アンバランスな取引である。
貸し金に関わる金利には、これまでは
利息制限法での上限金利
10万円以下 年20%
10~100万円 年18%
100万円以上 年15%
出資法による上限金利
年29.2%
の、二つがあり、貸金業者の場合、利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利との間の金利帯も、一定の要件を満たすと、有効とされてきた。これがいわゆる「グレーゾーン金利」で、一定の要件を満たさない場合も含めて、このお蔭で、業者は荒稼ぎをしてきた、といえる。最近は、多重債務問題で、いわゆる、過払い金の請求案件として、取り返す動きが活発になってきている。
今回の、貸金業法の改正で、このグレーゾーン金利が無くなり、利息制限法の金利水準に引き下げられ、一本化されたようだ。これまで、何故、抜け穴のようなグレーゾーン金利が存在したのだろうか、時間があれば調べたいものだ。今後、グレーゾーン金利が無くなれば、事業者側の旨味が無くなり、違法なヤミ金利だけが残る事となる。
でも、金を借りる場合の上限金利が、20%と低くなったとは言え、油断は禁物。就業や収入の見通しも不確かな上、銀行預金の金利は、桁違いに低く、株式投資の利回りなども極めて低い、という現今の経済状況からすると、借りる側としては、大変な利息を払わなければならない、ということに、代わりは無い。この両者の金利差で、金融業は成り立っている、ともいえるのだがーーー。
一方、クレジットカードのキャッシング枠を使って金を借りることも、今回の総量規制の対象となることから、最近は、クレジットカードのショッピング枠を使った、巧妙な現金化の方法が行われているようだ。クレジットカードで、特定の価値の低い品物(例 ビー玉)を購入すると、10%程度の手数料等を差し引いた現金が、手に入るという仕組みのようだ。この様な仕組みが、違法なのか、違法で無いのかは、微妙なようだ。手数料を含めて、全額を返済しなければならないのは言うまでも無い。
この話は、パチンコ屋で、パチンコ玉を特定の品物(例 剃刀の刃)に換えてもらい、それを近くの景品交換所に持っていくと、現金に換えてくれる、という仕組みに酷似している。
借金は、あくまでも人様の財産を使わせてもらうのだから、利息を付けて返さなければならず、返さないと犯罪になるのは当然だ。
個人の場合、借金を返せなくなった時、犯罪にならずに、借金を合法的に踏み倒す最後の手段として、破産宣告がある。又、会社の場合、事業が行き詰った時に、会社の更正や清算と言う、合法的な手続きがあり、借金は棒引きとなる。
いずれの場合も、借金が棒引きになり、詐欺や窃盗などの、犯罪にはならないということでは、救われるのだが、破産した個人や法人経営者の、その後の社会生活や社会活動がどうなるかは、別問題である。
金融業は、古来、何処か蔑まれて来た側面がある。たんまり抱えている資金を元手に、汗を流さずに、腕組みをしてぬくぬくと稼いでいる、といった風に見られている。その資金も、何か良くないことで荒稼ぎしたのでは、という、庶民の羨望とも、恨みともつかぬ気分が籠っていようか。シェークスピアの名作喜劇、「ヴェニスの商人」では、強欲なユダヤ人の金貸しシャイロックに対し、若い裁判官に扮する、美貌の女性ポーシャが下す、
“肉は切り取ってもいいが、血は一滴たりとも流してはならぬ”
という名判決に、世界中の人達が拍手を送ったことだろう。金貸しに対する、善良な市民の、日頃の恨み、辛みを、見事に代弁しているようだ。
とは言え、当今、金融関係でも、銀行業は憧れの職業で、かっこよく、バンカーなどと言われる存在になっている。一方の、消費者金融業は、身近な存在である半面、サラ金などと蔑まれ、怖れられても来たのだが、今回の抜本的な法改正等を切っ掛けにして、どのように変わっていくのだろうか。
消費者金融の分野では、事業者同士の競争もあり、貸付の垣根や審査は、甘くなる一方のように見える。一定期間は、利息が付かない、などという、甘い汁で誘惑する。融資は甘くする一方で、慈善事業ではないのだから、取立ては非常に厳しい、という側面も忘れてはなるまい。
最近の小売業界では、スーパーや本屋など、決済前に、自由に品物を手に取ることが出来るのは当たり前で、非常に敷居が低くなっている。この延長で、若い人達には、商品の万引きに、罪悪感が少ないというのも、頷ける面もある。自分の物と、他人の物との区別が、はっきりしなくなっているのだ。
自分の物と他人の物、自分の金と他人の金、の違いを、改めて教え込まないといけない時代なのだろうか?
マイクロファイナンスという金融事業があるようだ。発展途上国などで、資金力の無い主婦などの起業意欲を支援し、無担保で、小額の資金を貸し付ける仕組み(金利は決して安くは無い)であるが、真面目に取り組まれていて、資金の返済率も、極めて高いという。貸し付ける前の事業見込みの分析や、途中、途中でのサポートなど、親身に支援していることが、いい結果に繋がっているようだ。先日のニュースでは、国内の某自治体も、似た様な事業で、成果を挙げている、との報道があった。
これらを耳にする時、貸す側も借りる側も、真面目に取り組める環境の中では、人間の性は、本来、善である、ということを、信じたくなるような事案ではある。
当ブログで、先日(10/6/3)
消費者金融 その1
として、改正貸金業法などについて触れた。明日6月18日から、本改正法が本施行となるのを前に、今回は、その2として、関連の話題について述べてみたい。
前回取り上げた、某都銀のカードローンだが、その後、当該銀行の窓口に出向いて確かめたところ、長年仕舞い込んでいた、手持ちの磁気カードでも、問題なく使えることを確認できた。
ATMにそのカードを挿入し、何とか覚えていたパスワードを入力すると、恰も、数十万円の残高の預金があるように表示され、必要な資金を自由に引き出せるのである。これで、急な資金需要があっても、カバーできることが分かり、一安心である。勿論、立派な借り入れだから、返済しなければならないのは当然のことだ。
こつこつ金を貯めて、貯まったところで使う、というのが、ある意味で、理想的なのだが、なかなか貯まらず、どんどん時間ばかりが経過して、経済の規模も小さなものとなる。このため、時間の先ヅモとして、金融機関が預金で集めた資金等を基に、事業への融資や住宅ローンの貸付を行うことで、経済の規模も大きくなることから、世の中、信用をベースにした取引が、盛んに行われている訳である。
この文脈で、注意すべきは、国が国債を発行して資金を調達する方法だ。これは、国自体が、時間を先取りして、将来の世代に借金するという、最も安易で最も危険な方法なのである。日本の場合、国民一人当たりの国債残高が、700万円以上とも言われており、積年の政治の付けが廻って来ているのである。この件は、別の機会に触れることがあろうと思う。
通常の売買の商取引では、売る側は、物やサービスを提供し、買う側は、その対価として金を支払うということで、バランスしたやり取りとなり、分かりやすい。一方、資金の貸し借りは、取引とは言うものの、物やサービスの売買の時とは異なり、貸し手側の金融機関としては、借り手側の将来を信用する、のが基本となる。通常の取引と異なり、バランスしない、アンバランスな取引といえるだろう。それだけに、慎重な審査が行われることとなる。
貸し手側から見て、借り手側が返せなくなるリスクは常にあり、そのリスクを極力減らすために、担保を取ることも多い。これは、貸し借りの取引を、出来るだけ、バランス型に近づける工夫と言えよう。土地や建物等の不動産などが、担保物件となる場合が多い。
個人のレベルでは、銀行の住宅ローンなどの場合、物件自身が担保になっている。ローンが払えなくなると、担保物件の住宅を取り上げられてしまう。この様な担保物件がある場合でも、貸す側のリスクを極力少なくするため、借り手の就業状況や今後の収入の見通しなどについても、結構、厳しく審査が行われるのが普通である。自動車ローンの場合なども、同様であろう。以前は、七つ屋、16銀行などとも呼ばれて親しまれた質屋は、サラ金業者に押され気味だが、質草という担保を取って貸し付けているわけだ。返せなくなると、質草は戻らず、質流れ品として処分される。
余談だが、金融機関で住宅ローンを組む場合、銀行が、手続きも、懇切丁寧にやってくれる。が、何年か後、住宅ローンを完済すると、その住宅に設定されていた抵当権はなくなるのだが、この時は、銀行は何故か不親切である。結局、自分で不動産登記所に出向き、手続きを行って、住宅の登記簿から抵当権を消去してもらった、ことが思い出される。
今回の貸金業法の改正のポイントは、総量規制の導入と、上限金利の引き下げであろう。
前者については、前回触れたので、今回は、後者について述べたみたい。
此処で言う、貸金とは、いわゆる、個人向けの無担保貸付で、審査はあるものの、不動産物件等の担保を伴わない、アンバランスな取引である。
貸し金に関わる金利には、これまでは
利息制限法での上限金利
10万円以下 年20%
10~100万円 年18%
100万円以上 年15%
出資法による上限金利
年29.2%
の、二つがあり、貸金業者の場合、利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利との間の金利帯も、一定の要件を満たすと、有効とされてきた。これがいわゆる「グレーゾーン金利」で、一定の要件を満たさない場合も含めて、このお蔭で、業者は荒稼ぎをしてきた、といえる。最近は、多重債務問題で、いわゆる、過払い金の請求案件として、取り返す動きが活発になってきている。
今回の、貸金業法の改正で、このグレーゾーン金利が無くなり、利息制限法の金利水準に引き下げられ、一本化されたようだ。これまで、何故、抜け穴のようなグレーゾーン金利が存在したのだろうか、時間があれば調べたいものだ。今後、グレーゾーン金利が無くなれば、事業者側の旨味が無くなり、違法なヤミ金利だけが残る事となる。
でも、金を借りる場合の上限金利が、20%と低くなったとは言え、油断は禁物。就業や収入の見通しも不確かな上、銀行預金の金利は、桁違いに低く、株式投資の利回りなども極めて低い、という現今の経済状況からすると、借りる側としては、大変な利息を払わなければならない、ということに、代わりは無い。この両者の金利差で、金融業は成り立っている、ともいえるのだがーーー。
一方、クレジットカードのキャッシング枠を使って金を借りることも、今回の総量規制の対象となることから、最近は、クレジットカードのショッピング枠を使った、巧妙な現金化の方法が行われているようだ。クレジットカードで、特定の価値の低い品物(例 ビー玉)を購入すると、10%程度の手数料等を差し引いた現金が、手に入るという仕組みのようだ。この様な仕組みが、違法なのか、違法で無いのかは、微妙なようだ。手数料を含めて、全額を返済しなければならないのは言うまでも無い。
この話は、パチンコ屋で、パチンコ玉を特定の品物(例 剃刀の刃)に換えてもらい、それを近くの景品交換所に持っていくと、現金に換えてくれる、という仕組みに酷似している。
借金は、あくまでも人様の財産を使わせてもらうのだから、利息を付けて返さなければならず、返さないと犯罪になるのは当然だ。
個人の場合、借金を返せなくなった時、犯罪にならずに、借金を合法的に踏み倒す最後の手段として、破産宣告がある。又、会社の場合、事業が行き詰った時に、会社の更正や清算と言う、合法的な手続きがあり、借金は棒引きとなる。
いずれの場合も、借金が棒引きになり、詐欺や窃盗などの、犯罪にはならないということでは、救われるのだが、破産した個人や法人経営者の、その後の社会生活や社会活動がどうなるかは、別問題である。
金融業は、古来、何処か蔑まれて来た側面がある。たんまり抱えている資金を元手に、汗を流さずに、腕組みをしてぬくぬくと稼いでいる、といった風に見られている。その資金も、何か良くないことで荒稼ぎしたのでは、という、庶民の羨望とも、恨みともつかぬ気分が籠っていようか。シェークスピアの名作喜劇、「ヴェニスの商人」では、強欲なユダヤ人の金貸しシャイロックに対し、若い裁判官に扮する、美貌の女性ポーシャが下す、
“肉は切り取ってもいいが、血は一滴たりとも流してはならぬ”
という名判決に、世界中の人達が拍手を送ったことだろう。金貸しに対する、善良な市民の、日頃の恨み、辛みを、見事に代弁しているようだ。
とは言え、当今、金融関係でも、銀行業は憧れの職業で、かっこよく、バンカーなどと言われる存在になっている。一方の、消費者金融業は、身近な存在である半面、サラ金などと蔑まれ、怖れられても来たのだが、今回の抜本的な法改正等を切っ掛けにして、どのように変わっていくのだろうか。
消費者金融の分野では、事業者同士の競争もあり、貸付の垣根や審査は、甘くなる一方のように見える。一定期間は、利息が付かない、などという、甘い汁で誘惑する。融資は甘くする一方で、慈善事業ではないのだから、取立ては非常に厳しい、という側面も忘れてはなるまい。
最近の小売業界では、スーパーや本屋など、決済前に、自由に品物を手に取ることが出来るのは当たり前で、非常に敷居が低くなっている。この延長で、若い人達には、商品の万引きに、罪悪感が少ないというのも、頷ける面もある。自分の物と、他人の物との区別が、はっきりしなくなっているのだ。
自分の物と他人の物、自分の金と他人の金、の違いを、改めて教え込まないといけない時代なのだろうか?
マイクロファイナンスという金融事業があるようだ。発展途上国などで、資金力の無い主婦などの起業意欲を支援し、無担保で、小額の資金を貸し付ける仕組み(金利は決して安くは無い)であるが、真面目に取り組まれていて、資金の返済率も、極めて高いという。貸し付ける前の事業見込みの分析や、途中、途中でのサポートなど、親身に支援していることが、いい結果に繋がっているようだ。先日のニュースでは、国内の某自治体も、似た様な事業で、成果を挙げている、との報道があった。
これらを耳にする時、貸す側も借りる側も、真面目に取り組める環境の中では、人間の性は、本来、善である、ということを、信じたくなるような事案ではある。