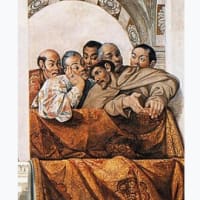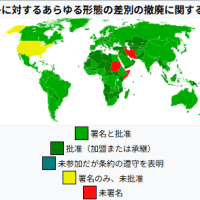2012年1月14日(土) 原発事故の検証
事故原発に関する、中長期のロードマップについては、先日の記事
事故原発との長―い闘い (2012/1/6)
で触れたが、今回は、その時に積み残していた、事故原因関連について、触れることとしたい。
昨年12月18日にTV放映された、NHKスペシャル
シリーズ原発危機 「メルトダウン~福島第一原発 あのとき何が」
は、衝撃的であった。
詳細な取材と聞き取り調査を元に、全電源喪失から、水素爆発が起こるまでの過程を丹念に再現している。メルトダウンについては、事故当時は、はっきりとは、報道されていなかった状況だが、意図的に隠したのではなく、当事者には、的確な状況把握が出来なかった、と思われる。その後は、メルトダウンや、メルトスルーはほぼ間違いなく起こっていると言われてきたことだが、番組では、このことを、コンピュタシュミレーションにより明らかにしている。
自分にとって、今回、新たに知った情報は、 非常用復水器(IC isoration condensor イソコン)の存在である。以前から、何やら設備があることは知っていたが、その機能については分っていなかった。
この装置は、全ての電源が停まったときに活躍する装置で、電気エネルギーが無い時に、熱エネルギーの交換だけで動作して、原子炉の冷却を行うものの様だ。
復水器に蓄えられた冷たい水で、原子炉の温水が冷やされ、それが熱交換で循環するという。この装置に蓄えられる水の容量はどの位なのだろうか、又、そんなに長い時間は持たないと思われるが、稼働出来る時間はどの位なのだろうか。
この装置、全電源断になると、原子炉と繋がっている部分のバルブが自動的に閉まる様に出来ているようだ。従って、その閉まったバルブを、手動で開けてやると、後は、自動的に循環して冷却ができると言う。
ICは、古い1号機にしか付いていない、という情報もあるが、他の原子炉では、この機能はどうなっているのだろうか。
事故現場では、当初は、この装置の事が良く分からず、後手に回ったようだ。全電源断の非常時に、バルブが自動的に閉まることが、よく理解されておらず、バルブは開いていると思われ、ICは、稼働していないのに、動いていると誤認していたようだ。
途中で、閉まっているのではと思い、開けに行ったが、放射線量が高く、近付けなかったとも言う。
又、長時間復水器を動作させると水が無くなって空炊き状態になり、タンクが爆発するのではと、動作を止めてしまった、ともいう。結局、最後の手段である非常用復水器は、機能することは無かった様だ。
最も残念なのは、日頃の訓練で、復水器を作動させ、バルブを操作した事が無かったということだ。 非常時という最悪の事態でしか使わず、しかも訓練で操作した事も無い装置は、まともに動かせる訳が無い。
番組では、アメリカの現場では、訓練で、イソコンのバルブを操作している風景が写されていたのだがーー。
日本では、そのような事態は起こる筈が無い、という、いつもの前提だったのだろうか。
もう一点は、原子炉の水位計のことである。
原子炉内部の状況を把握するには、各種計測機器に頼るしかないわけだが、暗闇の中で、原子炉内の冷却水の水位や温度をじっと監視したようだ。
炉内の実際の水位と、表示される水位とが異なっていたようだ。それも、炉内の水位が下がって、燃料棒が露出して危険な状態になるほど、計器の表示では、水位が上がって、安全な方になった、ということのようだ。
どうしてこのようなことになるのか、水位計の動作原理はどうなっているのか、などの、詳細は不明だ。現場の作業員たちが、表示が、実態と異なって、おかしくなっていることに気付いたのは、大分時間が経過してからのようだ。
制御室内は、停電で真っ暗で、計器類は正常に動作しているかは怪しく、表示は良く見えず、マニュアルの所在も分らなかったことなども、混乱を、より大きくしたようだ。
このような混乱した状況の中で、的確な措置ができず、次々と、水素爆発が起こってしまい、大量の放射性物質が、周囲に放出されたのである。
仮に、現場の関係者が、非常時に稼働する復水器等の操作に予め習熟していて、水位計の表示のことも頭に入っていたとしたら、メルトダウン・メルトスルーや水素爆発を、どの位遅らせられたのだろうか、あるいは防げたのだろうか。この辺については明確な報道はなかった。
一方、事故原因の調査・分析を進めるために設置された、事故調査・検証委員会(畑村委員会)の中間報告が、昨年暮れの、12/26に公表された。概要、本文編、資料編を含めて、700ページを超える膨大な分量の報告書である。
この中でも、上述の、イソコン、水位計のことも触れられているが、これらについて、さらに詳細な状況を、報告書を見て明らかにすることは、やめにしたい。
上述のように、仮に、イソコンや水位計について、作業員が十分に習熟していたとしたら、水素爆発はどうなったか、については、報告では明言を避けている。
中間報告では、事故後の現場での対応の問題や、事前の備えの段階での問題なども指摘されている。
又、安全に対する過信や、起こる筈が無いと、思考を止めてしまった事等の、精神的な側面の問題も指摘している。
今年夏頃には、最終報告が纏まり、事故原因の解明・検証を行うとともに、今後に向けた再発防止のための提言が、公表される予定だ。