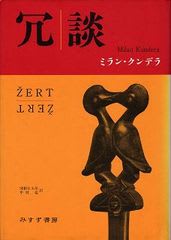
『冗談』 ミラン・クンデラ ☆☆☆☆☆
クンデラの作品第一番、『冗談』を再読。初期の作品ということで、後の傑作『存在の耐えられない軽さ』や『不滅』のように突然作者のエッセーが物語に割り込んでくるようなことはなく、より伝統的な小説作法で書かれている。また主人公ルドヴィークの悲惨な運命はもちろんのこと、登場人物たちはみな何かしら人生の苦さ、幻滅を与えられることになっており、クンデラ印のアイロニーとユーモアのせいで暗いとは言えないまでも、かなりビターな味わいの小説だ。プロットは悲劇的でも全体のトーンは饗宴的、祝祭的だった『存在の耐えられない軽さ』や『不滅』のような明るさはない。
本書はクンデラの他の小説と同じく七部からなるが、それぞれの章に登場人物の名前が振られており、その人物の視点から一人称で物語が語られる。つまり章によって視点が移り変わっていく。登場人物はある章では「私」として自分の内面を語り、別の章では他人から見た姿を語られることにより、多面的な存在となっていく。
主要な登場人物は数人いるにしても、やはり本書の主人公はルドヴィークである。彼は共産党員だった若い頃に恋していた女の子に出した一枚のハガキ、そしてそこに苛立たしさのあまり冗談で書いた一言(「楽天主義は麻薬だ。トロツキー万歳!」)によって反乱分子と断罪され、自由も学校も将来も友人もすべて失い、強制労働というか強制兵役に従事させられる。本書は基本的にこのルドヴィークが自分を断罪したかつての友人、ゼマーネクに復讐するためその妻ヘレナにしかける不倫の情事、そしてルドヴィークの回想の中で語られるルツィエとのラヴ・ストーリー、がメインとなっている。
タイトルの「冗談」はもちろんルドヴィークを破滅させたたった一言の冗談のことだが、同時に彼の復讐がたどる皮肉な結末のことであり、歴史が人々にしかける壮大な「冗談」の数々のことである。ミラン・クンデラはどこかで「時々、歴史が人々の人生を眺めながら腹をかかえて笑っていると思うことがある」みたいなことを書いていたが、本書はそうした歴史に翻弄される人々とその悲喜劇を描き出している。
他の登場人物にも触れると、ヘレナは本書中もっとも抒情的な性格の持ち主で、ルドヴィークとの出会いを真の愛との出会いであり、運命だと考える。しかしもちろんその愛は虚構なわけで、それを知った彼女は(自分の幻想の高貴さを保つために)死に憧れるが、そこでもまた現実に裏切られ、なんとも滑稽な、無残な結果に終わってしまう。本書の登場人物の中ではヘレナがもっとも残酷な扱いを受けているが、これは彼女の抒情的性格、そしてそれに対するクンデラの考えを反映しているのかも知れない。
それからルドヴィークの幼馴染ヤロスラフは民俗音楽に生きがいを見出す男で、彼が語り手である章ではクンデラの音楽的教養が披露される。彼は伝統の中に美と生きがいを見出し、新しい世代にそれを手渡したいと願うが、妻と息子の苦い裏切りにあって絶望する。
信仰者であるコストカは常に神の声に従って行動し、悲惨な人生を歩んできた娘ルツィエを救おうと努力する。彼は高潔な人格者で、ルドヴィークのアイロニー精神と懐疑主義を批判し、本書の中では珍しく幸福な確信の持ち主に見えるが、実は利己的な動機を神の声のせいにしていたのではないかという迷いの苦しみが、最後に告白される。
本書中もっとも幸福で、満ち足りているのはゼマーネクである。世界の抒情的傾向に自分を合わせ、常に人気をもっとも重視し、理性ではなく人々の感傷に訴えることによって物事をなそうとする政治的人物。彼は友人だったルドヴィークの冗談の件を知ると「あれは冗談だったんだ」という彼の必死の訴えを無視して彼を断罪し、追放し、それをもって党における自分の地位を確固たるものにする。そして時代とともに共産主義が失墜するとたちまち「反体制」を標榜し、「権威に反抗する若者の味方の大学教授」として学生たちの人気を集める。
クンデラのアイロニーが最高潮に達するのは、ルドヴィークとゼマーネクが再会する場面である。ゼマーネクはルドヴィークを古い友人として扱い、かつて自分が彼を追放し、人生を破滅させたことを忘れ去ったように振舞う。そして彼の若い、美しい大学生のガールフレンドはゼマーネクを「権威に迎合しない勇気ある人物」として褒め称える。しかしルドヴィークをもっとも打ちのめすのは、宿敵同士として対立していたはずの自分とゼマーネクは、いまや歴史の変遷によって「同類」になってしまったということである。つまり共産主義や党への忠誠など過去の遺物となってしまった新しい世代にとって、追放された人物にしろ、追放した人物にしろ、古いイデオロギーの中でドタバタしていた似たもの同士にしか見えない、ということだ。こうして冗談によって破滅させられたルドヴィークの人生は、その悲劇的な破滅までが冗談にされてしまった。
ルドヴィークはさとる、歴史の中で正しく振舞う機会は一度しかないのだと。自分がゼマーネクに復讐する機会は、自分が弾劾されていたその時以外になかった。ゼマーネクが集会の壇上で滔々と弁舌をぶっているその時にこそ、駆け寄ってその顔を殴りつけてやるべきだったのだと。
この小説は、当時の共産主義政権に対する糾弾にしてはアイロニカルで斜に構えすぎていると思われるかも知れない。作者のクンデラはこれをラヴ・ストーリーと呼んでいるが、ラヴ・ストーリーにしてはルドヴィークとルツィエの関係は曖昧で、劇的な展開にも結末にも欠け、中途半端だと思われるかも知れない。復讐譚としても溜飲が下がらない、苛立たしい作品と言われるだろう(卑劣なゼマーネクは勝ち誇り、幸せに満ち足りた人物として物語を立ち去っていく)。それではこの小説の核心はどこにあるのだろうか。
「冗談」のタイトルが示すように、本書は人々の人生を支配する不可解な、超越的なメカニズム(つまり歴史のメカニズム)を描き出したものであると同時に、人々が人生の中で何かを選択する時、その裏で作動する隠れたメカニズムを描き出したものでもある。人々はさまざまな動機で物事を選択するが、その動機は(イデオロギーや大義名分、打算や功利主義ですら)真の動機ではなく、さらにその下に決定的なキーワードが隠されている、とクンデラは考える。これは『不滅』の中でクンデラがグルントと名づけたものだが、グルントはイデオロギーの対立や相違とはほとんど関係がない。たとえば全体主義国家の独裁者と民主主義国家の議員が同じグルントに従って行動している、ということがありうる。この作品では登場人物たちの行動はすべて二重、三重に解釈されるか、あるいは解釈の余地が暗示される。世情に合わせて態度を変えるゼマーネクは果たして体制迎合者なのか、反体制者なのか。それは彼の真実とは無関係である。彼の真実とは、常にその時代の「最高権威」「最高審判者」に迎合する、というものだ(体制が若者が馬鹿にされる無難でみじめな存在に成り下がった時代には、若い世代の人気こそが最高権威になる)。
ルドヴィークはルツィエへの愛を自分の人生における聖域、もっとも真実な感情と考えた。しかし長い年月の後、故郷でルツィエを見かけた時に彼は悟る、自分が愛したルツィエは自分の鏡像だったのだと。ルドヴィークは悲劇的な自分の人生の姿に合わせた彼女の姿を愛していた。従ってその人生の状況が消えた時、自分が愛したルツィエは消えた。本物のルツィエは、自分が愛したルツィエとは異なる女だったのである。
こうした考察は本書のあらゆるエピソードを彩っている。なぜルドヴィークはあんなくだらない冗談を書いたのか。なぜルツィエに肉体の愛を拒まれた時、ルドヴィークはあれほど逆上したのか。なぜコストカはルツィエを救おうとしたのか。クンデラの視線は人間の行為を司る真の動機をあぶり出す。人間が不可解な行動を取るとき、勇敢な、あるいは卑劣な、あるいは自己犠牲的な、あるいは愚かな行動を取るとき、何がそうさせるのか。それを豊富なメタファーによってスリリングに、詩的に表現していくクンデラの変幻自在のエクリチュールにこそ、本書を読む醍醐味が存在する。
クンデラによれば、本書のアイデアは「墓場の花を盗んで恋人に贈った女」のついての記事を読んだ時に生まれたらしい。だとすれば、『冗談』はルツィエのイメージを核として生まれた小説であり、決して歴史哲学や共産主義批判が出発点ではないのだ。「『冗談』はラヴ・ストーリーなのです」というクンデラの言葉はそういう意味だと思う。ルツィエは本書における主要人物の中で、唯一自らの語りを持たないキャラクターである。そのため多くの男の人生にかかわって重要な役割を演じながら、自らは幻のままに留まる。このミステリアスで多義的なルツィエこそ、本書『冗談』を中心点で支えるポエジーの泉である。
クンデラの作品第一番、『冗談』を再読。初期の作品ということで、後の傑作『存在の耐えられない軽さ』や『不滅』のように突然作者のエッセーが物語に割り込んでくるようなことはなく、より伝統的な小説作法で書かれている。また主人公ルドヴィークの悲惨な運命はもちろんのこと、登場人物たちはみな何かしら人生の苦さ、幻滅を与えられることになっており、クンデラ印のアイロニーとユーモアのせいで暗いとは言えないまでも、かなりビターな味わいの小説だ。プロットは悲劇的でも全体のトーンは饗宴的、祝祭的だった『存在の耐えられない軽さ』や『不滅』のような明るさはない。
本書はクンデラの他の小説と同じく七部からなるが、それぞれの章に登場人物の名前が振られており、その人物の視点から一人称で物語が語られる。つまり章によって視点が移り変わっていく。登場人物はある章では「私」として自分の内面を語り、別の章では他人から見た姿を語られることにより、多面的な存在となっていく。
主要な登場人物は数人いるにしても、やはり本書の主人公はルドヴィークである。彼は共産党員だった若い頃に恋していた女の子に出した一枚のハガキ、そしてそこに苛立たしさのあまり冗談で書いた一言(「楽天主義は麻薬だ。トロツキー万歳!」)によって反乱分子と断罪され、自由も学校も将来も友人もすべて失い、強制労働というか強制兵役に従事させられる。本書は基本的にこのルドヴィークが自分を断罪したかつての友人、ゼマーネクに復讐するためその妻ヘレナにしかける不倫の情事、そしてルドヴィークの回想の中で語られるルツィエとのラヴ・ストーリー、がメインとなっている。
タイトルの「冗談」はもちろんルドヴィークを破滅させたたった一言の冗談のことだが、同時に彼の復讐がたどる皮肉な結末のことであり、歴史が人々にしかける壮大な「冗談」の数々のことである。ミラン・クンデラはどこかで「時々、歴史が人々の人生を眺めながら腹をかかえて笑っていると思うことがある」みたいなことを書いていたが、本書はそうした歴史に翻弄される人々とその悲喜劇を描き出している。
他の登場人物にも触れると、ヘレナは本書中もっとも抒情的な性格の持ち主で、ルドヴィークとの出会いを真の愛との出会いであり、運命だと考える。しかしもちろんその愛は虚構なわけで、それを知った彼女は(自分の幻想の高貴さを保つために)死に憧れるが、そこでもまた現実に裏切られ、なんとも滑稽な、無残な結果に終わってしまう。本書の登場人物の中ではヘレナがもっとも残酷な扱いを受けているが、これは彼女の抒情的性格、そしてそれに対するクンデラの考えを反映しているのかも知れない。
それからルドヴィークの幼馴染ヤロスラフは民俗音楽に生きがいを見出す男で、彼が語り手である章ではクンデラの音楽的教養が披露される。彼は伝統の中に美と生きがいを見出し、新しい世代にそれを手渡したいと願うが、妻と息子の苦い裏切りにあって絶望する。
信仰者であるコストカは常に神の声に従って行動し、悲惨な人生を歩んできた娘ルツィエを救おうと努力する。彼は高潔な人格者で、ルドヴィークのアイロニー精神と懐疑主義を批判し、本書の中では珍しく幸福な確信の持ち主に見えるが、実は利己的な動機を神の声のせいにしていたのではないかという迷いの苦しみが、最後に告白される。
本書中もっとも幸福で、満ち足りているのはゼマーネクである。世界の抒情的傾向に自分を合わせ、常に人気をもっとも重視し、理性ではなく人々の感傷に訴えることによって物事をなそうとする政治的人物。彼は友人だったルドヴィークの冗談の件を知ると「あれは冗談だったんだ」という彼の必死の訴えを無視して彼を断罪し、追放し、それをもって党における自分の地位を確固たるものにする。そして時代とともに共産主義が失墜するとたちまち「反体制」を標榜し、「権威に反抗する若者の味方の大学教授」として学生たちの人気を集める。
クンデラのアイロニーが最高潮に達するのは、ルドヴィークとゼマーネクが再会する場面である。ゼマーネクはルドヴィークを古い友人として扱い、かつて自分が彼を追放し、人生を破滅させたことを忘れ去ったように振舞う。そして彼の若い、美しい大学生のガールフレンドはゼマーネクを「権威に迎合しない勇気ある人物」として褒め称える。しかしルドヴィークをもっとも打ちのめすのは、宿敵同士として対立していたはずの自分とゼマーネクは、いまや歴史の変遷によって「同類」になってしまったということである。つまり共産主義や党への忠誠など過去の遺物となってしまった新しい世代にとって、追放された人物にしろ、追放した人物にしろ、古いイデオロギーの中でドタバタしていた似たもの同士にしか見えない、ということだ。こうして冗談によって破滅させられたルドヴィークの人生は、その悲劇的な破滅までが冗談にされてしまった。
ルドヴィークはさとる、歴史の中で正しく振舞う機会は一度しかないのだと。自分がゼマーネクに復讐する機会は、自分が弾劾されていたその時以外になかった。ゼマーネクが集会の壇上で滔々と弁舌をぶっているその時にこそ、駆け寄ってその顔を殴りつけてやるべきだったのだと。
この小説は、当時の共産主義政権に対する糾弾にしてはアイロニカルで斜に構えすぎていると思われるかも知れない。作者のクンデラはこれをラヴ・ストーリーと呼んでいるが、ラヴ・ストーリーにしてはルドヴィークとルツィエの関係は曖昧で、劇的な展開にも結末にも欠け、中途半端だと思われるかも知れない。復讐譚としても溜飲が下がらない、苛立たしい作品と言われるだろう(卑劣なゼマーネクは勝ち誇り、幸せに満ち足りた人物として物語を立ち去っていく)。それではこの小説の核心はどこにあるのだろうか。
「冗談」のタイトルが示すように、本書は人々の人生を支配する不可解な、超越的なメカニズム(つまり歴史のメカニズム)を描き出したものであると同時に、人々が人生の中で何かを選択する時、その裏で作動する隠れたメカニズムを描き出したものでもある。人々はさまざまな動機で物事を選択するが、その動機は(イデオロギーや大義名分、打算や功利主義ですら)真の動機ではなく、さらにその下に決定的なキーワードが隠されている、とクンデラは考える。これは『不滅』の中でクンデラがグルントと名づけたものだが、グルントはイデオロギーの対立や相違とはほとんど関係がない。たとえば全体主義国家の独裁者と民主主義国家の議員が同じグルントに従って行動している、ということがありうる。この作品では登場人物たちの行動はすべて二重、三重に解釈されるか、あるいは解釈の余地が暗示される。世情に合わせて態度を変えるゼマーネクは果たして体制迎合者なのか、反体制者なのか。それは彼の真実とは無関係である。彼の真実とは、常にその時代の「最高権威」「最高審判者」に迎合する、というものだ(体制が若者が馬鹿にされる無難でみじめな存在に成り下がった時代には、若い世代の人気こそが最高権威になる)。
ルドヴィークはルツィエへの愛を自分の人生における聖域、もっとも真実な感情と考えた。しかし長い年月の後、故郷でルツィエを見かけた時に彼は悟る、自分が愛したルツィエは自分の鏡像だったのだと。ルドヴィークは悲劇的な自分の人生の姿に合わせた彼女の姿を愛していた。従ってその人生の状況が消えた時、自分が愛したルツィエは消えた。本物のルツィエは、自分が愛したルツィエとは異なる女だったのである。
こうした考察は本書のあらゆるエピソードを彩っている。なぜルドヴィークはあんなくだらない冗談を書いたのか。なぜルツィエに肉体の愛を拒まれた時、ルドヴィークはあれほど逆上したのか。なぜコストカはルツィエを救おうとしたのか。クンデラの視線は人間の行為を司る真の動機をあぶり出す。人間が不可解な行動を取るとき、勇敢な、あるいは卑劣な、あるいは自己犠牲的な、あるいは愚かな行動を取るとき、何がそうさせるのか。それを豊富なメタファーによってスリリングに、詩的に表現していくクンデラの変幻自在のエクリチュールにこそ、本書を読む醍醐味が存在する。
クンデラによれば、本書のアイデアは「墓場の花を盗んで恋人に贈った女」のついての記事を読んだ時に生まれたらしい。だとすれば、『冗談』はルツィエのイメージを核として生まれた小説であり、決して歴史哲学や共産主義批判が出発点ではないのだ。「『冗談』はラヴ・ストーリーなのです」というクンデラの言葉はそういう意味だと思う。ルツィエは本書における主要人物の中で、唯一自らの語りを持たないキャラクターである。そのため多くの男の人生にかかわって重要な役割を演じながら、自らは幻のままに留まる。このミステリアスで多義的なルツィエこそ、本書『冗談』を中心点で支えるポエジーの泉である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます