◆『日本とは何か (講談社文庫) 』
』
堺屋太一のこの本は、1991年に出版されている。私は1993年に読んでいるから、ざっと20年前だ。最近読み直してみて、私が「日本文化のユニークさ」7項目として取り上げてきたこととかなり重なることを改めて感じた。私がこの本から直接影響を受けていた部分もあるだろうが、それよりも、こ本に書かれた内容がある程度、共通認識になっており、間接的にその影響を受けた面もあるだろう。日本文化論や日本人論において、それだけ影響力のあった本だと思う。
ただし、この本にも限界はある。それは、狩猟時代の文明は「今日の文明を考えるうえでどの程度の影響力を持つかは疑問だ」とし、農耕以前の時代を視野に入れていないことだ。したがって、日本とは何かを考える上で縄文時代が持つ意味についてもほとんど考慮しない。しかし私にとっては、「日本文化のユニークさ」を考える上で縄文時代が果たした役割は、ますます重要だと感じられるようになっている。そうした視点の違いからこの本を考え直してみたいと思った。
この本の第一章「平成の日本」は、今から20年以上前の日本の状況を語っており、抱える課題も現代とだいぶ違うので触れない。第二章「平和と強調を育てた『風土』」で歴史的な視点からの日本論が始まるが、その最初の節の見出しは「稲作からはじまった日本文化」である。この見出しからしてすでに縄文時代からの視点がない。したがって堺屋には、「日本文化のユニークさ」7項目のうち、
(1)漁撈・狩猟・採集を基本とした縄文文化の記憶が、現代に至るまで消滅せず日本人の心や文化の基層として生き続けている。
(2)ユーラシア大陸の父性的な性格の強い文化に対し、縄文時代から現代にいたるまで一貫して母性原理に根ざした社会と文化を存続させてきた。
のような視点はない。7項目のうちまず関係するのは、「(3)ユーラシア大陸の穀物・牧畜文化にたいして、日本は穀物・魚貝型とも言うべき文化を形成し、それが大陸とは違う生命観を生み出した」である。
日本は温暖湿潤で、険しい山地と狭い平野によって構成されているので、水田稲作には向いているが牧畜には不向きだ。日本の歴史には牧畜が存在せず、厳密には有畜農業の経験も乏しい。だから日本の歴史と文明は、牧畜を飛ばして稲作とともに始まったと堺屋はいう。稲作は、面積当たりの収穫量が高いが、一方で労働投入量も非常に高く、しかも家族の単位を超えた共同作業を必要とする。村落共同体による勤勉な共同作業が、勤勉で集団志向という日本人の基本的な性格を作ったというのは確かなことだろう。
稲作を始めたあと、牧畜や有畜農業をほとんど知らず、家畜とのかかわりが少なかったことが日本人にどのような生命観を持たせたかは、このブログでもすでに詳しく触れた。
日本文化のユニークさ04:牧畜文化を知らなかった
日本文化のユニークさ05:人と動物を境界づけない
日本文化のユニークさ06:日本人の価値観・生命観
堺屋が指摘するのは、牧畜や有畜農業からは奴隷制度が発達しやすい条件が生まれるということである。家畜を使役するとは、意思をもった相手を制御することだ。そこに支配・被支配の関係が生まれる。そこから、意思ももった相手を支配する技術と、それを正当化する思想が生まれる。キリスト教がその正当化のためどう機能したかは、上にリンクした記事で詳しく検討した。そして日本人は、意思あるものを支配した経験が乏しく、そのせいか、大規模な奴隷制度が発達しなかったのである。
このブログでは、牧畜を行わず、稲作・魚介型の文明を育んできた日本を、ユーラシアの文明に対し、次のような特徴をもつものとしてまとめた。→日本文化のユニークさ40:環境史から見ると(2)
①牧畜による森林破壊を免れ、森に根ざす母性原理の文化が存続したこと。
②宦官の制度や奴隷制度が成立しなかったこと。
③遊牧や牧畜と密接にかかわる宗教であるキリスト教がほとんど浸透しなかったこと。
④遊牧や牧畜を背景にした、人間と他生物の峻別を原理とした文化とは違う、動物も人間も同じ命と見る文化を育んだ。
ここでは詳述しないが、これらは多かれ少なかれ縄文時代以来の日本の文化を抜きにしては語れない。たとえば、日本列島に有畜農業がほとんどなかったのは、弥生人が持ち込まなかったのか、縄文人が取り入れなかったのかという問題もあるわけで、少なくともはじめから縄文文化を無視して論じるべきではない。また、日本にキリスト教がほとんど浸透しなかったのは、私たちが無意識に持っている縄文的な生命観とキリスト教とのそれとの間にに大きな隔たりがあることも一つの理由だろう。→日本文化のユニークさ02:キリスト教が広まらなかった理由
なお、堺屋は日本の特殊な気象と地形から、牧畜と大規模な奴隷制に加え、都市国家をも持つことがなかったという。稲作は、大量の労働力を必要とした。そのため隣の土地を支配した「王」は、そこの住民を殺すよりも働かせた。それゆえ住民もまた、堅固な城壁に立てこもってまで抵抗することはなかった。つまり城壁を巡らせた都市国家を作る必要を感じなかったのである。
こうして日本人は、強烈は支配・被支配の関係を嫌う「嫉妬深い平等主義者」になったという。
堺屋太一のこの本は、1991年に出版されている。私は1993年に読んでいるから、ざっと20年前だ。最近読み直してみて、私が「日本文化のユニークさ」7項目として取り上げてきたこととかなり重なることを改めて感じた。私がこの本から直接影響を受けていた部分もあるだろうが、それよりも、こ本に書かれた内容がある程度、共通認識になっており、間接的にその影響を受けた面もあるだろう。日本文化論や日本人論において、それだけ影響力のあった本だと思う。
ただし、この本にも限界はある。それは、狩猟時代の文明は「今日の文明を考えるうえでどの程度の影響力を持つかは疑問だ」とし、農耕以前の時代を視野に入れていないことだ。したがって、日本とは何かを考える上で縄文時代が持つ意味についてもほとんど考慮しない。しかし私にとっては、「日本文化のユニークさ」を考える上で縄文時代が果たした役割は、ますます重要だと感じられるようになっている。そうした視点の違いからこの本を考え直してみたいと思った。
この本の第一章「平成の日本」は、今から20年以上前の日本の状況を語っており、抱える課題も現代とだいぶ違うので触れない。第二章「平和と強調を育てた『風土』」で歴史的な視点からの日本論が始まるが、その最初の節の見出しは「稲作からはじまった日本文化」である。この見出しからしてすでに縄文時代からの視点がない。したがって堺屋には、「日本文化のユニークさ」7項目のうち、
(1)漁撈・狩猟・採集を基本とした縄文文化の記憶が、現代に至るまで消滅せず日本人の心や文化の基層として生き続けている。
(2)ユーラシア大陸の父性的な性格の強い文化に対し、縄文時代から現代にいたるまで一貫して母性原理に根ざした社会と文化を存続させてきた。
のような視点はない。7項目のうちまず関係するのは、「(3)ユーラシア大陸の穀物・牧畜文化にたいして、日本は穀物・魚貝型とも言うべき文化を形成し、それが大陸とは違う生命観を生み出した」である。
日本は温暖湿潤で、険しい山地と狭い平野によって構成されているので、水田稲作には向いているが牧畜には不向きだ。日本の歴史には牧畜が存在せず、厳密には有畜農業の経験も乏しい。だから日本の歴史と文明は、牧畜を飛ばして稲作とともに始まったと堺屋はいう。稲作は、面積当たりの収穫量が高いが、一方で労働投入量も非常に高く、しかも家族の単位を超えた共同作業を必要とする。村落共同体による勤勉な共同作業が、勤勉で集団志向という日本人の基本的な性格を作ったというのは確かなことだろう。
稲作を始めたあと、牧畜や有畜農業をほとんど知らず、家畜とのかかわりが少なかったことが日本人にどのような生命観を持たせたかは、このブログでもすでに詳しく触れた。
日本文化のユニークさ04:牧畜文化を知らなかった
日本文化のユニークさ05:人と動物を境界づけない
日本文化のユニークさ06:日本人の価値観・生命観
堺屋が指摘するのは、牧畜や有畜農業からは奴隷制度が発達しやすい条件が生まれるということである。家畜を使役するとは、意思をもった相手を制御することだ。そこに支配・被支配の関係が生まれる。そこから、意思ももった相手を支配する技術と、それを正当化する思想が生まれる。キリスト教がその正当化のためどう機能したかは、上にリンクした記事で詳しく検討した。そして日本人は、意思あるものを支配した経験が乏しく、そのせいか、大規模な奴隷制度が発達しなかったのである。
このブログでは、牧畜を行わず、稲作・魚介型の文明を育んできた日本を、ユーラシアの文明に対し、次のような特徴をもつものとしてまとめた。→日本文化のユニークさ40:環境史から見ると(2)
①牧畜による森林破壊を免れ、森に根ざす母性原理の文化が存続したこと。
②宦官の制度や奴隷制度が成立しなかったこと。
③遊牧や牧畜と密接にかかわる宗教であるキリスト教がほとんど浸透しなかったこと。
④遊牧や牧畜を背景にした、人間と他生物の峻別を原理とした文化とは違う、動物も人間も同じ命と見る文化を育んだ。
ここでは詳述しないが、これらは多かれ少なかれ縄文時代以来の日本の文化を抜きにしては語れない。たとえば、日本列島に有畜農業がほとんどなかったのは、弥生人が持ち込まなかったのか、縄文人が取り入れなかったのかという問題もあるわけで、少なくともはじめから縄文文化を無視して論じるべきではない。また、日本にキリスト教がほとんど浸透しなかったのは、私たちが無意識に持っている縄文的な生命観とキリスト教とのそれとの間にに大きな隔たりがあることも一つの理由だろう。→日本文化のユニークさ02:キリスト教が広まらなかった理由
なお、堺屋は日本の特殊な気象と地形から、牧畜と大規模な奴隷制に加え、都市国家をも持つことがなかったという。稲作は、大量の労働力を必要とした。そのため隣の土地を支配した「王」は、そこの住民を殺すよりも働かせた。それゆえ住民もまた、堅固な城壁に立てこもってまで抵抗することはなかった。つまり城壁を巡らせた都市国家を作る必要を感じなかったのである。
こうして日本人は、強烈は支配・被支配の関係を嫌う「嫉妬深い平等主義者」になったという。












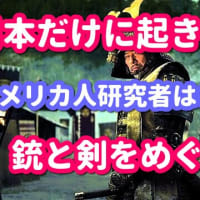




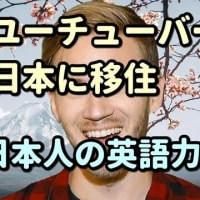


期待してます。
私個人としては、「山賊と権力」にも触れていだだければ
かなり和洋の差について迫れるとは思うのですが。
「山賊と権力」については私はよくわかりません。
調べてみますが、
何か教えていただければ幸いです。
という印象を持っています
それもとても忠実で他者の自由を制限しあう奴隷のような…
ええと、乱暴かつ短めに説明しますと
西洋=山賊(略奪者)が勢力を拡大して権力者になる(事が可能)
日本=山賊から地域住民を守護するものが(実質的な)権力者になる
と言った所でしょうか(ホントに乱暴ですが(汗)
西洋ではたとえ山賊あがりの騎士であっても教会に誓を立てて
認められれば領主として民衆にも認められる。(ドイツ騎士団とか
一方日本では、山賊あがりの武士から始まった大名もいましたが
結局民草の支援無く長続きしない。(というか支持しないでしょ感覚的に
と言う話です。
さっそくありがとうございました。
なるほどそういう意味でしたが。
興味深い指摘ですね。
じっくり調べてみたいです。
城壁というか、堀の遺跡も見つかっていたと記憶してますが。
あと、縄文人と弥生人は緩やかに融合したというのが定説のようですが、どの様な根拠からそうなっているのでしょうか。教えていただけると有り難いです。
環濠集落のことですね。吉野ヶ里などの環濠集落は村とは言えても、都市と言えるかどうか。
また環濠集落自体は、稲作文化と同時に大陸からもたらされ、次第に東日本に広がったようです。大陸の文化が持ち込まれたため、戦いがあったのは確かでしょうが、村同士の稲作に適した土地争いが原因だったようです。
しかし、2世紀後半から3世紀には消えていったといいます。
縄文と弥生の融合については、まとめてブログで書いてみたい気もするので、そちらで答えさせていただくことにします。