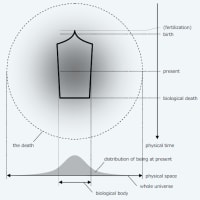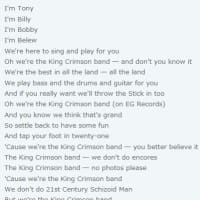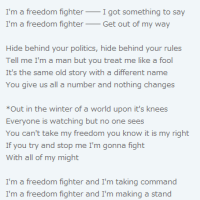そもそも働いたことがないか、ほとんどやったことのない人が「働きたくない」と言い出すのは奇妙なことなのである。そういう人は本当に、重症のうつ病の人のように指一本動かすことすらしんどいのかというと、ほとんどの場合そんなことはない。たとえばゲームをやったりすることなら非常に熱心だったりするわけである。それをすれば大なり小なり心身を疲労させるという意味ではゲームだってある種の労働には違いないのである。そういうのは全然へっちゃらでできるのに、いわゆる賃労働(あるいは家事労働)は嫌なのである。
どうして賃労働や家事労働に限って、しかもやればそれなりの報酬(後者のそれは金銭ではないが)があるのは判っているというような場合でさえ拒否感のようなものが生じるのか、それは昔からマルクスのような人がちゃんと言っていることで、それらが「疎外」された労働だからだということになる。わかりやすく言えばそうした労働に従事することは大なり小なり自分が自分であることを奪われているような状況に身を置くことである。
その違いはたとえば、たまたま趣味を仕事にしてしまった人が例外なく痛感させられることである。やってることの具体的な中身はほとんどまったく同じことなのに、趣味でやっている間はあれほど面白い、寝食を忘れるほど熱中してやれていたことが、稼ぎのための仕事としてやるようになった瞬間から、すべてはまったく、えも言われぬような最悪の苦痛の経験にしかならなくなる。もう1分1秒でもこんな作業にかかずらわっていたくはないというようなひどい思いの経験に変貌してしまうわけである。この感じの切り替わりは本当に一瞬のことで、世界が突然暗転したかのようにさえ感じられるものである。
裏を返せば「働きたくない」というのは要するにその痛苦や痛苦の予感を恐れて忌避しているわけだから、それさえ取り除いてしまうことができたとすれば、たぶん働くことは苦痛でも何でもなくなるわけである。マルクスなんかの場合はその根源的な理由を資本主義的な生産のあり方というところに求めたので、要は資本主義体制、資本主義に特有の生産のあり方といったものを打倒すれば人間は解放されるのだ、と、簡単に言えばそう主張したわけである。もちろん本当はそこまで安直な話ではないけれど、基本はそうだし、後に「マルクス主義」と呼ばれるようになったものは事実その安直な図式をそのまま実践課題にしたわけである。
ひと口に資本主義体制と言って決してヤワなものではない、よく組織され、ガチガチに固められた強度を備えているわけで、それを打倒するというのは誰がどんな風にすれば可能なのかと言ったら、まさにその資本主義生産の中で組織され、その強度の一部となっている労働者階級がそれを担うことによって可能なのだ、という論理をレーニンが発明したのである。ひらたく言えばあるものを最もよく破壊できるのは、それを作っている当の人間だということである。その場合の唯物論というのはだから、「大阪城を作ったのは豊臣秀吉(上部構造)ではなく大工さん(下部構造)である」という、まったくドリフのギャグみたいな認識のことにほかならないのである。そうは言っても確かに、難攻不落の大阪城といえども大工さんの気が変わればひとたまりもなく崩れ落ちてしまうはずである。
あと必要なのは「生産も破壊もリモコン次第」ということで、誰がそのリモコンを奪取してスイッチを逆倒するのか、ということになる。それがイデオロギー的によく訓練された共産党だというわけである。労働者階級は鉄人28号で共産党が正太郎君である。この時点で肝心の労働者階級はすっかりロボ扱いである上に、革命の正義だろうと何だろうと戦闘ロボが街を歩けばあらゆるものを破壊し尽くして回ることに違いはないわけで、ほかの人民大衆はひたすらエライ目に会わされるばかりのことになるのだが、しかし、これがどうも図に当たってしまった結果がソヴィエト革命だったのである。
どうして賃労働や家事労働に限って、しかもやればそれなりの報酬(後者のそれは金銭ではないが)があるのは判っているというような場合でさえ拒否感のようなものが生じるのか、それは昔からマルクスのような人がちゃんと言っていることで、それらが「疎外」された労働だからだということになる。わかりやすく言えばそうした労働に従事することは大なり小なり自分が自分であることを奪われているような状況に身を置くことである。
その違いはたとえば、たまたま趣味を仕事にしてしまった人が例外なく痛感させられることである。やってることの具体的な中身はほとんどまったく同じことなのに、趣味でやっている間はあれほど面白い、寝食を忘れるほど熱中してやれていたことが、稼ぎのための仕事としてやるようになった瞬間から、すべてはまったく、えも言われぬような最悪の苦痛の経験にしかならなくなる。もう1分1秒でもこんな作業にかかずらわっていたくはないというようなひどい思いの経験に変貌してしまうわけである。この感じの切り替わりは本当に一瞬のことで、世界が突然暗転したかのようにさえ感じられるものである。
裏を返せば「働きたくない」というのは要するにその痛苦や痛苦の予感を恐れて忌避しているわけだから、それさえ取り除いてしまうことができたとすれば、たぶん働くことは苦痛でも何でもなくなるわけである。マルクスなんかの場合はその根源的な理由を資本主義的な生産のあり方というところに求めたので、要は資本主義体制、資本主義に特有の生産のあり方といったものを打倒すれば人間は解放されるのだ、と、簡単に言えばそう主張したわけである。もちろん本当はそこまで安直な話ではないけれど、基本はそうだし、後に「マルクス主義」と呼ばれるようになったものは事実その安直な図式をそのまま実践課題にしたわけである。
ひと口に資本主義体制と言って決してヤワなものではない、よく組織され、ガチガチに固められた強度を備えているわけで、それを打倒するというのは誰がどんな風にすれば可能なのかと言ったら、まさにその資本主義生産の中で組織され、その強度の一部となっている労働者階級がそれを担うことによって可能なのだ、という論理をレーニンが発明したのである。ひらたく言えばあるものを最もよく破壊できるのは、それを作っている当の人間だということである。その場合の唯物論というのはだから、「大阪城を作ったのは豊臣秀吉(上部構造)ではなく大工さん(下部構造)である」という、まったくドリフのギャグみたいな認識のことにほかならないのである。そうは言っても確かに、難攻不落の大阪城といえども大工さんの気が変わればひとたまりもなく崩れ落ちてしまうはずである。
あと必要なのは「生産も破壊もリモコン次第」ということで、誰がそのリモコンを奪取してスイッチを逆倒するのか、ということになる。それがイデオロギー的によく訓練された共産党だというわけである。労働者階級は鉄人28号で共産党が正太郎君である。この時点で肝心の労働者階級はすっかりロボ扱いである上に、革命の正義だろうと何だろうと戦闘ロボが街を歩けばあらゆるものを破壊し尽くして回ることに違いはないわけで、ほかの人民大衆はひたすらエライ目に会わされるばかりのことになるのだが、しかし、これがどうも図に当たってしまった結果がソヴィエト革命だったのである。