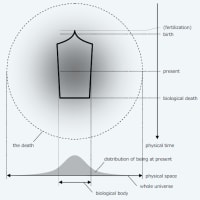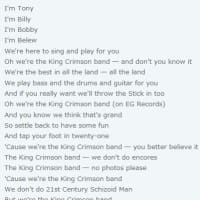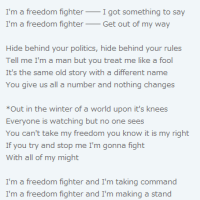3-12 複数の原因をもつ半知識(承前)
もし特定の対象どうしが常に連接しあっているとすれば、生活や行為をどうすればいいかはまったく楽な話だということになろう。恐れるべきことは己の判断の間違いだけで、自然の不確実性を懸念する理由はまったくないわけである。けれども実際は、ある観察に反する別の観察がありうる。また原因と結果の順序が、以前の経験とは異なることがしょっちゅうあるわけである。我々はこの不確実を考慮して推理を変更し、互いに反する出来事を考察しなければならなくなる。そこで問うべき最初の問いは「反対(contrariety)ということの本性と原因は何か」である。
普通の人々は対象を額面通りに受け取るものである。そこで出来事の不確実さは原因の不確実さと見なされる。普通の人々にとって原因とは、それが作用する途中で何ら障害されることがなかったとしても、時々わけもなくずっこけるような何かなのである。哲学者の見方によればそうではない。哲学者によれば自然というものは、そのいたるところに微小な(あるいは見えないところに)無数の動因や原理を隠し持っているのである。通例に反する出来事が生じるのは、原因がわけもなくずっこけたのではなく、反対事象を引き起こす原因のヒミツの作用から生じるのであり、少なくともその可能性があるのだということになる。この可能性は、さらなる観察によって厳密に精査してみて、通例に反する結果は通例に反する(別の)原因から生じている、つまり複数の原因が互いに妨害し対立していることから生じていることがわかれば、確実性に変わる。たとえば農夫は時計が止まる理由について「このポンコツはしょっちゅう機嫌を損ねやがるんだ」という以上の理由を挙げることができない。けれども時計職人は(その時計を調べて)バネや振り子に別条はなく、常に正常な力が歯車に加わっていること、しかしどうやら時計の動き全体を止めるようなゴミが入っていてちゃんと動作しなくなるようだ、といったことを容易に見抜くものである。だいたいこんなような事例のいくつかから、哲学者は、あらゆる因果の結合はすべて必然的なものであって、ときどき生じる例外は反対事象を引き起こす原因のヒミツの作用から生じるのだ、という原則を作るのである。
(つづく)
もし特定の対象どうしが常に連接しあっているとすれば、生活や行為をどうすればいいかはまったく楽な話だということになろう。恐れるべきことは己の判断の間違いだけで、自然の不確実性を懸念する理由はまったくないわけである。けれども実際は、ある観察に反する別の観察がありうる。また原因と結果の順序が、以前の経験とは異なることがしょっちゅうあるわけである。我々はこの不確実を考慮して推理を変更し、互いに反する出来事を考察しなければならなくなる。そこで問うべき最初の問いは「反対(contrariety)ということの本性と原因は何か」である。
普通の人々は対象を額面通りに受け取るものである。そこで出来事の不確実さは原因の不確実さと見なされる。普通の人々にとって原因とは、それが作用する途中で何ら障害されることがなかったとしても、時々わけもなくずっこけるような何かなのである。哲学者の見方によればそうではない。哲学者によれば自然というものは、そのいたるところに微小な(あるいは見えないところに)無数の動因や原理を隠し持っているのである。通例に反する出来事が生じるのは、原因がわけもなくずっこけたのではなく、反対事象を引き起こす原因のヒミツの作用から生じるのであり、少なくともその可能性があるのだということになる。この可能性は、さらなる観察によって厳密に精査してみて、通例に反する結果は通例に反する(別の)原因から生じている、つまり複数の原因が互いに妨害し対立していることから生じていることがわかれば、確実性に変わる。たとえば農夫は時計が止まる理由について「このポンコツはしょっちゅう機嫌を損ねやがるんだ」という以上の理由を挙げることができない。けれども時計職人は(その時計を調べて)バネや振り子に別条はなく、常に正常な力が歯車に加わっていること、しかしどうやら時計の動き全体を止めるようなゴミが入っていてちゃんと動作しなくなるようだ、といったことを容易に見抜くものである。だいたいこんなような事例のいくつかから、哲学者は、あらゆる因果の結合はすべて必然的なものであって、ときどき生じる例外は反対事象を引き起こす原因のヒミツの作用から生じるのだ、という原則を作るのである。
(つづく)