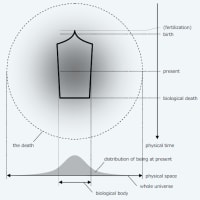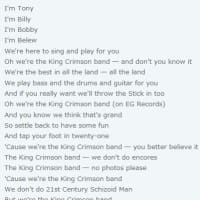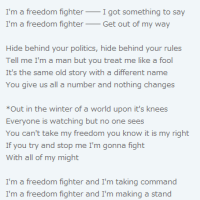タグに日本語が使えるようになって以来、twitterはすっかり大喜利会場のようになってしまっているわけである。面白かったのを拾ってみる。
ログがねずみ算・・・?この「ログ」とは日録(log)のことじゃなくて対数(logarithm)のことだと気づくまでしばらく考え込んでしまった。気づいたら気づいたで、この主の通っていた高校はいったい何だと教えていたのだろうということが疑問に思えてきた。
正確に言えばねずみ算というよりはねずみ算の逆なわけである。世代ごとに個体数が指数関数的(幾何級数的)に増えて行くさまを「ねずみ算」式というわけだから、対数というのはその逆関数である。まあ上の呟きはそこまで汲んだ上で「氷解した」ということなのだろうけれども。
ついでに、自分が高校生の時はどうだったっけと思いだそうとしたら、これが思い出せない。わたしは小学生のとき関数電卓で遊んで(ちょうどゲームボーイくらいの大きさだった)いるうちに覚えてしまったのと、電気工作少年だったからデシベル計算のために簡単な対数表はアタマに入っていた(電子回路をいじるならそのくらい覚えておけ、と「ラジオの製作」の記事に書いてあった)。電卓がないときはそのへんの紙や板に対数目盛を書いて即席の計算尺を作ったりもした。そんなものたいした役には立たないが、それも遊びというかイタズラのうちだった。「こんなんで掛け算ができるんだぜ?」「おー便利だな」なんて。
中学生になって計算機屋になればなったで、二分探索や高速ソートといったアルゴリズムの計算量にはlogが出てくる。なぜlogなのか。プログラムを書くことを知っていれば説明されなくてもわかるわけである。きわめつけは半導体の容量あたり価格の「ムーアの法則」のグラフであった(これは確か「トランジスタ技術」に載っていた)。対数グラフの意味と威力を理解するのにあれほど印象的なものは他になかった。
昔の理科系少年というのはだいたいこんなものであったわけなのである。学校で習うことはたいてい、すでに知っていることだった。その時までに知らなくて学校で初めて習ったようなことというのはたいてい、後々までめったに使うことのない受験テクニックの類ばかりだった。中高だろうと大学だろうと、いまのワカモノがこの手のことを「学校教育」から教わるよりほかになくなってしまったのだとしたら、それはさぞかしつまらない経験であろうことで、気の毒というか何というか、どうしたものなんだろうか。
| 「ログとはねずみ算の考え方です」 大学に入ってから聞いた。たいしたことじゃないけど、それまでの人生の疑問が氷解した瞬間。ぶっちゃけ、中高時代に教えてほしかった… (asterte) |
ログがねずみ算・・・?この「ログ」とは日録(log)のことじゃなくて対数(logarithm)のことだと気づくまでしばらく考え込んでしまった。気づいたら気づいたで、この主の通っていた高校はいったい何だと教えていたのだろうということが疑問に思えてきた。
正確に言えばねずみ算というよりはねずみ算の逆なわけである。世代ごとに個体数が指数関数的(幾何級数的)に増えて行くさまを「ねずみ算」式というわけだから、対数というのはその逆関数である。まあ上の呟きはそこまで汲んだ上で「氷解した」ということなのだろうけれども。
ついでに、自分が高校生の時はどうだったっけと思いだそうとしたら、これが思い出せない。わたしは小学生のとき関数電卓で遊んで(ちょうどゲームボーイくらいの大きさだった)いるうちに覚えてしまったのと、電気工作少年だったからデシベル計算のために簡単な対数表はアタマに入っていた(電子回路をいじるならそのくらい覚えておけ、と「ラジオの製作」の記事に書いてあった)。電卓がないときはそのへんの紙や板に対数目盛を書いて即席の計算尺を作ったりもした。そんなものたいした役には立たないが、それも遊びというかイタズラのうちだった。「こんなんで掛け算ができるんだぜ?」「おー便利だな」なんて。
中学生になって計算機屋になればなったで、二分探索や高速ソートといったアルゴリズムの計算量にはlogが出てくる。なぜlogなのか。プログラムを書くことを知っていれば説明されなくてもわかるわけである。きわめつけは半導体の容量あたり価格の「ムーアの法則」のグラフであった(これは確か「トランジスタ技術」に載っていた)。対数グラフの意味と威力を理解するのにあれほど印象的なものは他になかった。
昔の理科系少年というのはだいたいこんなものであったわけなのである。学校で習うことはたいてい、すでに知っていることだった。その時までに知らなくて学校で初めて習ったようなことというのはたいてい、後々までめったに使うことのない受験テクニックの類ばかりだった。中高だろうと大学だろうと、いまのワカモノがこの手のことを「学校教育」から教わるよりほかになくなってしまったのだとしたら、それはさぞかしつまらない経験であろうことで、気の毒というか何というか、どうしたものなんだろうか。