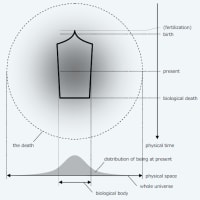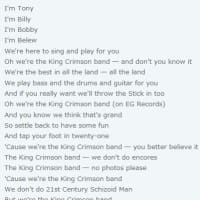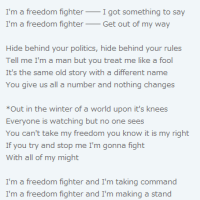タルスキの真理論については昨年出た飯田隆他「岩波講座 哲学〈3〉言語/思考の哲学」(岩波書店)(Amazon/7net) で簡潔平易な入門が読める、という書評を見つけた。リンク先のblogの主は本職の分析哲学の研究者である。ど素人のわたしがつべこべ言うよりこのサイトの書評を読む方が、絶対的に信頼できるはずである。
で簡潔平易な入門が読める、という書評を見つけた。リンク先のblogの主は本職の分析哲学の研究者である。ど素人のわたしがつべこべ言うよりこのサイトの書評を読む方が、絶対的に信頼できるはずである。
モデル論とかは数学基礎論にもかかわっているし、情報科学・計算機科学の理論方面では、プログラミング言語の意味論とかの超↑高級なところでたまに(・・・でもないか。そのあたりの専門家にとってはむしろ基本中の基本だ)このあたりの議論のお世話になったりする。だからわたしも本当はど素人でもない、全然知らないわけではないんだけど、ろくにわけも判らずにクリプキやらタルスキやらの本をめくったりしていた日々も、思えばもう十年前のことなのである。さすがに忘れちゃったよw 今のわたしはただのプログラマで、計算機の理論屋じゃないからな。
サールの言語行為論はこのあたりのほんとに形式的な言語論とは重なるようで実は全然重ならなかったりする(実際、形式言語の勉強をやってる間は、サールのサの字も聞かなかったよw)のだが、言語哲学と言っても片方にはこういうのを延々やってる人達がいるというのを知っておくと、サールのような議論の意義というか重要性が逆側からよく見えてくるような気がする・・・なんて、まあこんなことが言えるのも、わたしが研究者の道を放擲した人だから言えることなわけだ。そうでなかったら言語行為論なんて(形式的な理論の側から見れば)変なものに首突っ込んでる暇は、物理的にも精神的にもないはずである。それがプロの研究者の道なのである。
そう言やあ、サール先生はサール先生で、twitterで「Possible worlds semantics is the worst thing to happen to philosophy since the ontological proof(可能世界意味論は神の存在論的証明以後の哲学で最悪の事件だ)」などと呟いておられましたな。twitterだから軽い気持ちで言ってみただけなのか、逆にだからこそ本音だったりするのか、それは判らないけど。なーんとなく判るような気もするんだけどネ。
モデル論とかは数学基礎論にもかかわっているし、情報科学・計算機科学の理論方面では、プログラミング言語の意味論とかの超↑高級なところでたまに(・・・でもないか。そのあたりの専門家にとってはむしろ基本中の基本だ)このあたりの議論のお世話になったりする。だからわたしも本当はど素人でもない、全然知らないわけではないんだけど、ろくにわけも判らずにクリプキやらタルスキやらの本をめくったりしていた日々も、思えばもう十年前のことなのである。さすがに忘れちゃったよw 今のわたしはただのプログラマで、計算機の理論屋じゃないからな。
サールの言語行為論はこのあたりのほんとに形式的な言語論とは重なるようで実は全然重ならなかったりする(実際、形式言語の勉強をやってる間は、サールのサの字も聞かなかったよw)のだが、言語哲学と言っても片方にはこういうのを延々やってる人達がいるというのを知っておくと、サールのような議論の意義というか重要性が逆側からよく見えてくるような気がする・・・なんて、まあこんなことが言えるのも、わたしが研究者の道を放擲した人だから言えることなわけだ。そうでなかったら言語行為論なんて(形式的な理論の側から見れば)変なものに首突っ込んでる暇は、物理的にも精神的にもないはずである。それがプロの研究者の道なのである。
そう言やあ、サール先生はサール先生で、twitterで「Possible worlds semantics is the worst thing to happen to philosophy since the ontological proof(可能世界意味論は神の存在論的証明以後の哲学で最悪の事件だ)」などと呟いておられましたな。twitterだから軽い気持ちで言ってみただけなのか、逆にだからこそ本音だったりするのか、それは判らないけど。なーんとなく判るような気もするんだけどネ。