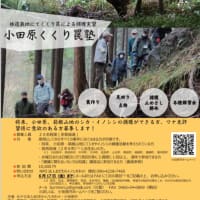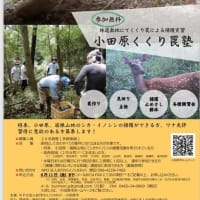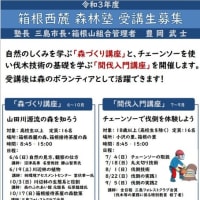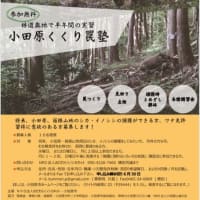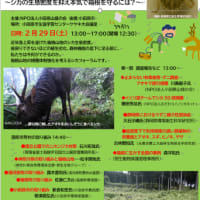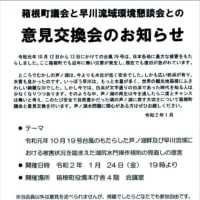平元 泰輔(1997) 相模湾における定置網型の変遷-2 大型定置網型-(1),神奈川県水産総合研究所研究報告第2号,25~47
http://www.agri-kanagawa.jp/suisoken/pdf/SUISKN/suiskn2-05.pdf
P27~28の「表1-2 年別漁場別ブリ漁獲尾敷数 1925 年~1994 年(大正14 年~平成6年)」の数値をグラフ化

ブリ漁獲尾数は昭和5年(1930年)189430尾であったが昭和7年492864尾、昭和8年528604尾となり、その反動か丹那トンネルが開通し東海道線が熱海経由になった昭和9年は28253尾と約1/20まで激減した。
その後は徐々に回復し太平洋戦争が始まる昭和16年は185564尾、戦争中の大量伐採があっても影響はまだ出ずに昭和19年は320459尾までになった。昭和20年の終戦を経て昭和21年は79980尾と減少、ここにきて大量伐採の影響が出てきたのであろう。以降、復興期の木材需要にあっても人工造林の効果がまさり漁獲は増加していき、人工造林第一回目ピーク(43.3万ha)の昭和29年には575381尾を数えるまでになった。
しかし高度成長期が始まった昭和30年からは漁獲は減少また減少となる。昭和35年は、木材輸入自由化が始まり、香川県ではハマチ養殖が成功し、昭和36年は、人工造林第二回目ピーク(41.5万ha)となりほとんどが拡大造林で、以後10年間は毎年30万ha前後の高い水準で拡大造林が行われた。昭和38年は20079尾まで減少したのである。
木材輸入前面自由化が実施され、西湘バイパス着工のあった昭和39年からは漁獲の回復の兆しがあったが、西湘バイパスの一部供用を開始した昭和42年は1万尾をも割り5277尾まで低下した。
昭和46年は50841尾であったが、その後、箱根町を起点に小田原市と真鶴町を通り湯河原町を終点とする白銀林道が全線開通し、養殖ハマチの需要が関西から関東に拡大し、そして高度成長期が終わった昭和48年は8440尾、酒匂川取水堰が供用開始した昭和49年は3284尾、三保ダム完成の昭和54年は7663尾、そして巻き網漁が急激に増えていき、平成3年は39尾とブリは全くいなくなってしまった。
すなわち、人が豊かさを望んだ高度成長期が始まる昭和30年までは、自然の中で人が生活していました。ブリを獲り過ぎてブリが減ってもやがて回復し、戦時中・復興期の大量伐採にあってもまだ自然が残っており回復しました。しかし、高度成長期の昭和30年から昭和48年の人工林の拡大造林、西湘バイパス、酒匂川取水堰、そして、それ以降の三保ダム、養殖ハマチ用のモジャコの漁獲、巻き網魚による若年ブリの漁獲、人工林の手入れ遅れ、あるいは温暖化など、人の中に自然が存在するようになり、自然が少なくなったのと同じように自然の一員であるブリはいなくなってしまったと思うのです。
自然を再認識した今、問われているのは人のありようではないでしょうか。
【寄稿:ブリ森サポーター 小貝】
http://www.agri-kanagawa.jp/suisoken/pdf/SUISKN/suiskn2-05.pdf
P27~28の「表1-2 年別漁場別ブリ漁獲尾敷数 1925 年~1994 年(大正14 年~平成6年)」の数値をグラフ化

ブリ漁獲尾数は昭和5年(1930年)189430尾であったが昭和7年492864尾、昭和8年528604尾となり、その反動か丹那トンネルが開通し東海道線が熱海経由になった昭和9年は28253尾と約1/20まで激減した。
その後は徐々に回復し太平洋戦争が始まる昭和16年は185564尾、戦争中の大量伐採があっても影響はまだ出ずに昭和19年は320459尾までになった。昭和20年の終戦を経て昭和21年は79980尾と減少、ここにきて大量伐採の影響が出てきたのであろう。以降、復興期の木材需要にあっても人工造林の効果がまさり漁獲は増加していき、人工造林第一回目ピーク(43.3万ha)の昭和29年には575381尾を数えるまでになった。
しかし高度成長期が始まった昭和30年からは漁獲は減少また減少となる。昭和35年は、木材輸入自由化が始まり、香川県ではハマチ養殖が成功し、昭和36年は、人工造林第二回目ピーク(41.5万ha)となりほとんどが拡大造林で、以後10年間は毎年30万ha前後の高い水準で拡大造林が行われた。昭和38年は20079尾まで減少したのである。
木材輸入前面自由化が実施され、西湘バイパス着工のあった昭和39年からは漁獲の回復の兆しがあったが、西湘バイパスの一部供用を開始した昭和42年は1万尾をも割り5277尾まで低下した。
昭和46年は50841尾であったが、その後、箱根町を起点に小田原市と真鶴町を通り湯河原町を終点とする白銀林道が全線開通し、養殖ハマチの需要が関西から関東に拡大し、そして高度成長期が終わった昭和48年は8440尾、酒匂川取水堰が供用開始した昭和49年は3284尾、三保ダム完成の昭和54年は7663尾、そして巻き網漁が急激に増えていき、平成3年は39尾とブリは全くいなくなってしまった。
すなわち、人が豊かさを望んだ高度成長期が始まる昭和30年までは、自然の中で人が生活していました。ブリを獲り過ぎてブリが減ってもやがて回復し、戦時中・復興期の大量伐採にあってもまだ自然が残っており回復しました。しかし、高度成長期の昭和30年から昭和48年の人工林の拡大造林、西湘バイパス、酒匂川取水堰、そして、それ以降の三保ダム、養殖ハマチ用のモジャコの漁獲、巻き網魚による若年ブリの漁獲、人工林の手入れ遅れ、あるいは温暖化など、人の中に自然が存在するようになり、自然が少なくなったのと同じように自然の一員であるブリはいなくなってしまったと思うのです。
自然を再認識した今、問われているのは人のありようではないでしょうか。
【寄稿:ブリ森サポーター 小貝】