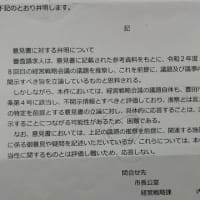7章 変動相場制下での財政破綻―欧州の経験
通貨が流通するのは価値が安定(信用)しているから。資金流出が止まらなくなった時、ドルなどやピットコインに変換する。国際金融のトリレンマ,①自由な資本移動、②為替レートの安定、③金融政策運営の自主性の3っつを同時に達成することはできない。
我が国は預金封鎖や財産税、デノミを断行した。アイスランドは国民の重い税負担で、資本移動の規制解除できたのは2017年3月の8年4ヶ月の後だった。我が国の財政事情は、アイスランド、キプロス、ギリシャが危機に突入した2008年より相当悪い。何も起こってないからとして、放漫財政をこのままにして良いのか。円安が物価高騰につながるだけでなく、通貨安が金融危機になりかねない。日本は1ドル150円を超えた時、円買いをし、10年国債の金利を0.5%まで許容した(その後マイナス金利とYCCなど解除)。外貨準備があるが、持続可能だろうか。連休前から日銀・政府は円買い介入した。)
8章 我が国の再生に向けて
わが国では、高所得者層ほど負担率は低下している。1億円の壁である。「経済成長なしで財政再建なし」で、税制も十分議論されず与党の税調で決まってしまう。1964年東京五輪から「60年償還ルール」ができた。1975年石油危機後から、建設国債から赤字国債が「特例国債」として制定された。60年償還ルールが放漫財政の主犯でないか。
真に独立した中央銀行としての抜本的な立て直しを。市場メカニズムの回復として、10年国債の金利の許容範囲(現在0.5%)の拡大、0%設定している10年国債金利を徐々に引き上げる。財政再建に向けて本腰を入れる。慶応大学深尾教授が「量的緩和、マイナス金利政策の財政コストと処理方法」を書いている。
日銀が、他の中央銀行が決して採用しないYCC政策を実施した結果、短期金利を0.2%上げただけで、あっという間に「逆ザヤ」に転落する。しかもETFを買い入れている。これ以上、財務の過度な悪化を招かないよう、日銀に段階的な正常化を取り組むことを促す。
政府も財政運営を見直すこと。国債発行額を減らす(軍事費倍加の岸田政権、緩和継続の植田総裁ではそれらの姿勢は見られない)。内閣府は26年度までプライマリーバランスの黒字化はできない、つまり国債発行は続けるとしている。自民党内では60年償還ルールを80年にするなどの議論がある。国債の元本も償還する気もないのか。市場の信用を失う。国債金利が急上昇するか、円安が一段と進展するかして、財政運営が行き詰まる。(いつか?)米国では国債は財源として考えられていなく、10年単位で償還を設計する。米政府もコロナ化で財政出動をやり過ぎたと認めた。政府、日銀に場当たり的でなく問題の所在を明らかにさせ、国民も甘えや無責任から脱却しなければならない。
私のコメント
植田総裁は、金融緩和を継続し、「物価目標2%」評価を1~1.5年でやる、と表明し危機意識が弱い。①アベノミクスの失敗を日銀・政府、国民が総括しなければ、小手先の円安解消に為替介入ではできないであろう。②自民党は金権腐敗政治を止めること、③武器の爆買いを止めること、防衛費の拡大をしない、④無駄な公共事業(万博、リニアなど)を止める、⑤消費税の減税(もちろん0%が好ましいが、財政的根拠と野党の合意も必要である)、⑥地方自治体から少子化対策の推進などである。これら金融・財政、経済再生を国民的共通政策の柱の1つにして、政権交代しかないように思われる。
少子化対策で西三河では給食の無償化(みよし、安城、豊田、碧南予定)、コミュニティバスの無料化が進んだ。豊田市では2月の市長選挙を機に、18歳医療費の通院無料、体育館の空調設置も前進した。しかし、小中の少人数学級、大学の奨学金制度(碧南市予定)、非正規の改善(みよし市方向)、非核自治体宣言(みよし市)はまだである。国の指揮命令による地方自治改悪は許されない。