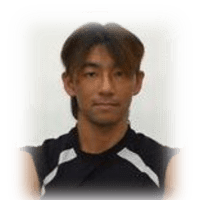●発芽の方法
① 玄米を洗う
② 洗った玄米をたっぷりの水に浸す。
出来ればこの時30~35℃の水温に保てると発芽に理想的な温度になります。
③ 発芽が始まると米からでたアクなどが発酵しますので、
濁ってきたら水を入れ換えます。
④ 水温を30~35℃に保てる様でしたら12~24時間で発芽します。
室温放置の場合は夏場ですと12~24時間
冬場は24~48時間程度で発芽する様です。

発芽の芽があまり伸びすぎるのも良くありませんので、
発芽は軽く膨らむ程度でいいそうです。
発芽に要する時間は無農薬の天日干し玄米の場合は短時間で発芽しますが、それ以外の場合は発芽に要する時間は長くなります。この辺りはお米によっても若干の違いがありますので、お米によって発芽の状態を確認してから浸水させる時間を決めてみて下さい。また、発芽の方法はネット上でも様々な方法が紹介されていますので是非、調べてみて下さい。
発芽前

発芽後

●発芽玄米に最適な玄米の見分け方
■天日干しによる自然乾燥の玄米を使用しましょう。■
灯油バナーなどで人工乾燥させた玄米だと、発芽しない可能性があるだけでなく悪臭を発生させる恐れがあるので、
必ず、天日干しによる自然乾燥をした玄米を選びましょう!
■無農薬・化学肥料不使用の玄米を使用します。■
農薬や化学肥料を使用して栽培された玄米には、農薬や化学肥料が胚芽部分に残ってしまう可能性があります。ですから、必ず、無農薬・化学肥料不使用の玄米を選びましょう!
たまに発芽しない玄米があるようです。発芽する、しないの分かれ目は、やはり「生命力」の差です。玄米が発芽するためには、その玄米が生きていて、水分を与えられたら発芽できる力を保っていることが条件なんです。農家によっては、自然乾燥でなく、乾燥機械による高温処理をしているところもあり、玄米が死んでしまうこともあるそうです。死んだ玄米は、浸水・吸水しても発芽力がないので、発芽しないです。
生命がある玄米も高温処理などによって生命を断たれてしまった玄米も、「玄米」あるいは「白米」としての姿や形はありますから、同じ「お米」として市場に流通しています。わたしは、同じ一食をいただくなら、生命力のある発芽する玄米を食べたいと思っています。お米の生命力を見極めるためにも、家で発芽玄米を作って実験してみて、「あ、これは自然乾燥させたお米だ!生きているんだ!」と感じられるのもなんだか楽しいです。食べるお米を選んでゆくのも大切なことですね。
●発芽の腐敗防止法
いつものように洗米して水を加えます。水は後で取り替えるので正確に計る必要はありませんが、米の量よりも多い方がよいと思います。水に漬けてからしばらく経つと、水中に気泡が上がってきて水が濁ってきます。このときに水を取り替えればよいのですが、、ちょっと忘れると酸っぱい匂いがしてきて、そのままほっておくととんでもない悪臭を放つようになります。これは黄色ブドウ球菌などの菌が繁殖することによるものです。この匂いや酸味は、炊飯前に水を取り替えてもご飯に残ってしまうことがあります。そういうわけで、こまめにチェックする必要があるのですが、数時間ごとに水を取り替えるのはさすがに面倒。そこで、回数をできるだけ少なくする方法はないかといろいろ実験してみました。
浄化作用のある炭や天然塩などはまず最初に思いつくものですね。重曹も効果がありました。これらは水のpHを弱アルカリ性に保つようです。重曹には繊維質を柔らかくする働きもありますが、ビタミンなどを破壊するとも言われています。また、同様の原理でアルカリイオン水も効果があります。アルカリイオン水でそのままご飯を炊くときには、pH9以下ならOKらしいです。
その他には市販の発芽玄米を作る機器【発芽美人など】には銅が使われていて、銅イオンの微量金属作用による殺菌効果が利用されています。実際、十円玉を入れておくだけでも十分効果があります。また、生きた菌を含む食品を加えることによっても、腐敗菌の繁殖を防ぐ効果があるようです。私はヨーグルト(乳酸菌)、塩麹(麹菌)、イースト菌で試してみましたが、いずれも効果がありました。
あと、オススメなのが、水をいったん沸騰させて、40℃ぐらいまで冷ましてから使うこと。雑菌の少ない水を使うことで、腐敗菌の増殖を遅らせることができます。私の場合は、この中からいくつかを併用しています。たとえば、備長炭は常に入れておき、その他にパン用のイースト菌を少々(米 3 合に対して小さじ 1)とかですね。これだと、水を取り替える回数はかなり少なくて済みます。
発芽するまでの時間もできるだけ短縮したいので水温を上げてみました。稲の発芽に最も適した温度は 30~37℃ということですが、温度が上がると雑菌の活動も活発になります。上限の 42℃を超えてしまうと発芽しませんので注意して下さい。それらの結果、発芽までの時間は室温の場合よりも数時間ほど早くなりましたが、劇的に早くなるというわけではないようです。
●関連記事
長岡式酵素玄米はなぜ麹漬けを一緒に食べるのか
抜群の健康効果がある酵素玄米の作り方
玄米よりも発芽玄米の方が安全な理由
実際に酵素玄米を作ってみました。
発芽玄米と酵素玄米の効果・効能
① 玄米を洗う
② 洗った玄米をたっぷりの水に浸す。
出来ればこの時30~35℃の水温に保てると発芽に理想的な温度になります。
③ 発芽が始まると米からでたアクなどが発酵しますので、
濁ってきたら水を入れ換えます。
④ 水温を30~35℃に保てる様でしたら12~24時間で発芽します。
室温放置の場合は夏場ですと12~24時間
冬場は24~48時間程度で発芽する様です。

発芽の芽があまり伸びすぎるのも良くありませんので、
発芽は軽く膨らむ程度でいいそうです。
発芽に要する時間は無農薬の天日干し玄米の場合は短時間で発芽しますが、それ以外の場合は発芽に要する時間は長くなります。この辺りはお米によっても若干の違いがありますので、お米によって発芽の状態を確認してから浸水させる時間を決めてみて下さい。また、発芽の方法はネット上でも様々な方法が紹介されていますので是非、調べてみて下さい。
発芽前

発芽後

●発芽玄米に最適な玄米の見分け方
■天日干しによる自然乾燥の玄米を使用しましょう。■
灯油バナーなどで人工乾燥させた玄米だと、発芽しない可能性があるだけでなく悪臭を発生させる恐れがあるので、
必ず、天日干しによる自然乾燥をした玄米を選びましょう!
■無農薬・化学肥料不使用の玄米を使用します。■
農薬や化学肥料を使用して栽培された玄米には、農薬や化学肥料が胚芽部分に残ってしまう可能性があります。ですから、必ず、無農薬・化学肥料不使用の玄米を選びましょう!
たまに発芽しない玄米があるようです。発芽する、しないの分かれ目は、やはり「生命力」の差です。玄米が発芽するためには、その玄米が生きていて、水分を与えられたら発芽できる力を保っていることが条件なんです。農家によっては、自然乾燥でなく、乾燥機械による高温処理をしているところもあり、玄米が死んでしまうこともあるそうです。死んだ玄米は、浸水・吸水しても発芽力がないので、発芽しないです。
生命がある玄米も高温処理などによって生命を断たれてしまった玄米も、「玄米」あるいは「白米」としての姿や形はありますから、同じ「お米」として市場に流通しています。わたしは、同じ一食をいただくなら、生命力のある発芽する玄米を食べたいと思っています。お米の生命力を見極めるためにも、家で発芽玄米を作って実験してみて、「あ、これは自然乾燥させたお米だ!生きているんだ!」と感じられるのもなんだか楽しいです。食べるお米を選んでゆくのも大切なことですね。
●発芽の腐敗防止法
いつものように洗米して水を加えます。水は後で取り替えるので正確に計る必要はありませんが、米の量よりも多い方がよいと思います。水に漬けてからしばらく経つと、水中に気泡が上がってきて水が濁ってきます。このときに水を取り替えればよいのですが、、ちょっと忘れると酸っぱい匂いがしてきて、そのままほっておくととんでもない悪臭を放つようになります。これは黄色ブドウ球菌などの菌が繁殖することによるものです。この匂いや酸味は、炊飯前に水を取り替えてもご飯に残ってしまうことがあります。そういうわけで、こまめにチェックする必要があるのですが、数時間ごとに水を取り替えるのはさすがに面倒。そこで、回数をできるだけ少なくする方法はないかといろいろ実験してみました。
浄化作用のある炭や天然塩などはまず最初に思いつくものですね。重曹も効果がありました。これらは水のpHを弱アルカリ性に保つようです。重曹には繊維質を柔らかくする働きもありますが、ビタミンなどを破壊するとも言われています。また、同様の原理でアルカリイオン水も効果があります。アルカリイオン水でそのままご飯を炊くときには、pH9以下ならOKらしいです。
その他には市販の発芽玄米を作る機器【発芽美人など】には銅が使われていて、銅イオンの微量金属作用による殺菌効果が利用されています。実際、十円玉を入れておくだけでも十分効果があります。また、生きた菌を含む食品を加えることによっても、腐敗菌の繁殖を防ぐ効果があるようです。私はヨーグルト(乳酸菌)、塩麹(麹菌)、イースト菌で試してみましたが、いずれも効果がありました。
あと、オススメなのが、水をいったん沸騰させて、40℃ぐらいまで冷ましてから使うこと。雑菌の少ない水を使うことで、腐敗菌の増殖を遅らせることができます。私の場合は、この中からいくつかを併用しています。たとえば、備長炭は常に入れておき、その他にパン用のイースト菌を少々(米 3 合に対して小さじ 1)とかですね。これだと、水を取り替える回数はかなり少なくて済みます。
発芽するまでの時間もできるだけ短縮したいので水温を上げてみました。稲の発芽に最も適した温度は 30~37℃ということですが、温度が上がると雑菌の活動も活発になります。上限の 42℃を超えてしまうと発芽しませんので注意して下さい。それらの結果、発芽までの時間は室温の場合よりも数時間ほど早くなりましたが、劇的に早くなるというわけではないようです。
●関連記事
長岡式酵素玄米はなぜ麹漬けを一緒に食べるのか
抜群の健康効果がある酵素玄米の作り方
玄米よりも発芽玄米の方が安全な理由
実際に酵素玄米を作ってみました。
発芽玄米と酵素玄米の効果・効能