"@I_Yoichi: 「赤ん坊が泣くのは当たり前だろ」どまりでは理解は生まれない。"私の自閉症の息子は小学1、2年生の頃、赤ん坊、幼児の泣き声、奇声、拗ねる声、我が儘な振舞いに対して逃場のない閉所で衝動的なpanicを惹起こし、体当り、髪を掴み引き摺る、押倒す等を繰返して…(続
"@I_Yoichi: "承前)現在19才の彼は遣過ごし方を覚えましたが…その辛さを克服したかと言うと、遣過ごしも逃場もない閉所では凶器を突付けられるほどの辛さを感じるようです。聴覚→痛覚の問題だと思いますが…当時は殴る蹴る等と同様の理不尽な暴力を被った思いで仕返したそうです。
@I_Yoichi 彼の名誉の為に追加(笑)泣き声全てに不快感を覚えた訳ではなく、同時期に札幌行きの機内で幼児の泣き声…『いい子するんだよ♪直ぐに着くから』と周囲の微笑を誘う息子の言葉。私の判断ですが…泣くのが自然な泣声と拗ねる甘えるの作為的駆引きの泣声を判別していたと思います
乳幼児は泣くのは当然と言う言辞は半分肯定で半分は…?です。乳幼児は泣くことで便尿、空腹、目覚め等を通知します。極めて自然なことですが…大人の不手際、放任、手抜きに対する抗議の泣声、拗ね甘えの駆引きの泣き声は違うtoneで前者には感じない不快感を後者に特に敏感に感る人がいるのでは?
@I_Yoichi 水島さんの言葉の通りだと思います。確かに一見すると乱暴にもいきなり叩くなどの行為の背景にその人なりの物語があり、その背景からの行為だと理解出来ることが多数有ります。問題行動をする人は実は困っている、抱えている問題を言語表現出来ない行動は言葉の表現を求めている。
痛くもないのに痛がる、我を通す為に泣いたり、拗ねたり、透かしたり駆引きして暴れたり、奇声を上げる。そのわざとらしい作為的な声のtoneと自然の泣き声と言う乳幼児のコミュ手段の区別を発達障害者の方が敏感に感じ取っているのではないでしょうか?発達障害者には作為的な行動は不快な行動。
@yosh0316「 困った人は困っている人」という水島広子先生の言葉はホントですね。端から見るとただの我慢のできない自分勝手な子、と見えてしまいます。なのに心の内側というブラックボックスを垣間みると、途端に評価がひっくり返りますね。どんな人にも言えることかもしれません。
@rinngonokimoti 『卒原発』お粗末な言葉感覚。卒業の連想?…『卒』は俄にバタバタと慌て不徹底ながら終わるの意味。卒業とは業を慌てて止めること。卒中、卒倒、卒塔婆の意味を考えたら全て俄に、狼狽しての意味。嘉田新党の俄仕立、飯田某の原発に対する姿勢は成る程卒然。
“発達障害者には作為的な行動は不快な行動。”とTWしてハッと閃きました!心理学でアン・サリー課題等の心の理論に関する論文を読む時に私が学生時代から感じて来た心理実験への違和感の根拠は『故意の実験背景に有った!』と。意図と故意の作為の間には深くて…などと何故か黒の舟歌が(苦笑)
@ronsyo_note @mirai_list 不思議な感覚ですね。数の問題でしょうか?私はぶれずに継続だと思うのですが…(^-^)v










 YOSH @yosh0316
YOSH @yosh0316 石川陽一 @I_Yoichi
石川陽一 @I_Yoichi



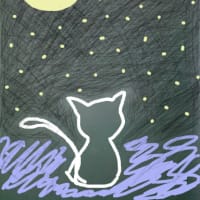
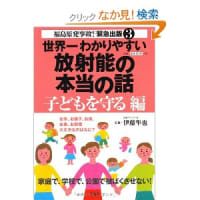
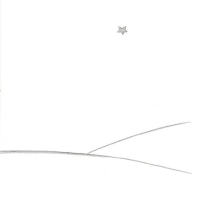
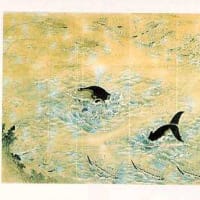

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます