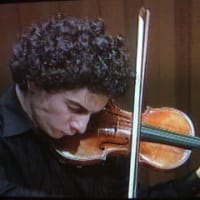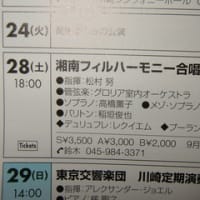すみませんm(_ _)m ヒデミちゃんリサイタルの感想をエントリーする前にどうしてもひとつだけ先にエントリーしておきたいものがあるのでなにとぞご理解を
◆REQUIEM Op.9 (モーリス・デュリュフレ)◆
というわけで、先日エントリーしたモーリス・デュリュフレのオルガン作品に続いて今日は彼のREQUIEM Op.9を。
先日も書きましたが、ワタシにとってデュリュフレはなんと言っても“サイレンス”(寡黙・沈黙・静寂)を実感させてくれる作曲家なんです。全身を心地よく弛緩させてくれる、まるで母なる海にわが身を委ねているような感覚にさせてくれる。心地よく、そしてどこか懐かしい。深い海に意識が溶け合って、いつのまにか海そのものと自分が同化しているかのような気持ちにさせてくれる。このデュリュフレのほかに“サイレンス”を明確に感じさせてくれるのは、ウェーベルンと武満、そしてブリテンくらいかな。あくまでワタシ的にはですが。
フォーレのレクイエムから60年後に作られたこのレクイエムは、フォーレのそれとほぼ同じテクストを使用しています。選んだ調性もフォーレのそれと同じd-moll。作曲の動機については、正確にはデュラン社からの正式な作曲以来が直接の動機ということらしいのですが、父親の死がきっかけとなっている点でフォーレのレクイエムと類似している。誰もが認めるデュリュフレの代表作です。
この曲には3つのヴァージョンがあるんだそうな。
フォーレのレクイエムとは違って、全ての稿が作曲者自身による。
第1稿[1947]:フルオーケストラヴァージョン
第2稿[1947]:オルガンヴァージョン
第3稿[1961]:室内オーケストラヴァージョン(3Tp、Timp、Hp、弦、Org)
第3稿だけがだいぶ後に書かれているのがわかります。
本人はこの第3稿を決定稿としたらしいが、この室内オケヴァージョンはあくまで演奏の利便性を優先してのことであって、本音はやはりフルオケヴァージョンで演奏されることを内心望んでいたということらしい。
この3つのヴァージョンのうちワタシが聴いたことがあるのは第1稿と第3稿。
個人的には、機動性のある室内楽が好みという点と、合唱の美しさを存分に味わいたいという点で第3稿に軍配をあげたい。フルオケヴァージョンはうまくいったときはいいのだが、なかなか全体をバランスよく仕上げるのが難しいですわな
第3稿でワタシがオススメなのがこれ。

【演 奏】アン・マレー(メゾ・ソプラノ)、トーマス・アレン(バリトン)
トーマス・トロテア(オルガン)
マシュー・ベスト指揮 イギリス室内管弦楽団
コライドン(コリドン?)・シンガーズ
【曲 目】・Requiem Op.9 (第3稿)
・Quatre Motets Op.10
【録 音】1985年10月
【レーベル】Hyperion
【品 番】CDA66191
※このディスクはコチラで試聴可能です♪
もう合唱の美しさときたらハンパじゃない。特に女声パート。この女性パートはどうも少年が担当しているらしいのですが(どおりでくっどいヴィブラートが皆無なわけだ )、この女声パートのパーフェクトな音程と、一糸乱れないアンサンブル、天に突き抜けるようなフォルテッシモ、たゆたうようなピアニッシモ、非常にクリアーなソノリティ、どれをとっても天下一品です
)、この女声パートのパーフェクトな音程と、一糸乱れないアンサンブル、天に突き抜けるようなフォルテッシモ、たゆたうようなピアニッシモ、非常にクリアーなソノリティ、どれをとっても天下一品です “本物のハーモニーとはかくあるべき”ということを否応なく納得させられる演奏♪
“本物のハーモニーとはかくあるべき”ということを否応なく納得させられる演奏♪
聴きどころは、ゆったりめのテンポをとりつつ非常にファンタジックな表現が素晴らしい入祭唱&キリエ、主イエス・キリストの中間部(4'00”付近)および終結部(8'00"付近)における静謚で幻想的な女声合唱、うちよせる波のごとくたゆたうサンクトゥス、教会のステンドグラスから差し込む柔らかい光に包みこまれるかのような聖体拝領唱、激情とかすかにゆらめく灯し火のように微細な感情表出の対比が素晴らしいリベラ・メ、そして究極の癒しの音楽イン・パラディスム・・・といったところでしょうか。 <ほとんど全部じゃねーか
デュリュフレのイン・パラディスム(天国にて)というのは、フォーレの溢れんばかりの幸福感に包まれたそれとは少し違って、何か“無”と“静寂”の無機的とも思える空間美と、幸福感と呼ぶには心もとないくらいのほのかな体温、という絶妙なバランスのうえに成り立っているように思えてならなりません。実に慎ましく、そしてクールな美的センスが発揮された名曲。この“高貴な慎ましさ”とでも呼ぶべきセンスにワタシはデュリュフレ流のモダニズムを感じてしまう。
前にも書きましたが、このイン・パラディスムがいつもSF映画の金字塔『ブレード・ランナー』におけるラストシーンで、最後のレプリカントがデッカート刑事との激戦の末に、寿命(!)で死んでしまうシーンと重なってしまうんです(^-^; 美しい合唱とともに全てが静寂へと導かれるように、一人の人間(レプリカント)の死もまたひとつの静寂へ・・・。うーん、これぞ究極の美

もうひとつ。ピエ・イエスを歌っているメゾソプラノは抑制の効いた上品な表現が素晴らしい。ただ、自分の好みからするともう少ししっとりとしたというか、くぐもったような柔らかい声質のほうがこの曲に関してはワタシの好み。
逆にフォーレのピエ・イエスなんかだと、こういう透明感のある声質が好みなのだが
それぞれの曲における声質の好みは、フォーレのそれが上昇形の旋律線を描いているのに対し、デュリュフレのそれは下降形の旋律線を描いていることに起因しているのかもしれない(なかなか理屈に合ってるでしょ )。
)。
バリトンも抑制の効いた表現がよいですね。素晴らしい。
オケのイギリス室内管弦楽団も上手いとしかいいようのない見事な演奏♪
カップリングの《4つのモテットOp.10》の美しさもまた格別。
とにかくこの天空に突き抜けるかのような美しい合唱を一度聴いてみてください。
もうあなたはデュリュフレの虜☆
自分の葬式でこの曲かけてもらえたら最高だなぁ~( ̄~ ̄)
とりあえず、哀れな、そして当然の報いを受けたほりえもんにこの曲をささげ・・・るにはもったいないな(-∀-) やっぱやーめた


◆REQUIEM Op.9 (モーリス・デュリュフレ)◆
というわけで、先日エントリーしたモーリス・デュリュフレのオルガン作品に続いて今日は彼のREQUIEM Op.9を。
先日も書きましたが、ワタシにとってデュリュフレはなんと言っても“サイレンス”(寡黙・沈黙・静寂)を実感させてくれる作曲家なんです。全身を心地よく弛緩させてくれる、まるで母なる海にわが身を委ねているような感覚にさせてくれる。心地よく、そしてどこか懐かしい。深い海に意識が溶け合って、いつのまにか海そのものと自分が同化しているかのような気持ちにさせてくれる。このデュリュフレのほかに“サイレンス”を明確に感じさせてくれるのは、ウェーベルンと武満、そしてブリテンくらいかな。あくまでワタシ的にはですが。
フォーレのレクイエムから60年後に作られたこのレクイエムは、フォーレのそれとほぼ同じテクストを使用しています。選んだ調性もフォーレのそれと同じd-moll。作曲の動機については、正確にはデュラン社からの正式な作曲以来が直接の動機ということらしいのですが、父親の死がきっかけとなっている点でフォーレのレクイエムと類似している。誰もが認めるデュリュフレの代表作です。
この曲には3つのヴァージョンがあるんだそうな。
フォーレのレクイエムとは違って、全ての稿が作曲者自身による。
第1稿[1947]:フルオーケストラヴァージョン
第2稿[1947]:オルガンヴァージョン
第3稿[1961]:室内オーケストラヴァージョン(3Tp、Timp、Hp、弦、Org)
第3稿だけがだいぶ後に書かれているのがわかります。
本人はこの第3稿を決定稿としたらしいが、この室内オケヴァージョンはあくまで演奏の利便性を優先してのことであって、本音はやはりフルオケヴァージョンで演奏されることを内心望んでいたということらしい。
この3つのヴァージョンのうちワタシが聴いたことがあるのは第1稿と第3稿。
個人的には、機動性のある室内楽が好みという点と、合唱の美しさを存分に味わいたいという点で第3稿に軍配をあげたい。フルオケヴァージョンはうまくいったときはいいのだが、なかなか全体をバランスよく仕上げるのが難しいですわな

第3稿でワタシがオススメなのがこれ。

【演 奏】アン・マレー(メゾ・ソプラノ)、トーマス・アレン(バリトン)
トーマス・トロテア(オルガン)
マシュー・ベスト指揮 イギリス室内管弦楽団
コライドン(コリドン?)・シンガーズ
【曲 目】・Requiem Op.9 (第3稿)
・Quatre Motets Op.10
【録 音】1985年10月
【レーベル】Hyperion
【品 番】CDA66191
※このディスクはコチラで試聴可能です♪
もう合唱の美しさときたらハンパじゃない。特に女声パート。この女性パートはどうも少年が担当しているらしいのですが(どおりでくっどいヴィブラートが皆無なわけだ
 )、この女声パートのパーフェクトな音程と、一糸乱れないアンサンブル、天に突き抜けるようなフォルテッシモ、たゆたうようなピアニッシモ、非常にクリアーなソノリティ、どれをとっても天下一品です
)、この女声パートのパーフェクトな音程と、一糸乱れないアンサンブル、天に突き抜けるようなフォルテッシモ、たゆたうようなピアニッシモ、非常にクリアーなソノリティ、どれをとっても天下一品です “本物のハーモニーとはかくあるべき”ということを否応なく納得させられる演奏♪
“本物のハーモニーとはかくあるべき”ということを否応なく納得させられる演奏♪聴きどころは、ゆったりめのテンポをとりつつ非常にファンタジックな表現が素晴らしい入祭唱&キリエ、主イエス・キリストの中間部(4'00”付近)および終結部(8'00"付近)における静謚で幻想的な女声合唱、うちよせる波のごとくたゆたうサンクトゥス、教会のステンドグラスから差し込む柔らかい光に包みこまれるかのような聖体拝領唱、激情とかすかにゆらめく灯し火のように微細な感情表出の対比が素晴らしいリベラ・メ、そして究極の癒しの音楽イン・パラディスム・・・といったところでしょうか。 <ほとんど全部じゃねーか

デュリュフレのイン・パラディスム(天国にて)というのは、フォーレの溢れんばかりの幸福感に包まれたそれとは少し違って、何か“無”と“静寂”の無機的とも思える空間美と、幸福感と呼ぶには心もとないくらいのほのかな体温、という絶妙なバランスのうえに成り立っているように思えてならなりません。実に慎ましく、そしてクールな美的センスが発揮された名曲。この“高貴な慎ましさ”とでも呼ぶべきセンスにワタシはデュリュフレ流のモダニズムを感じてしまう。
前にも書きましたが、このイン・パラディスムがいつもSF映画の金字塔『ブレード・ランナー』におけるラストシーンで、最後のレプリカントがデッカート刑事との激戦の末に、寿命(!)で死んでしまうシーンと重なってしまうんです(^-^; 美しい合唱とともに全てが静寂へと導かれるように、一人の人間(レプリカント)の死もまたひとつの静寂へ・・・。うーん、これぞ究極の美


もうひとつ。ピエ・イエスを歌っているメゾソプラノは抑制の効いた上品な表現が素晴らしい。ただ、自分の好みからするともう少ししっとりとしたというか、くぐもったような柔らかい声質のほうがこの曲に関してはワタシの好み。
逆にフォーレのピエ・イエスなんかだと、こういう透明感のある声質が好みなのだが

それぞれの曲における声質の好みは、フォーレのそれが上昇形の旋律線を描いているのに対し、デュリュフレのそれは下降形の旋律線を描いていることに起因しているのかもしれない(なかなか理屈に合ってるでしょ
 )。
)。バリトンも抑制の効いた表現がよいですね。素晴らしい。
オケのイギリス室内管弦楽団も上手いとしかいいようのない見事な演奏♪
カップリングの《4つのモテットOp.10》の美しさもまた格別。
とにかくこの天空に突き抜けるかのような美しい合唱を一度聴いてみてください。
もうあなたはデュリュフレの虜☆
自分の葬式でこの曲かけてもらえたら最高だなぁ~( ̄~ ̄)
とりあえず、哀れな、そして当然の報いを受けたほりえもんにこの曲をささげ・・・るにはもったいないな(-∀-) やっぱやーめた